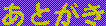不機嫌なビタミン剤
「あそこはどう?」
「やだ。ゴテゴテしすぎ」
僕が指し示したピンクと白の小さな城を、即座に却下したのは向坂拓斗。
僕より五つ下の恋人。医学部の一年生である。
僕は桂川龍樹。昔は医者をやっていたこともあるが、今は小さな茶店のオーナーだ。拓斗は開店初日からの常連で、ずっと僕の片思いの相手だった。口説き抜いて、今は晴れてパートナーとなっているが、僕が恋の奴隷なのは相変わらずなのだ。
「じゃあ、あのホテルでいい?」
手っ取り早く近間を選んだ僕に、拓斗は鼻で笑って返事をした。
「だめ。カジノみたいで安っぽい」
確かに、一番ネオンサインがきつかったから、目に付いたんだった。
そろそろ決めないと、峠のホテルも数が少なくなってきている。僕は少し焦りを感じていた。何しろ僕の堪忍袋ならぬスケベ袋がはち切れそうで。
「あっちの看板のは?」
緑の中に突き出た看板が、五〇メートル先にパーキングがあると教えていた。
「名前が変。“風がはこんだ物語”なんて、不味そうな土産菓子みたいだ」
「名前なんて、なんだって良いじゃないか」
言った途端に、拓斗がちらりと僕をねめつけた。
サラッとした癖のない絹糸のような髪を掻き上げ、黒目がちの大きな瞳をすがめて。
流し目のようなそれは、大変色っぽいのだが、不機嫌なときしか見せない表情だから剣呑なのだ。
「ネーミングのセンスでオーナーのセンスが分かる。絶対砂吐きものの部屋だぜ」
僕は小さな溜息をついてアクセルを踏んだ。
全開の窓からは気持ちの良い風が吹き込む。空は青く、木々の緑は美しい。エンジン絶好調の車は心地よいスピードで車通りの少ない道路を突き進む。
そして、隣には愛しい想い人。
何もかもが最高のドライブ環境なのに。
恋人がへそを曲げているのは何故なのか、僕には分からなくて。
そりゃ、ドライブに誘っておいて、急にしたくなったからホテル入ろうなんて、獣臭かったかもしれないけど。
二週間もお預けだったんだもの、大目に見て欲しい。
拓斗の身体からは僕を扇情するオーラが発せられてるに違いなく、毎日していても彼の側にいるだけで、いつでもスタンバイOKになってしまう僕だから。
拓斗の前期試験期間の二週間は本当にきつかったのだ。
勉強に集中したいだろうと、寝室を譲ったのは僕だけど。狭いソファでの独り寝は、やっぱりわびしかった。
試験明けの週末は土日の連休だと言うから、店の方を臨時休業にして出かけることにした。H解禁をうんと楽しめるように。
なのに……。
「……拓斗君、したくないの? だったら、我慢する……」
だから、どうか、僕に微笑んで。
「我慢も何も……予約したホテルまで行く間じゃないか」
獣め! なんて目で言ってくれて。ちっとも微笑んでくれない。
「もしかして、頭の中まで白い血で充血してるの?」
ああ、やっぱり何か怒っている。
拓斗がこういう言い方するときは、僕が彼を怒らせたときなんだ。
「……ごめん……」
「何でそう、すぐ謝るわけ?」
「……君が怒ってるから……」
「俺が怒ってれば謝るの?」
「……だって……。君のそういう態度、僕が怒らせたときだけだから……。僕が何かしちゃったんだよね?」
「わかんないで謝るなんて、誠意が足りないとは思わない?」
「あ……ごめん……」
「また謝る!」
ゴメンと言いそうになって、口をつぐんだ。
どうしよう。
「龍樹さん! 信号!」
「!」
赤に変わっていたのに通り過ぎてしまった。
「危ないよ。運転に集中してよ」
とがった声で責められて、尚更気分が暗くなった。
「わかってる……」
とは言っても、頭の半分以上が原因究明に使われてしまい、どうしても集中できない。
だんだん悲しくなってきてしまった。
こんな事なら家にいれば良かった。二人でくつろいで、テレビ見て、時々キスして。
こんな、喧嘩になるなら、ドライブなんて……。
「……泣くなよ」
鬱陶しいって溜息。
「龍樹さんみたいな男がこんな事で泣いてると、なんだかむかつく」
「っ!」
思わず嗚咽も飲み込んで固まった。
対向車線に出そうになって、慌ててハンドルを切り、路肩に停めた。
「あっぶねー。ちょっと、そこの空き地に入って少し頭冷やしたら? 脳味噌にちゃんとした血を通わせた方がいい」
他人事みたいに言われてカッとする。
ガッと思いっきりアクセルを踏んで、拓斗の指し示したところに車を突っ込んだ。
砂利がバチバチと跳ね上がる音が、僕らのささくれた気持ちみたいに耳障り。
木漏れ日が僕らの肌に揺れる模様を刻印してる。日差しが適度に遮られてるから、風はひんやりと肌を撫でて通る。
言われたとおりに頭を冷やすのもしゃくで、窓を全部閉めた。
「……ドライバーを動揺させるなんて酷いナビだ」
「龍樹さんがすぐ泣くからいけないんだ」
「君が泣かすからだろっ」
「普通、あれくらいで泣くかよ。信じらんない」
呆れた口調で言われて、僕は絶望に一歩近づいた。
拓斗が僕に愛想を尽かし始めてる。そう感じたが為に、僕の涙腺は異常を来し始めた。
ボワッと溢れ出る涙はコントロール不能。
これ以上泣き顔を見せたくなくて、ハンドルの上に突っ伏した。
「な、涙が勝手に出ちゃうんだからしょうがないだろっ」
……くやしい。確かに些細な言葉だけで泣いてしまう自分に、僕だって呆れてるんだ。
拓斗に嫌われてしまう。いや、もう嫌われ始めてる。
辛くて、心臓から広がっていく痛みが体中を蝕んで。本当に死んでしまうかも。
だから、その刺激に瞬間反応できないでいた。
助手席から伸ばされた手が、僕の股間に忍び込んでいたのだ。
「一人で何回、ここ弄った?」
「!」
服の上から握られて息が詰まった。
「毎晩出してただろ? 俺をオカズにして」
「ああっっっ」
気持ちとは無関係に快感が奔った。辛いのに、気持ちいい。拓斗が握ってくれているから。こんなに体中が彼を求めてる。触れられただけでイッてしまいそうに感じてる。
「言えよ、何回イッた?」
指が僕のジッパーをおろして忍び込んできた。直に握られて、元々硬くなっていたペニスは一気に膨張した。
「そんな……事……」
「言えない? 俺は知りたいよ。このスケベな身体が、どのくらい俺のこと思い出して震えたか……」
ああどうしよう。喘ぎを抑えるのがやっとなのに。拓斗の声は果てしなく色っぽく聞こえて。怒った拓斗も素敵すぎて、TPOを考えずにイッてしまいそうだ。
「……っかい……」
「聞こえない。もう一度」
「……六回ずつ……毎日……」
「……え?」
素っ頓狂に響いた拓斗の声に、僕の身は縮まった。
「毎日六回! 信じらんねー」
「だ、だって……」
拓斗を襲わないためには絞りきらないといけなかったのだ。
「それでもう、こんなか。もうすぐ三〇に届くって歳で……。ホントに龍樹さんて、化け物みたい」
僕が傷つくようにわざと言ってる。
こんなに不機嫌で意地悪な拓斗は初めてで、いよいよ僕は萎縮した。
泣いても許してはもらえない。かえって、火に油……。
「拓斗……、どうして怒ってるの? 僕が悪かったんなら、謝るから。もう許してくれないか?」
「分からないで謝るなって言ったろ?」
「じゃあ教えてくれよ!」
不毛な睨み合いは拓斗の方が窓の外に視線を移して打ちきった。
「……昨日もマス掻いたろ」
硬い声音が僕を責める。
「う……」
「昨日解禁でも良かったのに、俺の前ではやせ我慢して、一人で出してたよな」
「き、君を壊したくなかったから……けっ獣とか、化け物とか、言われたくなかったから……」
はあっと盛大な溜息を拓斗が吐いた。
「じゃあ、何で、予定変更してホテル入ろうなんて言い出したのさ?」
「……我慢……出来なくて」
「俺は便所じゃないよ。出したくなったからやりましょうなんて言われて、応えられるわけないじゃん」
「そんなんじゃないっ。……今日泊まるの純和風旅館なんだ。多分、部屋の鍵もかけないだろうから……」
「どうしてそういうとこ、とるかね?」
「君と一緒に美味しい料理食べて、露天風呂入って……楽しみたかったから……」
「エッチは二の次?」
「うん……いや。したいけど、それだけじゃやだったんだ。……贅沢だった?」
「欲張り……」
呟きの声音は、優しかった。
「それでこそ龍樹さんだ……」
機嫌、直ってきたんだろうか。拓斗の左手が、優しく僕をさすっている。
「拓斗……許してくれるの?」
「……なにを?」
身を乗り出して、僕の首に腕回してきた。
手放されたペニスが途端に寒くなる。代わりに唇をチュッと吸われ、熱が上がった。
拓斗の黒い瞳が、深い輝きに慈愛を乗せて注ぎ込んでくる。
「俺に許されなきゃいけない事、龍樹さんはしたの?」
「……分からない……分からないよ……」
ふりほどかれないのをいいことに、しなやかな細身を抱きしめた。拓斗の匂い……。
項を香るのは若い男の汗の匂いとシャンプーの匂い。甘くてセクシーな、拓斗だけの匂い。フェロモンがたっぷり含まれているんだろう。
「僕をあんまり虐めないでくれ……。君に冷たくされると、どうしていいか分からなくなる……」
「冷たくなんてしてないよ」
「うそ。僕に愛想尽かし始めてるんだろう?」
「龍樹さんてば……」
ぎゅっと抱きしめられて慌てた。
拓斗の膝が、僕のペニスをグリッと踏みつぶしたから。
「うっ」
「あっごめっ。ああもうっ、このシフトレバー、邪魔っ」
太股に拓斗の重みを感じながら、彼を抱き留めて支えた。
「愛想なんて、どうしたらつかせられるんだろうね……」
言いながら僕の髪を掻き上げた。瞳が優しく微笑んでいる。バカだなぁって、僕に笑いかけてる。
「龍樹さんの髪は柔らかくて、美味しそうな飴色で、触るとすごく気持ちよくて好き。このまっすぐな鼻筋も、眉のラインもこれ以上ないほど綺麗で憧れてる。この瞳は琥珀色のくせに金色に輝いて、俺を吸い込んでしまいそうで怖いほど綺麗。この唇は色も形も最高」
拓斗の指が優しく僕の唇を撫でた。
「こうやって触れると暖かくて柔らかくて、ずっと触れていたくなるほど好き」
ああ……。言葉での愛撫……。拓斗の声で聞くと、なんて心地よいんだろう。
「俺の一言でピンク色になるほっぺは、美味そうで思わずかじりたくなる」
カプッと唇だけで僕の頬を銜えるようにキスした。そのまま唇が這い降りて……。
「この顎。輪郭も、腕も足も身体も。全部の作りとマッチして整ってるから、俺だけが独占できるなんて嘘みたいだと思う」
なのに。と、僕をにらみつけると、拓斗は僕のペニスをかじった。
「いっっ」
あまりの痛さに色気のない声を出してしまった。
「こんなに格好良くて何でも出来るのに、俺の言葉一つで泣き出すなんて、あんまり情けなくてむかつく」
僕のを口に含んだまま呟かれて慌てた。拓斗にされると、毎日抜いておいたにもかかわらず、達するのが超特急になってしまう。このままでは彼の口か顔に思いっきり……。
「拓斗、お願い……やめて。出ちゃうよ。君を汚しちゃう……」
拓斗は尚更執拗に僕を舐め始めた。
「俺のためとか言って我慢するのもむかつく」
「そんな……っ、ああっあっあっんくっ」
拓斗が口でしてくれるなんて……。僕が要求しないせいもあるけど、すごく特別なことなのだ。
「欲しいのに、こんなドライブとか誘わなきゃ欲しいって言えないで、家でマス掻いてるなんてむかつく」
熱く絡みつく舌の感触はものすごく愛しげなのに、言葉は僕を虐めるように発せられてる。なのに僕と来たら、体が熱くなる一方で……。
「ホントはどこでも良いからやりたいくせに、シチュエーションにこだわるなんて、むかつく」
「拓斗……? ああっん拓斗……」
「俺のこと、腫れ物を触るように扱うのはサイッコウにむかつく!」
「あっふうん」
キュッと搾るように吸い上げられて、僕はとうとう出してしまった。
拓斗は、その瞬間に口を離した。
「あ、だめっ!」
叫んでも、もう間に合わない。
ビシャッと拓斗の顔に、真正面からかけてしまったのだ。
「あ……あ……あ……」
放出の快感に、素直に酔うことは出来ない。
拓斗に顔射をしてしまうなんて……。
とろりと拓斗の額や頬を伝う白い液体。可愛らしい小鼻から赤い唇に伝っていったそれを、更に赤い舌がクニュリと顔を出して舐め取った。
妖しいほどの色っぽさ。拓斗はこんな顔もできたのだ……。
「龍樹さんの……すごいや……」
止めることも出来ずにドクンドクンと出続ける僕の精を、拓斗は顔を拭うこともせずに舌で舐め取った。手探りでティッシュを探す。ポケットのハンカチを探り当て、拓斗の頬に当てた。
「ごめん……まともにかけちゃったよ。ごめんね」
ふき取ろうとした僕の手をそっと押しとどめた拓斗は、半ば恍惚とした表情で微笑んだ。
「謝らないでよ。龍樹さんのだから、気持ちいいよ。俺でも龍樹さんをイかせること、出来るんだって、嬉しい……」
僕は思わず彼の顔に舌を這わせていた。ハンカチではなく、僕の口で綺麗にしたかった。
拓斗が嫌がらないのをいいことに、額、瞼、鼻に頬……全てを舐めまくった。
「……気持ちよかった?」
最後に残しておいた唇を舌で舐め取っていたら、クッと唇が動いてそんなことを尋ねてきた。
「ああ……とっても……」
口の中もきっちり綺麗にしようという気になった。歯の裏、舌の裏、口蓋……。
全部愛しい。
「んっんっ」
わざと逃げを討つ舌をからめ取って吸った。
彼の怒りのポイントが、やっと僕にもわかり始めていたから。
「拓斗……だめ。全部しなきゃ気が済まなくなったよ。受け入れてくれるよね?」
本気で彼の腰を砕けさせる。彼の感じるスポットを順に刺激して欲望を高めていくのは、スイッチを入れていくような楽しさ。
僕の恋人は、一度スイッチが入るとものすごくエッチになるんだ。
いつもは恥ずかしがりなくせに、とっても大胆な娼婦のように変わる。
「拓斗……いいだろ? いいよね?」
彼を助手席に横たわせ、リクライニングのレバーを引いた。
「あ……っ!」
倒れ込んだ拓斗の上にのしかかった。
狭いけど、ここをベッドにしよう。
「龍樹さんっ龍樹さんっ」
拓斗が積極的に腕を絡ませてきた。
「んっううっんっ」
キス、キス、キス。全身にキス。
拓斗がしてくれたように、舐めて、しゃぶって……もっと念入りに。
「拓斗、イイ?」
「あ……んんっいいっ気持ち……いいっ」
口から溢れ出る涎が煌めきながら色っぽく震える顎の線をなぞった。
「綺麗だよ。君はこんなに淫らでも、清らかな色をしてる……」
パンツはブリーフと一緒に膝まで下ろした。シャツははだけさせ、両の乳首を露わにして。少しきついけど、ぎゅっと膝を折らせて押さえつけた。丸まった拓斗のパンツを胸で押さえるようにのしかかったまま、彼の蕾を探った。とうにとろけて、僕の指にからみついてくるそこは、クチュクチュと湿った音で僕を誘う。
「ああ……やだよ。その音……俺が女になってく音だ……」
「僕と繋がる事は君が女になることとはイコールなの?」
「実質……そうだろ?」
「チェンジしてみる? それでもいいよ。僕は君に愛されるならどっちでもいいんだ」
「そんな、変だよ。俺みたいのが龍樹さんを……なんて」
「どうして?」
「誰がみたって、俺の方が受け入れる側だって考えるよ」
「見た目なんて、関係ないだろう? 要は嗜好の問題だ。僕は君とセックスしたい。君がタチが好きなら僕はネコになる。君がネコを好むなら僕はタチに徹する。ただそれだけ」
「何? それ……タチとかネコとか」
「受動か能動かの区別だけど、大抵ネコは受け入れる側。タチは……」
「する側か。ならどうして俺をネコとして扱ったの?」
「……君に自覚して欲しかった。男と寝るって事……。身体で受け入れることで、僕を本当に受け入れて欲しかったんだ。それと……」
ちらりと拓斗をうかがった。
「女と決別して貰いたかったってのもある」
女じゃ満足出来ないように。僕は全力で彼に男とのセックスの良さを教え込んだのだった。
「女のことなんか……考えないで。僕だけを思って……」
「ごめん……ごめんね。龍樹さんが不安になるの、俺のせいなんだね」
拓斗が僕を引き寄せて抱きしめてくれた。
「龍樹さんだけは入ってきてもいいんだよ。ここ、してよ。思いっきり突いて!」
服を蹴り捨て、脚をM字型に開いて、拓斗の菊花がパクパクと僕を呼んだ。
拓斗、君は僕のもの……。
熱い火口に押し入って、存分に狭い柔襞の壁を味わった。
「あああああっ! んんっそこっん」
ああ、君の反応。僕と繋がって嬉しく思ってくれてるね。
「龍樹……さんっ。信じてっ俺を……信じて!」
信じてるさ。自分に自信がないだけなんだ。
君が受け入れてくれる度、僕は怖くなる。
いつか、もう付き合いきれないって言われそうで。
「君が笑ってくれれば、僕は幸せ……。それで、たまにこうして僕を包んでくれれば……」
「たまにで良いの?」
「……出来れば毎日……」
突き上げのインターバルに彼の瞳を覗き込んで白状した。
「ほら、そういうとこ。龍樹さんは自分で分からないうちに俺に嘘をつく。ホントの気持ちを我慢して、俺の顔色をうかがって……」
キュキュッと僕を抱くそこが締まって、僕の遂精を煽る。
「うあっんん。待って、拓斗」
「龍樹さんのは、全部俺に飲ませなきゃだめなんだから……」
腰を揺すりながらリズミカルに締め付けてくる。とても耐えられそうにない、ヘビーな刺激。仕方なく僕は、突き上げの速度を速めて、彼の中に射精した。
脱力した僕を抱きしめて、髪を撫でてくれる。愛しげに、満足げに。彼はまだ出していないのに。
「俺……欲しいってねだられるの待ってたのに……。龍樹さんはもう、俺の身体に飽きたんじゃないかって思った。昨日色っぽい声で俺の名前叫んでるの聞くまで、勉強どこじゃなかったんだから……」
「……大事な試験に集中したいだろうって気を使ったつもりだったんだけど、裏目に出たか……」
「家庭教師面で俺を寝室に取り残したりして。そんなことされたら、抱いてなんて言えなくなっちゃうだろ? 半年分のテスト範囲なんだ。試験前に詰め込み勉強したって意味無いよ。龍樹さん、そういう面でも俺のこと信用してないんだな」
「え、そういうわけでは……」
「俺の頭、久しぶりの禁欲生活で白い血が回ってたから、今度の試験落ちるかもしれない」
「……追試代は僕が払おう」
「金で片付ける気かよ?」
「いや、僕は君の奴隷だからね。それは別件てことで。なにしたらいい?」
「……八十四回」
「え?」
「一日六回二週間分。毎日の分にあわせて、してくれなきゃ許してあげない。分割可能だけどね」
「君が死んじゃうよ?」
「いいもん。龍樹さんに抱かれて死ぬんならいい」
「君にそんなことで死なれたら、僕が生きていけない。死なない程度にがんばるから。それで許してくれる?」
「うん。心を込めて愛してくれなきゃ不可だからね」
「……了解。まずは君のここから始めよう」
先走りを垂らしている彼のペニスを口に含みながら、先のことは考えまいと誓った。
気がついたら一生を共にしていた、なんて人生の終わりが来ればいい。それまでは常にその時その時の歓びと感動に浸ろう。今を幸せに過ごすために。
「ああっあんあん」
再び僕を求めて呼吸し始めた彼のアヌスに慰めの指を与えながら、僕も自分の獣性を解放した。
ああ、旅館に到着が遅れると電話をしなければ……。
お終い
ふりだしに戻る