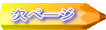12
「さやか、どうした?」
ひろしが先頭を切って庭に出ながら言った。
「なんでもないの」
着慣れているはずの着物の裾が、緩やかな風に何故かまとわりつかれて、どうも歩きにくくて出遅れてしまった。
私は、差し出されたひろしの手をしっかりと握りしめて、立ち止まって私を迎えるひろしの側に寄り添った。
野点の用意がされた庭には、既にお弟子さん達が集まり始めている。
「桜の季節がまた来たね」
ひろしは茶席周辺の騒がしさに背を向け、昔私達の部屋だったところを見おろすように立つ大きな桜の木をふり仰ぎ、ぼそっと呟いた。
その声音には、感慨以上のものが感じられる。
「そうね……」
あの一夜以来、幾度も桜の花が咲いては散っていくのを、私達は眺めてきた。
時には一人で、また時には今のように二人よりそって……。
あの、不思議な瞳の青年達の顔は、記憶の向こうになつかしさで飾られ、ピントのずれた画像となって残っている。
彼らに言われたとおり、確かに私達の身体には、これといって異常なことは起きていない。
しかし、桜を見る度にあの時のことが思い出されてしまう。
「何だか、最近、どうしても彼奴等に会ってみたいような気がしてね」
やはり……。
私も同じように思っていたのだ。
彼らは今も、あの時と同じように若々しい微笑みと遠い記憶を映す冷めた瞳でいるのだろうか。
あれから、二十五年が過ぎ去った。
あの事件以来、ひろしと私は親公認の仲になった。義父も、母も、仕方のないことと認めしまうしかなかったと思われる。
私は、予定通り高水の家を出て、祖父母の家から大学に通った。その時から、父の姓である南雲を名乗っていた。
そうして五年。ひろしが大学を出てすぐに結婚した。
一番上の息子が、もうすぐあの時のひろしと同い年になる。
私達の肌や髪に、少しずつ老いの兆候が現れ始めている今、あの時の彼らの申し出は、少し魅力的に感じられるのだった。
「今、またロイかチャールズが現れて、今からでも仲間に迎えると言ったら……」
「そうね。少し考えてしまうかもしれないわね」
私とひろしは、昔のように目配せしあった。
「だけど、いかない!」
声を揃えて言ってみて、吹き出してしまった。
私達は、私達の時を、精いっぱい生きていけばいいのだ。
哀しそうな瞳で私達を庇ったひとは、それを望んだ筈だから……。
桜が、不意に花を落とし始めた。緩やかな風は相変わらずなのに、まるで、私達の想いを具現して見せているかのような動きである。
優しい吹雪は、私にロイが花びらを舞わせて見せた時を思い出させた。
両手をさしのべて、花びらをすくいとっていたら、ひろしが後ろから私を抱きしめた。その力強さも、荒々しさも、熱い息づかいまで、あの夜のように若々しくて、私まで少女に戻ったような気分になってしまった。恥じらいと、ときめきと、畏れと……、それらがない交ぜになった不思議な興奮が、私の体を駆けめぐる。
「どうしたの……?」
「さやかが、どこか行ってしまいそうな気がした。俺は、今でも桜吹雪は苦手みたいだ。会いたい筈の彼奴等が、もし本当に現れてさやかを連れて行きたいって言ったら……」
「馬鹿ね、行かないって言ったばっかりじゃない」
「うん……」
ほっとしたような声音を出しながら、なおかつまだ不安げな色を瞳に映すひろしは、あの時と同じ純粋さで、私のことを思ってくれているようだ。何となくこそばゆく、けれど、とても嬉しい。私は、頬が弛みそうになり、照れ隠しにひろしを喧噪の方に押し出した。
「ほら、そろそろ行かなくちゃあ。みんな待ってるわよ」
「うん……」
と、言いながら、またひろしが立ち止まった。
「なあに?」
「よく考えてみたら……」
ひろしは唇を一撫でしながら、私の方を睨んだ。
「?」
「俺のファーストキスって、チャールズとじゃないか! さやかがやらしてくれなかったから……」
……。何言い出すんだか、恥ずかしいったらない。幾つだと思っているのだろう、今更止めて欲しいものだ。
「んもう、馬鹿なこと言ってないで! ほら、行きなさいって!」
「けどなぁ!」
「問答無用!」
ひろしの背中を押しながら、私は、ふと桜の木を見上げた。
もしかしたら、金糸の髪の王子様か、亜麻色の髪の青年紳士がいるかもしれないという幻想を、知らず知らず抱いていたのかもしれない。しかし、そこには何の変哲もない桜の木があるだけだった。