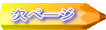10
チャールズが瞳を金色に燃えさせてドアを凝視すると、オーク材の重いドアは、すうっと音もなく開いた。
「あっ!」
その戸口に、金縛りにあったように立ちすくむ吉住さんを見て、あたしは思わず驚きを声に出していた。
タキシードではなく、タートルネックの黒いセーターと、黒いぴちっとしたスラックス。見慣れない格好の吉住さんは、同じ眼鏡をかけていてもシャープな雰囲気に見えた。
「今日は、珍客の多い日だな。歓迎はしないが、入りたまえ」
冷たい笑みを満面に浮かべ、チャールズが誘うように手を広げた。
吉住さんは、首をゆっくり横に振りながら、あとじさった。確かに、あんな招き方されたら、あ、どうもって、入って行くわけにはいかないだろうな。怖いもの。
「やり残した仕事があったから戻ってきてみれば、ひろし君が血相変えて走っていくじゃないか、気になったから追ってきたんだが。君達、夜遊びするのはまだ早いよ。早く帰りなさい」
媚びるような浅い笑いを浮かべた早口で抑揚のない言い方は、今言ってることが方便だって、暗に言っているようだった。
「じゃ、車のとこにいるから。はやくおいで」
吉住さんはきびすを返し、立ち去ろうとした。だけど、歩を進めようとした体制のまま固まってしまった。顔を真っ赤にして、思うように動かない体を動かそうとしている。この場から逃げ出すためなら、何でもしてしまうんじゃないかというくらい。
ふと見ると、チャールズではなく、ロイの瞳が金色に輝いていた。ロイの金色の瞳を見るのは初めてじゃないけど、意図の違うものだと、こんなにも恐怖感をあおるものなのだろうか。吉住さんの怯えは、本物だ。
「入りたまえと、言ったはずだ。君、僕らの話を聞いていたんだろう? ひろしを見かけて追ってきたのなら、当然だな」
ロイは、低い声に更にドスを利かせていて、意外な一面を見せられた思いだった。もう、吉住さんの顔は、泣きそうに歪んでいる。話を聞いていたなら、彼の運命はあたし達以上に危ないのが、わかっているだろうから。
「吉住さん! なんだって来たりしたんだよっ。俺達、何にも変な事しないよ。聞いちまったら、俺達と同じになっちまうんだぞ」
「いや、そうはならないね。ひろし、君は分かってない。先ほど言った処置というのは、あくまでも特別扱いなんだ。そこの男には、当てはまらない」
チャールズは、さらっと言ったけど、それって、つまり………。
ロイは、今度は止める気もないらしい。優しい鳶色の瞳は、金色になったままで、真っ向から吉住さんを睨み据えている。そして、口元だけゆがめて、笑いになってない笑顔を作った。
ただでさえビビッている吉住さんは、チャールズの言葉とロイの笑顔で、もう、本当にパニック状態。
「ねえ、どうしてそんなに意地悪するの? 吉住さん、怖がってるじゃない。どうして吉住さんには当てはまらないの?」
あたしが言ったことが、チャールズにはひどく滑稽に思われたらしい。火がついたような大爆笑をされてしまった。げらげら笑って止まらないチャールズを、笑みを浮かべた瞳でちらっと見やってからロイは、呪縛が一瞬解けた隙に逃げ出そうとした吉住さんを、あたし達の前に弾き飛ばした。
「意地悪とは、参ったね。さやか、あんな格好をした彼が、何故、今現れたのか、分からない? 本当に?」
もう! そんな、先生みたいな口調で言わないで欲しい。分からないわよ。いけない? フンッ!
あたしは、こっくりと頷いた。
「ひろしが三歳の時、付き添いが居たにも関わらず、川で溺れたってね」
ひろしも、あたしも、目を見張ってしまった。
「ロイ、何が言いたいの?」
あたしが尋ねても、曖昧な笑みを向けただけで、ロイはかまわず続けた。
「六歳の時、家にあったブランコがひっくり返って下敷きになった。七歳の時には、階段から落ちて右腕を骨折した。階段には、何故かひろしのお気に入りのおもちゃが置いてあり、その前後には何かを固定してあったような痕がついていた。さやかの誘拐も、同時期だな。八歳の時は、交通事故にあった。十の歳には、駅のホームに落ちて、ホーム下の溝に隠れたおかげで命拾いした。そうそう、中学の時には、チンピラに絡まれて腹を刺されたっけね。後は、道を歩いていて、上から物が落ちてきたことが何件か。……まだあったような気がするな。ねえ、吉住さん」
急にふられて、吉住さんは飛び上がった。あたし達の視線を一斉に浴びて、脂汗をだらだら流している。今のロイの話のどこがそんなに怖いのかな。
「ひろし、君は、今までのこういった出来事を、全て偶然だと思うかい? 一人の子供が遭う災難にしては、バラエティがありすぎると思わない?」
ひろしは、ただ黙ってロイを見つめていた。やがて、開いた唇からは、震えた声が弱々しく吐き出された。
「よく……知ってるな。まるで居合わせたように」
ひろしは、強ばった表情で視線を吉住さんに注いだまま呟くように言った。チャールズが、笑いを残した声で少し苦しそうに言った。
「居合わせたんだよ。気づかれないように邪魔するのには、結構苦労したんだからね。だいたい、実行犯はその度に雇われる不特定の人間だし、接触はほとんどなし。連絡などは、いろんなメディアを利用して、間接的に行われる。依頼主が誰か、実行犯もはっきり把握していない状態だ。恩を売る気はないが、ひろしが知っている事故の倍は企画が実行されていたんだよ」
「さやかを誘拐した奴も、俺がターゲットだったんだろ。俺は、狙われている。それは認めるよ。俺の知らない理由で、俺は、ガキの頃から殺したいほど憎まれている訳だ。全部そいつが仕組んだことだと、そう言いたいんだな?」
すごく哀しそうで寂しそうな表情のひろしを、あたしは、抱きしめてやりたい気持ちでいっぱいになって、ひろしが何度もそうしてくれたように、そっと彼を抱き寄せた。
「ひろし、気にすることないさ。理不尽なその理由は、そこの彼に聞きたまえ。詳しく教えてくれるだろうよ」
チャールズの冷たい言い方は、さっきまでの笑いを、微塵も残していなかった。
「下手な鉄砲もなんとやらだったのかな。まあ、おかげで、少しずつ影が濃くなってきたんだ。そこの、彼のね」
彼らは、吉住さんを、今までの事件の犯人として告発している。あたしとしては、信じがたい事。
あの、親切な人が?
なにかの間違いであることを、吉住さんの口から聞きたかった。ひろしだって、同じように思っていただろう。
だけど。
そこで、見た吉住さんは、二人の言葉を、表情で肯定していた。
吉住さんは、今まで見た事もない程、恐い顔をしていたの。憎しみや、恨みや、そういった、どろどろしたマイナスの感情でつくられた顔。いつもにこにこして優しいあの吉住さんと、本当に同一人物なんだろうか。
「なんで、あんたが」
ひろしの声を聞いたとたん、吉住さんの顔が、さらに憎々しげに歪んで、ひろしの方に向けられた。首をひしゃげたように傾げ、ものすごくバランスの悪い立ち方をして、ヒステリックな笑い声をあげている。眼鏡越しの瞳は血走り、必要以上に見開いて、ひろしを睨み殺そうとでもしているみたい。
「どうしちまったんだ?」
ひろしは、あたしを自分から引きはがして、距離を置いた。あたしへのとばっちりを避けるつもりらしい。さっき、あたしが言ったこと、分かってるのかしら。
ロイが、嫌悪感を露にして、口を挟んだ。
「ひろしを今日こそ殺そうと追ってきたんだろう。さやか、君の友達に対しても、彼には責任が、ありそうだな。彼は、チャールズがマークしている真ん前で」
「るうううううううぅっ!」
吉住さんが、跳んだ。
手には、ぎらぎらした大きなナイフ。登山ナイフって奴。ひろしの方へ跳んだの。
がすって音がして、その後、影が固まった。
「ロイ!」
チャールズが、吼えるように叫び、固まりに向かっていった。次の瞬間、吉住さんが、暖炉の方にたたきつけられた。
残った固まりは、ひろしに抱き留められたロイ。
ナイフは、ロイの背で柄だけを見せていた。ひろしは、ロイを抱いたまま凍り付いている。チャールズの手がロイをはぎ取るまで、ひろしは動かなかった。それから、自分をかばったロイを凝視し続けた。
のろのろとした動作で、吉住さんが、起きあがろうとしたのだけど、チャールズの一瞥で、また、壁にたたきつけられた。
「吉住さん! 何で? どうしてなの?」
そして、なんで、ひろしを?
憎しみの視線は、未だにひろしに向けられている。
あたしの質問には、暖炉の前のラグに、うつ伏せの状態で寝かされていたロイが答えを返した。
「彼…は、…ずっと、裏切っ…てい…た。…君…達…や、両…親、高…水流…の人…たち…を……」
「ロイ! 無理するな!」
ロイの背から、ナイフを抜き取り、傷のあたりに手をかざしながら、チャールズが叫んだ。背中の左側にある傷からは、だくだくと血が吹き出してくる。ロイは、泣きそうに歪んだ顔をして自分を見つめるひろしに向かって、微笑みかけた。青白く弱々しいのに、瞳の光だけは、凄惨なほど力強い。
ゴフッと血の固まりを吐きながら、さらに何か言おうとするロイを、押さえつけて、チャールズが後をとった。
「さやかを誘拐させたのも、彼だ。……多分ね。ひろしの事故には、何故かいつも、君達に近しい人の影がちらついていたんだ。確証がなかったから、ぎりぎりで庇うことしかできなかったが。そして、君の友達……。ひろしや、さやかを狙っていると思っていたから、ちょっと油断してね。美代子って娘には悪いことをした。かばえなくて……。てっきり奴は君たちを狙うと思っていたんだ。肝心の君達が、反対ホームにいたのには驚いたよ」
「美代子? じゃあ、やっぱり、美代子の相手は」
あたしの質問を、ひろしの声が、哀しそうに遮った。
「なんで……。嫌われているとは、思っていたけど、そこまで…? ……なんでだよお!」
ひろしは、吉住さんのことを好いてはいなかった。でも、人にそこまで憎まれていたって事自体、とてもショックな事よね。だから、何故? と尋ねてしまう。
改めて壁にたたきつけられた吉住さんが、よろよろと立ち上がった。
「しつこい奴だな」
言葉とほぼ同時に、また吉住さんは、見えない何かによって床に押さえつけられた。
あたしは、チャールズに好かれてないとか考えてたけど、彼に本気で嫌われると、吉住さんみたいな扱いされるのね。それっくらい、今の言い方は怖かった。
吉住さんは、もう、取り繕うことはやめにして居直ってしまったのか、その場であぐらをかいて座り込んでしまった。ぐるりと、チャールズやロイ、あたし達を見回しながら、さっきみたいな狂った高笑いを響かせる。
「ああ、そうだよ。みーんな俺がやったんだ。よくもまあ、やることなす事邪魔しやがって。お前らみたいなガキどもに、俺の人生めちゃくちゃにされてたまるかよ!」
……きれてる。
「吉住さん……? あたし達が、何したって言うの?」
「何しただと? 馬鹿言ってんじゃねぇ! お前らがいるだけで、迷惑なんだよ。人のこと、生意気に顎で使いやがって。ひろし! お前なんか生まれてこなきゃよかったんだ! お前さえいなければ……!」
唇を震わせながら、吉住さんを凝視するひろし。吉住さんの言い分は、なんだかあんまり理不尽で、かえって絶句してしまった感じ。
「ひろしが生まれなければ、俺が高水流を継いでいた。家元なんざ、どうだっていい。だがな、あの、土地、債権、支流から入る上納金、どれをとっても魅力的だ。一生こき使われて終っちまった親父の分まで、この俺が戴く予定だったのに。家元の奴、ひろしが生まれたとたん、掌返しやがって。
いいか、俺はな、お前らとは出来が違うんだよ。本当なら、あんな所でくすぶってる必要はないんだ。……俺は、飼い殺しにされたんだ! お前の親父になっ<」
もっともらしく人差し指を突きつけられて、あたし達は、呆気にとられてしまった。
だって、吉住さん、それは被害妄想だよ。
「あたし達、そんなつもり全然」
「うるせぇ! そんなつもりもどんなつもりも、お前らがいるだけでむかつくんだよ! このくそガキども<」
聞く耳持たずって感じ。吉住さん、完全にキレてる。
義父は、決してそういう扱いはしてなかった。確かに、高校、大学と、義父が学資を出していたけど、それは、あくまでも好意だったはずだ。吉住さんが望む進路を邪魔するつもりも、学資を盾に飼い殺しにするつもりもないと、母に話していたのを、あたしは聞いている。
まあ、出すほうの気持ちは別にして、それを枷と感じる気持ち、分からないでもないけど。いつもにこにこしていた顔の裏で、こんなに憎しみを募らせていたなんて、嫌と言えない質の吉住さんは、少しずつ狂気に近づいていったのじゃないかしら。
それに、この、ものの考え方。
義父が、もし本当に、高水流を継がせる予定だったとして、ひろしが生まれなくても、いずれは変更したんじゃないかな。
「美代子っ! 美代子を、何で? あの娘は吉住さんのこと、本当に好きだったのに! 何で、死なせたのっ?」
吉住さんは、ひゃひゃひゃって、笑い出した。
「なっ、何がおかしいのよっ!」
「美代子なぁ、よかったよ。ありゃ、いい女だ。ちょっと声かけてやったら、ホイホイついてきてな、ちょっと口説いてみたら、すぐ脚を開いたよ。いろんな事教えてやった。そのたんびヒイヒイいい声で啼いたぜ。だがな、それだけじゃダメなんだ。俺には釣り合わない。ガキが出来たから結婚してくれなんてな。てめぇがまだガキのくせして、計算高い所なんか、娼婦みたいだよなぁ。そうだな、さやか、お前ならいいぜ、結婚してやる」
格好つけてあたしの方に人差し指を突きつけ、にやりとした。
「なっ! 冗談じゃないわよっ! 誰が!」
人のことなめてんの、自分じゃない! 馬鹿にするのもいい加減にしろってぇのよ!
ひろしは、相手にするのは止めだっていうように、吉住さんに背を向けてしまった。それが、吉住さんを煽ったようだ。彼は、ぎりぎりと歯ぎしりをしながら、ゆらりと立ち上がった。
「ほんとぉーに、やなガキだなぁ、おまえって」
「あんたに言われたくないな。吉住さん、あんた、すっげーやな奴だよ。思ってた以上だ。ガキの頃から、何となくだが、あんたの敵意みたいなの、感じてたけど、まさか、これほど腐ってる奴だなんてな。自分に何か問題あるのかと思って悩んでた俺が、馬鹿みたいじゃないかよ。情けねーよ」
ホントに、煽ってるみたい。でも、言ってることは、多分本気。ひろしの敵意は、吉住さんが誘ったものだったんだ。じゃあ、横で見ていて気がつかないあたしの方が、もっと間抜けってこと? 参るわね。
怒りに駆られた吉住さんは、もう一度ひろしに飛びかかろうとしたけど、失敗に終わった。チャールズと、ロイが、両方とも金色の瞳になって、吉住さんを睨んでいたんだもの。動けるわけなかった。
チャールズが、ゆっくりと吉住さんに向かって歩き始め、それにつれ、吉住さんの表情が蒼く変わっていく。
「な、なんだよ!」
おどおどとした吉住さん。チャールズは、傍目にも全身冷たい殺気に満ちていて、親しみやすさを完全にどっかへ置いてきてしまったようだ。
「本当なら、ロイの傷を治すために協力してもらうのだが、君のを戴いたりしたら、ロイが発狂してしまいそうだからな」
そう言って、優雅に片手をあげたチャールズは、吉住さんの顔を覆うように鷲掴みにした。少しづつ吉住さんの体が持ち上がっていく。チャールズの手で吊り下げられた吉住さんの顔はよく見えないけど、チャールズの指が食い込んでいくのは見えた。
くぐもった悲鳴が、だんだんと大きな絶叫に変わっていく。
「ちとやっかいだが、あまり時間がない。君には死んでもらうよ。欲を出して、こんな所まで来なければよかったのにね」
口振りはいかにも残念そうだったけど、声には楽しいっていうリズムが含まれていたみたい。
それは、まずいと思うわ。第一、あたし、そんなところ見たくない。美代子のことですごく憎らしいって思ってるけど、やっぱり、チャールズが平気で殺せるなんて思いたくない。
「ちょっと! 待って! ねえ、ホントに殺すの? 止めてよ。いくらなんでも、殺すなんて…」
あたしの声に、チャールズはゆっくり振り返って微笑んだ。
「気絶しちゃった」
チャールズの足下に、吉住さんが崩れ落ちた。
「ホントに殺すと思った?」
くすくす笑いながら吉住さんをかつぎ上げると、柱の所に放り出し、ロープでくくりつけた。
「どうするの?」
「……死んでもらうよ、もちろん。でも、ここでじゃない。こんな奴でも、いますぐ死んだら、困ることあるだろう? 君達の親だって、納得できないだろうしね。だけど……」
そこまで言って、チャールズは瞳をギラつかせてあたしを睨んだ。
「後は、口出し無用だよ。『何も殺さなくても!』ってね。……君達は言うだろうけど、私達には私達のやり方がある。いいか、これ以上この事で何か言ったら、君達も生かしてはおかないからね。くれぐれも言っておくが、先ほど言った処置はロイに免じての事だ。不都合があれば、すぐさま撤回するからな!」
基本的にチャールズの声は、ドスの利くタイプの声ではないと思うんだけど、全身からわき上がる圧迫感が、あたし達から声を奪った。
どうしよう。吉住さん、殺されちゃう。美代子にしたことを償わないまま死なせてしまうなんて。チャールズ達の掟だか都合だか、なんだか知らないけど、あたし達が見て見ぬ振りすれば、それは私刑と同じ事になってしまうし……。
でもでも、どうすればいいの?
ひろしの服をつかんだまま、あたしは吉住さんを見つめることしかできなかった。
「この時代に、誰があんた達のこと言って信じるかい? あいつを抹殺する必要なんてないと思うよ。言って騒げば、即、病院送りだよ。きっと」
「そう思って油断して、仲間を何人か消滅させられたことがあるんだ。確かに、世間は信じないだろう。だが、そこに我々のことを知り、なおかつ敵対する者がいるなら、そいつは我々のうちの何人かに打撃を与えることが出来る。
仲間にしたいと思い、迎える人物は、そうそう居るもんじゃない。仲間はみんな大切なんだ。私達にとってはね……」
一瞬遠い目をしたチャールズは、すっときびすを返してサイドボードの方へ向かった。もう、吉住さんについては受け付けないと、その背中が言っていた。
もどってきたチャールズの手には、綺麗なベネチアグラスのシェリーグラスが二つと、精巧な細工の施された、冷たい光を放つ短剣があった。
テーブルに、そっと並べられたグラスは、ほのかな暖炉の明かりを映して、いろんな淡い光に揺らめいた。
「綺麗なグラスだね。高そう」
「十六世紀のだよ。私がまだ人間だった頃、屋敷で使っていたものだ。これには、色々な思い出が染み着いている。値段はつけられんな。……儀式には、もってこいだろう?」
言いながら、チャールズは持っていた短剣で、自分の手首を切り裂いた。ぱっくり開いた傷口からは、見る見るうちに真っ赤な血がもりあがってきた。二つのグラスに滴る血を盛り分け、一定の量を満たすと、傷を軽く指で押さえた。それだけで、どくどくと流れ出していた血は止まり、血潮の跡を残して傷はふさがってしまった。
薄青いグラスには、鮮血が黒ずんだ色を映している。
「邪魔が入って遅くなったが、始めよう。儀式と言っても、これを君達が飲めばそれで完了だ。一気にやってくれたまえ!」
と、言われても、人の血飲むなんて……。
渡されたグラスを見ると、ありきたりな色の血が、とっぷんと緩やかに揺れた。生臭いような、ちょっぴり青臭いような血の臭いが、鼻を突いた。……うっぷ。
「これ……、飲むの?」
「我々の種族は、生殖によって増やすことは出来ない。血液中の特定成分により、人間を変質させて仲間にするんだ。ウィルス感染のようなものだな。君達は、完全な変質を起こすほどではない量で、不顕性感染患者となるわけだ。いわゆる、キャリアーだな」
自分の血を病原菌扱いして、なおかつ人に飲めだなんて、チャールズも人が悪いな。よけい、飲み難くなっちゃう。
ひろしも、嫌そうな顔して、グラスとにらめっこしていた。
「後から、突然に発現してしまうことは?」
「多分ない。保証は出来ないが、変質できる量じゃないんだ」
ひろしの冷静な問いに、チャールズは悪戯っぽく答えた。あたし達の反応を楽しんでるように見える。
いつまでも、あたし達が躊躇していたら、チャールズが、苦笑しながら言った。
「早く飲んでくれ! 鮮度が落ちたら、僕はもう一度手首を切らなきゃならない。いくらすぐ治るったって、切れば痛いんだから」
ひろしは大きく溜息をつくと、
「しゃーない、トマトジュースだと思っていくか。ホントに大丈夫なんだろうな?」
と、言って、すばやくチャールズとロイを見回し、鼻を摘んで一気に飲み干した。
「うえーっ、血の味がする。二度と、こういうのはご免だぜ!」
ひろしってば、あたしはまだ飲んでないのにぃっ。トマトジュースなんかに例えないでよね。一生トマトジュースを飲めなくなっちゃうじゃない。
「さやか、お願いだから、早くして」
チャールズの方を思わず見たら、金色の瞳に捕まってしまった。あたしの腕が、ゆっくりと持ち上がり、鼻を摘んだ。グラスを口元でゆっくりと傾け、同じくコントロールされた唇が、グラスの中身をすすり始めた。全部飲むまで、この呪縛からは逃れられないのかしら。口の中に、ホンの少し甘く、しょっぱい血液特有の味が拡がった。
やだやだやだーっ。自分で一気飲みした方が良かったよぉ。
「チャールズ、ひどいよ……お……」
抗議の声を上げようとしたのだけど、何故だか急に、何もかもが遠くなり始めた。
「なん…で? …影…響は…無い……って言っ……たは……ず……………」
既にひろしはソファに倒れ込んでしまっている。
あたしは、ものすごく不安になったのだけど、もう、体に力が入らなくなってしまっていた。椅子の中にじわじわと沈み込んでいくように感じて、やがて目の前が真っ暗になった。
「大丈夫、目覚めたときは何もかも終わっているはずだ。君達は、普通に暮らしていけばいい」
穏やかなチャールズの声が、しみこむように遠くから聞こえてきて、あたしは目を閉じた。