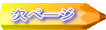9
あたしは人の言い争う声で目覚めた。なぜか体の方は金縛りになったように言う事をきかない。仕方がないので、そのまま耳だけに意識を集中した。
話声は、かなり早口な英語。ロイとチャールズの声だ。立場がいつもと逆転したみたいに、ロイがチャールズを責めている。意味はよくわからないけれど、ムードはかなり険悪。
しばらく沈黙の後、重々しい靴音が近づいてきて、あたしの側に誰かがかがんだ気配がした。次には、冷たい手が、優しくあたしの額にかかる髪をかきあげた。
この手?
あたしは突然、この手があの夢の手と同一である事を知った。なぜかは解らないけど、確信があった。誰の手かもなんとなく判っていたけど、確かめねばならない。
重い瞼を努力して開くと、目の前には、心配そうにのぞき込んでいるロイの顔があった。
やはり、ひろしの言った通り。
「さやか、すまない。こんな風にするつもりはなかったんだ」
ロイの気づかわしげな柔らかい声は、心からあたしを心配してる感じだった。
「……ここ……は……?」
尋ねながら、ロイに助けられてやっとの事で身を起こすと、あたしは辺りを見回した。
あたしが寝かされていたのは、暖炉の側の寝椅子。暖炉には、今にも消えそうな火が力無く瞬いている。
窓際の大きな一人用ソファには、チャールズが腰掛けていて、外を眺めている。その姿にいつもの艶やかさはなく、とても寂しげで、あたしはいつもの彼よりも親しみを感じてしまった。
ああ、ここは例の洋館だ。ロイが倒れたとき、運び込んだ部屋。あの時、ロイを寝かした寝椅子に、今あたしがいる。
「あたし……、どうなっちゃったの?」
ロイは、本当に返答に困っていた。
「君を、さらってきたんだ」
チャールズが声高に言うと、ロイは顔を背けてしまった。
「君を、一緒に連れていく」
「やめてくれ、チャールズ」
ロイが低く、唸るように言った。
「彼女は知っているよ。十年前の事。ひろしが見ていたんだ。もう、ぐずぐずしてはいられない」
ロイは、「十年前」というところで、端の目にも明らかなほど、びくっとした。あたしの覚えていない事で、もっと何かあったに違いない。頭の隅で、何かが見えたように気がしてるんだけど、どうもうまく浮かんでこなくて、あたしは苛立っていた。
「二人とも、何の事言ってるのか、あたしに解るように言ってよ」
二人は顔を見合わせ、ロイの方が大きく息をついて話し始めた。
「何から言えばいいのか……。確かに僕たちは、十年前も君を知っていた。君の……、ひろしの記憶にある通り、今と同じ姿で存在していた」
あたしは、そこまで聞いて息を飲んだ。わかっていた事でも、本人から認められると、そこに事実の重さが加わる。ありえない事を、今彼は、自分から認めたのだ。では、彼らは一体何なの?
あたしの顔、多分、今は畏れを表に出してると思う。
チャールズがそれに気づいて、フッと笑った。この世の物とは思えぬ妖艶な微笑み。
「僕たちが何なのか、実を言うと、僕らもよくは解らないんだ。ただ、いちばん近い形としては……」
チャールズのブルートパーズが、冷たく煌めいた。
「君達の言う、吸血鬼……だな。おや、……君、やっぱり、って顔してるね。
ああ、ひろしが吹きこんだんだな。彼は、実に良いナイトだ」
「黙って、チャールズ、頼むから」
ロイが、苦々しげに言った。言葉付きよりも、ずっと高圧的な語気に、さすがのチャールズも口を噤んだ。いつも穏やかな人って、怒ると結構迫力なのよね。
「さやか……」
向き直ってあたしを見つめたロイの瞳は、あくまでも穏やかな光をたたえていた。
「僕が怖い?」
あたしは、即座にかぶりを振った。
「ロイは、ロイだもの。今までの事、全部が嘘だった訳じゃないでしょ。びっくりしたけど、怖くはないわ」
ロイの瞳をのぞき込むようにして、あたしは言葉を接いだ。真意を見極めたくて。
「あたしを殺すわけじゃないでしょ?」
ロイは、またかと言うような、やりきれなさそうな顔をして、すうっと目を閉じた。次に、クッと目を見開いたときには、声に断固とした調子が加わっていた。
「僕らは、普通、人を殺したりしない。殺す必要はないんだ」
「嘘だっ<」
突然介入してきた大声に、あたし達は、三人揃って振り返った。
「ひろし?」
大きく肩で息しながら、ひろしが扉口に立っていた。タキシードのまま、家から走ってきたらしい。つかつかと大股であたしのところに近づいてくると、横にいたロイに激しい怒りのこもった一瞥をくれ、彼を押し退けてあたしの側に跪いた。そして、あたしの手を取り、まるで幼児をあやすような口調で言った。
「さやか、帰ろう。な。」
黙って見ていたチャールズが、クスッと笑った。さもおかしそうに笑うその様は、第三者のような、他人事として受けとめている感じが強かった。
「いきなり入ってきたと思ったら、君のナイトはせっかちだな、さやか」
前から感じていた事だけど、チャールズって、あたしの事、よく思ってないみたい。今の言い方も、そこはかとなく意地悪さが含まれている。小馬鹿にした調子が、わざとらしいくらい強調されて。
ひろしも、むっとしたらしく、すごい勢いで怒鳴った。
「不法侵入なら、てめぇの方が上手だろ。いったい、御園さんの他に、何人毒牙にかけやがったんだ!」
言った刹那、チャールズの瞳が一瞬青白く燃え上がり、ひろしを真正面から貫いた。そして、彼が小首をクイッと動かしたと同時に、ひろしは吹き飛ばされて、壁にたたきつけられていた。本当に、指一本触れなかったのに、まるで思いきり殴り飛ばされたみたい。
「不作法は止めたまえ! 人の家に招かれもせず来たあげく、暴言を吐くなんぞ、次期家元のすることじゃないな」
冷たいチャールズの声は、その態度ほど怒っているようには響かなかった。あたし達にしてみれば、それでも十分圧倒されたけど。
あたしは、思わず駆け寄って、ひろしを抱き起こしていた。
「ひろしっ> だいじょうぶ?」
ひろしは、首を振りながら立ち上がった。あたしをかばうように、片手で自分の背後に押しやった。
「…ってぇー。さやか、今の見たろ。あいつら、普通は殺さない、って言ったよな。やれば出来るってことなんだぜ。だから危ないって言ったんだよ」
ロイが、困ったなという顔で、子供をあしらうように言った。
「ひろし、出来ないって事と、しないって事の違いも解らないのか? 僕らは、したくないんだ」
「そっちの貴族野郎は、したいかもしれないだろ」
その口の悪さが、自分の寿命を縮めているの、ひろしは解ってるのかしら。さっきみたいのをまたくらったら、やっぱりただじゃ済まないと思うんだけど。
あたしの予想に反して、チャールズは笑いだした。得意の冷笑ではなく、屈託の無い笑い方。ロイでさえ、驚いた顔で彼を見つめている。
「確かに。確かにそうだ。僕は、したいかもしれない」
にこやかな笑顔は、今までよりも数倍は、チャールズを魅力的にしていた。天然の氷を思わせるブルートパーズの輝きから、友好的なサファイアブルーに落ちついた瞳を、まっすぐ向け近づいてきたチャールズを、ひろしは息を飲んで見据えていた。
「なっ、なんだよっ」
チャールズの真っ白で優しげな手が優雅に踊り、ひろしの顎をすうっと捕らえた。
ひろしは、必死にあらがっているにも拘らず、一見優しげに見えるチャールズの、指一本ですら微動だにも出来ないでいる。ひろしの目は、近づいてくるチャールズを、恐怖を露にして凝視している。
「なにするつもりっ? やめてよっ! ひろしに変な事しないでっ」
気がつけば、あたしは叫びながら、チャールズの腕にかじりついていた。けれど、チャールズは、あたしをその腕にぶら下げたまま、ゆっくりとひろしに顔を近づけ、震えている唇に優しく薔薇色の唇を重ねた。
チャールズが身を引いた途端、ひろしの体から一気に力が抜けていくのが、端からも感じられた。
「やだあっ! ひろしっ、しっかりして!」
ゆっくりと足元に崩れ落ちるひろしを、あたしは抱きしめた。チャールズの笑い声が、覆いかぶさる様に背後で響く。
「安心して、ただのキスだから。僕はこの乱暴者が気に入ってるんだ。ただ殺しはしないよ、さやか」
あたしはひろしをかばうように、ただ、抱きしめていた。
「冗談が過ぎるぞ、チャールズ。……さやか達も落ち着いて欲しい」
ロイは、いつもの穏やかな声音に苛立ちの和音を乗せて、あたし達の間に割って入った。
「まず、君達の友人の死に関して、僕たちには何等関係はないと断言しておく」
ひろしはそれを聞くと、反抗的な視線をロイに送ったけれど何にも言わなかった。沈黙は金なりって言う事を学んだらしい。
「ご期待に添えず申し訳ないのだが、本当なんだ」
と、チャールズ。肩をすくめて言う調子は、人を喰ったような能天気さがあって、かえって怖い感じ。とっても綺麗なのに、もったいないほど綺麗なのに、ううっ、……歪んでるよぉ、このひと。
「あんた、このあいだの日曜日、御園さんと駅前を歩いていたじゃないか。それに、御園さんの死んだ日も同じホームに居たよな」
ひろしの突っ込みに、チャールズは余裕の微笑みで答えた。
「誰のことかと思えば。貧血起こした彼女を確かに、病院まで送ったが。いずれも、たまたま居合わせただけでね、目標は別にあった。ある人物を尾行していたんだよ。僕にだって、好みも、選ぶ権利もあるんだ。送り狼になるほど不自由はしていない」
「チャールズ! いい加減にしてくれ< 遊んでる余裕はないんだ」
ロイが、吐き捨てるように言った。チャールズは、片眉を上げて沈黙したけれど、その瞳には、冷笑的な光が宿っていた。そして、再び口を開いたとき、その口調は一変していたの。
「仰せのとうり。仕事は手っとり早く済ませた方がいいな。では、ロイ、さっさと終わらせてしまおう。どうも、私にはこの国の気候は合わないようでね。そろそろ故郷に帰りたいのだ。……君がやりにくいと言うのなら私が手を下してもいいがね」
ロイは、チャールズが『わたし』と言った時点で、目に見えて青ざめた様だった。
ひろしの手があたしの手を握りしめた。あたしも思わず握り返していた。ロイの顔つきを見ていたら、そうしたくなってしまった。周囲の空気が一変したような気もする。その冷たく重苦しいムードは、妙にチャールズの美しさを際立たせていた。
「チャールズ……。待って! 僕の仕事だ。最後まで僕に……」
ロイがあとじさりながら、あたし達を背にかばうように立った。ひろしの手に力が入り、手の痛みにあたしは一瞬息をつまらせた。
だけど、ロイの言葉が空気をもとに戻した。チャールズは、ふわりと優しく笑って………。
え? 笑って?
この人って一体どういう性格なの?
「邪魔が入って、論点がずれてしまったな。順を追って話そう。ひろし、しばらく黙ってロイの話しを聞いてやってくれないか。……長くなるから、座って楽にしたまえ」
ロイが言っていた『保護者』という言葉が、不意に頭に浮かんだ。今のチャールズは、まさしくそれ。おじさん臭い話し方もそうだけど、青年の仮面を脱ぎ捨てて、多分本来のものであろう年齢に見合った表情を浮かべていたの。顔というのは、その人の情報を結構いろいろ見せてくれるものね。いったい、本当は幾つなんだか。
あたしたちは、勧められたソファに並んで座った。チャールズは、最初に座っていた一人がけに腰を落ちつけたけど、ロイは立ったままだった。
ロイは、すうっと息を整えるようにして姿勢を正すと、あたし達の方に向き直り、語りだした。ようやく嫌な仕事をかたずける為に重い腰をあげたという感じ。
「僕らの正体を知らせたのには、理由がある。まず、さやか。君のお父さんの事から……」
「親父の?」
ひろしが不思議そうに声をあげた。ロイはやんわり笑みを浮かべると、頭を振った。
「いや、死んだ本当のお父さんの事だよ」
あたしとひろしは、顔を見合わせてしまった。何だか、またややこしくなりそうな……。
「僕は、……僕はね。さやかのお父さんを死なせてしまったんだ」
「!」
急に。急に何を言うの?
ひろしの腕が、あたしの肩にまわされ、あたしの戸惑いを、ひろしが口にした。
「事故で亡くなったって、聞いてるぞ」
「事故だった。確かに。十五年前に起きた事故だ。……でも、僕さえいなければ、起きなかった事故だ。…………僕さえいなければ!」
ロイの声が震え始め、あたしは聞き取るのに集中しようとしたのだけど、話の展開についていくのを苦痛に感じ始めていて、出来なかった。無意識にあたしは、ひろしの胸に顔を埋めて、逃避の体制にはいっていた。
ロイの震える声は、いつものような心地よさを感じさせない。
お父さんの死に責任があるって、本当なの?
「じゅ……、順を追って話そうと思うんだが。うまく言えないもんだな。
……つまり、その、さやかのお父さんが走らせていた車に、僕は飛び込んでしまったんだ。僕を避けようとしてお父さんはハンドルをきり、スリップして、崖から転落してしまった」
「飛び込んだって言ったな。その時、もう、不死身だったんだろ? それなのに、自殺でもするつもりだったのか? それとも、さやかの父親を狙って、わざと、か?」
ひろしは、あたしをきつく抱きしめ、声に非難を込めてロイを追求した。
「狙ってなぞいない! 信じてくれ!」
とんでもないと言うように、狼狽した声をあげたロイ。と、それまで黙っていたチャールズが、いつになく暖かい声音でもって割って入った。
「ロイは、その前にも何度か自殺を試みている。実際、難しいし、愚かな事だが、全然不可能と言うわけでもないんだ。我々は、損傷がはげしければ、消滅する事もありうるのでね。回復が早く、肉体の衰えがないだけの話しなのだ。
ま、限りなく不死に近いことは確かだがね」
「待って、チャールズ。何度も言っただろ、あの時はそういうつもりじゃなかったんだ。本当に自殺のつもりで飛び込むなら、車じゃなく電車にしてるよ。その方が、まだ可能性が高いからね。
いや、だから僕は、単に、あの道に降り立っただけだった。真夜中だし、車の通りもないと思って。あの日は、雨で、人通りもないだろうからと、空中散歩にでたんだ」
「飛べるのか?」
ひろしの問には、チャールズが軽く肩を竦めて答えた。
「少しなら」
「……とにかく。転落した場所に降りてみたら、まだ息があったんだ。急いで車から引きだしたんだが、下半身が潰れていた。直後に車が火を噴いて……。その時の破片が、彼の胸に刺さって絶命したんだ」
聞きたくないと思った。
そういうふうに、お父さんが死んだところを詳しく聞きたいとは思わなかった。痛みが、お父さんの苦痛が、伝わってくるような気がして。だけど、きっと、今あたしが想像できるものよりずっと痛いんだろうと思うと、胸が苦しくなってくる。
それにしても、チャールズが言っていた、あたしをどこかへ連れていくという話と、お父さんと、何の関係があるというの?
ロイはふいとその場から立ち去り、またすぐに戻ってきた。その手には、薄汚れた包みが納まっている。
「彼は、何度も『さやか』と呼んでいた。手には、これが握りしめられていたんだ。僕はこれを持って立ち去った。名乗り出る事は出来なかった。僕には、そこにいた理由を説明する事が出来ないから」
ロイから包みを渡され、あたしはそれをただ見つめていた。
「彼の言っていた『さやか』を、僕は探すことにした。彼の無念そうな表情は、今も忘れる事が出来ない。僕は、彼の心残りを代わりに渡したいと思ったんだ」
包みには、どす黒い茶のシミが、点々とついている。血みたい。
軽くて、柔らかい感触。お父さんが最後に持っていた物。
「……開けてみれば?」
ひろしのいたわるような優しい口調にうながされ、あたしは包みを開いた。
兎のぬいぐるみ………。
顔も覚えていない、お父さんが、多分あたしに買ってくれた最後の品。
喉元が苦しくなって、あたしは兎を抱きしめ、顔を伏せた。瞼も熱い。肩に回されたひろしの手に力が入って、あたしはまたひろしの胸に抱かれた。そうしていると、少し楽になる。ひろしが居てくれて良かった。本当に。
「事故処理を陰で見ていて、君の所在もすぐ判った。けど、それを渡す事は出来なかったんだ。出来るわけがなかった。あの場から逃げだした僕が、どうやって渡せるっていうんだ。
……君は可愛かった。お母さんに抱かれて、お葬式の時も、お父さんはどこ? って、聞いていた。まだ二つだったんだ。無理もない。
それから僕はいつも君を見守って来た。お父さんの代わりになれるとは思っていなかったけど、何かの時は影ながら力になりたいと。罪滅ぼしがしたかった。一生見守って、君の幸せを見届けようって……。あの、誘拐事件までは、そのつもりでいたんだ。」
ロイの声は、耳に入って来ては居たけど、頭にはよく入って来ていなかったので、誘拐事件と聞いて、あたしは飛び上がった。
「さやかを誘拐したのは、あんたたちか?」
あたしが訊こうとしたこと、ひろしが先に訊いてしまった。
ロイは、ゆっくりと首を横に振った。
「たぶん………、彼らは、ひろしとさやかを間違えたんだ」
「俺と?」
ひろしは甲高い声で叫んだ。予期していないことに出会って驚くと、ひろしはそんな声を出す。
「さやかがひろしの家へ来て、日が浅かったせいだろうが……、確かに、彼らは、間違えたと言って、焦っていたよ。僕は、さやかをマークしていただけだから、いきさつはよく判らない」
「彼らって? 何者なの?」
「うーん、判らないけど、誰かに雇われたちんぴら…って感じだったな。目的意識は感じられなかった。よりによって、この家をアジトに利用してくれてね……。僕らがさやかをマークするために家をあけていた間に、すっかり空き家として荒らされていたんだ」
ロイは大きなため息をついた。
「できれば、指示をくだした奴を突き止めたかった。そいつを何とかしない限り、危険は何度もふりかかってくる。ひろしが目的だとしても、近くのさやかがどう巻き込まれるか、分かったもんじゃないからね」
「それで?」
「黒幕は誰だったんだ?」
ひろしもあたしも、ロイが次に何を言い出すかに、すっかり神経を集中していた。これからどうなるのかとか、そういうことが念頭から消えていたと言っていい。
ロイは続きを言いよどんで、沈黙した。
「突き止めたんだろう?」
ひろしは、いらいらした口調で先を促した。自分を狙っている人がいると聞いて、気にならない方がおかしいものね。
不意にチャールズが、
「そこからは、私が話そうか? ……その方が、良さそうだな」
と、言うと、ロイは心配そうな顔つきをした。チャールズは、一つ嘆息すると言い足した。
「話すだけだから。言い難いんだろう? 時間短縮に手を貸してやる」
微かに頷いたように見えたロイに代わって、チャールズは、事務的な口調で語りだした。
「私たちは、この家で眠らされているさやかの無事を確認するつもりで、この家に侵入した。自分達の家なのに、変だけどね。その時点で糸をひいている奴は判ってなかったから、行動を起こすつもりなかったし、犯人達を刺激したくなかったんだ。だけど、状況が変わった」
「状況?」
ロイはいたたまれないといった表情で、黙ったまま立ちすくんでいた。
「犯人は二人組だったんだが、一人の方が、さやかに興味を持ったんだな」
「興味って?」
あたしの問に、ひろしは、小さくため息をついた。
「まじでわかんない? そいつはロリコンの気があったってことじゃないか」
「ご明察! 暇を持て余していた上に、さやかは可愛かったからね。薬を嗅がされていたさやかが目を醒ましかけていたとき、奴は、さやかの下着に手をかけたんだ。それから、自分のズボンのジッパーを下ろした」
あたしは、そんなこと全然覚えていないけど、人から聞かされただけで、鳥肌のたつ思いだった。
「……あたし、いたずらされちゃったの?」
チャールズは、肩で軽く笑った。
「ロイが居たのに? まさか」
じゃあ、何であんなに言い難そうにしているのだろう。ロイは、いよいよ顔が青ざめてきて、すごく居心地悪そうにしている。
「ロイは、逆上して奴を殺してしまったんだ。その後、もう一人も、そこを見られたから殺った。ひろし、殺ろうと思えば出来るってのは本当さ。普通そこまでしないがね」
ひろしが拳を握りしめたまま、吐き出すように言った。
「俺だって。俺だったら、やっぱりやっちまう。ぐちゃぐちゃになるまで、ぶん殴って、踏みつけて……。さやかにそんな真似されてたまるか! ぶっ殺してやるっ」
ひろしの過激な口調に驚きながら、胸の奥で喜んでる自分を見つけて、あたしは動揺していた。
けれど、チャールズは、軽くいなして続けた。
「ロイは、初めてだったんだ。殺意を持って、人から生命力を奪い取るのは。以来、彼はベジタリアンでね。それは、今でも変わらない」
「ベジタリアンだと?」
「???」
あたしは、ロイの顔色をうかがった。相変わらずすぐれない顔つきでうつ向いたまま立っている。
チャールズは、すいっと立つと、テーブルにあった花瓶から、薔薇を一輪とりだした。
「よく見てて」
繊細な指先からすうっと伸びる薔薇の花は、みるみるうちに干涸らびて萎びてしまった。
「私たちのエネルギー源だ。他生物の生命力は、こうして私たちに吸収されるんだよ。加減しなければ、このように死にいたらしめることになる。人は、もっとも生命力に富んだ、お手軽なエネルギー源なのに、ロイは、効率の悪い植物との交流を好んでいるんだ」
『効率の悪い』…と、いうところで、ロイはゆっくりと窓際に近寄り、ふっとため息をついて窓を開けた。観音開きのフランス窓を開いたとたん、ざあっと夜風が吹き込んできて、窓際の桜の枝がロイに話しかけるようにサヤサヤとしなった。
「自然は、僕達の存在を認めてくれているから……。人間は、僕らを化け物扱いするけれど、自然の懐は深くて暖かいよ。意に沿わぬもの達を死なせてまで生きていたくはないからな……」
「植物なら喜んで命を捧げるとでも?」
あ、こら。
また、ひろしの嫌みだ。あたしは、ひろしの頭を後ろから小突いてやった。彼は、何するんだよ、ってな目配せしたけど、おとなしく黙っていた。チャールズがすごく真剣な目をしていたからだと思う。
「ロイは、薔薇を枯らしたりしない。生命力を少しずつ分けてもらって、共存を望んでいる。そういう奴だからこそ、私は彼を仲間にした。本人の意志とは関係なく、ね」
最後の方を、自嘲的な笑みでもってしめくくったチャールズは、とても寂しそうだった。
「我々には、一応掟のようなものがあってね。
我々の正体を知った者達については、仲間にするか、死を与えるか、どちらか選択せねばならない。仲間にするということは、親となり、後々その者の行動に責任を持つということだ。なかなか衰えない種だから、やたらな者を仲間には出来ない。我々一族全体を陥れるような種を取り入れるわけにはいかないんだ。ロイは、だから、二人目を勢いで始末してのけた。だが、三人目はできなかった」
「三人目?」
別にとぼけた訳じゃないけど、ぴんとこなかったので尋ねたら、ひろしの瞳が暗い表情を持って、あたしを射抜いた。
「おまえのことだろ、さやか」
「そう。覚えていないかもしれないが、さやかの瞳は、二人の死にざまをしっかり映していたはずだ。我々の掟に、もう一つ、仲間は成人の容貌を持つ者に限る、というのがある。
子供のさやかの始末に、ロイは悩んだ。仲間に出来ない以上、殺すしか道はなかったが、ロイに、さやかを殺せるはずもなかったからね。
そこで、私たちは、賭をした。さやかの記憶を封じ込め、大人になるのを待ったんだ。封印がそのまま解けなければ、何事も起こさない。解けた場合、ロイの伴侶として迎えるか、仲間としてふさわしくない成長の仕方なら、その時点で始末をつけようと……」
伴侶って? その言葉は、あたしの頭の中で、不思議な彩りを持って、ぐるぐると回っていた。
ロイは、あたしのこと、そういう目で見ていたわけ?
門の前で言いかけたことは、この事だったの?
胸の動悸が激しくなる。状況はどうあれ、そういう気持ちは、やはりうれしく感じてしまう。あたしって、見境無いのかな。
あたしは、ロイの表情をのぞき見ようとしたんだけど、目があった瞬間、彼は、窓から見える宵闇に溶け込むようにうつむいて、亜麻色の髪の落とす陰で表情を隠してしまった。かすかに見える口元は、苦渋を表すかのように、これ以上無いというくらい力を込めて引き絞られ、震えていた。
ロイは、あのとき、あたしを迎えることを断念したんじゃないかな。殺すこともできなくて、そのまま帰ってしまった。
言葉通り、今の状況は、彼にとっても不本意なんだわ。
「封じ込められた記憶さえ、そのままなら、僕らは姿を現す必要がなかったんだ……」
「だが、さやかの夢の話を偶然耳にしてからは、行動せねばならなくなった。夢は、封印がほころびかけている印だからだ。残念だよ」
ロイの低いつぶやきを、チャールズが引き継いで言った。
ひろしは、ふるふると身を震わせ、拳を振り下ろしながら怒鳴った。
「伴侶だなんて、冗談じゃねえっ! そんなの、両方ともお断りだぜ。自分たちの都合で決めるようなことじゃないだろっ? さやかの気持ちはどうなるんだよっ、本人の意思は無視するのかよ!」
サファイアブルーの輝きが細められ、フッと笑った。
「そうだね。だが、ひろしの決めることでもない。君だって、さやかを自由には出来ないはずだ。自分の気持ちを押しつけるのは、よくないよ」
チャールズにぴしゃりと言われて、ひろしは、ぐっとつまり、黙ってしまった。そして、チャールズのことを睨み据えた瞳を燃え上がらせ、あたしの手を手探りで手繰り寄せると、ぎゅっと握りしめた。その手が、何処へも行くなと脈打ちながら、あたしに語りかけているような気がして、胸の奥がきゅっと締め付けられ、痛んだ。
ロイが窓辺に気怠げにもたれたまま、あたしの方を見ないようにして言った。
「僕は、さやかをずっと見てきた。さやかが愛しい。ずっと一緒にいたいと思っていた。掟に従って、仲間にしてしまえば、希望はかなえられる。だけど、僕の望みは、僕にとって最も避けたい行為でしか達成できないんだ。優柔不断な僕の態度が、チャールズを苛つかせているのも解っている。そのために、こんな風に、君たちを渦中に放り込むことになったのも……。すまない……。僕は、僕は……、どうしたらいいのか分からない……!」
ロイは力無く窓辺に崩れ落ちた。飛び上がるようにして、チャールズが駆け寄った。
「ロイッ! また、おまえ、断食したな> ほら!」
言うなり、ロイの頚動脈のあたりに荒々しく口づけたので、あたし達は小さく息を飲み込んだ。
チャールズの金糸の髪が、ロイの白蝋のような顔に緩やかにかかり、二人は数十秒そのまま動かなかったのだけど、その光景は、禍々しい、それでいて魅惑に満ちた美しい絵を作り上げていた。あたし達は、ただギャラリーとして、その絵を見つめることしかできなかったの。やがて、青白かったロイの顔に赤みがさしてきて、チャールズは顔を上げたのだけど、そのきれいな顔には、疲労が色濃く浮かんでいた。
ロイが英語で何か呟いた。謝っていたみたい。それを聞いて、チャールズがフッと笑う。二人一緒なのが、すごく自然。
「今の、何をしたんだ?」
ロイが、チャールズに肩を貸して、ソファに座らせるのを目で追いながら、ひろしが尋ねた。毒気を抜かれたみたいな言い方で。
弱い微笑みを浮かべながら、チャールズが答えた。
「不思議な光景だった? 私たちは、生命力を吸い取るだけじゃなく、逆に相手に送ることも出来るんだよ」
チャールズの疲れた笑顔は、かえって暖かく感じる。
「吸血鬼……じゃないのか?」
ひろしの問いに、チャールズは笑みをかき消して答えた。
「そういう名前で呼ばれるのは、ありがたくないな。私達は、人を含めた自然総てとの共存を旨として存在している。いいかい、私達の存在を、自然は認めているんだ。だから、私達はここにいる。認めていないのは、人間だけだよ。そこに異質さを見ると、人は、あり得ないものとしてそれを無視するか、抹消しようという心理が働くようだな」
ひろしが、息をついた。
「本当に、御園さんは関係ないみたいだな。あんたとロイの目を見ていたら、そんな気がしてきた。……仲間にするという表現を使ったよな、あんただって、人間だったんだろう?」
ひろしの突っ込みは、チャールズの痛い所を突いたらしい。瞳が、一瞬青白く燃え上がった後、すうっと光が退いてゆき、暗いかげりをおとして落ちついた。
「人間だったこと? あんまり昔で、覚えておらんな。ただ、一つ言えることは、こうなってからの方が、暮らしが人並みになったってことだ。こんな暮らしでもね……」
くっと笑う、チャールズの笑い方は、とっても哀しげだった。
「あなたは、どうして、そうなったの?」
あたしが尋ねると、彼はゆっくりと頭を振った。
「……今は、私のことを話す場ではない。それよりも、君たちの今後だ。こうして、私達の手の内を明かしてしまった今、私は、ひろし、君にも決断を迫らなければならない。ここで命を絶つか、私達のように永遠の時を過ごすか、だ」
ひろしは、いきなり視線をあたしの方に移すと、低い声で言った。
「さやかと…、さやかと生きられるなら、永遠て奴でもいいかもしれない。だが、そうでないなら、俺は嫌だ。もちろん、今死ぬのもお断りだけどさ。どうしてもって言うなら、さやかだけはそのまま生かしといてくれよ。それなら俺、死んでもいいや」
ひろしが言った刹那、あたしの平手が、ひろしの頬を張り飛ばしていた。
だって、そんなの、ちっともうれしくない。
「ばっ、ばっかじゃないの? 死…死んでもいいなんて。冗談じゃないわよっ。そんなこと言ったって、あたしはちっともうれしくないんだからっ。あんたが死んで、あたしだけ助かったって、ちっとも……!」
ひろしも、ロイも、チャールズまで、目を見開いて、あたしを見つめている。自分でも狼狽するほど、感情に支配されてしまったみたい。
あたし……。
あたし、ひろしが好き。今は認めたくないことけど、ひろしじゃなきゃ、いや。
抱えきれない想いのために、目からボロボロ涙がこぼれ落ちて、止められなくって、自分でも訳分からないこと口走ってる。
「もう、やだからねっ。命なんて、そう簡単にやりとりするもんじゃないんだからっ。お父さんだって、美代子だって、死にたくなかったんだから。ロイだって、言ってたじゃない。残された者も不幸になるって。あたしは、もう、やなんだからっ!」
一人で、べそべそやってたあたしを、ひろしの腕が、優しく抱き寄せた。
「ごめん、さやか……。ごめん……」
ひろしのあやすような声を聞きながら、あたしは、まだ、譫言のように言い続けていた。
「あた……あたしは、どっちも選べない。永遠に生きるって、大好きな人たちに、いつか置いて行かれることよね。そんなの耐えられない。それに、今、あたし達が死んだら、きっと悲しむ人たちがいる。それも耐えられない!」
溜息が聞こえた。空気が動いて、あたし達と、チャールズの間に、立ちはだかるようにロイが立った。
「やっぱりだめだ、チャールズ。僕には出来ない。連れていくことも、殺すこともどっちもできないし、君にもさせない」
ロイの低い声が、静かに、でも断固とした調子で響いた。
「この二人は大丈夫だよ。僕らのことで、騒いだりしない。さやかの言うとおりじゃないか。僕は、同じ思いを二人にさせたくないよ。今まで通り、処分を保留してくれないか、チャールズ?」
「ロイ、お前、それでいいのか? さやかを連れて行きたくはないのか?」
ロイが、不意にあたしの方を見つめた。穏やかな鳶色の瞳が、寂しげに光った。
「彼女の瞳に、僕は映らない。十年前とは、違う。今は、彼女を守るナイトがいる。僕の出る幕じゃない。ただし……」
そこまで言って、ロイはひろしを睨み据えた。ロイが、人を睨むところなんて、初めて見た。チャールズと同じくらい、冷徹で怖い。ひろしが息をのむのが聞こえた。
「状況が変わって、さやかが泣くようなことがあったら、すぐにでも連れて行くよ。その時、ひろし、君は殺す。僕は、今、嫉妬で狂いそうなんだから…」
物騒なことを言った後、ロイは、にっこり微笑んだ。そして、
「せいぜい、幸せになるんだな」
と、言った。
ひろしは、黙ったまま、あたしを抱く腕に力を込めた。
チャールズは、仕方ないと言うように、肩をすくめた。
「ロイがそう言うなら……。だけど、条件がある。ただ君たちを返すわけにはいかないんだ」
「チャールズ!」
「大丈夫。殺しも、仲間にもしないから。長期の保留処置だ。本当に、特別なんだよ、これは。現にロイだって知らない」
「条件て、何だ?」
ひろしが、不安そうに声を上げた。
チャールズは、悪戯っぽく、少年のような笑みを浮かべた。
う、おもしろがってるよ、この人。
「二人が、なりふり構わず命ごいしたら、どうしようかと思ったが、良かった。二人には、少しずつ私の血を受けてもらう。なあに、体質には変化無いほど微量だ。……病気になり難くはなるかもしれんが」
「チャールズ、どう違うって言うんだ? 血を受けるってことは仲間に……」
ロイは、本当に知らないらしい。戸惑いが顔に出ている。
「どっちでもないなら、血を受けると、どうなるって言うんだ?」
ひろしは、案外冷静でいる。
「君たちが何処にいても、動静が私に伝わるのさ。我々に不利になる行動を、君たちが起こした場合、私が直ちに粛正に現れる。解ったかね? それ以外に、実害がないことは、私が保証する」
チャールズの真剣な顔には、信頼に足る誠実さが現れていた。
「いいだろう。あんたを信じよう」
ひろしの発言には、あたしも驚いた。あんなに、うさんくさがっていたのに、変わり身が早いというか。
「ひろし、急に物わかりが良くなって、どうしたの?」
ひろしの不敵な笑いが、あたしを迎えた。
「俺が何を恐れていたか、さやかは解ってないね。さやかを連れて行かれること……、それが一番怖かった。俺にとって、チャールズの申し出は、この上なしの好条件だね」
「や、やーねっ。恥ずかしいこと言わないでよ!」
頬が熱くなってくるのを意識して、つい、突っ張った口調になってしまった。だってひろしったら、すっかり態度が一変してしまって、……やだわ、あたしの気持ち、すっかりバレてしまってるみたい。だからこそ、ひろしが妙に落ちついているんだ。
あたしを見るときの目つきからして、すがるような光は姿を消し、自信を持って、『これは、俺の女だ』って言ってるみたい。
「我々が、すっかりひろしに自信をつけてしまったようだね。さやかの思惑の邪魔になったな」
チャールズの苦笑する姿は、最初の歪んだ雰囲気とはかけ離れていた。
幾つの仮面を持っているんだろう、この人は。どれが本当の彼なのか。
知れば知るほど謎めいてくるけど、どうやら、基本的には思っていたより、やっぱり、いい人らしいってことで………。
「思惑って何だよ?」
あたしの考えは、ひろしの声に遮られた。
「高水の家で、君に恋人面されては困るんだ、彼女はね」
チャールズは、本当に面白がっている。ひろしの不服そうな顔。それにしても、何でそんなに知っているの? ひろしなんて、まだ納得できないって顔しているのに。
「本当に分からないのか? さやかが追い出されるか、誰かの嫁にでも出されたりしたら、自分が一番困るくせに」
今度は、ロイ。ロイの口調は、少し、寛容さを失っているみたい。まあ、今までのひろしの態度から考えれば、当たり前か。
「家元にとって、跡継ぎである君がどれだけ大切か、分からないわけではないだろう? 彼は、一番悪い虫候補がさやかだと分かれば、ためらいなく君から遠く離れたところにさやかを追いやるだろうな」
「そんなこと…! 俺がさせないっ。絶対に!」
「ひろし………」
「何のために今まで、俺が………。俺は、ずっと、やりたいことも我慢して、高水流を継ごうと頑張ってきたんだ。たった一つ、欲しいもののために………」
ひろしが、あたしを抱く腕をほどき瞳に熱い炎をたたえて、あたしを見据えた。
「さやかをとるために………。
親父の奴、俺の気持ちはとっくに気づいてたよ。さやかが欲しかったら、実力で家元の座を勝ちとれって。さもなきゃ、認めないって言ったんだ。
俺、頑張ってたんだぜ。だけど、俺が、いくら家元になったって、さやかが俺を選んでくれるかどうか、分からないよな。そう思うと、居ても立ってもいられなくなっちまったんだ。ほんのちょっとでいい、確証が欲しかった。俺のやってることは無駄じゃないって、信じたかった………」
「サッカーやめたのも、そのせい?」
小さく頷くひろしは、幼い頃の素直な表情を浮かべていた。
あたしのために…………?
微熱で冒されたように、あたしはクラクラしてきた。
「ひろし………。あたしのためだけなら、好きに生きてよ。御義父様の言いなりになんて、ならないで」
だって。そんな生き方耐えられない。あたしは、ひろしが自分で道を選んだと思っていたから。あたしのために好きなこと我慢するなんて、いけないと思う。
「さやか、言わないで。今までの俺を、否定しないでくれよ。俺、ある意味では、親父の言葉が、よりどころだったんだから、頑張れば、さやかが手に入るって、信じていたかったんだから」
ひろしの言葉を遮るように、手をたたく音が聞こえた。はっとして振り返ると、チャールズが優しい微笑みを浮かべ、こちらを見ていた。
「さあ、君たち、続きは自分の家でやるとして、用を済ませてしまおう。まずは………」
それから急に、キッとなって、ドアの方に向かって怒鳴った。
「お前だっ! そろそろ出てきたらどうかね?」
その声の冷たさったら。
閉じられたドアの向こうに、チャールズは何を見たんだろう。さっきまで、優しげなムードをまとっていたのに、今は、初対面の時よりも、人をよせつけない、ぴりぴりとした感じになっている。