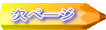8
美代子のお通夜から帰ると、家の門前でロイが待っていた。門柱によりかかり、深刻な顔つきで、じいっと地面を見つめてる。半分以上は闇に溶け込みながら、くっきりとした陰影で映し出されたロイの顔は、外灯の薄明かりにぼんやり照らされて、いっそう青白く見える。
「どうしたの?」
声を掛けると、弾かれたようにこちらを向いた。あたしの服装を見て、目を見張る。
「君こそ…、その格好は?」
「美代子……友達が死んでね、今日、お通夜だったの。後かたずけ手伝ってたら、遅くなっちゃった。……なんか、ずっと信じらんなくて……」
言いながら、美代子の顔が思い出されて、あたしは涙があふれでるのを止められなかった。
後で刑事さんから聞いた話しでは、美代子は妊娠していたらしい。ご両親も、全然気づいてなくて、相手とか、誰も見当がつかなかったようだ。元気のなかった美代子……。
「自殺かも知れないって……、刑事さんが……。あたしは、何も判らなかった。友達だったのに、何も……。美代子は、一人でいろんな想い抱えて……。あたしには、何にも話してくれなかったの……」
それに、何故あの駅……、美代子の家と反対方向のうちの近くの駅に、あの朝いたのかも………。朝練があるからと言って早朝に家を出たそうだけど、何故そんな嘘をついたのかしら。
一瞬トリップしたあたしを、ロイの声が引き戻した。
「……、かわいそうに……。突然の死って奴は置いて行かれた者をも不幸にするからね」
ロイは、痛ましそうに、両の目頭を押さえた。
しんみりとした沈黙。
あたしは、見も知らぬ筈の美代子のために涙するロイを、複雑な気分で見つめた。この人に、あの日のチャールズのこと聞いたら、どんな顔するかしら。ううん、この人はきっと関係ない。
「ロイ…? 何か、あたしに用だったんじゃないの」
ロイは、慌てて顔を掌で拭うと、弱々しく微笑んだ。
「いや…、別に、ちょっと顔がみたくなっただけなんだ」
あ、なんか、ごまかしてる感じ。
「ほんとに?」
「何でもないんだ。じゃ、また明日」
そう言って、立ち去ろうと、ロイは身を翻した。
「ロイ………?」
二、三歩行って、あたしの声に引き留められ、彼はまた振り返った。じっとあたしを見つめる。その瞳は、寂しげで、切なげで、物言いたげで…。
あたしも黙って、ロイの言葉を待った。
かなり長く感じられた沈黙の後、ロイの唇が微かに動いた。低く、甘く、そして、いつもよりずっと力無く、声が紡ぎ出された。
「さやか…、僕と…」
唐突に、呟くようにそこまで言って、ロイは言葉を切った。
「え?」
よく意味がつかめず、あたしはロイの方に向き直って続きを待った。けれど、夜風にあおられる葉ずれの音があたし達を包むばかり。
あたしは言葉を促すように、ロイの瞳を捉えた。それは、いつもの穏やかさをかなぐり捨てて、妖しく金色に輝き始めていて、あたしはグラッとなってしまった。時刻(とき)も何もかもどこかにいっちゃって、金色の光に吸い込まれそうだったの。
気が遠くなりそうになったとき、沈黙を破ったのは、ロイだった。
いつもの、穏やかな瞳の……。
「何でもないんだ、忘れて」
あくまでも優しい口調なのに、有無を言わさぬ調子がその語気にはあって、あたしは言葉を継げられなかった。
ロイは、フッと笑みを浮かべて、黙って見上げてるあたしの首筋に軽くキスすると、
「おやすみ」
と言って駆け去った。
ロイの姿が夕闇に消えると、あたしはロイがキスしたところに手をやった。ほとんど無意識に、傷がないか調べてしまったの。
あの、金色に見えた瞳のせい。気が遠くなるような、妖しい誘いを秘めた瞳………。ホラー映画でもありがちな奴を、あたしは連想してたんだと思う。
でも、ふれた指先には一滴の血もついてなかった。ありえない事を心配した自分を心の中で笑い、幾分ほっとしながら、あたしは玄関の鍵を開けた。
両親とひろしは、お弟子さんのひとりで高水流の後援会をやってくれている、さる財界人の誕生パーティに出席して留守のはずだし、この時間では、トキさんも帰ってしまっているはずだったから。
真っ暗な玄関に入って戸に鍵を掛けたとたん、パアッと光に照らされて、あたしは反射的に手で自分の目をかばった。
明るさになれて前を見ると、ひろしが照明のスイッチに手を掛けたまま仁王立ちになって、行く手を塞いでいた。いつ帰ってきてたのか、着替えもせずタキシードのままの姿で。
あたしを見おろすひろしの表情は、見るからに腹をたててる感じで、黒耀石のような双眸からは、いつもの涼しげな輝きが形を潜め、暗い炎がちらついている。ひろしの無言の威圧に気圧されて、身に覚えがないのに、いつの間にかあたしは卑屈な笑いを頬に浮かべていた。だいたい何時も立場は、姉弟と言うより兄妹みたいに逆転してるのが常だけど、それにしても今日のノリは一体何?
一応、平静を装ってみたりして、
「やだあ、びっくりさせないでよ。やけに早かったね、お義父様達は?」
なんて、聞いてみる。
ひろしは、あたしの問には答えずあたしの腕を掴むと、おもいっきり引っ張りあげた。
あたしはよろけながら、靴を蹴飛ばすように脱いだ。ひろしの奴、脱いでる間だけ待って、また、グイグイあたしのことを引っぱり、早足で、家の奥に向かった。あたしが引きずられてきたのは、ひろしの部屋の前。
一体、どうしちゃったんだろ、本当に。十年の間、こんなひろしには一度もお目にかかったことなかった。ぶっきらぼうだけど、何時だって思いやりのある優しい子だったのに。
強引で荒々しい、このひろしは、あたしの知ってるひろしじゃない。全く未知の男。
あたしは、何でこんなに乱暴に扱われなければならないのかと、驚きが失せ始めてからは無性に腹が立ってきて、ひろしが部屋に引っ張り込もうとしたとき、目一杯の力で踏みとどまって、ひろしの腕を振り払った。
「ちょっと! 痛いじゃないっ! あんた、なに考えてんのっ? あたしが何したってぇのよっ」
あたしは、真正面から挑みかかるように睨みつけた。ひろしは、瞳の中の炎を一層燃え上がらせて、あたしを見据える。ややあってから、小刻みに震わせた唇から出てきた台詞は。
「キスしてた」
「はあ?」
「キスしてた!」
う。
ちょっと待って。
「誰が……、ロイのこと? 挨拶程度にちょっと触れるくらいじゃない。いつもの事だよ」
「いつものことだとぉ?」
ひろしは目を丸くして怒鳴ってから、顔を真っ赤にして横に背けた。
「ふつう、するか? 首筋にキスなんて。挨拶だなんて……。誰にでも言って見ろ、いい笑いもんだぜ。おまえって、そんな簡単にキスさせちまうんだ」
ああ、見てたんだ。うーん、確かにあれは変だわ、あたしもそう思う。ふつう、おでことか、ほっぺとかよね。
「でも、ほんとに挨拶なんだよ。ほら、外人だしぃ」
ひろしは、あたしのそんな返事を全く無視するかのようにして、あたしをグイッと引き寄せ乱暴に髪を押し退けると、ロイがキスした側のあたしの首筋を、矯めつ眇めつ調べるように見た。そして、ほぅっと息をついた。
「よかった…」
「なにが?」
また、答えは無し。今度はあたしの両肩をがっちり掴んで、悲しい目をしてあたしの顔をのぞき込み、ゆっくりと言った。
「あいつとはもう会うな」
「え?」
「あいつは危険だ。いいか、よく聞けよ。ジャパニーズドールっておまえを呼んだのは、あいつだ」
「だって、あれは夢…」
と、そこまで言って、あたしは、ひろしに遮られた。
「現実だっ。俺が見てたんだからなっ。十年前に=」
あんまりひろしが真剣だから、逆にあたしは笑ってしまった。だって、とりあえる内容じゃないもの。
たとえあの夢が現実だったとしても、あの時あたしを呼んだのは、大人の声だったもの、甘く低い声……。
「十年前は、ロイだって子どもだったでしょ」
ひろしはプルプル首を振った。
「だからっ= だから危険なんだ> あいつは…、ロイは…、同じだったんだよっ、姿形がっ。子供じゃない。今と同じだ<」
ひろしは激しい口調でそこまでまくしたて、あたしが全然とりあってないのを見て取ると、うつむいたまま語調を弱くして続けた。
「あいつ、人間じゃねーよ、きっと。信じがたいけど、人間じゃねーんだよ」
さっきまでの、未知のひろしは、もう消えていた。あたしは安堵感に胸をなで下ろし、ひろしの額を人差し指でつついた。
「ったくぅ、何かと思えばっ。冗談にしては凝り過ぎだよ」
「冗談じゃねえっ= 俺、言ってたろ? ずーっと『変だ』って!
…何が変なのか、俺もよくわかんなかったけど、今日、窓からおまえ達見てて解った。あの時の『あいつ』は、あいつだってな」
ばっと顔を挙げて、反駁したひろしは、また瞳に暗い炎を宿していた。
「あいつらがこの辺に越してきてからだぜ、貧血の奴が増えたのは! おまえだって、そうじゃないか!
ロイは、具合が悪くなった時、ベンチでなく草の上に直に寝かしてくれと言ったよな。ロイが寝た後の草を覚えてるか? そこだけ枯れていただろ?
昼間から歩き回ってはいるが、強い日差しは苦手らしいし、吸血鬼……っぽくないか? 馬鹿らしいって、俺だって、何度も打ち消してきたけど、確かに、俺が昔みた奴はあいつなんだ!」
ひろしの言葉は、そのまま、さっき感じたロイに対する妙な疑惑を言い当てていた。けど、どう考えても非現実的なことなので、頭から認めるのはムリだった。
はい、そうですかって、ロイをお化けとして見るなんて、できない。
あたしは、ひろしの手を肩からはずし、一歩退いて言った。
「証拠がないよ。そんな風に他人の事悪く言うなんて、最低! そんなひろし、大っ嫌い<」
言った刹那、ひろしの表情が変わった。うつろな、失望したような表情。
もし、今あたしの顔を鏡に映したなら、きっといやな顔してる。ひろしにあんな顔させてしまって。そんなふうに思えてくるほど、何時にない力の抜けた顔をしていたの。
あたしにはずされた手を、そのまま空に漂わせ、ひろしはじいっとあたしを見つめた。
その、切なげでいて静かな表情は、あたしの胸の、ずうっと奥の方を、鈍い痛みと共に切り裂いた。なんだか、あたしが、ひろしをものすごく傷つけたような気がしてきて、何もいえなかった。それで、思わず顔を背けてしまった。
すると、ひろしは、すうっと片腕をのばしてきて、あたしの片頬を優しく手の甲でなでた。
「さやか……、ごめん。怒らせるつもりなかったんだ。ただ、俺、あいつのやる事見てカッとしちまって…。俺が悪かったよ。まだ言うべきじゃなかった。証拠……ないもんな」
ひろしが、しんからそう言ってるのは声音で解ったけど、それが、追い打ちを掛ける事になった。あたしの胸の痛みはひどくなる一方で、痛みに任せて言葉が先走り、口をついてでた。あたしって、本当、かわいくない。
「そんなとこで、いきなりあやまんないでよ! ひろしの馬鹿!」
ひろしが小さくため息をついたのが聞こえた。
「俺、さやかに嫌われたくないんだ。なあ…、さやか、こっち向いてくれよ」
だめ。
ひろしの顔見たら、また傷つけるような事言ってしまいそうで、恐くてできない。
「頼むから……」
すがるような調子のある声。
やだあ、よけい、自分が悪い奴みたいに思えてくる。
えーん、できないったら。
あたしはそっぽをむいたまま言い放った。
「あー、もう、解ったわよ! あたしが言い過ぎたわよ」
言葉の刃を持て余して動揺してるあたしを見て取ったのか、ひろしは力なく笑って、あたしとの間合いを詰めた。ひろしの体温が肌に触れ、あたしは、周りの空気の変化に呪縛された様に、動けなかった。そうしたら、更に空気が熱く動いて、ひろしの囁きが、耳に触れた。
「さやかはホントに可愛いな」
どきっ。
姉を姉とも思わぬそのせりふに、不覚にも、あたしはときめいてしまった。
あたしの視界を、ひろしの大きな手がかすめ、次の瞬間には、ひろしの胸に、あたしは抱き寄せられていた。
「ロイが何だろうと、どうでもいいや。俺、さやかは絶対守ってみせるから」
いったい、今日はなんなのっ?
ひろしの胸は、見た目よりもずっと厚く、たくましく、あたしは見知らぬ男をひろしに感じて驚いた。十年ていう月日は、あたしに何を見せていたんだろう。悲しいくらい、ひろしが男になってしまってたのに、あたしはずうっと同じでいられると、信じ込んでいた。
ううん、信じ込もうとしてただけかも。
あたしよりも小さくて、怖い夢を見たと言っては、あたしに身を寄せて眠っていた、あの可愛いひろしはもういない。
反射的に身を退こうとするあたしを更にかき抱くようにして、ひろしは、熱い吐息混じりに言った。
「もう、ずうっと前から、こうしたかった…。何時だって近くにいるのに、こうして抱きしめる事さえ出来なくて、気が遠くなりそうなほどつらかった。俺……、俺、さやかが好きだからな」
ゾクっとする様な艶っぽい声。それは、あたしの全身に一瞬電流をはしらせ、あたしをとろけさせた。ひろしったら、こんな声も出せるなんて、とても意外。
ひろしはあたしの顎をそっとすくって、優しく振り仰がさせた。それから、吸い込まれそうな黒い瞳があたしの瞳をのぞき込んで、甘い笑みを浮かべた。
「もちろん、女としてだぜ。さやかは? ……俺の片思い、想いが通じるかな……?」
今のひろしは、あたしの事、姉だなんて毛ほども思っていない。
いつも、視線がちょっと合うだけで、避けてるみたいに一歩退くような事していたのが嘘のよう。今は、あたしの方が、ひろしに真正面から見据えられて、ドギマギしている。
驚きと戸惑いが抵抗する力を取り上げてしまったみたいで、逃げだそうにも体が言う事聞かない。
ひろしの顔を間近で見つめる事になり、あたしは顔に全身の血が集まってしまうかと思うほどの火照りを感じていた。
ひろしは黙ってあたしの顔をのぞき込んでる。
やだ、これってちょっとあぶない構図。
ひろしの瞳に慈しみの暖かい輝きを見いだして、あたしは、胸の動悸が激しくなるのを感じた。
ひろしから流れ出る、いつもとは違う甘い空気が、あたしを虜にして酔わせているんだ。
でもね、一応あたし達、姉弟なんだよ。ひろしの気持ちは、存外にうれしかったけど、あたしの思いは複雑だった。
まずいと、頭の隅で思いながらも、あたしはひろしのきらめく瞳を憧憬を持って見上げ続けた。
あたしの茫洋とした態度にしびれを切らしたのか、性急さを声に出して、ひろしは言った。
「さやか、返事聞かしてくれよ」
「急にどうしたの……? あたし、もう、何がなんだか」
ひろしは、更にあたしを堅く抱きしめ、あたしの髪に顔を埋めると振り絞るよう言った。
「ずっと好きだった。多分、初めて会ったときから…。自分でもどうしようもないくらい好きだ。さやか以外、見えない。他の女じゃ、ダメなんだよ。それなのに……。今更、他の奴に盗られてたまるかよ<」
ああ、そうか、ひろしの変身は嫉妬のせいだ。それで、煮つまっちゃってる。ここまで乱れたひろしは、見た事がなくて、それがあたしのせいだっていうのは不謹慎だけど、喜びを感じていた。
だって、ひろしとの間に距離を感じたときはとても寂しかったから……。あたしに、こんなになる程関心を寄せてくれてたんだって解って、すごくうれしかった。
でも……。
「ひろしの事、大好きだけど、ごめん、待って……」
ひろしは、それを聞くと、あたしの両肩をぎゅっと掴んで自分の胸から引き剥し、目を大きく見開いて真っ向から睨み据えた。
「いつまで? …いつまで待てばいいんだよっ= 俺、ずっと我慢してたんだぞ。俺のものにはならないけど、他の奴のものにもならなかったから。だけど……もうだめだ。限界だよ。こんなに近くにいるのに、何時も一歩退いてなきゃならないなんて。……弟だなんてっ!」
ひろしの指が、肩に強く食い込み、あたしは思わず吐息をもらした。
「ひろし……、やめなさいよ。痛いじゃないの」
それで、ひろしは慌てて手を放したけど、睨み据える瞳はそのまま。
「そうやって、いつまで姉貴面するつもりだよっ。俺は、さやかのこと、姉貴だなんて思った事、一度もねーからなっ」
言われてみれば、ひろしの今までの態度は、確かにそういう方向性を持っていた。
ただ、一緒に住んでる以上、そういう関係になるべきではないと思う。父や母や、他の人まで巻き込む修羅場は避けたかった。
世間体がある。それも、超大変な……。
高水流は、この辺では、束ねの位置につく主流だから、注目度が違う。後ろめたい事がなくても、あたし達のような家庭に関して邪推する人はとても多い。そんな人たちに、格好の話題を提供する事になるのよ、あたしとひろしの関係は。
ひろしだって、十分承知していたはずなのに、ここへきて急に狂ってしまった。
あたしがひろしを追いつめてしまっていたの?
ひろしはあたしを見据えたまま、瞳にすがるような光を映して言った。
「さやか…、俺のものになってくれよ」
う?
ひろしの思い詰めた表情が、本気で言っている事を示している。困った。
ひるんだあたしを、もう一度優しく包み込むように抱きしめて、ひろしは続けた。
「俺、大事にするから……、俺だけのさやかでいてくれ。お願いだ……」
ひろしの手が、あたしの背中を這う度に、あたしの意識はとろけて、力が抜けていく。
じかにあたしの肌に伝わる、ひろしの胸の高鳴りが、あたしの意志をぐらつかせた。あたしの心臓も、ひろしと同じように声高な叫びをあげ始めてる。
熱い指先が、あたしの口元にきて、ゆっくりとあたしの唇を開かせた。もう片方の腕は、しっかりとあたしの腰を押さえ、ひろしにあたしを密着させている。
「さやか……、いいね?」
あたしの消極的な抵抗を、肯定の意味に取ったのか、ひろしは熱くかすれた声で、あたしをまっすぐ見つめながら言った。瞳が、蜜の味を帯びて潤んでいる。
ひろしの全身が、あたしを好きだって、欲しいって叫んでる。ともすれば、ひろしの愛撫に身を委ねてしまいたくなるのを、必死でこらえて、あたしは、口づけしようと、近づいてきたひろしの顔を、弱々しく押し戻した。
「ひろし、だめだよ。やめて……。母さん達が、帰ってきたら……」
ひろしは、あたしの手を取り上げ、掌に口づけながら言った。
「今夜は誰も帰ってこない。向こうで部屋の用意しててね」
戦法を絡め手に変えて、あたしを突き崩そうというのか、心地よい刺激は、掌から手の甲へ、腕、耳たぶへと、移動し始めた。あたしはすでに、崖っぷちに追いつめられている気分。何とか踏みとどまらねば。
だけど、落ちてしまいたいと思ってるあたしがいるのも確かだった。
どうしよう、あたし……。ひろしの手があたしの肩や背を這いまわるだけで、そんな気分になってしまうなんて。
取りあえず、この状況からは逃げ出したかった。なし崩しにされるのは嫌だった。
「……だって、ひろしは? どうして泊まらなかったの?」
ひろしは、あたしの耳から髪へ、そして今は瞼へと唇を這わせて、キスの雨を降らせながら答えた。
「明日大事な試験があるからって言ってきた。御園さんが、あんな死に方したんだ、さやかを一人にしたくなかった。心配だから」
むっ、こいつう。
「狼になりながら言うせりふじゃないわね」
両親は、あたし達を信用して、二人きりになるの解っててひろしを帰したのに。
何が『心配』よぉ。
ひろしは、あたしの首筋にキスしながら、あたしの背のファスナーに手を掛けた。
「ほんとに心配で帰ってきたんだぜ。なのに、さやかは、ロイとデートして、キスまでしてて……。もう、俺、良い弟するのやめたんだ。俺だって男なんだからな」
何処でこんな事覚えたのかと、疑りたくなるほど、ひろしの愛撫は素敵で、その息づかいだけでも、あたしをクラクラさせる。
だけど……。
あたしは、両親の信頼を裏切る事は出来ない。今、流されて、ひろしを受け入れてしまったら、多分、一生うしろめたさを感じて生きていく事になると思う。
いいえ、それは建て前かもしれない。ひろしったら、今までそんなことおくびにも出さずに、急に俺のものになれなんて、あたしからしてみれば、あんまりにも性急すぎる。やはりちゃんとステップを踏みたいなって思うのよね。好きって気持ちからくる、いろんな行動の一つ一つにドキドキしたいじゃない? それを、こんな怒涛のように済ませちゃうなんて、絶対、絶対、いやーっ!
そういう想いが、あたしに力をくれた。
ひろしの唇が、あたしの唇を捉えた瞬間、あたしは、ひろしの顔を思いきりはたいた。
頬がみる間に紅潮して、あたしの手形をくっきりと映し出す。
うっ、痛そう。ごめんね、ひろし…。
どうか、神様、あたしの声のふるえに、あたしの砦が崩れそうだって事に、ひろしが気づきません様に。あたしは、ひろしへの好意を、残らず心の隅に押しやって、突き放すように言った。
「いい加減にしなさいっ、あたし達、今は家族なんだよっ。それ、壊す気?」
「さやか……?」
頬を押さえながら驚愕に瞳を見開いたひろしの声は、予想に反して押し殺された震え声だった。もっと荒れるだろうと、覚悟してたのに…。それは、かえってひろしのダメージの大きさをあたしに自覚させた。
「おれ達、本当の姉弟じゃないって事、はなから解ってたじゃないか、俺がさやかを好きになったら変か? 俺の事嫌いなら、そう言ってくれよ。俺、あきらめるように努めるから。とにかく、もう俺、宙ぶらりんの状態には耐えられないんだよ」
あたしの中に、なにかがこみあげて来た。胸の中のくすぶりが、あたしを内側から灼き焦がす。
あたしはかぶりを振った。何度も何度も。かぶりを振りながら、ひろしの腕を振り解いた。
「……なわけ……無い……」
「さやか……?」
「嫌いなわけ無いじゃないっ! あたしを追いつめるのはやめて>」
あたしは、半ばひろしを突き飛ばすようにして、ひろしの部屋とは斜向かいの自分の部屋へ駆け込んだ。ひろしの激情から、また、それに酔って流されてしまいそうな自分から逃げ出したかったから。
「さやかっ?」
ひろしの悲痛な叫びにも似た呼び声を背に、あたしは扉の鍵を閉め、背中で押さえた。扉をドンドンと叩くひろしの拳の振動が、背中に伝わってくる。あたしの名を何度も叫びながら、ひろしが扉を叩いてる。
「やめてったら! あたしに考えさせて」
あたしは夢中で叫んだ。
「ひろし= 聞いてる? 理屈では変じゃなくても、いろいろしがらみがあるじゃない。あたしにだって、それなりの心構えってものが要るのよ! あんたがそんなだと、あたし、明日にでもこの家出てかなきゃならないっ>」
「いやだっ! 出ていくなんて言うなよっ> 他には何にもいらないっ。さやかさえ居てくれれば、何にもいらないからっ」
「だったら頭冷やして= 二度とこんなことしないで<」
自分でも驚くほど、冷たく突き放した声になってしまった。
息を飲むような気配の後、ドアの向こうが沈黙した。しばらくして、ひろしのしわがれた弱々しい声が聞こえてきた。
「さやか……。俺、苦しいよ……」
そこまで言うと、声が途切れ、押し殺したすすり泣きになった。
泣いたところなんて、見た事も無いひろしを泣かせてしまった。とても、とても、重い涙……。
今すぐ出ていって、抱きしめてしまいたいたかった。ドアノブを握りしめた拳が強ばる。
「ひろし……、ごめんね。もう少し時間を頂戴。あたし、誰のものにもならない。他の人を好きにならない。約束するから…」
あたしの声も、涙でかすれちゃってる。ちゃんと聞こえたかしら。ドア越しのひろしの気配を感じとろうとして耳を澄ませたとき、背後の空気がスッと動いた。
「そんな、無理な約束はしない方がいい」
「?」
その声は、ベルベットのように柔らかく耳に触れた。けれど、その芯には無機的な冷たさがある。
あたしの部屋に、誰か居る。
「誰っ?」
窓が開いていて、おぼろな月明かりを受けながらカーテンが、フワリと翻った。
あたしは、壁にぴったりと背をつけたまま、窓の真正面に位置するように移動した。同じ時、ゆっくりと影が動いて、月明かりの中に現れた。
ほっそりとした長身の影。
金色にたなびく長い髪だけが、逆光の中で彼が誰であるかを物語っていた。
「チャールズ?」
あたしは驚きの余り、大声で彼の名を呼んだ。
チャールズは、芝居っ気たっぷりに優雅なお辞儀をしてみせた。
彼が顔をあげた瞬間、あたしの視野は七色にうねり、あたしは吸い寄せられるように彼の瞳を見つめた。金色に輝く、甘美な宝石を……。
「ここを開けてっ! さやかっ、奴がそこにいるのかっ? 奴の目を見るなよっ、絶対見ちゃだめだ<」
あたしの声を聞きつけて、ひろしが、ドアをけたたましく叩きながら叫んでいる。
あたしは、チャールズの腕に抱かれながら、どういう意味だろう、と、ぼんやり考えていた。
ひろしの声が、だんだん遠くなっていく。
ドアをけ破る音を聞いたような気がするけれど、定かではない。