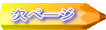7
月曜の朝の駅は、一段と慌ただしい気がする。前日の遊び疲れが尾を引いているのかどうかは知らないけど、だるそうな人が多くみられる。朝の電車って、大体同じ顔ぶれになるのだけど、月曜だけは、ちょっぴりそれに変化が付くのよね。
遅刻なのか、時計と時刻表を交互に見てそわそわしているサラリーマン。場所から言って完全遅刻だろうと想像できるところの制服を着て、ぼんやり立っている学生。変にべたべたしながらドア口地蔵を狙う、やけに年齢差のある怪しいカップル。…等々。
だいたい、あたし達の利用駅は、各駅停車しか止まらない駅で、隣の駅が大きな駅なものだから、下り利用の者でも長く乗る人は、上りでその駅を経由するという乗り方をする。ホントはそういうの、キセルっていって、いけないんだけどね。あたし達も、ご同様。まあ、そういうわけで、ただでさえ混む上りホームは、毎朝戦争みたい。いつものように、その戦争に飛びこもうと改札に向かう途中。
「せんせぇー!」
間延びした甲高い声がどこかで叫んでいるのが聞こえた。人混みの中では誰だか判別できないけど、まず他人事と考えていたのに、実際袖をつかまれ立ち止まらせられたのは、ひろしだった。
「先生ったらっ> んもう! 綾乃が一所懸命呼んでるのに、ちっとも気がついてくれなんだからぁ」
何なのよ、この女……。ひろしの方を見ると、困惑げにその子を見つめていた。だいたい、ガクランの男捕まえて、先生呼ばわりするもんだから、回りの好奇の目が集まる集まる。ひろしなんて、もしあたしがそんなことしたら、絶対怒鳴りつけてたはずだわ。
お嬢様学校で有名な所の制服に身を包んだ彼女は、ひろしの腕に自分の腕を絡ませ、幼顔の割に豊満な胸を押しつけている。胸の校章の色からすると、高校一年生らしい。天然パーマというには出来すぎた綺麗な巻き毛を揺らし、甘えるように媚びた微笑みを浮かべ、反対側にいたあたしを何気なく突き飛ばした。ひろしに見えないように。
むっかーっときたあたしは、極力上品にひろしの前に立った。優雅な会釈くらいお手の物なんだからね。
「ひろし、可愛い方ね。お姉さんに紹介してくれないの?」
ひろしは、傷ついた目をして、それでも、高水流の顔を崩さず彼女をあたしに紹介した。
「桜小路綾乃さん。僕の教室の生徒さんです。桜小路さん、これが、僕の姉のさやかです。一つ上で、学校の先輩なんですよ」
一つ上ってのをやけに強調した声が、ひろしの機嫌の悪さを表していた。何さっ、頭にきてんのは、あたしの方なんだからねっ。
あたしの正体を知ると、女はやばいって顔になった。あたしのことを知らないなんて、お教室に入って日が浅いのね。だけど、桜小路といえば母親の方が、たぶん高水流の上客じゃなかったかな、と、思いだし、頭の中で綾乃の後ろ頭にけりを入れている自分を想像しながら、お上品な高水姉を通そうと心に決めた。
「先生のお姉さまなの? 道理で綺麗な人だと思ったぁ」
綾乃の、鼻にかかった甘えるような声音は、すごくあたしの癇にさわった。あたしに対する態度、今更変えたって、遅いのよっ。
「お上手ね、綾乃さん。ひろしにこんな可愛い生徒さんがいるなんて、ちっとも知らなかったわ。私は、お仕事のお手伝いをしていないものですから」
ころころと声を転がすように笑ってみせる。いつものあたしを知っている人に見せたら、ちょっと寒い光景かもしれない。
ひろしも、そう思ったのか、わざとらしく時計を見ると、改札に足を向けた。
「君の学校、バス通学だったよね。僕らも遅刻してしまうから、この辺で」
「あん、先生ったら、真面目ねえ。じゃ、今度のお教室でね。失礼しまぁす」
そう言いながら、彼女は追ってくる様子もなかったので、あたし達はそのまま改札を抜けた。あいつがバスでよかった。
「ひろしったら、やけに丁寧で優しげだったじゃない? 生徒にモテモテなのね」
だいたい、あたしに対する態度と違いすぎるよね。
「さやかこそ。ちょっと、嫌みな感じだったぜ。何怒ってんだよ?」
「……怒ってないもん。ただ、あの子、意地悪だから……」
肩を揺すって、溜息をつくように笑いながら、ひろしがあたしの手を取った。
「あの子は、母親からしてあんなだからな。損な性格だよ、可哀想だと思ってやらなきゃ。あんなでも、良いとこもあるんだからさ」
「……わかってるわよ。あんたが相手にしてないのも分かってるけど……」
ひろしの、あたしを握る手に力が込められた。あたしの顔を覗き込むようにかがんだひろしの瞳には、ほんの少し甘い光が走った。
「さやか、妬いてるの?」
「ば、馬鹿ねっ。そんなわけないでしょっ! 弟のことで妬いてどうするのっ」
ひろしの甘い笑みが凍りついた。すっとあたしの手からひろしの手が離れていく。
「馬鹿で悪かったね。どーせ、俺は馬鹿だよ」
「ひろしったら、やーね、そんな怒ることじゃないじゃない。言葉のあやってやつでしょ。ほらぁ、すねてないで、学校行こ。ほんとに遅刻になっちゃうよ」
あたしは、ひろしの腕をつかんで、さっき綾乃がしたようにその腕に抱きついた。びくっと身じろいだひろしは、それでもあたしを振り払うことなく歩き始めた。
「さやかって……」
ぼそっとつぶやくようなひろしの声。ほんの少しうわずって、ふるえていた。
「なによぉ」
「何でもない……。弟って、損だよなぁ」
まあ、そうね。あたしみたいな姉に使われるんじゃ、そう思ってもしょうがないか。
あたしは、ひろしにかばってもらいながら、結構快適に、満員電車をやり過ごすのが常なのだ。確かに、歩美の言うとおり、幸せものかも知れないな。
ひろしは苦痛かもしれないけど。何しろ、おしくら饅頭状態の他人の重みを全部自分で受けて、あたしの楯になってくれているんだから。誕生日も過ぎたし、今度のバレンタインデーには、なにか感謝を示す物を渡そうかな。
乗り降りする客で、ごった返すホームで、そんなこと考えながら、ぼんやり歩いていたら、ひろしが突然立ち止まり、横で小さな叫びをあげた。その後すぐに、甲高いきしるような、電車の悲鳴が聞こえ、鉄のこげる匂いが鼻を衝いた。
ホーム半ばで、通過予定だった特急電車は止まっている。ざわめきが何倍にもなって、ひろしが見つめる車両の最後尾の一点を中心に、波紋のように広がっていった。
「事故だ!」
「飛び込んだぞ」
「押されたみたいだったよ」
「かわいそうに、まだ学生じゃないか」
「うっわー、血みどろ」
そんな様な科白を、みんなが口々に吐いている。
『ただ今、当駅にて人身事故が発生しました。事故処理のためしばらく停車致します。ダイヤが乱れ、お客様には、お急ぎのところ御迷惑をおかけしますが、ご了承願います』
放送が入ると、更に野次馬が集まり始めて、上りホームはまるで芋洗いの様な混雑ぶりになった。みんなが背伸びをしつつ、事故現場をその目に焼き付けようと、躍起になっている。中には、見たくもないのに見てしまったらしく、悪心を催して群れから抜け出してくる人もいる。
後からくる野次馬に何度か小突かれ、あたしはひろしの胸に飛び込む形になった。
ひろしは、機械的にあたしの肩を抱いてかばってくれたけど、心此処にあらずといった風で、最初に凍り付いた視線を外そうとはしなかった。
「さやか…、俺、見たよ」
抑揚のない、低く押し殺したひろしの声は、あたしをハッとさせた。次ぎにどんな言葉が出るか、具体的な想像は出来ないけど、あたしたちにとって、ただの事故ではすまなさそうだということを感じさせる声だった。
ひろしの顔色は、目に見えて青ざめ、あたしの肩に戦慄が伝わってきた。
「ひろし……?」
「あいつだ」
ほとんど唇を動かさず、ひろしは呟いた。
よく視線をたどってみると、ひろしは事故現場よりもっと遠くを見つめていた。対岸の下りホーム上も当然野次馬が集まっているのだけど、その黒山に、一つだけ金色の頭が朝陽を浴びて光彩を放っている。しかし、目立っているのはその髪ではなかった。顔の向きが、他と違う。その視線は事故を見ず、まっすぐこちらに向けられていた。ひろしのそれと絡み合い、お互いを突き刺しあって………。
あの氷の瞳、よく見なくたって、判る。
あれはチャールズだ。
チャールズは、あたしの視線に気がついたのか、瞳から凍てつく光を取り去って軽く会釈すると、にっこり笑った。あたしもつられて会釈を返したら、あたしの肩を掴むひろしの手にぎゅっと力が入った。
「あんな奴に、愛想振りまかなくったっていいよっ!」
「ったいなぁ、なんで、あんたってば、そう、彼を目の仇にするのっ?」
あたしは、ひろしの腕から抜け出した。ふと対岸を見ると、すでにチャールズの姿はなくなっていた。
「あ、いなくなっちゃった。ちょっと失礼じゃない? あんたの態度」
言いながら、目をひろしに向けると、さっきまで青ざめていて、今度は紅潮してるひろしの顔に出合った。ひろしは、少し震えた声で吐きすてるように言った。
「俺は、御園さんが落ちるとこを見たんだっ」
「?」
今、なんか変なこと聞こえたような…。
「今、御園って言った?」
ひろしが目を背けた。
イエスってこと?
「美代子のこと?」
ひろしの腕が、あたしを抱き寄せた。
…イエス。
「落ちたの、美代子?」
ひろしが、あたしをぎゅうっと抱きしめた。ひろしの汗と、制服特有の匂いが、あたしの息を詰まらせた。
イエス、イエス、イエス。
「あっちのホームから、崩れるように落ちていくのが見えた。……変じゃないか、その近くに、今、あいつがへらへら笑って立っているなんて……」
途中から、ひろしの声はあたしに届いてはいなかった。
美代子が……。美代子だって言うの? あの人だかりの向こうにいるのが…………。
ひろしの最初の叫び、あれは落ちる美代子を目にしたからだってこと?
「うそぉっ>」
あたしは、ひろしを突き飛ばすようにしてその腕から抜け、黒山に突進した。
「さやかっ! だめだ< 見ない方がいいよっ」
後からひろしが追ってきて、あたしの腕を掴み、引き戻そうとしたけれど、あたしはそれを振り払った。
「いやっ! 信じないっ。自分で確かめるまでは>」
「さやかっ>」
もみ合うあたし達は、いつの間にか野次馬の注目を集めていた。たちまちヒソヒソ声が、あたし達を取り囲む。
「あの子と同じ制服だ」
止めて…。
「県立青葉だろ、あれ…」
止めてったら!
黒山は、あたし達を促すように、二つに割れ、道をあけた。
線路上では、何人かの駅務員が、大きな袋を持って駆け回っていた。あたしは、そこに美代子の姿を見いだせなかった。枕木や敷石が、どす黒い赤に染まっているのが、事故のあった証拠。あたしは、膝の力が抜け、その場にへたり込みそうになった。ひろしが背後から支えてくれなかったら、確実にそうなってただろう。
「美代子は? 美代子は何処?」
あたしは、すがるようにひろしの袖を掴んだ。
「どこよぉっ!」
ひろしは目をうるませ、歯を食いしばったような顔をして、無言で一人の駅務員を指さした。車両に引っかかっていたものを、取り出している最中の駅務員。その駅務員が手に持っていたのは…。
血だらけだけど、白くて、ほっそりとした腕……。手首にブレスレットが巻いてあるまま。美代子のお気に入りだった銀の……、誕生日にあたしが贈った……。
「いやぁぁぁぁぁっ」
音がだんだん遠のいていく。ひろしの腕の感触も、全て、あたしが真っ赤な闇に取り込まれて行くのを止めることは出来ない。
他の色を失っていく中、あたしは、もう一人、知った顔を目にしたような気がしていた。