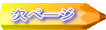6
試合の日、あたしは、無理矢理くっついてきたひろしにお弁当をもたせ、駅でみんなを待った。あたしはいつも、集合時間より十分くらい早く来て待つようにしているの。
ひろしは暇を持て余してか、駅前の道を歩く人たちを、ぼんやりと観察している。けれど、道行く女の子達のほとんどから、ひろしも観察されているのよね。
ひろしを目に止めて、立ち止まるでしょ。それから、足元の大きなバスケットを見て、それによりかかるあたしを見つける。そして、なあんだって顔して歩き出す。複数の場合、この各要素にひそひそ話が入るの。
たまに、あたしに気がつかない子達が声掛けようとして近寄ってくる事もあるけど、あたしがひろしに話しかけていると潮が引くように去っていく。
いいだろー、これ、あたしんだぞ、ってなもんでして。
あらためて、あたしはひろしを見つめた。
………、確かに、水準以上だわ。
スリムなブラックジーンズにボートネックのブラックシャツ、短い丈の真っ赤なブルゾンの袖を無造作にたくしあげて柱によりかかってる姿は、長身で引き締まった体躯がアピールされていて、遠目にもいい線行ってるし。流行やおしゃれに気を使う奴じゃないけど、結構、自分に似合うものは知ってるんだな。
遠くを見つめる瞳はちょっぴり冷たさを秘めて漆黒の煌めきをたたえ、引き締まった口元は強い意志を隠し持っている感じ。すうっと通った鼻筋といい、造りの全てがバランスよく配置され、そこに育ちの良さと、もって生まれた性格が美しい彩りを与えて、ひろしを造り上げている。
持つべきものは、ハンサムな弟ってね。ちょっと優越感。……不毛だけど。
「ねえ、ひろし」
「ん?」
「あたし達って、どういう風に見えてるのかな」
言ったとたん、ひろしは、ズルッとバランスを崩した。
「あ、こけた」
「しぃっ」
誰かの声と、複数のクスクス笑いが、背後から聞こえてきた。
「ななっ、なに言い出すんだよっ>」
あたりをすばやく見回し、小声で叱責するように言うひろしの顔は、まるでゆでダコみたい。
「………、やっぱり、兄妹に見えるかな。姉弟じゃなくて」
ひろしは、ぐったりとしゃがみ込んで両腕に頭を埋めてから、恨めしそうに横目であたしを見上げた。
「どおせ、そんなとこだよな、さやかの言いぐさじゃ…。なんか、俺、自己憐憫に浸りたい気分だ」
「そう?」
生返事しながらも、あたしの意識は、すでに別の事に飛んでいた。
「おいっ、聞いてんの?」
無反応のあたしの目線を追って、ひろしも同じところへ目を向けた。車道をはさんだ向かい側、美代子がふらふらと歩いている。
「なに…、御園さんじゃないか」
美代子といえば、あの保健室の一件以来学校も休みがちで、歩美と二人で心配していたんだけど、あたし達には何も相談してくれなかったんだよね。吉住さんに訊いてみたって、やっぱり否定的な答えしか返ってこないし。
昨日だって欠席だったのに、今、何だってこんな所にいるんだか。美代子の家は、学校を挟んで、こちらとは反対方向に駅三つ行った所なのよ。買い物なら、美代子の家に近い方に、横浜っていう大きな駅がある。あたし達だって、そこまで行くことが多いのに。
しかも横には、すごく目立つ人物が……。つながりが全く見えないんだけど、美代子の陰から見えかくれして、明らかに同道しているんだから不思議。
「一緒にいるの…、チャールズじゃない?」
ひろしが強ばるのが、横で感じられた。
「あんな、長い金髪の美形、やたらにゴロゴロしてないよね」
「まあな」
ふらつく美代子を、チャールズが支えるようにして歩いている。
「何やってんだ、あいつ」
眉をひそめて言うひろしをわきに押し退け、声を掛けようとしたのだけど…。
「さやか!」
逆に後ろから自分の名を呼ばれて、タイミングを逸してしまった。
振り返ると、ほんのちょっとの間に、まるで申し合わせたかのように子供達が集まっていた。子供達の真ん中では、ロイがにっこり笑って立っている。
いつもと違い、ぐっとくだけた格好で、ショート丈のGジャンとハードロックカフェのTシャツにストレートのブルージーンズって姿。頭にはすっぽりとつばの大きな野球帽、胸ポケットに無造作に引っかけてあるのはレイバン・オールドファッションのサングラス。プレッピーの権化みたいなイメージだったんだけど、服装って結構人を変えてしまうのね。
「どうしたの? 二人して」
「あんたの相棒が、さやかの友達と一緒にいたのが見えたんだよ」
「へえ、奇遇だね。今朝は僕より早く出たんだ、彼。買い物に行くって、言ってたんだけどね」
ひろしの投げやりな口調を、全然気にする風でもなく、ロイは受け流した。あ、中身は、いつものロイだ。
「御園美代子っていうんだけど、ロイは知らないの?」
ロイは、記憶の中に美代子の名を探して、一瞬考え込む様な顔つきをしたけど、即座に明確な調子で答えた。
「聞いた事ないけどな。うん。それより、切符は買ったの? みんな揃ったみたいだけど」
あたしは、言われて、慌てて買っておいた切符をみんなに配った。美代子のことが少し気になったけど、子供達を放り出してく訳には行かないものね。
「ひろしのこと、ごめんなさい」
電車に全員乗って落ちついた所で、ロイと隣り合ったあたしは、言ってみた。ひろしは、久しぶりに会った子供達に囲まれて、こちらをちらちら見つつも邪魔しには来ないようなので。
「なにが?」
おっとりとした笑い顔で聞き返されて、言わなきゃよかったかなって思ったけど仕様がない。
「え……、あのね、どうも、あいつってば、何でだかロイに風当たり強いみたいで……。いつも、悪いなって思ってるの。さっきだって、嫌な言い方してたでしょう?」
ロイはフッと笑みをもらした。
「うん? ああ、今もこっちが気になって仕様がないみたいだよ。すごい目で睨まれた。……まあ、僕が逆の立場なら、やっぱりああなるかな。別に気にしてないから、さやかも気にしないでよ」
気にしないって。気がついていて、そう言えちゃうなんて。このロイに比べると、やたらに突っかかっていっては相手にされないでいるひろしが、ひどく子供に思えた。
ロイの瞳が柔らかく揺らいで、あたしを取り込むように見つめ、あたしの頬に火をつけた。
何を赤くなっているんだろう、あたしってば。ロイって、ときどきすごく色っぽい感じになる。それとも、あたしが、色気過剰なのかな。
「……さやかの家は、家族以外に何人住んでるの?」
ロイったら、何言い出すのよ。こんな時に。
「急に、なあに? ……住み込みは、秘書兼運転手の吉住さんと、お手伝いのトキさんだけよ。みんな、家族同様だけどね」
「ずっと前から同じ?」
「え? う、うん」
「そう………」
考え深げに黙りこくるロイを見ているうち、突き刺さるような視線に気づいて、あたしは振り返った。案の定、視線の主はひろし。ひろしは、あたしと目があってもそらさずに、絡み付くように見返してきた。責めているような、悲しんでいるような、そんな視線を受けているうち、今、あたしがひろしでなくロイのそばにいるのが、とてもいけないことのような気がしてきた。変よね。
「さやか、ひろしの所に行ってやりなよ。僕に謝る前に、君が種をまかなきゃいいんだよ。気になるんなら、ね。僕は、結構、ひろしって好きだな。直情型って感じだろう? 僕が気に入らないらしいのは残念だが、見ていて飽きない奴だよ」
冷静に言ってくれるなあ。もう、全然相手になっていない。
ひろしの所に行くまもなく、全員合流して目的地に着いた。
ロイは柳に風という風に、ひろしの向けるプレッシャーを受け流している。かえって子供達の方が、気を使うように両者を見比べてしまう始末。
ったく、ひろしなんか連れてこなければよかった。
そうこうしているうち、あたし達は、定刻通りキックオフをむかえた。審判は、ロイと黄金学院の先生たち。
相手チームは、何しろ強い。子どもの遊びと言うには、ちとハイクラス過ぎるくらい。うちの監督の出身校である黄金学院の肝いりで、主に同学院の初等部の生徒で構成されている練成チームなの。でも、今見ている限り、うちの連中だって互角で頑張っている。
「……やるもんだな」
唸るように呟いたのは、試合を食い入るように見つめているひろしだった。
「あいつらの上達ぶりは、コーチだった俺にはよく判る。ロイは良いコーチだってことだ。悔しいけど、それは認めるよ」
「今日は、やけに素直なのね。どうした風の吹き回し?」
「あいつが胡散臭い奴だっていう俺の考えはかわらないけど、サッカーの実力に関しては認めてるさ。公平な目で見てるつもりだぜ、俺は」
ひろしの瞳が、きらっと光った。
「さやかこそ、あいつらのいい子ぶった態度に惑わされてるんじゃない? あいつらのこと、何にも解ってないだろ。俺達と年がかわんないのに、やけに達観したみたいな態度だったり、爺むさい様な分別臭い表情とか、生活様式一つとっても、変なところが沢山あるのに」
いつもの様に、怒ったような口調で言われれば、簡単に反論出来そうなのに、ほんとに冷静な顔して、とつとつと言われると、そう言えばって気になってくるから不思議。
「また怒られるかもしれないけど、俺、ロイとかチャールズ見てると、胸騒ぎがするっていうか、この辺がもやもやっとして、いやーな感じになるんだよな。ロイなんて、すごい人当たりいいのに、善い奴なのに、俺の中の警報機は、鳴りっぱなしなんだ。ただの勘てやつだけど……。ほんとだぜ」
胸の辺りで手をひらつかせるひろしを、あたしはじいっと見つめた。
「裏が有るっていうの? 何のために」
「知らないよ。それが判りゃ苦労はないさ」
「そういうの、無責任な中傷っていうのよ」
「ちぇーっ。もぉ、勝手に騙されてろよ」
ふてくされた言い方した後は、試合に集中するつもりか、ひろしは黙ってボールを目で追い始めた。
ったく、なに考えてるんだか、意味不明。ひろしはひろしなりに考えて、ロイ達を嫌っているらしいってのは判ったけど、そんなんであたしを説得することはできない。基本的にいい人ならいいじゃない、と、思ってしまう。それに、いい人と暮らしているチャールズだって、取っつきにくいけど、いいとこあるんだと思うのね。
ひろしにいわせれば、あたしの考え方は甘いっていうだろうけど。でもでも、それにしても、ロイ達に対しては必要以上に厳しいというか、神経質になってる。ひろしってば………。
「さやか!」
物憂い気分になって放心していたあたしは、ひろしに呼び戻された。
「ロイが変だ。動きがおかしいぜ」
言われてみれば。息一つ乱さず長時間プレイできる筈の人が、ジュニア・ルールの前半の主審もこなせず、動きが鈍くなっている。
「大丈夫かな、あと少しでハーフタイムなのに」
真剣に心配しているひろしを見て、あたしは少し荷がおりた気分になった。
「後半は、あんたが入ってくれる?」
「うん、わかってる」
苦しげな表情のロイが、時計を見ながらホイッスルを構えた。
「よかった。ホイッスルの音が、こんなにありがたいと思った事なかったな」
笛の音が鳴り響くと、ひろしはそう言いおいて、立ってるのがやっとという感じのロイに駆け寄った。あたしも驚いていたけど、ロイの驚いた顔ったらなかった。嬉しそうに微笑み、ひろしの肩を借りて、こちらに戻ってきた。
「貧血みたいだ。さやか、ベンチ空けて」
「いや。すまないが、僕をそっちの草の上に置いてくれないか。……ありがとう、ひろし」
一段と蒼い顔をして、ロイは、ぐったりと横になった。ひろしがロイの帽子を取ってきて顔の上に乗せると、弱々しい声が帰ってきた。
「すまない。かえって、迷惑かけてしまったね」
「気にしないで。それより、大丈夫? つらかったら、今から送って行こうか?」
「いや、君がいなくなったら、士気が低下する。僕は平気だから…。ただ、強い日差しが苦手なだけなんだ。ここでこうしていれば、よくなるから」
今日がピーカンでなければ、よかったのにね。ロイの意外な弱さを目にして、子供達は驚いていたけど、ハーフタイムの間に、口々に言葉をかけていった。ロイは、みんなの心を掴んでる。ひろしとだって、引っかかる事がなければ、とっくに仲良くなっていただろうに。ロイの親しみやすさは、一つの武器だわね。
うがった見方かも知れないけど、ひろしとしては、自分が公平である事を示したかったんじゃないだろうか。とりあえず、自分の気に入ってない人物に対しての態度としては、良い評価をあげようと思う。
後半が始まり、線審をやっていた先生に、主審を代わりにやってもらって、ひろしが線審として飛び出していくと、あたしはロイの側に移った。ロイの具合は、自分で言っているよりもずっと悪そうだ。透き通るような青白さがいっそう増して、死人のよう。
「本当に、大丈夫? 電話かけてみようか、チャールズが帰ってるかも知れないよ」
「だめだ= 止めてくれ> こんな体たらく彼に知れたら、もう、サッカーやらせてもらえないよ=」
ことのほか激しい口調で言うロイに、あたしは魂消て目を見張った。
「……。彼は、……チャールズは、僕の友人である前に保護者なんだよ。それも、とびきり厳しい。彼には心配ばかりかけてるから、僕がこんなだから、いつまでも彼は解放されないんだ。早く一人立ちしなきゃいけないんだけどね」
なんだかよく解らない。ロイの言葉は、あたしに言っているようで、実は自分に向かっている節がある。モノローグみたいに。
「ロイの事が、大切なんだね。心配だから怒るんでしょ。チャールズも……」
「ああ、うん。そうだね。
……ごめん、少し眠りたいんだが……」
「うん、眠って。でも、試合終わったら、送ってっちゃうからね」
ロイは、帽子の下で弱い笑い声をもらすと、そのまま眠ったようだった。
あたしは、後で求められるであろうコメントのために、試合に集中する事にした。
確実なパスワーク。それぞれのリズムを掴んだフェイントの数々。初めてロイのプレイを目にしたときの感動が、そのまま身になっているのが判る。ロイのようにボールをさばきたいという希望に衝き動かされ、みんなここまできた。しかもロイは、個々のキャラクターを無視せず細かく指導してくれたから、型にはめられる事もなく育ってくれた。
勝敗はうちの負け。けれど、結果よりも過程が問題よね。結果は、サドンデスのPK戦で決まったのだから。それまでのプレイは、本当によく頑張ったもの。
失敗した子は泣いてしまって大変だったけれど、誰も彼を責める子はいなかった。もう、次の目標のために、自分のプレイの復習を始めている。
「今日の試合は、良い刺激になったな。あいつら、みんな、いい顔してる」
ひろしの嬉しそうな声。駆け戻って来ての、第一声だ。
「……、ロイは?」
眉をひそめて言うひろしの視線につられて、横のロイを見ると……。
いない。
「やだ、どこいっちゃったのかしら。さっきまで、そこに居たのに」
辺りを見回すあたしの横で、ひろしが難しい顔をして、しゃがみ込んだ。
「枯れてる……な…」
「え?」
ひろしの指に摘まれた芝は、白茶けた色に変わっていた。極一部に過ぎないのだけど、他が一面若草色なものだから、結構目立つ。
「なんか、病気なんじゃないの?」
「ああ、そうかもな。それとも………」
「監督ぅ、いたよ!」
声のする方を見て、あたしは血の気が退く思いだった。ロイは確かにいたけど、校舎とグラウンドの間の並木の一本によりかかるようにして座っているロイは、まるで死んでいるみたいに力を失っていたから。
顔色だって、緑色に見えて………。そう、今にも周りに溶け込んで、なくなってしまいそうに影が薄くなっていたの。
「ロイ!」
あたし達は、慌ててロイの所に駆け寄った。
「おいっ、どうした? しっかりしろよ!」
ひろしがそっと抱き起こしながらロイに呼びかけると、瞼が弱々しく瞬いた。
よかった、生きてる。ひろしもほっと息ついているとこみると、同じように考えていたんだ。
「ああ……、ごめ……ん。涼しいところに……避難していたんだ……」
「もおっ、ビックリさせないでよ。死んでるかと思っちゃったわよ」
「あんたって、何か病気なのか?」
あたしとひろしに、かぶさるように言われて、ロイはちょっと目を見開いた。
「なんだか、怒られているみたいだな……。ああ、いや、病気と言えば、病気……かもしれない。ごめん。貧血のひどいのだと、思ってくれればいいよ。無理しちゃ、チャールズに叱られてるんだ。……また、叱られるな」
うつむき加減で、恥ずかしそうに言うロイは、口元を気怠げな笑みで飾った。
「とにかく、送って行くから。ひろし!」
仕様がないな、というように、ひろしが息をついて、ロイに肩を差し出した。
「つかまれ」
ロイの青白い腕が、ひろしの赤いジャケットの色を映して、ほんのりピンク色になった。
夕方の光ではただの白人に見えた彼も、陽の光の下では不自然な白さが際だって、ひろしの示唆する疑問を、いやでもあたしに思い出させる。
「……ありがとう…………」
ロイの深みのある声が、あたしの幻想をストップさせた。
まさかね。ひろしが、変なこと言うからいけないんだわ。
あたし達は、ロイが平気だと強く主張したので、電車で解散予定の駅まで子供達を引率してから、タクシーをつかまえて乗り込んだ。
「ロイ、病院で診てもらった方がいいんじゃないの? 貧血だって、甘く見ない方がいいよ」
車中で、あたしは言ってみた。ロイはうつむいたまま。
「さやか、無駄だからやめな。こういうの初めてじゃないんだろ、ロイ? チャールズにいつも叱られてるって言ってたもんな。自分の体のこと、十分解ってるんだ、あんたは」
きついな、ひろしは。ロイに対しては、いつもよりずっときつい。ロイは知ってか知らずか、いつも平静でいるけど、今はそのゆとりも無いらしい。
「解っているよ。だから、死にそうに見えたとしても、放っておいてくれていいんだ。本当に、大丈夫なんだから」
吐き捨てるみたいに言ったロイの顔、ちょっと怖かった。その後は、ロイの家に着くまで、気まずい空気のまま皆だんまりで過ごした。
車からロイを降ろしていると、チャールズが飛び出してきた。
「どうした?」
「試合中に倒れたんだ。本人は平気だって、きかないけどね。ご覧の通りだ」
冷たく言うひろしの肩からロイを引き継ぐと、溜息混じりにチャールズは言った。
「馬鹿だな、あれほど止めろと言ったのに」
体格は、どちらかといえばロイの方が大きい位なのに、チャールズは、ぐったりしているロイを軽々と抱き上げて、ずんずん中へ入って行く。
「止めろと言われて、何でもはいはい聞くほど、僕はいい子じゃないよ。チャールズ、僕のことはもう、いい加減あきらめてくれないか? どう考えても、僕は君のように生きていけるとは思えないんだ。主義主張が違いすぎるよ」
寝椅子に寝かしつけられながら、譫言のように言い続けるロイは、駄々っ子のよう。
「どんな者になろうと、僕は、僕は……」
「しっ!」
ロイの口を手でふさぎ、後からついてきていたあたしとひろしの方を、くるっと振り返って見たチャールズは、とっても険しい顔をしていた。
「君たち、ありがとう。後は僕だけで大丈夫だから。こいつの病気には慣れっこなんだ」
言葉だけはちゃんと選んでいるみたいだけど、ギンッと、あたし達を睨むその目は、即座に出て行けと言っていた。
「さやか、行こう」
ひろしに腕をとられ、あたしはあとじさる様に部屋を出た。
この洋館は、明治の時代によく建てられたような、外国人向けの住宅らしい。造りの一つ一つは、アールヌーボーとか、アールデコとか言うのかな、今では高価になりすぎて、誰も用いないような材料と手法が活かされている。だけど、古いせいだけでない、かび臭い様な寂れた雰囲気は、人が住んでいる感じをさせない。二人の居たところだけは、使っているって感じだったけど。
「すごい家だね。お庭もすごいけど。手入れすれば、立派なお屋敷になるのにね」
辺りを見回しながら、あたしは溜息をついた。だって、こういうお家って、女の子の憧れよね。きれいなら、だけど。
何しろあたし達の家は、広いことは広いけどつまらない。高水流の部分は純和風を装っていて、茶室もあるし、野点なんかも庭で出来ちゃう。だけど、実際の住居の部分はよくある折衷で、普通の家なのよね。純和風の部分は、桧を多用した平屋なんだけど、あたし達が住んでいるところは二階建てで、昔の土蔵を利用し、更に建て増しをしたもの。中なんて、どっかのマンションのモデルルームみたいに、ありきたりな間取り。夢に出てくる桜の庭は、あたし達の部屋の窓に面した裏庭で、そこに並んで車庫と通用口があるから、家の者はほとんど正門をくぐることもない。
うーん、やっぱり憧れちゃうな、ああいう洋館。
「もったいないなぁ」
あたしの足どりが未練たらたらだったせいか、ひろしが声を苛つかせてあたしの腕を持つ手に力を加えた。
「呑気なこと言ってないで、さっさと帰ろうぜ。日が暮れちまう。人様の家の手入れを文句つけたって、仕様がないだろう?」
「うーっ」
唸っているあたしを横目で見て、ひろしはフフンッと鼻で笑った。
「何がおかしいのよ?」
むっとしたあたしの声に、奴は弱いところがある。機嫌をとるように弁解を始めるのは珍しくない。それなら、最初からそういう態度をとらなきゃいいのにね。
ひろしは、弁解するでもなく、笑いを噛みしめながら言った。
「いや、さやかも、女の子なんだなって思ってさ。白い馬に乗った王子様に、あこがれる方だろ? さしずめ、チャールズみたいのがタイプでさ。こういうお屋敷に住むのが夢だったりして」
あたしは、ただ、じろりとひろしを睨めつけた。何となく、含むところがあるようで、素直に頷けなかったのよね。全部じゃないにしろ、当たっている部分はあったんだけど。
ひろしはあたしの視線を受けると、ふいって目をそらした。
その瞬間。
風圧が、すごい勢いであたし達を襲った。
「!」
ひろしに突き飛ばされて、あたしは塀に激突した。チャールズの家の塀は、ツタがびっしり絡んでいて、勢いの割に痛みはなかったけど。ただ、窒息しそうな程ひろしの身体を押しつけられ、あたしは面食らっていた。
すごいスピードで車が走り去っていく音がした。
「ひろし……?」
音は高い音から低い音にに変化しながら消えていったのに、ひろしが動かない。ひろしと壁に挟まれて、あたしも身動きできずにいた。
「大丈夫? ひろし……」
半ば押しのけるようにしてひろしの腕から抜け出すと、ひろしは、そのままの形で小刻みに震えていた。
「今の……、ブレーキ全然踏んでなかった。この道が、もう少し狭かったら……。……さやか……、怪我ない?」
「うん、ひろしは?」
「大丈夫。でも、車のナンバー見損ねた。くやしいなあ」
そうは言っても、ひろしのジャケットは裂けて、肩から腕のあたりの布地は赤が濃くなっている。出血しているんだ。
「大丈夫じゃないじゃない! 怪我してるよ、ひろし!」
「俺は、いいんだよ。さやかが怪我しなけりゃ……」
ひろしは、にっこり笑いながら言った。痛いだろうにやせ我慢して、困った子ね。
それにしてもホント、頭に来る。どこのどいつだか知らないけど、いつか事故って、死んじゃうんだから。
「こんな、すぐに来るとは思わなかったな。早く帰ろうぜ。また殺されかけたらたまらん」
「……物騒なこと言うじゃない?」
ひろしは肩をすくめた。目線は、あのロイ達がいると思われる部屋の窓に向けられている。
「さっきのチャールズの目。俺、あれで殺されるかと思ったけど、結構正攻法で来たよな」
「どういう意味よ?」
「あいつらの差し金だって事だよ」
「何のために?」
「ロイの変な病気を見た上に、俺が騙されそうもないからさ。さやかみたいにね」
またまた! 何言い出すんだか。
「ひろしぃ、らしくないわよ。今までで、一番無理のある話だわよ、それ……。冷静に考えれば、すぐ分かるでしょう? あの人達が、そんなことするメリット、全然ないじゃない。リスクの大きさ考えてみなさいよ」
ひろしの膨れっ面は、あたしの言ってることを認めていた。素直にごめんなさいが出ないのは、困りものね。まあ、あたしに言われても困るけど。
ひろしの態度が、以前より荒っぽくなったり、短絡的になったのは、中学に入ってから。ほとんどあたしに対してだけだから、周りはそんなに気にしてないみたい。あたしにしても、理由は分からないけど、ひろし自身がそんな自分を持て余し気味でいるようなので、気にしないようにしている。いつか、相談に乗れるようになりたいんだけどね。
帰り道は、それからあんまり話さずに、二人とぼとぼ歩いていたの。車に乗るには近すぎる、歩いてはちょっと遠い距離。まるで、あたしとひろしの間みたい。
日が落ち始め、あたしとひろしの影が、長く伸び始めた。二つ重なることなく進む。
「ずっと、こうなのかな……」
あたしは、無意識の中に口をついて出た言葉に、自分自身愕然として立ち止まった。
同時に立ち止まったひろしから、何か静電気のようなものが発散され、あたしの横ではじけた。
「なにが?」
少し震えた声で尋ねるひろしは、なんだかよそよそしい。尋ねながら、実は、あたしよりも言葉をしっかり捉えているようで、少し怖かった。あたし自身が、自分の言葉をつかめないでいるのに、ひろしには伝わったらしいなんて。見えない力で、裸にされてしまったような気がしてくる。
「何でもないの。自分でも何言ってんだか、よくわかんないんだから。気にしないでよ」
努めて能天気な声を出すようにしたんだけど、あんまり上手くできなかった。
「そう?」
ひろしは、そっけない声でそう言うと、足早にまた歩き始めた。ひろしの背中が遠くなるにつれ、胸の奥が、ゆっくり締め付けられように痛みだし、あたしは後を追えずに立ちすくんだ。
「………ひろしの馬鹿! ……」
思わず出た言葉は、弱い溜息になって消えた。たぶん、聞こえていないはず。
「さやかちゃん? どうしたの?」
突然、後ろから滑るように近づいてきた車から、聞き慣れた声がした。見れば、窓から首を半ばだして、吉住さんがこちらに微笑みかけている。
「吉住さんこそ。今、帰り? 一人なの?」
「うん。家元を送ってから後、もう一ヶ所まわるとこがあってね」
「お義父様、もう帰ってるの?」
「そうだよ。珍しいでしょ。帰るんなら、乗りなさい」
吉住さんがロックを解いたドアを開けながら、あたしは吐息をもらした。
義父は苦手なのよね。普段、あんまり家にいない人だから、助かってるんだけど。
あたしは高校を卒業したら、あの家を出る気でいる。出来れば、大学は遠くにして。学費は高水の家から出してもらうんじゃなく、亡くなった父の保険金とかで、あたし名義の奴を使うつもり。
この十年、世話になったのは感謝している。別に、普段の生活で差別されたりとか、そんなこともないし、かえって義父はあたしに気を使っているような所さえあるけれど。
でもね。
あの家で、あたしは、他人なの。そうね、吉住さんと似たようなものだわ。
あたしの戸籍は、南雲という死んだ父の姓のまま。
便宜上、普通は高水を名乗っているけど、パスポートや公的文書は、南雲じゃないと作れない。学校だって、特別措置として高水で通るようにしてあるけど、基本的な書類は南雲になっているらしい。
あたしが知ったのは、パスポートを作るとき。誰にもみせないようにしているから、ひろしも知らない。
不足のない生活をさせてもらっても、実の母がいるにしても、あたしが高水家にとって要らない子供であるという事実は、変わらない。初めて知ったときのショックが、胸の奥底にしこりとなって残っている。
義父に対して他人行儀になってしまうのも、そのせい。悪いけど、仕様がない。変な態度をとらなくて済むように、あまり顔を合わせたくないのよね。とりあえず、卒業までは。
「さやかちゃん?」
吉住さんの声で、あたしは我に返った。
「! ひろし。ひろしも、その辺にいるはずなの。あの子、怪我してるのっ! 早く手当しなきゃ」
キョロキョロと見回すあたしを、吉住さんは、車に引っぱり込んだ。
「帰るとこなら、途中で捕まえればいいよ。とにかく、動かないと」
なるほど、後ろに、迷惑そうな顔をした女性ドライバーが、辛抱強く待っている。
「ごめんなさい」
「ひろし君と、何か、あったの?」
「ううん。そうじゃないの。乱暴な車にひかれそうになって、ひろしが庇ってくれたの。それで、怪我までしちゃったのに、あたしがぐずぐずしていたから、荷物まで持って先帰っちゃった。手当してやらなきゃいけないのに、あのこったら、歩くの速くて」
「そう……。彼は、君を大切にしていると思っていたんだが。……僕なら、君を置いていったりしないな」
「え…………?」
吉住さんの低い声音は、あたしをどきっとさせた。
……何を言い出すの?
「吉住さん、そういう言い方、みんなにしてるの? 誤解されるよ」
「……してないよ。さやかちゃんだからさ。だけど、誰かさんは、友達との仲を取り持とうとするんだから。まいっちゃうよな」
「吉住さん………?」
何と言っていいか分からなかった。どうしちゃったの? って感じ。
人を混乱に陥れておきながら、吉住さんの方は、それっきり、前を見たまま機械的にハンドルを操っている。
「ああ、いた」
言葉通り、一つ目の角を曲がったところに、ひろしが立っていた。バスケットを地面に置いて。
「ひろし! 何やってるのお?」
車の窓から、声をかけると、ひろしの目がまん丸になった。
「おまえこそ! なんで?」
言いながら、目線を運転席に向けて、表情を強ばらせたひろしは、黙って後部のドアを開くと、乗り込んできた。頭の後ろにひろしの視線が突き刺さるような気がして、あたしは居心地が悪くなり、何度も座りなおしてしまった。吉住さんが、気を使うように、ちらっとあたしを見てから、口を開いた。
「途中で、さやかちゃんが、ぼんやり立っているのを拾ったんだよ。ひろし君、あんな所で待ってるくらいなら、最初から置いていかなきゃいいのに」
「…………」
ひろしは、黙ったまま。全く、この二人は……。どんな風に仕事してるのか、心配になってくる。今、車の中は、急にブリザードが吹き荒れ始めたような感じ。確かに、吉住さんの言い方にも、刺があるみたいだったけど、ひろしも頑なすぎるよね。
乗っている時間が短くて良かった。車を降りたとき、あたしは、大きく深呼吸した。
でも。
車庫入れしている吉住さんを残し、玄関へ向かう間、ひろしの冷たいプレッシャーに一人さらされ、車の中での気まずさは引きずったまま。
「ひろし、何をそんなに怒ってるの?」
「あ? 怒ってねーよ」
「嘘。怒ってる!」
ひろしは、気怠げにゆっくりと首を振った。
「何で、そう思うわけ? さやか、俺が怒るようなこと、した覚えがあるんだ」
「覚えがないから、聞いてるんじゃない。ひろしなんて、顔で、すぐ判っちゃうもん。今、ひろしは怒ってます。絶対怒ってる!」
ひろしは、いい加減にしろって顔で、肩で一息つき、あたしを見据えた。
「覚えがないならそれでいいじゃない。怒って無いって、俺は言ってんだから。今度言ったら、本当に怒るかもしれないぜ」
ひろしの目が大真面目で、とっても怖かったから、あたしは言葉を飲み込んだ。
「………吉住さん、何か言ってなかった?」
しばらくして、ひろしは、話をすり替えるつもりか、急にぽつりと言い出した。
「何か、って?」
もう、みんな、何なんだか。ひろしは、何故だか、あたしの返事に満足したらしい。表情が急に暖かくなった。
「いや、いい。なんでもない。俺、腹減っちゃった、早く飯喰おーぜ」
さっさと歩き出してしまう奴を追って、あたしも歩き出した。
「勝手なんだから。この男は〜〜」
あたしの言葉に、ひろしはリズミカルに振り返り、にっと笑った。機嫌がすっかり直ってる。今にも、スキップを踏み出しそうなほど。やーね、やーねっ。
だけど、そんな、ひろしがかわいくて、あたしまで、笑ってしまった。
あーっ、もうっ。疑問符で溺れそう。自分の気持ちすら掴みかねているんだから、人の気持ちなんて、そうそう解るもんじゃないけどね。でも、知りたいし、解りたい。
うん、そうだ。美代子のことも。チャールズとのつながりだって、聞いてみたい。
それで、夕食後、美代子の家に電話してみた。お母さんが出て、気分が悪いと言って寝ているからと、取り次いでもらえなかったけど。
「何、つまんなそうな顔してんだよ」
受話器を置いたところで、通りがかりのひろしが、あたしの頭をクシャクシャッとやった。
「なにすんの? あんたこそ。……美代子が調子悪いんだって。電話かけたんだけど、出てもらえなかったのよ」
「御園さんが?」
ひろしは笑顔を消し、眉根を寄せた。
「また、変なこと考えてるでしょ」
「別に。……あの人、最近変だろ? 今日のことといい。明日、学校こなかったら、見舞い行けよ」
「うん…………」
言われなくても!
美代子は、あたしの友達なんだからね。
そう思いながら、口には出さなかった。ひろしと言い合うのは、もう沢山て気分だったから。