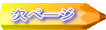5
あたし達のチームにロイが来るようになってから、二週間が過ぎた。思った通り彼は良いコーチで、子供達もレベルアップ間違い無し、と、いう感触。あたしも、本当の監督に胸を張ってチームを返せるから、すごくうれしい。
ひろしが辞めた後、監督の留守中は、監督の学生時代のお友達でプロの選手が、時間を割いて来てくれていたんだけど、やっぱりそんなに頼っていられないもの。忙しい人たちだから。
学校の都合で、どうしても後から顔を出す形になるあたしの代わりに、ロイは、あたしよりも先に来て子供達の自主トレの面倒をみてくれていた。その上、帰りは家まで送ってくれて、しっかりナイトの役目までしてくれる。これはオフレコだけど、英語の宿題も手伝ってもらえるの。
あたしは、自分の選択に満足しつつ練習風景を見守った。
「さやかーっ」
ロイがあたしに気づいて、子供達に囲まれながら手を振った。
「今日は早かったね」
いち早く駆け寄って来てロイが言い、後からみんなが集まって、あたしを取り囲んだ。
「今日は授業が午前中だけだったの。それで、試合決めてきたからね」
子供達が一斉に歓声をあげた。
「どこと?」
「黄金SCだよ」
あたしの予想通り、どよめきが広がった。相手チームは、全国大会でも常連なのよね。
「いつ?」
「さ来週の日曜日。場所は黄金学園内のグラウンド。十時にキックオフ、九時にJR鶴見駅集合ね。みんな、自分の上達ぶりを、この試合で確かめてね」
子供達が元気に返事をしてはしゃいでいる中、ロイの顔色が優れないのに、あたしは気がついた。
「ロイ…? どうかした? あ、都合悪い日だったら、無理しなくてもいいからね」
ロイは、困ったという顔をして微笑んだ。
「都合は悪くないし、行きたいんだけど、……朝に弱くてね。……でも、行くよ、がんばって」
「よかった、みんな喜ぶわ。お弁当作って行くからね」
「楽しみだな」
ロイの穏やかな微笑みは、いつでもあたしを安心させるものを持っている。あたしは短い間に、ロイと話したり笑い合うのが、大好きになっていた。
練習の帰りには、その道すがら、いろいろと語り合った。ロイは聞き上手で、あたしの家の事、ひろしの事、学校の事……、とにかく、あたしはいつの間にか、かなりの情報をロイに与えていた。それに反してロイは、自分達の事にはほとんど触れない。いったい、何をやっているのか、あたしの問に対しては、抽象的に『旅をしている』とかしか、言ってくれない。しかし、それもあまり気にならないくらい、道々出会う自然物についてのロイの話は面白かったので、許す事にしたの。ちらほらと見えかくれする博識ぶりもさることながら、何もかもが愛しい、と、いうような熱っぽい語り口が、あたしの心のどこかを揺さぶるの。
そして、口癖は、
「自然は皆、心から語り掛ければ応えてくれるんだよ」
………なの。
聞きようによっては、かなりクサいセリフだけど、彼の口から出ると、本当って気がして不思議。小さい頃から、歩きなれて、見慣れたものばかりの道ですら、彼と歩くと、初めて来たところのように新鮮に感じるの。
「ものの見方が、全く違うのよね。それにね、今日なんか、ロイが幹に触れたとたん、桜並木でざあっと花吹雪起こっちゃって。もう、ほとんど葉桜なのに、よ。不思議な人よね」
夕食の席でロイの事を話していたら、向かい側に座っていたひろしが、箸を止めた。目線がまっすぐあたしに向けられ、一瞬突き刺すような光がその瞳に走った。また、意地悪を言われるかも、と、あたしは心密かに身構えたのだけど……。
「さやか、あの夢の話はした?」
なんか、違う。
「してないわよ。あれからみてないし。別に、会った人毎に話してまわってるわけじゃないもの」
ひろしは、気むずかしげな顔をして言った。
「あいつにしてみればいいよ。きっと、なんか違った反応するぜ」
「引っかかるわね、その言い方」
「そお? 別に他意はないけどね。ただ、俺は、あいつが気に入らないだけだ。あいつは、どっか変なんだよ。ぜーったい普通じゃないね」
もどかしげな、いらいらとした口調で言いきるひろしにむっとして、あたしは言葉を返した。
「なにひねてんのよ。何が気に入らないわけ? よく知りもしない癖に、あの人、良い人よ。あ、サッカーで負けたから?」
「ちがっ!」
ひろしが、頬をカッと燃え上がらせて、反駁しようとしたとき、今まで黙って聞いていた母の怒声がとんだ。
「さやかっ! 言い過ぎよっ。ひろしも、知らない人の事、悪く言うものじゃなくてよ」
母は、怒ると結構恐い上に、くどい。あたし達は身を竦ませ、上目遣いでお互いを見て休戦協定を結んだ。
「それにね、さやか、夢って、いつものあれなら、もう喋って歩くのやめなさいって、言ってるでしょ。誘拐犯の記憶なんて、頭の奥にしまっときなさい」
あたしとひろしは、顔を見合わせた。あたし達の記憶には、誘拐のゆの字もないのだから。
「誘拐って?」
二人でハモッてしまった。
母は、薮蛇って顔をして、口元を手で覆った。
「あら? オホホ」
笑ってごまかす気だ。うちの母の得意技。
「あら、じゃないわよ」
「オホホじゃないよ」
今度は、二人で不協和音。怒った母も恐いけど、あたしとひろしの共同体も、結構影響力あるの。
左右からあたし達に睨まれて、母は首を竦めた。
「……七つの時にね、さやかは丸一日誘拐されていたのよ。身代金要求の電話もあったし、本当の誘拐だった筈なのよ」
「なんだよそれ、俺、全然知らないぞ」
「ひろしはその二日前くらいから、熱だして寝込んでたから、事件からつんぼさじきだったのよ。大体、そんな事を小さい子に、いちいち説明する大人は居ませんよ」
「それで?」
あたしは、ひろしに黙ってるように合図すると、先を促した。
「次の日の夜に、一人で帰ってきたのよ。夢見たとおり、夜桜の花吹雪の中に立ってたの」
「なにそれーっ?」
あたしは、狐につままれたような想いでいた。ひろしと二人、もう一度顔を見合わせる。
「つまり、犯人が、さやかの頭を撫でて、家まで連れてきてくれたって事? ちょっと変じゃない?」
ひろしの問に、ふぅっと母は、ため息をついて言った。
「だから未だに、犯人出てこないんじゃない。はっきり言って、さやかは知恵遅れじゃないかって、あの時心配したわ」
飲み掛けたお茶を吹きそうになって、あたしは、慌てて口を押さえた。ひろしは、肩をゆすって笑っている。
「お母さん、ひどーいっ」
「だって、警察でなに聞かれても、あんたは、あの能天気な話しかしなかったのよ。お母さん、恥ずかしかったわぁ」
ひろしが、とうとう耐えきれずに爆笑した。ったく、人ごとだと思って、あん畜生。
「あれは、犯人じゃないわよ、きっと。だって、とっても優しかったもの。犯人の事、全然覚えてないなんて、確かにあたしも変だと思うけど、でもね、これだけは絶対って気がするの」
あたしは、かなり熱を込めて言った。だって、本当、これだけは譲れないもの。
ひろしは、ふと真顔になった。
「さやかの言うとおりだとすると、誘拐事件には、第三者が絡んでるってことになるな。第一、その方がすっきりする。結局、金もさやかも無事だったんだよね」
「誘拐して電話かけた奴と、あたしを返してくれたのは、別ってわけ?」
「そう」
「もしそうなら、その人にお礼しなきゃいけなかったのに。さやか、恩人の顔も覚えてないなんて、恥ずかしいわよ」
「そんなこと言ったってぇ」
「そいつにも、なんか後ろぐらい事でもあったんだろうな。門前にちっちゃい子一人残して、かえっちまうんだから」
「あら、何で知ってるの?」
「よく覚えてないけど、俺、窓から見てたような気がするんだ、そのシーン。……俺のは、夢じゃない」
そう言った後、ひろしは、ちらっとあたしを見た。その目は、一瞬鮮やかな炎を浮かび上がらせ、まだ何か言いたげに揺らめいた。
「なに?」
「いや、なんでもない」
それきり、ひろしは黙りこくって、残りのご飯をかき込むと、
「ごちそうさま」
と、言って、さっさと部屋に下がってしまった。
お手伝いのトキさんが、即座にあと片づけを始め、あっという間に、ひろしの席はきれいになった。義父と吉住さんが外食なので、食卓には、あたしと母の二人だけになった。
母は、じいっとひろしの席を見つめている。
「……さやか、ひろしと何かあったの?」
「?」
あたしは、母の顔をのぞき込んだ。真顔で言っているのだけど、真意を量りかねたのだ。母は、あたしの反応から、あたし自身には身に覚えがないのを嗅ぎ取ったらしく、深いため息をついて続けた。
「仲良くしなきゃダメよ。お姉さんらしくね」
「ひろしがつっかかってくるの、止めたらね。それに、あいつったら、ちっともあたしの事を姉扱いしてくれないんだもん。そういうの、あいつに言ってほしいわ」
母の困った顔を見て、あたしは口を噤んだ。解ってる。立場が違うんだよね、あたしと、ひろしでは。こういう場合、母は、まずあたしに言い、それからひろしに言う。いつもの事。ま、なるようになれ、よね。
ややこしい事は棚上げにして、あたしは、お茶を啜りながら考えた。あの夢をしつこいほど見た理由が、やっと解った気がする。手がかりは少ないけど、あたしの意識は、あたしを送ってくれた人を忘れないように、繰り返し記憶を反芻させていたんだと思う。
……、それにしても、犯人の記憶はどこいっちゃったんだろう。