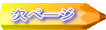序
「彼女、夢を見るそうだ」
「ほう……」
「七つの時の桜吹雪の庭……。それが舞台だ」
「……。まずい……な……、破綻したようだ……」
柔らかく響く声は、深刻そうな物言いの割に面白がっているようでもある。
「どうやら、動かざるを得ないようだ。君、接触してみるかい?」
丹念に磨かれた爪を見せつけるように、青年は優雅に、もう一人に人差し指を突きつけた。
「ん……。しかたない……な……」
指さされた青年は疲れた溜息をつきながら、腰掛けていた木の枝から飛び降りた。
1
そこでは、あたしは七才の子供だった。
何もない、上下の感覚すら危うい、まったりとした空間に所在なげにたたずむ子供。
それがあたし。
この空間自体が投げかける感覚は、迷子のままに歩きまわって全く知らない所に出てしまった時の不安感に似てる。
あたりを見回しているうちに、突如これまでになかった人の気配をすぐそばに感じて、あたしはすくみ上がった。
「怖がらないで…、お家まで連れて行ってあげよう」
甘く穏やかな響きでそう言ってあたしの頭を撫でた手は、やけに冷たかった。でも、とても優しかったので、安堵感があたしの心に広がった。
誰だろう。
いくら首を巡らしてみても、その人の顔をみることができない。密度の高い闇に覆われているようで、わかるのは手の感触と心地よく耳に触れる低い声。
ずうっとこの優しさに身をゆだねていたいなどと思い始めてると、あたしの頭を撫でていた手が、ふっと消えた。
「いつかまたね、ジャパニーズドール。早く大きくおなり…」
声とともに突風が色彩のある闇を吹き飛ばし、あたしの目の前には自分の家が立ちはだかっていた。どこにも人の姿は見あたらない。ただ、庭の桜の木から吹雪のように花びらが舞い降りてくるばかり…。