
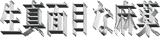 龍樹サイド
龍樹サイド
『いい加減にしてくれないか? 君、今日退院の筈でしょう?』
『だって、先生はまだ治してくれていないわ。私の、ここ……』
胸をさする赤い爪の小さな手。
鼻にかかった甘え声。
『そこは専門外だね。別のドクターを紹介しよう』
『先生じゃなきゃ嫌! 先生しか治せないのよ!』
『僕には絶対無理だよ。第一、君は勘違いしている。何で僕等の間に恋愛感情が湧くと思ったのか、僕には到底理解できないね。届けられた患者を機械的に診ただけなのに……』
『好きになるのに理由っていらないと思うの』
微笑んだ鼻声を伴って絡みついてきた腕を払うとき。僕は嫌悪感しか持てなかった。
『僕は君を愛せない』
『……冷たいのね……』
『そうしないと、また君は勘違いするだろう? 僕と君は医者と患者の関係だけしか成立していないと思うんだけど……。最初からね』
『傷が治れば……その関係すらなくなるのね』
真っ赤な唇が歪んだ笑みを作った。
ゆらりと僕の前に突き出された両手。
シュッと剃刀がひらめき、びちゃっと生暖かい飛沫が僕の顔面を襲った。かけていたゴミ避けの素通し眼鏡も真っ赤なスクリーンにふさがれ、僕は視界を失った。
『あたしの血、綺麗でしょ? ねえセンセ、これでまた貴男の患者よ……私……』
勝ち誇ったような笑い声がいつまでも響く。思わず僕は耳を塞いだ。
瞼の中のスクリーンが赤から臙脂に変わった。
光の加減を意識してしまった自分に心の中で舌打ちしながら、夢のように甘美な一夜の名残を、指先に力を込めて確かめようとした。
いない……。
改めて手探りをしてみて……。
いない……。
夢だったのだろうか。本当に。
嫌だ。それなら一生目覚めなくたっていい。
目尻に涙が滲み出そうになる。
拓斗がいない。
いない!
嫌だ……!
叫びをあげようとした時、不意に腕を持ち上げられ人肌の感触が滑り込んできて……。
そっと胸に押しつけられた髪の感触が僕に安堵感を与える。
僕は幸せを抱き締めた。
滑らかな肌を直に合わせて息づいて。ほんのり温かく柔らかで、けれどしなやかな筋肉の堅さが息づく度に手のなかでそれと主張する。
「拓斗……拓斗……愛してる」
眠りについた耳に囁きかけて。
ゆったりと息づく肩を抱きしめ、その感触を楽しんだ。
向坂拓斗。
アメリカから帰国して半年後に出会った僕の運命の人。
僕の店『El Loco』の開店初日に客として現れたのが最初。
一目で好きになって、受け入れてもらえなくても側にいるだけでいいと思うようになった。
初めて告白して髪に触れたときには、緊張に全身をこわばらせ、男に想いを寄せられることの戸惑いと困惑を「わからない」という言葉で伝えてきて。
そんな彼が、僕を受け入れるためにどんなに悩んだか。想像に難くはない。
友人の紫関にカミングアウトしたときは文字通り僕から一メートルは飛び退いた。僕が彼に望んでいるのはただの友情だと理解してからは、ある程度解ろうとはしてくれているみたいだが。それでも、女性に興味を持たない僕という人間を、どこか壊れているんだなと言う目で見つめる。
それが普通の反応。
だから拓斗も同じように反応するだろうと覚悟を決めて告白した。
どうせ報われないなら僕の本当の気持ちを知って欲しくて。
彼がガールフレンドを連れてくる度、理不尽な嫉妬心で焼けただれたような気分になる。知らないで見せつける拓斗に対して、しまいには憎しみさえ抱いてしまいそうになって。僕の密かな片思いは抱えきれないほどに膨らんでいたから。
結果は、拒絶と友情。
それから僕は諦め気分で指をくわえ、物欲しそうな目で彼を見つめるだけの生活を強いられてきた。
彼が僕のそばに来てくれるだけでもうれしくて。
まるで麻薬のようだ。
経験してしまった瞬間の甘美さが消退すれば、更なる苦しさが待っているのに、やはり甘さに酔いたくて求めてしまう。
昨夜のような至福を味わってしまった僕はもう、自分を抑制することが出来ない。
愛しているし、愛されたい。
そんな見返りを求める愛に溺れてしまいそうになる。見つめるだけで幸せになれた僕はもういない。
「君は……大変なことをしてしまったんだよ。悔やんでも、もう遅い。僕は変化してしまった……」
無邪気な寝顔に見入りながら囁いてみた。
絶対、君を離さないからね。
僕の独占欲を、君は知らない。ひたすら忍耐力だけで触れてきた僕しか知らない君には、僕の中にこんなドロドロの想いが存在することが理解出来ないかもしれないね。
どうか、それを知ったときにも君が背を向けないでいてくれますように……。
これからもこの甘美な麻薬を僕だけのものにしておけますように……。
「ん…………」
目覚める直前の浅い溜め息。それすらも僕にとっては誘惑の仕草。
二、三度瞬いた瞼がくっきりと見開かれ、黒目がちの瞳が、覗き込んでいた僕の視線を捕らえた。すっかり骨抜きにされた男がそこに映っている。物欲しげで、所在なげで、情けないほどしょぼくれた桂川龍樹という男。
寝ぼけ眼の定まらぬ視線のまま僕を見つめていた拓斗は、僕が覗き込んでいたのを頭の中で認識した途端、飛び上がるように起きあがった。
「うわあああっ、龍樹さんっ。おはっ、おはっ…………はよっ」
うわずった叫びで始まった朝の挨拶を、後半は消え入るような小さな声で呟いた。
俯いた首筋から耳たぶから、見えるところ全てが茹で蛸状態の君は、なんて可愛いんだろう。
「おはよう……」
肩を抱き寄せた。
瞬間抗いながらも、口づけを許してくれて。息継ぎも不器用に僕の舌を受け入れ、応えてくれた。
僕がその反応に十分満足して彼を解放すると、とろけかけた瞳で小さな吐息を吐き、更に真っ赤に染まった頬を肩口に寄せてくれた。
「龍樹さん……俺……」
「ん……?」
努めて平静な声を出しながら、どうか「やっぱりだめだ」なんて台詞を出してこないようにと胸の内で祈った。
拓斗は所在なげな瞳で僕を見上げてきた。
「俺、変じゃない? 今の俺……変だよね?」
ああ、何を言い出すんだか。
「どこも……変じゃないよ。向坂拓斗という、ものすごく魅力的な男が僕の目の前にいるだけで」
「俺……、今ね、世界で一番恥ずかしい男になった気分……」
「どうして?」
僕に抱かれたせい?
「後悔……しているの?」
声が震えてしまう。
思いがけず与えられた幸せは、自制心や忍耐力を僕から根こそぎ取り去ってしまったらしい。
(ぼくを捨てないで)
言葉にはしたくないその台詞を、全身で表してしまっていただろう。
「違う! そうじゃないっ!」
慌てたように拓斗が抱き締めてきた。ひたりと触れる肌の感触すら失いがたく、泣きそうになる。
「あー、もうっ。俺ってどうしてこう、口下手なんだろ。ね、俺、ホントに龍樹さんが大好きなんだよ!」
ズキンと、拓斗が密着したところから心臓に痛みが集束していく。この感動をどう伝えたらよいものか。
抱き締めて、愛らしい唇を貪って。疲れ切った彼をまた……。
そんな僕の欲望を知ってか知らずか拓斗の腕に力がこもり、背中を優しく撫でながら上気した体を押しつけてきた。
「龍樹さんが俺を変えちゃったんだ。こんな……龍樹さんにキスされた途端に俺……」
腿に触れた熱くて固い感触は一昨日まで禁断の果実だったもの。そっと盗み見て確認したそれは、生理的な朝の営み以上に欲望に膨れ上がり、逞しくそそり立っていた。
「俺……恥ずかしい。きっと、みんなにも分かっちゃうよ。今の俺、そういう顔してるもん。きっとしてる」
泣き出しそうな声音。
「俺ったら、あんな龍樹さんを悩ましてた癖にっ! まるで……まるで、色情狂みたいじゃないかっ」
「!!」
僕は言われた瞬間に彼を押し倒していた。
なんて事言うんだろうね。それじゃあ、僕は何なんだ? いつだって君が欲しくてたまらない僕は……?
彼は恥ずかしさに燃えながら視線を逸らして……。素直に僕を欲しいとは言ってくれそうもない。
上気した滑らかな肌にぷつんと起った葡萄色の乳首。首筋にも鎖骨にも、胸にも……、腕、脇、腰、内股にも、昨日僕が刻印した愛の証が浮かび上がっている。
そして、愛らしく震えるバラ色の男根。
全てが僕のなけなしの自制心を吹き飛ばそうと誘惑している。
僕を獣に変えてしまう力を彼は持っているんだ。
「……恥ずかしいことなんてないよ。君のここがこうなのは……」
言いながら彼を握りとった。
「はんっ……。いや……だ……」
やんわりとしごくとピクピクと戦慄しながら、のけぞった。
「君が僕を好きでいてくれる証拠なんだから……」
ゆっくりと責めるようにしごきながら、昨日の夜の愛の印を唇でもう一度辿った。
拓斗の全身が僕を欲しがってくれている。嫌じゃないって……、したいって……。
嫌われたくないばっかりに欲しいと迫ることが出来なかった僕をこんなに喜ばせることはない。
「昨日の今日だし、疲れてる君のために我慢しようと思ってたのに……とても出来そうもない……。また欲しくなった。……いい?」
「あ……んっ。だ……め……」
切なげに喘ぐ甘い声でそんな風に言われても、止まれないよ。いつも素直なくせに、どうしてこういう時だけ素直じゃないのかな……。
「……な様にも見えないけど……やめる?」
「んっ。やっやだ!」
内股にキスをしていた顔を上げ、手を止めると、拓斗の手が僕の頭を抑えるように鷲掴みにした。僕を求めて喘ぐように呼吸する彼の菊花に導くように押さえられた。誘われるまま指と舌でそこをなぶる。
「ああっ! 龍……樹……さんっ! そこっ……んんっ」
甲高く裏返った喘ぎ声が微かに残っていた僕の理性を完全に払拭してしまった。
こんな風に僕を求めてくれるなんて。そんな自分に戸惑っている君。可愛くて、どうしようもなく愛しくて。
「あああああんっ」
彼自身を口に含んで舌で撫で上げた途端に悲鳴が上がった。
そんな自分を叱りつけるように歯を食いしばって喘ぎをかみ殺そうとする。
「君は……誰にされてもこうなる訳じゃない。僕だから……僕のキスだからこうなるんだろう? 君を狂わせるのは僕だけ……そう言ったじゃないか。君は……僕だけのものだ。僕だけの……」
「あっあっあっ……やっだっんんっ」
絞り出すように彼を責め続ける。指で根元を押さえながら舌と唇でしごいて。
「んっんくっ……。ああああっああぁん」
弓なりに仰け反りながらフルフルと痙攣し、とうとう僕の口の中に撃ち出した。僕にとってはどんな妙薬よりも効果のある薬。至福の気分で飲み下した。
それだけでイッてしまいそうになる。熱く動悸する自分の暴発を先送りにするにも力を振り絞らねばならないほど。
そんな猛り狂う僕を彼のそれに擦り付けると、喘ぎが甘く艶めいた。
「は……う……」
指を突き入れて侵入の準備にはいった。ビギナーの強張りが嬉しい。犯す指を増やしながら解いていく楽しみは彼を征服していくという実感にあふれている。
「ふ……」
指を三本に増やしたあたりでヒクヒクと呼吸した。とろけかけ、うねり、もう一度拓斗が元気を取り戻すのを助けるほどに感じているようだった。
「僕だって……君じゃなきゃこんな風にならない。君だから……僕は……」
喘ぎが苦しくて、語りかけるのが辛かった。語るより拓斗の中に入って落ち着きたい。熱い火口を貫いて、揉みしだかれる快感に全てを委ねて……。
「ひあぁっ」
解けきるのを待ちかねて彼を貫いた。悲鳴を耳にして狼狽しながらも止める気にはなれず。
「拓斗、君を愛してる。愛しているんだよ」
ぐいぐいと押し出される力に逆らいながら中に侵入していく。それは快感なんて言葉で表現したくはなく。全ての神経細胞が悦びに溺れて麻痺し始めている。
今、僕は拓斗の中にいる。そこから動悸が重なっていく。まるで一つのものに溶け合っていくように。
拓斗のすんなりと長い脚が腰に絡みついてきた。
力を盛り返した彼自身が固くなって腹をつつく。
「あっあっあっ……やんっ……たつ……っきさんっ。っもっと! もっとぉ!」
僕が突き上げる度にリズミカルに腰をくねらせながら声を上げ……。
「あああん。い……いぃっ……っ。やだ……こんな……俺……どうかしてるよぉっ」
ほんの一瞬我に返ったようにそんなことを呟きながら目尻から涙を伝わせた。
「は……あっんんっ。も……もうっっっ」
熱いほとばしりを下腹部に感じ、僕も拓斗の中に撃ちだした。
僕の腕の中で崩れ落ちながら、困惑の表情を浮かべて顔を背けてしまった。
涙ににじんだ瞳は恍惚感の奥に後悔の光を隠し持っているのを曝してしまっている。
拓斗、君は……。まだ自分の中でわだかまりを持っている。
男に抱かれることを本音では良しとしていない君。快感に浚われて欲望の虜となった自分を恥じる君。
君のそんな部分すら僕にとっては愛しさの対象でしかない。
けれど。
これから先、一度解放された僕の欲望は僕自身を凌駕し、君を巻き込んでしまう大渦となって僕等の今まで築き上げてきたものを全て突き崩してしまう可能性がある。
そうして君との間を引き裂かれてしまったら……。僕は、君を独り占めするために君の命を奪ってしまうかもしれない。変質者のような執着を持って。
そんな自分が怖い。
胸の内で大きな溜め息をつきながら、僕は拓斗の中から恐怖に萎えた僕自身を引き出した。
「ああ……んっ」
瞬間嬌声に近い喘ぎが拓斗の口から漏れ、そんな自分の声に慌てたように身じろぎして。恥ずかしさで真っ赤になってしまった身体を毛布をたぐり寄せて隠してしまった。
隠し損ねている肩に口づけをしたら、ビクッと怯えたように身体を強張らせた。
大丈夫。もうしないから。
喉元まで出かかったけれど、飲み込んだ。
代わりに出たのは、いつもの台詞。
「朝御飯、何がいい?」
「あ……。何でもいいけど……」
歯切れの悪い言い方。こういうときの拓斗は僕を拒絶した後の自己嫌悪に陥っているらしく。
元気がないのは、僕のせい?
それとも疲れているから?
「そうだな……、今朝はワッフルって気分かな。旨いジャムが手に入ったし、フレッシュバターと、……好みでメイプルシロップもあるよ。カナダの友達が送ってくれたんだ。それに、君は二つ目玉のベーコンエッグでしょ。あー、野菜どうしようかな。サニーレタスとオニオンスライス、ラディッシュあたりでいい? 温野菜もつけようか」
頭の中のメニューを並び立てる度、拓斗の瞳に輝きが戻ってくる。
「うん!」
拓斗にとって食事はとても幸せな行為。
僕が作ったものをそれは嬉しそうに口にする彼に、どのくらい救われてきたか。見ているだけで僕まで幸せになれる表情。
『El Loco』開店初日、彼が僕の煎れたコーヒーを初めて口にしたときの表情を思い出す。
素直な感動がその可愛らしい顔に浮かび、煎れた僕を見上げると驚いたように黒目がちの澄んだ瞳を見開いて見つめた。
「美味しい……。こんなの初めて飲んだよ」
『美味しい』は言われ馴れていた。しかし、プロとして金を取っていけるかは不安があった。この町で定着していけるかどうか。僕の味が客の心を掴むことが出来るかどうか。拓斗の素直な反応がどんなに当時僕を元気づけたか。思えば、あの瞬間から、彼が僕の特別になったんだろう。一目見て恋を覚えた相手だけれど、愛しさが膨れ上がり始めたのは……多分……。
そんな彼が不意に心配そうに僕を覗き込んできた。
「龍樹さん……具合……どうなの? 熱は?」
そうだ、この幸せは僕の体の不調を心配してくれたからこそ与えられたものだったね。
確かに昨日の夜の僕は……。心と体のバランスがとれなくなっていた。
拓斗を真冬の海から救い出して連れ帰り、風呂で温めたあの日。僕は彼の全裸を目にしてしまった。それまでは夢で思い描く想像に過ぎなかったものが、実在感を持った3Dホログラムのように、触れることだけは許されぬ実物として僕の目前に……。あの時はそれどころじゃなかったけれど、脳裏に焼き付いた想像以上に美しく魅惑的なそれは僕を毎日毎晩苛んでいた。
それが二週間。
彼の姿を目にする度、頭の中で彼の服を剥ぎ取った。彼に微笑みかけられる度、抱き締めて押し倒しそうになる腕を見えないようにつねって押さえた。僕に話しかける口元の動きをうっとりと見つめながら、柔らかそうな唇に僕のそれを重ねて、舌をねじ込んだときの感触を想像した。
夢とも現実とも区別の付かぬ妄想の中で、拓斗は僕を誘い続けた。時には本物の拓斗が絶対しそうもない淫猥な動作で。なのにその身体は細部まで本物の拓斗のもので、抱き心地も僕の腕はちゃんと覚えていて。
彼が気持ちだけでも僕を受け入れる用意があると知ったとき、僕ははじけた。
無理矢理にでも僕のものにしてしまいたい。
そんな想いに駆られるほど追いつめられていたのだけれど。
実際そんなことをしたら破局が来る。
今度こそ僕は全てを失う。
きっと彼は言うだろう。
(そんなのは愛じゃない!)
好きだと言ってくれていたその口で僕を罵り、二度と『El Loco』には現れないにちがいない。
理性的な恋を出来る身体なら苦労はない。拓斗を愛する気持ちは、本物の筈なのに。毎夜肉欲に苛まれる自分を嫌悪する。いつまで自分の中の獣を抑えることが出来るか、それが不安で。時に暴発しそうになるその激情は、拓斗を傷つけるものにしかならないだろうに。
だからこそ出来ぬ我慢を、無理矢理にでもし続けていくしかなかったのだ。
そんなストレスが僕の体に異変を起こした。
僕の熱情は本当に発熱という手でもって吹き出てしまったのだ。
しかし。
僕は救われた。
同情だろうがなんだろうが、拓斗がその身を投げ出してもいいと思う程度には僕のことを愛してくれているのだから。
僕の気持ちと彼の気持ちは、同じ好きという言葉でも中身が違うのだと彼は言う。
言いたいことは分かるけど、好きには違いないだろう?
その比重と密度が違うだけ。
今は僕の気持ちの方が君に勝っているけれど。いつかは僕と同じだけになってくれるよね?
それが今の僕の夢。
拓斗の頬にそっと手を遣り軽く撫でた。愛していると精一杯の想いを込めて微笑みかけて。
「僕はもう大丈夫。現金なものだよね。君っていう極上の薬を飲んだら、治った……」
そんな僕の台詞はまた拓斗を赤面させてしまったけれど。
「起きれる? 朝食、ここに持ってこようか?」
拓斗は一瞬僕のことを見上げ、気恥ずかしげに目を伏せた。
「龍樹さんこそ……。その……、疲れてない?」
君にそう言って貰えるだけで元気百倍なんだよ。
「心配してくれるの? 何ならもう1ラウンドいく? 君が相手なら、僕はまだまだいけるよ。十回でも……」
「ば……っ……か……。死んじゃうよ……」
これ以上は無理というほど赤面して呟く君。大好きだよ。
「さて、君を見てると、また食事作るの忘れてしまいそうだ」
ベッドから降りてパジャマの下をはいた。
上は彼に着せかけ、額にそっとキスして。
今度は強張ることなく受けてくれた。
「超特急で作ってくるから、もう少し寝ていなさい」
「ん…………」
君のための最高の味になるように作るからね。
ベッドに置いた広めの盆をテーブルに、僕と分け合ったパジャマの上だけを羽織った拓斗と胡座をかいて向かい合った。
拓斗の表情を見て、見た目も合格点を貰ったのが分かった。
「おいし……!」
ワッフルを頬張りにっこり笑った。それはそれは幸せそうな笑顔で。
「よかった……」
僕が見つめているのを意識した途端、拓斗の頬に朱が走る。
「そんな、見ないでよ。俺、龍樹さんに餌付けされてるペットみたいだ」
照れた台詞に笑った。
「ペットはひどいな。知っているかどうか知らないけど、君は食べているときが一番幸せそうに見えるから……。その表情見たさに僕が料理に力入れてるって言ったら、信じるかい?」
「ん……」
恥ずかしそうに俯いたまま頷いた。
今日も君を独占できたら……もっとそんな可愛い表情をさせてみたい。
「今日の予定は?」
「えと……、親父の会社に行く」
残念だな。一日中一緒に過ごせるとよかったのに……。
「会社?」
「親父が頼んどいてくれた人に、保証人のサインとハンコ、貰いに行くんだ」
……冗談じゃ無いぞ。
「何の保証人なの?」
「入学手続きに、一応親以外の保証人の欄があって……。要するに授業料支払いの保証だと思うんだけど……。俺んち、親戚ないし、誰かに形だけ書いて貰わないと……。他の手続きは済んだんだけど、その書類だけなってくれる人探すのに手間取って……。事情話して待って貰ってるんだ」
……そんな大事なこと、僕に黙っていたのか……?
「それ、いつまで?」
つい口調がきつくなってしまったら拓斗がビクッと身をすくめた。
「二十五日まで……」
怖ず怖ずと応えた彼に慌てて微笑みかけた。
「あー、そういえば。健康診断書とか、色々あったね。思い出した。僕の頃もなんだか色々揃えたっけ……。うーん。それって、その人じゃないとだめ?」
「え?」
「保証人には僕がなる。なりたい。……君のそんな大事なこと、いくらお父さんが頼んだ人でも全くの他人になんてやらせたくない。僕の知らない奴になんか……」
「龍樹さん……?」
眉をひそめた表情が断るつもりだと明確に伝えてくる。
また僕との間に壁を作るつもり? 一番大切な人っていう君の表現、僕にとっても同じなのに。
「これから君んち寄って書類取ってきて、その足で学校まで出しに行けばいい」
押し切るつもりで言い募った。
「ちょっ、ちょっとちょっと、お店、どうすんの?」
「拓斗のためならいつだって定休日!」
「だ、だめだよっ! そんなの。そんな……、俺、なんて言うか……」
オロオロと首を横に振って身を退いた彼に縋った。
「ねぇ、僕にやらせて。大丈夫。そのくらいの資産はあるから」
「龍樹さん!」
首を横に振り続ける拓斗。
たたみ込もうと屁理屈を口にした。
「会社のその人だって、形だけだからって事でなってくれることになったんだろう? 僕は……ほんとに必要になったときはちゃんと保証人やれる。万が一の時……、ちゃんと出来るよ」
グッと詰まって視線を逸らした。
「でも……」
君は変に律儀だね。もどかしいくらいだけど、魅力でもある。そんな君だから全てをつぎ込みたくなるんだ。
「君をそれで縛ろうとかは思ってないから……。ねえ、そうして」
躊躇いがちの揺れる瞳で考え込んだ拓斗は、うんという返事を待つ僕に根負けしたように微かに頷いた。
「龍樹さんに迷惑かけないようにするね……」
拓斗の役に立って特別なポジションを得たい僕はうれしさに思わず彼を抱き締めていた。
「ありがとう……」
僕の囁きに拓斗は困ったように俯いて。
「それは俺の台詞だと」
他人行儀な台詞を吐こうとする口をキスでふさぎ、遮った。
「……嬉しいんだ。君の役に立てるのが……。……今年のホワイトデーは一生忘れられない日になったな…………」
つい感慨深げな声になってしまう。ホワイト・デーにこだわるつもりはないけれど、記念日にしてしまいたい気分だった。
「……、別にお返しのつもりだったわけじゃないよ。龍樹さんが熱だしたからだもん……」
ぼそっと言う拓斗。
その好意は……特別なものだよね?
図々しい期待を持ってもいいだろうか?
「恋人だって、思ってもいい?」
ピシッと拓斗が固まった。
「なに?」
訝しげな声音に僕は怯えた。口に出した言葉をそっくり取り戻したかったけれど、それは絶対無理。居直った気分で念押しを口にした。
「君を……。君は僕だけの恋人だって……思いたい。いい?」
たった一度、ベッドを共にしただけで独占欲丸だしの台詞……。鬱陶しがられても仕方ないだろうけれど。僕の夢であり、一番の望みなんだ。
残念ながら拓斗の返事は沈黙だった。
「拓斗君……?」
瞳を揺らしながら僕を見据えていた彼の表情はけしてご機嫌ではなく。
落胆と、やっぱりという諦めと。
それでも僕はもう少しの間君と一緒にいたい。二人だけの時間を持ちたい。
つけあがるなという罵倒を覚悟して怯えた僕は彼の怒った顔を見つめたまま固まっていた。
しかし!!!
彼はやがてゆっくりと身を乗り出すと、僕の唇をとらえたのだ!
怖ず怖ずと舌がノックしてきて。
君から舌を差し出してくれるなんて。こんな感動的なことはない。
もちろん僕は甘く彼のキスを受け取った。メイプルシロップの味のする、でも、味付けのせいではない甘いキス。
夢中になりそうになった僕から唇をもぎ離すと、赤らめた頬のままそっぽを向いてボソッと言った。
「俺、ただの友達とこういう事する趣味ないから……」
つまり……僕を恋人にしてくれるの? 自ら口づけをしてくれたのは僕に対してだけ……。そういうことだよね?
ああ、どうしよう。君を愛したい。もっと、もっと、もっと!
「龍樹さん、シャワー、借りていい?」
僕の物欲しげな視線に気づいたのか、いつもの逃げ出すときのような表情で拓斗がベッドから降りた。
「あ……いいよ。場所、分かる?」
「うん」
言いながらよろけた。
「拓斗君!」
転びそうになった彼をベッドから飛び降りて支えて。
「無理しちゃだめだよ」
抗う彼を抱き上げた。
「龍樹さん? 待って! まっ……!!」
「風呂場まで運んであげる。階段落ちなんかされたら堪らないからね。大丈夫、心配しないで。風呂で戯れるのは今夜の楽しみにとっておくから……」
囁きつつ、抱かれて逃げ場のない拓斗の唇を貪った。
僕の胸に熱い頬を押しつけることでキスから逃げおおせた彼は、怒りの全くこもっていない声で責めた。
「んもう! 龍樹さんがこんなにエッチだなんて思わなかったよ!」
つい彼の優しさにつけ込むように甘え声を出していた。
「だって……、一年だよ。一年近く我慢して……。あきらめかけてた夢が叶ったんだ。もう少しの間、僕に幸せをかみしめさせてよ」
瞬間拓斗の表情が強張った。何が彼を怯えさせたんだろう。瞳の揺れは僕に縋るように注がれた怯えの光。震えた唇が小さく動いて。
「やだ……」
漏れた呟きは意地の悪さを微塵も持っていなかった。でも、ノーはノーだ。
どんな小さな拒絶でも、たちまち僕の中に咲いていた悦びの花はしぼんでしまう。
「拓斗君……?」
腕に伝わる微かな彼の身体の戦慄は何だったのだろう。僕は何か失言をしてしまった?
「龍樹さんは俺のこと離さないって言った。ほんとにそう思うなら、少しの間じゃなくって。俺のこと、そんな風に急いで食べちゃって、直ぐ飽きちゃったら……そしたら……俺……」
泣きそうな顔で俯いた。
なんてことを!
「飽きないよ……。そんなこと出来ない。出来る訳無いだろう?」
半ば諦めかけながらも、君から目を離せないでいた僕の気持ちは……。エロスの愛に分類されるものだけで出来上がっていたわけじゃない。
「ねぇ、拓斗、僕は肉欲のために君を愛したんじゃない。君が好きで好きでたまらないから欲しくなってしまうだけで……。だから……。君が望むなら二度とキスとかしたりしないから。我慢するから……。僕を信じて」
自然腕に力が入ってしまう。拓斗の手がふわりと僕の頬を撫でた。
「龍樹さんたら…………」
恥じらいを含ませた柔らかな言い方が、拓斗の返事。僕はまだ彼の恋人でいられるようだ。
「シャワー浴びたら出かけよう。今日の仕事は今日の内に、だよね」
浴室の前で拓斗を降ろした。
僕のパジャマを羽織って、すんなり長い脚を剥き出しにした彼の姿。とても貴重で美しい僕の宝物として目に焼き付いた。
もう一度抱き締めたいと思ったけれど我慢した。
浴室のドアを開けて彼を誘う。
「先に使って。着替え、用意しとく」
自制心が消え去らない内に朝食の後かたずけに行ってしまおうと、背を向けた。
「あ、龍樹さん!」
「え?」
呼ばれた振り向きざまに唇をかすめ取られた。チュッと柔らかく吸われて。
「俺も……愛してるから」
小さな声で呟くように言うと、驚きで反応できないでいる僕をおいて、だだっと浴室に駆け込みドアを閉めてしまった。
彼の消えたドアをぼんやり見つめたまま、思わず唇を撫でて。
僕の……拓斗。
心の中で繰り返し呟き、キッチンまでの距離をスキップで埋めた。
こんな朝を迎えられるなんて本当に夢みたいだ。
愚かな僕は君の一言でこんなにも舞い上がってしまう。君は僕を舞い上がらせるコツを心得ている。時には計算ずくなんじゃないかと疑いたくなるほどに。
いや、それは彼に対する冒涜的な考え方。
今はただひたすらこの喜びを噛み締めていよう。
全てが輝いて見えるのも気持ちの持ち方なのだな。心情的にも、その日の僕は世界一幸せな男だった。一番欲しかったものを手に入れたのだから……。
『いい加減にしろ!』
日勤後のオフに向けて帰宅した僕は、自分の部屋で彼女を見つけて、思わず吐き捨てるように叫んでいた。
夜勤夜勤と続いたあげくのやっとのオフだ。疲れも頂点で、優しくあしらうどころではなくキレていた。
『だって、病院では会ってくれないんですもの、こうするしかないじゃない』
甘ったれた声は全然堪えていない証拠。僕の疲れはいや増しに増す。
『僕が担当である限り、君には生傷が絶えないみたいだからね。病院は治す所なんだから。第一、医者と患者の関係でしかないんだから、無駄に会う必要もないでしょう』
『会いたいの。先生に会っていたいのよ。好きなんだもの』
『言ったはずだ、君のことは好きになれない』
『本気で誰かを愛したことないんでしょ。ちゃんとあたしのことを見て』
『興味ないね。それより何で今、君が僕の部屋にいるのか聞きたいもんだ』
赤い唇にほくそ笑みが浮かんだ。
『妹だって言ったらドアマンが入れてくれたわ』
『住居不法侵入だ』
『だって……夕食一緒にしようと思って……』
確かにテーブルには料理らしきものが皿に。バラの花瓶。キャンドル。全て僕が大事にしていたもの。皿はロイヤルコペンハーゲンのイヤーズプレートだし、花瓶は赤いベネチアングラス。蝋が垂れ落ちている燭台は磨くのにかなり苦労する銀細工。
皿の上の料理は……野菜くずと消し炭……?
見ただけで気が滅入ってくる光景だ。
『帰ってくれないか? 食欲無いんでね』
彼女を部屋の外につまみ出した。ドアマンには誰も入れないように念押ししておかなければ……。
部屋中をくまなく調べて回った。盗聴装置なども手軽に入る世の中だから。
コンセントに二つ、電話の受話器の中に一つ、テーブルの下、冷蔵庫の裏、照明の中。
大掃除をしながら引っ越しを真剣に考えた。
ホッと一息付いたのは深夜。病院から渡されている携帯電話が鳴って、溜め息をつきながら応答したら……。
『ねえ、明日病院に行くわね』
最も聞きたくない声が囁いて。僕は即座に電話を床にたたきつけていた。
「本当にいいの?」
スニーカーに足を入れながら拓斗が呟いた。
「何が?」
「保証人だよ」
「言ったでしょ? 他の奴にそんなことさせられない。大丈夫だから、心配しないで」
言いながら彼の家に書類を取りに行くべく家を出た。
外に出た途端によろけた拓斗を後ろから支えて。
「……太陽が黄色く見えるのって、ホントだったんだなぁ……」
気恥ずかしげな微笑みを含んだ声をうっとりと耳にしながら、僕は有無を言わさず彼を背負った。
「恥ずかしいよ、降ろして」
「だめ。おんぶが嫌ならお姫様みたいに抱いてってあげるよ」
「……おんぶでいい……」
彼の息づかいを首筋に感じながら向坂の家まで歩く。
本当は頭の中にしっかり地図があったけれど、彼の指示通りに歩いた。
向坂家はスペイン瓦を使った瀟洒な家。チャイニーズオレンジの瓦にオフホワイトの土壁風のモルタルづくり。同じモルタルの土塀に囲まれた敷地は、今ある家の倍はある。
外から見える範囲は努力しなくても細部まで目に浮かぶ。何度も何度も、この家の前は往復した。偶然見つけた向坂の表札。ポストの方には小さく拓斗の名前も入っていた。以来彼の顔が見たくなったときは向坂家の回りを徘徊していたのだ。
黙って入ることは簡単。想い人に快くドアを開けて貰ってこそ意味がある。
その感動を胸に門の中に足を踏み入れた。
お世辞にも手入れの行き届いたものとは言い難い庭は、綺麗にすれば南国風の美しい造りだろう。
「お父さん……何してる人なの?」
ドアを開けている拓斗に庭を見渡しながら尋ねてみた。
「サラリーマン。外資系の。この家は母さんの親の土地。爺ちゃんも婆ちゃんも両方とも死んだけど、援助して貰って建てたって。家建てた頃は一緒に住んでた。……俺一人になってから一年……だな。龍樹さん見たら驚くよ。スゲー散らかってんだ。ここ広すぎて、掃除とか行き届かなくて……」
恥ずかしそうに言いながら、上がり込んだ。
うん、でも言うほど凄くない。
「……? どうぞ。あがって! 汚くて恥ずかしいけど」
ぼんやり見回していたせいで促されてしまった。
「ああ……。君が言うほど汚れてないなって思ってさ。結構一人で頑張ってるんだ、拓斗君……」
嬉しそうな照れた微笑みを浮かべて頭を掻いた。
「えへへ。俺、家事の中で料理が一番苦手なんだ」
リビングまで案内される間、僕は辺りを見回しっぱなしだった。
これが君という人をはぐくんだ家……。居心地良さそうな空気で一杯の所だね。
「舌は肥えてる方みたいなのに……。ああ、一年前まではお母さんの料理食べてたのか。じゃあ、得意は?」
「得意って言えるのはない。……龍樹さんみたいに何でも上手い人は尊敬しちゃうよ」
言いながら奥に行き、書類袋を取り出してきた。
「一人暮らし歴の違いさ」
「それだけじゃないと思うけど」
僕を優しく睨みながら言った。
「これなんだ」
袋から取り出された一枚の書類。六年前に僕も手にしたものだ。僕は中退したけれど、拓斗はここで医者としてのステップを昇り始める。
「ここに住所と名前、それとハンコ」
「よし、さっさと書いちゃおう」
手近のソファに掛けて書き出した僕の横で、拓斗が呟いた。
「あれ? 留守電入ってる。昨日は入れてない筈なのに……」
「え?」
僕が聞き返した途端に拓斗は、かぁっと赤面した。
「あ……。か……帰る前に外から入れるんだ。ただいまって言っても誰も出ないだろう? 留守電のメッセージランプが点いてると、ちょっとホッとするから。ば、バカみたいかもしれないけど、俺……」
気恥ずかしそうに絶句した彼を、思わず抱き締めていた。
「一人暮らし一年生だもんね。分かるよ。僕には分かる」
誰もいない部屋に毎日帰り着く侘びしさは、経験したことのない者には分からないだろう。
無意識の内に物言わぬ鉢植えや人形に話しかけるようになってしまったり、拓斗のように留守電を利用したり……。とにかく独りぼっちじゃないという意識を保つための術なのだ。
僕の店に来続けてくれたのも、こういうバックグラウンドがあってこそだったのかもしれないね。
寂しがりやの君……。また一つ、僕の知らなかった君がみえた……。僕の中でいろんな君が増えていく度、愛しさも増幅する。そうやって、君の存在が大きくなっていく。それを少しでも伝えるために口づけしたいと思った。
腕に力を込めて……。
僕の気持ちを知ってか知らずか、拓斗は瞬間僕に体を預けてから、
「留守電……聞かなきゃ……」
と呟き、そっと僕の腕を外して再生のスイッチを押した。
ピーッというお決まりの音の後に流れてきた声は男の声。僕は耳をそばだてた。
「……MS社の藍本です。ご両親と妹さんが事故に遭われました。至急こちらに連絡下さい。電話番号は……」
事故という時点で拓斗は硬直した。早口な電話の主の言う番号は僕がメモした。番号からみて携帯電話らしい。
無機質な女の声で録音時の時間が十一時半だと告げた。
それは丁度僕が彼の身体を貪ってこの世の全ての幸せを手に入れたという気分に酔っていた時刻。なんてことだろう。
考えを遮るようにピーッという音がまた無機質に響いた。
「藍本です。ああ、まだ帰らないのか。拓斗君。ご両親はあちらの病院で先ほど息を引き取りました。君の連絡があり次第、社の者が付き添って向こうへ飛びたいと思っています。連絡を……」
メッセージの終わらない内に拓斗がへなへなと座り込んだ。
宙を見つめる虚ろな瞳。わななく唇は言葉を発することを忘れたように痙攣しているだけ。
いくら寂しさを紛らすためとはいえ、こんなメッセージを望んではいなかった。
僕に出来ることは……。
冷静に。
言われた番号をダイヤルすること。
直ぐに相手は出た。何をやっていたんだといわんばかりの慌ただしさで。
「ああ、拓斗君? やっと捕まったか!」
責める口調で機械のように抑揚のない声が言った。
「いえ、僕は代理の者です。彼はショックを受けて自分を見失っている状態で……。メッセージを今聞きましたので。……どうすればいいですか?」
「拓斗君を連れてすぐ出られますか?」
「はい。……そちらへ?」
「拓斗君がパスポートをお持ちかどうか……判りませんよね。いえ、いいです、こういう場合ですから何とかなるでしょう。とりあえずこちらへお越し下さい」
こちらと言われても困るので電話の側にあったメモ用の鉛筆を手に取った。
「場所は?」
「臨海副都心です。ユリカモメのテレコムセンター駅が最寄りで。首都高速なら湾岸線十三号地出口を出てすぐ右折して下さい」
「分かりました。直ぐ連れていきます」
電話を切って拓斗の腕を抱え上げた。
「拓斗、直ぐ出かけるから。パスポートは持ってない? ああ大丈夫、こういうときはなんとかなるから。鍵出して。開けたのは玄関だけだよね?」
がくがくと頷くだけの拓斗を抱き留めるように支えた。拓斗から取り上げた鍵をかけ、そのまま僕の家に向かった。
言われたMS社の場所は車で行った方が早い。
僕は車に拓斗を押し込むと一番手近なインターチェンジに向かった。平日の首都高速は混んでいるが、時間的には比較的穴な時だったようだ。出来る限りとばしてMS社を目指した。
それでも三十分以上はかかる。
大井料金所前の渋滞で減速したとき。虚ろな瞳でぼんやりしていた拓斗の瞳からぽろりと涙がこぼれた。
「…………そ……だ……」
低くしわがれた声。
「……そ! うそだ! うそぉ!!」
痙攣した身体を両腕で抱き締めるようにして叫びだした。
「そう、何かの間違いかもしれない。それも向こうへ行けば分かる。だから……出来るだけ落ち着いて。泣くのは本当に確かめられてから。ね?」
「っ! だって……」
「うん、落ち付けって言う方が無理だけども……。急ぐことしか今は出来ないから……」
「ごめ……。龍樹さんには関係ないのに……俺、当たっちゃって……」
「寂しいこと言うなよ。関係はある。僕の恋人の家族なんだから」
「あ……」
まずいことを言ってしまったというように俯いた。話題を変えよう。
「このお金、渡して」
拓斗に小銭を手渡した。窓を開けて料金所の窓口に横付けて。左ハンドルは、こういう時に不便だ。だが、これからは拓斗が一緒にいる。助手席を指定席にして恋人を乗せることが出来る感動を僕は改めて味わっていた。
拓斗はぼんやりと係員の促すままに金を渡して領収書を受け取った。
窓を閉めて再度加速。
「……どこに赴任してるんだっけ?」
「……ミュンヘン支社。ドイツの……」
「ドイツか……。僕はあんまり役にたたなさそうだな。ドイツ語なんて、医学生時代にしか触れてないし。でも、出来るなら付いていきたい」
「龍樹さん?」
「誰か付いていってくれるそうだけど、君が心配だから……」
本音を言えば、これは僕のただの我が儘。今は一時も拓斗と離れてなんかいたくない。
向こうにいたときの習慣で、パスポートとクレジットカードは常に身近なところに置いてある。車を出すときに取ってきておいた。
急ぐときにそういうことをしてしまう、それが僕の人間性。拓斗に一生愛される自信が持てないのもそのせいなのだ。
十三号地出口から有明方面に向かった。
テレコムセンターの側のビルがMS社の社屋の筈。
開発途中のせいか閑散とした道路。ビルの前に乗り付け、車から降りたところで、待ってましたというように男が走り出てきた。片手にアタッシュケースを持っている。
「早かったですね。二時間後の飛行機をキープしました。これから成田へ向かいます。緊急ですので、拓斗君のパスポートは臨時のものを発行して貰いました。当座必要なものは向こうへ着いてから用意させますから」
声で藍本氏だと分かった。思ったよりも若い。きっちりなでつけられた髪、銀縁の眼鏡。身長は僕と大差なく、理知的な面立ちが冷たい印象を与える。いかにもなエリートサラリーマン風で、上質の背広がよく似合う。
「成田まで送りましょう」
言った途端に渡りに船というように乗り込んできた。
「すみません、お願いします」
一足飛びに成田まで行きたい気持ちでアクセルを踏んだ。
「あなたが彼に付いて行ってくれるのですか?」
車を走らせながら尋ねた。
「いえ。そのつもりだったんですけれど急な仕事が入ってしまいまして。自分は成田で手続きをするだけで帰らせていただきます。向こうで社の者が迎えに出ていますので。すみませんが、飛行機だけは一人で乗っていただきます」
申し訳なさそうに発せられたその言葉に僕は飛びついていた。
「僕が付いて行ってはだめですか? 今の彼の様子を見ていると、どうも心配で……」
「え? ……しかし……」
あんたは誰だ? というようにフロントミラーを使って覗き込んできた。
彼の恋人だと胸を張って宣言したいところだが、きっと拓斗が困った顔をするだろう。
「僕は彼の友人で家庭教師です。医学部受験のための……。入学手続きに保証人が必要ということで、書類を書きに彼の家に行きまして。そうしたら……」
鏡越しに疑り深げな切れ長の瞳がニヤリとしたような気がした。
「そうでしたか……。空席を確認してみます。パスポートはお持ちで?」
「ええ、一昨年の秋までアメリカにいましてね。更新して間もないのがあります」
「ああ、それで車もコルベットですか。高かったでしょう? 特別色だし」
あんまり口調がうらやましそうだったので、入手経路を言っておいた。
「知人との賭に勝って手に入れました。嫌がらせ半分でショッキングピンクに塗装されてしまいまして。しかし、譲渡契約書の隅に、引き渡し後向こう五年間は転売しても色を変えてもいけないと小さく書き添えてあったんです。契約前に見たとき、ボディは白だったし、気にも留めていなかったんですがね。引き渡し直前に塗装されたんです。……確かに引き渡し後の禁止は記載されていたけれど、その前に関しては規定されていない。やられた! って感じでしたよ」
これは僕の好みじゃないと言いたい。フォルム自体は大好きで、賭に勝ったときは大変嬉しかったのだが……。なにしろ色がいけない。人格を疑われるから拓斗には見せたくなかったし、当然乗り回したくはなく……。こんな緊急事態じゃなかったら、外に出したくはなかった。
「もし契約を破ったら?」
「車の値段の五倍は違約金を要求されます」
「それも小さく書いてあった?」
「ええ。しかも、日本にあっても僕が持っていることが確認できるように年に一度車と僕のツーショット写真を送る約束です」
ぶっと吹いたのは拓斗だった。但し声は泣き笑いのように聞こえる。
「それも契約?」
「ああ……」
どうせクリスマスカードを送るついでだと考えていたんだよ、その時は。実際には契約日から一週間以内だったけど。
「やっぱりタダより高いものはなかったってわけだ」
クスクス笑う拓斗。それは僕の大好きな表情の一つだけれど。
僕は赤面するのを止められなかった。この車、やはり拓斗に笑われてしまったではないか。
「五年経ったら、直ぐ塗り替えようと思ってる。黒かなんかに。それまでは出来るだけ乗り回さないでおく」
僕の声はむくれ声になっていた。それをいなすように拓斗の手がシフトレバーを握る僕の右手に載せられる。指先がそっと愛撫するように僕の甲を撫でて。
「どうして? もったいないよ。俺、こういう車、好きだな。お茶目じゃない? それで乗ってるのが龍樹さんなら、そんなにおかしくないよ。かっこいいもん」
ああ、運転中じゃなかったら、藍本氏がいなかったら……!!
『平常心』を心の中で唱えながら応えた。
「変な奴にしか見えないよ」
「変じゃないって……!」
優しく言うと、後部座席に首を巡らした。
「藍本さんて言ったよね? 親父達の事故って何ですか?」
拓斗の冷静さに不安を感じた。
しかし藍本氏は拓斗が落ち着いたと思ったのか、安心したように吐息を吐いて話し出した。
「どうも、詳しいことは分からないのですが……。郊外にノイシュバンシュタイン城というのがありましてね。ほら、あの、シンデレラ城のモデルです。どうやらそれの一日観光に家族で繰り出したらしいです。そこで観光バスと……」
「春美……妹の状態は?」
「重体です。意識がないと……。現状は向こうで確認して下さい。直行便でも十三時間以上はかかりますし。……フランクフルトで国内線乗り換え、一時間なので。あちらには飛行機の到着予定時刻を伝えてあります。迎えの者は日本人ですから安心して下さいね」
言うだけ言うと携帯電話を取り出した。僕の分の空席の問い合わせをしてくれているらしい。問われるままに僕の胸ポケットを拓斗に探らせ、パスポートを取り出して貰って渡した。高速道路というのは料金所でもない限り停車する時間はないから。全ては車を走らせながらになる。
「……桂川……!」
彼の口調が瞬間機械的ではなくなったのは向こうの応対が焦れったかったせいだろうか。やがて、ほうっと大きなため息をついて交渉は終わった。
空席は幸いあったらしい。MS社は気前がいいのか、僕の分までビジネスクラスで取ってくれて。長いフライトの場合はエコノミーでは辛すぎる。心遣いが嬉しかった。僕の分は僕が負担すると申し出てみたのだが、藍本氏は承知しなかった。拓斗を一人で送り出すことに多少後ろめたさを感じていたのかもしれない。結局、僕の負担は空港の駐車場使用料と高速の料金だけだった。
留守の間に大騒ぎされるといけないので、僕の親には空港から電話した。
店は定休日の札がかかったまま。
僕等は慌ただしくチェックインをすませ、出国カードを書き。時間通りに成田を後にした。
飛行機はルフトハンザ。ドイツの会社だ。
ドイツというのは律儀な国民性で、日本人と見れば取りあえずは英語で話しかけてくるそうだ。日本の第二公用語は英語だからだ。乗務員は全員英語が達者だった。この調子だと、あちらでもさほどは不自由しないだろう。
僕は拓斗の世話をやけるのが嬉しかった。
拓斗が冷静に見えたのもつかの間。
食いしん坊の拓斗が機内食をほとんど残した。確かにお世辞にも旨いとは言えなかったものの、食べられないほど不味いわけではない。ルフトハンザを利用するのは初めてだったが、他社と比べても旨い方だった。
つまりはそれだけ拓斗が打ちひしがれている証拠。
僕はブランケットの下から手を忍ばせ、彼の手を握りしめた。ビクッとしたように僕の方を向いて。その瞳は潤み、今にも泣き出しそうに唇を震わせていた。
「無理して食べなくてもいい。眠ってしまいなさい。今薬をあげる」
スチュワーデスに水を頼み、常備のピルケースから催眠誘導剤を取り出した。
「飲んで。今は眠るぐらいしかできないから……。泣くのは向こうに着いてからだよ。ちゃんと確認して、それからだ」
拓斗はコクリと頷いて薬を飲んだ。
心配げに具合が悪いのかと聞いてきたスチュワーデスには、彼の家族が事故に遭い、危篤なので会いに行くところだと説明した。
途端に彼女の顔に哀れみの色が浮かんだ。
拓斗への同情と励ましの言葉を訳して伝えると、彼は弱々しく微笑み、サンキューと小声で呟いた。
抱き締めてやりたい。そんな弱々しさだった。せめてもの想いで、縋るように握り返してきた手を固く握りしめた。
やがて規則的な吐息が聞こえてきて。上下する胸、柔らかく閉じた瞼。乾いた頬の痕をなぞるように時折滲み出ては伝い落ちる涙。けして安らかとはいえない強制的な眠りに落ちた拓斗。
親戚がいないと言って保証人を僕にさせるくらいの彼は、家族を失ったら天涯孤独になってしまうだろう。
僕が少しでも彼の救いになれたら……。
もどかしく、悔しい。
何故に僕の天使がこんな目に遭わねばならないのだろう。どんな罪を犯したというのだ。
もしも僕を受け入れたこと自体が罪だと言うなら……。全ての罰は僕が受けるべきもので……。
ああ、でも神様。どんな罰でもいいけれど、僕から拓斗だけは奪わないで……。
そんな虫のいいことを考えていた罰だろうか。その後に与えられる苦しみの存在を、まだ僕は感知していなかった。
僕等を載せた飛行機は定刻通りに到着した。ランディング時の不快感は何度乗っても馴れない。拓斗は眠りでも安らげなかったのだろう、疲れた顔をしている。入国審査が終わった途端、出口を探して目をさまよわせ始めた。
他の日本人の集団に着いていこうとする肩を捕まえて囁いた。
「拓斗、ここはフランクフルトだから。ここから後一時間、乗らなきゃ。乗り継ぎのミュンヘン行きは出発まで一時間あるんだ」
「あ……ごめ……俺……」
何か言いたそうに唇を震わせた。やがてその震えは全身に拡がって。
泣くのを抑えようとしている。抑えきれない悲しさが震えになって溢れ出している……。
ポンポンと背中を叩いて乗り継ぎゲートを示した。
「一時間後にはあそこから出発だ。しっかりして」
「う……うん」
「考える時間があるからいけないんだな。一応、ここで必要なもの買っておこう。下着くらいは換えが欲しい。取るものもとりあえず出て来ちゃったし。こっちの空港の方が大きいから……」
拓斗の返事は聞こえてこなかった。
ぼんやりと公衆電話を見つめている。
「何……?」
「電話……かけたい」
「え……?」
切なげな泣き笑いの表情で僕を見上げた。
「ここからなら国際電話じゃないんだよね。用がないときはかけてくるなって怒られてたけど。必ず、母さんか春美が出て、何か用? ってきくんだ」
両親宅へかけるつもりらしい。無駄だと止めることは出来なかった。拓斗の納得のいくことをさせてやりたかったから。
「待ってて、小銭用意してくるから。電話の側にいて。動いちゃだめだからね」
僕は走って近くの免税店に飛び込んだ。キャンディスタンドのブロックだったのでチョコレートを買って日本円を出した。電話をかけたいから釣りは小銭でと頼んだら、快くよこしてくれた。
拓斗は空で覚えている番号を手早く押した。それくらい何度も使っている番号。海を隔てて遠く離れていても彼は家族としっかりつながっていたんだ。
僕は横から受話器に耳を近づけた。
単純な呼び出し音だけが続く。
受話器を掛け、小銭を取り出し、もう一度トライ。
もう一度。
もう一度……。
「留守みたいじゃないか。何度かけても留守は留守だよ」
野太い声が後ろから降りかかってきた。癖のある英語。
ふりかえれば、僕らの後ろには電話が空くのを待つ人が二人ほどたまっていた。
「拓斗、拓斗、後ろの人が電話を使いたいって……。また後でかけてみよう」
「やだ……。もう少し……。いるはずなんだ。絶対いるはず……」
言いながらも、電話から後ずさった。
「拓斗、後で。後でかけよう」
肩を抱いて促した。震えが掌に伝わってくる。
「い……、いる筈なのに。母さんか、春美が……いる筈なのに。留守なんて……」
しゃくり上げながら切れ切れに紡ぎ出されるつぶやきはやるせなさばかりを増長させる。
もちろん、拓斗にだって解っている。これは逃避の行為だ。現実を認めたくないばかりの。
間違いだったと一縷の希望を持てればいいのに、既に確認、死亡という言葉を耳にしてしまっている拓斗は悲しみから抜け出すことが出来ないのだろう。
僕は拓斗を引き寄せた。
拓斗が一人で耐えようとしているのが悲しかった。
我慢できずに抱き締めてしまった。
「た、龍樹さん?」
「今だけ……。今だけだから……」
「…………うん……」
拓斗が力を抜いて僕に身体を預けてきた。顔を僕の胸に埋めると、息を殺すようにした嗚咽が微かに聞こえてくる。
そう。僕の胸で泣くことを覚えて欲しい。僕は何時だって君の側にいるから。
「……遺体安置所だ」
石造りの古い建物を不思議そうに見回す拓斗に囁き掛けた。
遺体安置室の雰囲気というのは、どこの国でも大差ない。生きている人間を寄せ付けないような冷たい雰囲気。それは黄泉の国への暗いトンネルの入り口のようで。死者のための空間だ。
僕等が連れて行かれたところには、三体の遺体が横たわっていた。
死体袋が二体と、寝台に布をかぶせられて横たわる一体。一回り小さい寝台上の遺体が今朝息を引き取ったという妹さんだろう。
ぱっくり口を開けた死体袋のジッパーの中をそっと覗き込んだ拓斗は、その場で立ちすくんだまま凍りついていた。
既に遺体の確認は会社の人間がしてくれていたが、拓斗には遺体に会う権利がある。
「……んで……」
動かない唇から漏れる声。硬直して遺体を見つめたままの拓斗が、いきなりガッと死体袋の中身に拳をぶつけた。
「なんでだよぉっ!!!」
立て続けに父親を殴りつけて。冷凍保存されていたために拓斗の拳がぶつかる度に硬い感触の鈍い音が響く。
「や、やめなさい! 拓斗!」
慌てて後ろから羽交い締めにしたのだけれど。いつにない馬鹿力で僕をふりほどいてしまって。
「いつだって俺だけおいてくんだっ! こうやって、突然にっ!」
急に気が違ったのかと思うほどの変貌ぶりに、僕は慌てた。激しい怒りだった。
「俺のことなんか、どうでもよかったんだろう? え? 俺はとっくに見限られてたんだ。病気持ちの俺なんか、役立たずだから、だから……!!!」
父親の遺体を殴り続けながら、叫ばれる呪詛の言葉は、天使の拓斗を只の人間に見せていた。
「俺がどうなったっていいんだ。そうだろ!」
これは理不尽な怒り。多分、我に返ったときに取り戻して消してしまいたい台詞だろう。
拓斗なら。
今はそうやって怒りをぶつけることで自分を立て直そうとしている。逆上することで、喪失感を埋めようと……。
エゴに満ちた行為ではある。
でも、醜いとは思わない。僕の中にもある部分。拓斗が持ち合わせていることを知るのは、悦びですらある。
だが。
日本語で叫ばれる呪詛は分からなくても遺体を殴るという行為はその場に居合わせている係員にも分かる。
どうか、この拓斗だけを見て判断しないで。彼は、本当は天使なんだから。
「拓斗! 止しなさい!」
僕は拓斗に当て身を喰らわせた。
うっと低く呻いて崩れ落ちる拓斗を抱えて。
「彼は疲れているんです。宿に案内、してもらえませんか?」
拓斗を抱き上げながら言った台詞は、高圧的な語調に聞こえたらしい。僕等を案内してきたミュンヘン支社の堀田氏は、半ば恐ろしげに後ずさってカクカクと頷いた。
中央駅の前のホテルに僕等の部屋は用意されていた。
ビジネスホテルのような、何の変哲もないツインルーム。
ベッドがダブルでないのは悲しかったが、拓斗がそれどころでない状態だし、まあ妥協できる。
気絶したままの拓斗をベッドに横たえた。
服を脱がして楽にしてやりたかったが、堀田氏の見ている前なので止めておいた。僕の手つきで僕等の関係がばれてしまいそうだから。
「……今後の予定を聞いておきましょう。遊山の旅ではありませんし。……向坂一家の住んでいた部屋にも彼を連れていきますか?」
「ええ、そのつもりです。部屋の整理もしませんと……。いえ、大体家具付きの部屋ですし、彼が持ち帰りたい物以外はこちらで処分しますが」
「遺体の移送は? もう出来るんですか? ……やはり、葬式は日本で出した方がいいですよね」
「お帰りになられるときに一緒に。事故現場には……行かれますか?」
「……彼の意志に任せます。といっても、こちらも仕事のある身でして、あまり長居は出来ません」
「ああ、そうですね。春美ちゃんの死に目ぐらいには間に合うかと思いまして、こちらにお呼びしたんですが……。何とも残念でした……」
日本人の顔を画一的に見せる銀縁眼鏡の奥に涙が光っていた。
「痛み入ります」
本気で気の毒がっている堀田氏は向坂氏の部下だと名乗っていたが、拓斗の父親は良い上司だったらしい。拓斗は父親の仕事をしているときの姿を知らないのだろう。
彼の家族の話題からもはじき出されていた父親と拓斗のすれ違いが、僕には想像できた。
「取りあえず、明日の朝九時にお迎えに上がります。午前中にフラットへご案内して、御希望があれば現場へ向かいましょう。食事はホテルのルームサービスをご利用下さい。必要なものはありますか?」
「いえ。フランクフルトで大体揃えておきましたので」
「では、また明日」
「色々ありがとうございました」
丁寧に頭を下げて堀田氏は帰っていった。
ドアが閉まった途端にホッと溜め息が口をついて出た。拓斗の横に腰掛けて彼の顔を覗き込んだ。
二十歳にしては幼げな顔立ち。
陸上の練習を受験勉強にすり替えた半年は彼の肌から小麦色を抜き取って、本来の白さを浮きたたせている。漆黒の髪や眉毛や睫の黒さが際立って、元々はっきりした顔立ちをくっきりと見せている。程良い赤味の唇もより誘惑に満ちて。口角が上がっているせいで、こんな時ですらうっすら微笑みを浮かべているように見えないこともない。
「服……脱がせた方がいいな。その方が楽だろう……。拓斗、脱がせるからね」
力無く横たわる彼に呼びかけ、ゆっくり服を脱がせた。クローゼットにしまいながら、寝間着を用意するのを忘れていたことに気が付いた。
「寝間着は……要らないよね」
空調は丁度良かったし、裸で寝るのも嫌いじゃない。
拓斗がどうかは知らないが、僕の好みでは裸の方が……。
四〇〇メートル陸上の選手だったという拓斗の身体は、短距離選手ほど分厚くなく長距離選手ほど貧相ではない、しなやかな筋肉を持っていて。細身だが筋力と持久力を併せ持つそれは、ベッドでも美しく動く。
時差のせいで、長時間飛行機に乗ったにも関わらず、初めて拓斗を抱いてから一日経ったに過ぎないのだと思い起こし、僕の体は熱を持ち始めた。体中に残る甘美な記憶が僕を誘惑し始める。
拓斗の寝顔が微笑んで見えるせいかもしれない。意識のあるときの、逆上し、悲しんでいる彼をどうにかしたいなどとはあまり思わなかったのに。
抱き締めて、キスして。それはしたいと思っていた。
常に。
だが、この横たわる拓斗の身体をまさぐってみようなど……。
いけないという意識を頭の隅でとらえながら、僕の手は制止する理性を無視して彼の身体を撫で始めていた。
受け入れて貰えた経験が僕を大胆にしていた。既に僕は彼の身体の感触を知ってしまっている。それに裏付けられる図々しい安心感。欲求は抑え難い高まり方で……。
ああ、肌の感触まで僕好み……。
そう思って眺めてみて、下着が邪魔に思えてきた。
脱がせる必要のない下着の中に手を忍ばせ、彼の柔らかく眠っている秘部を撫でながらゆっくりと脱がせかけた。
「ふ………………」
ドキッとした。慌てて彼の顔を覗いて。勃ち上がりかけたペニスとやんわりひそめた眉以外は僕のしていることに気づいていない様子で……。
彼の怒った顔が目の前に浮かび、途端に理性が僕の邪な手の抑制に成功した。
下着を元通りにし、毛布を掛けた。
拓斗が目を覚ましたときに空腹だといけないので、ルームサービスで夜食を頼むことにして。
電話したその足でバスタブに湯を溜めに行った。
湯気の沸き立つバスタブの水面を横目にバスルームのチェックをする。四つ星クラスではないが、清潔で割と広めなのはありがたい。総タイル張りなので、多少湯があふれても問題は無さそう。但しトイレを直ぐに使いたい者には迷惑だ。
「シャワーが固定式か……」
思わず呟いていた。ホテルなどの、一般向けの高さの固定式のシャワーは身長のせいで使いにくい。屈むか、座らないと頭から湯をかぶることが出来ないのだ。
水量を確認して栓を閉めた。途端に静寂が訪れる。滴る水音だけが時折空気を塗り替えて。
ドスンと音がした。
「拓斗っ?」
慌ててバスルームを出た。
床の上でのろのろと身を起こすと、拓斗は僕の方を向いてホッとしたように微笑んだ。
「よかった、そこにいたの? ……龍樹さんの当て身、きつすぎ……。まだ足に力はいんない。バランス崩して転んじゃった……」
「すまない! 加減したつもりだったんだけど」
駆け寄って抱き上げ、そっとベッドに降ろした。だが、彼の腕は僕の首から外れなかった。引きずられ、倒れ込むように僕はベッドサイドに腰掛けた。
肩に彼の頭の重みを感じて。うなじから立ち上がる彼の匂い……。僕の家の石鹸の香りに混ざって若い男の汗の……僕を狂わせる甘美な……。
ああ、君の匂いは甘すぎる。
うなじに吹き付けられる溜め息は、先ほど抑え込んだ僕の欲望の燻りに火を点けた。
抱き締めて組み敷こうと腕に力を込めた途端、拓斗の声が響いた。
「ごめん……」
絡ませていた腕を外し、ベッドの上で正座をして。
「俺のため……だろ? 俺が親父を殴るの止めさせるため……」
潤ませた瞳で僕を見上げ、直ぐに俯いてしまった。
僕はもう一度力尽くで欲望をねじ伏せ、彼の頭をそっと撫でた。
「君は……逆上してたから……」
「……うん……。ありがとう……。あのままだったら俺、もっともっと嫌な奴してた……」
目を伏せたままそれだけ言うと、いきなりしがみついてきた。
「嫌いになった?」
「え?」
「俺が嫌な奴だから……。もう、嫌いになった?」
「ならないよ……。なるわけない」
しがみつく拓斗を抱き締めて。ふと不安になって彼の頬を両手で包んで瞳を覗き込んだ。
真っ直ぐに、正直な気持ちを読みとるために。
「……嫌いになった方が……いいの?」
僕自身は縋る瞳になっていたかもしれない。拓斗の瞳には、たずねた途端に怯えが走った。
「違う! 俺……、俺は……」
唇を震わせ、拗ねたように目だけを背けた。
「龍樹さんは……意地悪だ」
目元から一筋こぼれ落ちる涙。
「拓斗……?」
「俺には龍樹さんしか残っていないのに……。もう、龍樹さんだけなのに……」
そんな拓斗の台詞が僕の理性を霧散させてしまった。
「拓斗っ!」
夢中で彼の唇を貪り、舌でこじ開けた歯の間を通り、甘く柔らかな舌を導き出して吸い上げた。彼を包む物は小さな下着だけ。一夜で知った彼の敏感な場所を全て唇と指でなぞりながら組み敷いた。下着の中に手を入れて彼を握りとると、熱い強張りが手の中で動悸を早くしていく。
彼の強張りを押さえる布を剥ぎ取って自由にした途端、それは見事に勃ち上がっていた。
硬い先端を舌で撫で上げた。
「はああぁぁっ」
「意地悪だなんて言うな……。こんなに、こんなに好きなのに。……だから……君の言うことなら……何だって聞いてしまうの知っているくせに……。嫌いになって欲しいみたいに……僕を不安にさせて……。君の方が……意地悪だ……。そんな……そんな絶対に出来ない無理難題をふっかけて……」
くわえ込んで舌と口蓋でしごき、唇で締め上げながら、彼を責めた。
「はぁっ……ごめ……んっ……はぁっ……んんっ……あぁ……んんっ」
「いい? 声、出して。……ねぇ、もっと叫んで」
身悶えしながら羞恥を感じたのか瞬間僕を押しのけようとした。
「や…………!」
「恥ずかしい? 君の声、素敵なんだ。意地悪しないで……聞かせてよ……。もっと! もっと大きく!」
拓斗を苛めるつもりはない。捨てられないこだわりを何とか忘れて僕との行為を楽しんで欲しい。快感に溺れて、何もかも投げ出して……。
「あんっあっあっ……はぁぁぁっ、たつ……き……さんっ……俺……。や……だ……出ちゃう……やぁ……っんんっ」
「いいよ……。嬉しい…………出して……」
「ああっあぁぁぁぁっっっ」
たまらげな喘ぎが叫びに変わっていくのを耳にしながら、彼が出してしまうまで続けた。独特の味の熱いほとばしりを飲み下して。小刻みに震え、放出の後の脱力にとらわれた彼の、感じやすい内股にキスしてから抱きしめた。
彼の熱い火口に指を入れながら。
「入って……いい? ……君の……中に……」
そこはまだ堅く、行為になれるまでは辛さが残りそうな……。でも僕にとっては誰の手も触れていない至高の聖域。彼を馴らすのは僕。初夜にして腰を使えるほどの素質を彼は持っている。嬉しかった。そうして僕は一夜にして溺れたのだ。彼の身体に。
僕の愛はどこに比重があったのだろう。
こんな時に僕は彼を抱いている。慰めではなく僕自身の欲望のために。
「や……。だめ……」
あらがいは全て力尽くで押さえつけた。あんなに熱く愛し合った君だもの、本気で僕を拒絶したりしないよね。
「君が欲しくて欲しくてたまらない。愛してる……愛してるんだよ」
愛している。だから欲しい? イエス。
欲しいから愛している? ……ノー!
そう心の中で叫んでも、別のところでそれは嘘だという声も聞こえてくる。
「たつ……き……さんっ。……やめっ」
喘ぎに交えて彼が言っている言葉……。
なのに……。
「だmだよ。止められない……」
実際、拓斗の返事も聞かずに僕は彼の腰を持ち上げ貫くつもりで僕をあてがったのだ。
「いやだぁぁぁぁっ」
いきなり蹴り飛ばされた。ばたばたと足を暴れさせて僕の腹に何度かヒットした。その程度では僕を止めることは出来ない。僕の熱さを増長させるだけ。抗いをのしかかることで全て封じ、もう一度挿入しようとした。その瞬間の隙をつかれた。抱え上げた脚を押さえる手を腰に移したとき。拓斗の蹴りが丁度僕の怒張しきったものをまともに蹴り上げたのだ。
「っっ」
頭の中で火花が散った。
口がきけない。僕の両手は本能で痛みの中心を抑え込んでいた。
気が遠くなりそうだった。痛みを散らすことに全神経を使って。
前のめりに倒れ込んだ。
「たっ、龍樹さんっ?」
辛さを吐き出せない上に拒絶されたショックが上乗せされていた。
滲み出た涙は痛みだけに押し出されたわけじゃない。
「ごめ……っ。俺、そんなつもりじゃ。只、い、今は嫌で……。ごめん、ごめんね。痛い……? ……よね……。ホントにごめん……」
肩に添えられた手を小さく寝返りを打って振り払った。
「龍樹さん……。怒っちゃった? ねえ」
「…………」
痛みが僕を子供に帰していたのだ。心配そうに言い訳をする拓斗を、黙殺した。
大抵の男は佳境でいきなりの拒絶を受ければ逆上すると思う。蹴られた痛みで動けないせいで、彼を犯さずにすんだのは幸いだった。
「ねえ、龍樹さん、返事してよ」
僕の肩を揺さぶる拓斗の声が涙声になっている。泣きたいのは僕の方なのに……。
シーツの中に埋もれたまま呟いた。
「拓斗は僕のこといやなんだ。ほんとはいやなんだろ?」
拗ねた口調になってしまったけれど。
「ち、違うよっ。嫌じゃないよっ。好きなんだ、ホントに……」
「違わない。君の気持ちは僕のとは違う。そう言ったじゃない」
「愛してる。愛してるよっ。俺には龍樹さんしかいないんだから!」
「じゃあ、なんでっ?」
我ながら子供っぽいとは思う。感情というのは時に抑制しがたく、後で思い返せば赤面ものな行動をとらせるらしい。
「……だめなんだ……」
まろやかな拓斗の声がやるせない調子で僕に降りかかってきた。拓斗の指先が優しく僕の髪を梳いて。それだけでゾクゾクと感じてしまう僕の体。情けない獣だ。
「ごめん。龍樹さんには何の責任もない。只、俺……今はそんな気になれなくて……」
見上げた先で、拓斗の黒目がちの瞳が潤んだまま優しい光を浮かべて僕に注がれていた。それは慈愛のような、いうなれば母性の光。こんな目で見下ろされては…………。
「キスして」
「え?」
「愛してるって、心を込めてキスしてくれたら許してあげる」
「……キス……だけでいい?」
困ったように覗き込む拓斗を見据えて正座した。
「うん……」
一旦目を閉じ、待ちきれずに半目を開けて伺えば。
揺れる瞳の拓斗の顔が近づいてきた。半開きの口元は舌を差し出すつもりであることを示していて。
僕の唇に重ねられ、吸い付いては離れていく拓斗の唇。甘い吐息混じりの息継ぎを繰り返しながら僕の舌や口腔をなぶっていく柔らかな舌。
優しく、甘く、念入りに。重ねる度にぎこちなさは消えて、僕の官能を誘う力も増していく。
頬に添えられた手にも力がこもる。
ああ、だめだ。今やめないと……。
キスだけという約束を破ってしまいそうになる……。
僕は自分が強請ったキスを、もぎ離すようにして止めさせた。
拓斗は悲しげな瞳でそんな僕を見据えて。
「龍樹さんが入れようとしたとき、……親父達が見えたんだ。龍樹さんにされてる最中に、親父達は死んだんだよ。そう思ったら、龍樹さんにされて、あんなに燃えてた自分がどっかにはじき飛ばされちまった……。少し……待ってくれない? 俺……、まだ混乱してる……」
僕は五つも下の男に甘えてる。一度僕を受け入れてくれたってだけで、それが続くと信じていた。僕のものだって、支配欲を出して。
「すまない、拓斗……。君を苦しめるつもりじゃなかった……。風呂の用意してあるから。入っておいで」
機嫌を直した印として彼の頬に軽く口づけした。
「うん……、ごめん……」
ホッとしたように微笑み、拓斗はベッドから降りた。
タタタと足音が軽く響いて。やがてドアの鍵をかける音。バスルームの鍵だ。
耳障りで嫌な音。僕を拒絶する音……。
遠くでする水音が、僕の寂しさを増長させた。
空港で買ったロンシャンの大きなボストンを開いた。歯ブラシ二本、カルバンクラインのTシャツと、ブリーフを二枚取り出した。拓斗のは白、僕のはブルー。
取り違えないように色分けしたのだ。僕はよくても、きっと拓斗は気にするから……。
こうなっては、先見の明としか言いようがない。実現して欲しくはなかった予感だ。
拓斗の使った下着を後で洗おうと探したが無かった。自分で持っていったらしい。
僕と距離を置くつもりだろうか。それとも、ただ気を使っただけ?
いずれにしろ同じだ。僕の心は孤独感と置き去りにされたような悲しさでふさがっていたから。
いや、拓斗は待ってくれと言った。
いいとも。半年以上も我慢できたんだ。
そう思う側から辛くなる。報われないと諦め気分で我慢するのと、相愛と思えた甘美さを知ってから我慢するのとでは……辛さが全然違う。
使ってないベッドの方に拓斗の下着を置いた。せめて拓斗の汗のしみ込んだベッドで彼のにおいに囲まれて眠りたかった。言えばきっと彼は嫌がる。僕はそこが僕の領域であることを主張するようにボストンを置いた。
乱れた服を直し、拓斗が出るのを待つことにして。遅ればせながら軽く何度か飛び跳ねてみた。蹴られた場所柄、治療行為に近いのだが、その間抜けな姿は拓斗に見られたくなかったのだ。
軽いノックは、一通りのことが終わった時に響いた。
ハンサムなゲルマン顔のボーイがワゴンを押して入ってきた。ヨーロッパというのは何を頼んでものんびりしている。ルームサービスも頼んでからだいぶ経つが、今回だけはそれに感謝した。なまじ早く来られていたら、僕は拓斗に一生許してもらえないだろうから。
ワインのテイスティングだけすませ、2マルク渡して後はするからと彼を追い出した。
通夜のつもりで頼んだワインは、クーラーの中から翠色の首を出している。ずんぐりとした下膨れのデザインは、フランケン・ワインの特徴。ドイツのワインはどちらかと言えば甘口中心。地方によって味も少しずつ違う。今回はきもち辛口が欲しくて、フランケンの白にしたのだ。物を食べながら飲むときは、あまり甘いと食が進まないから。ミュンヘンのあるバイエルン地方ではビールが有名なのだが、つい、自分の好みで選んでしまう。食事はホテルおすすめの白ソーセージのジャガイモ団子(クヌーデルとかいう)添えと、保存食じみたアイスバインのマッシュポテト添え。ジャガイモが主食だけれど、塩粒の付いたブレッツェルも少し頼んだ。それと、グリーンサラダ、チーズの盛り合わせ。デザートにはケーキ。アップルパイしか残っていなかったので、それを頼んでおいた。
「拓斗、拓斗君?」
バスルームのドアをノックした。シャワーを止める音がする。
「なに?」
声に警戒心がほんの少し。それが僕を悲しませる。君が望まないことはしない。誓うから、僕を疑わないで……。
「ルームサービスの食事が届いたんだ。食べられたら……食べて」
「……うん、もう、出るから……」
「じゃ、待ってる。ワイン、白だけど飲む?」
「うん!」
「寝間着無いから、Tシャツ……おいとく」
「あ……ありがとう」
申し訳なさそうな声音に、僕は小さく溜め息をついた。せっかく縮めた拓斗との距離が一度に延びてしまったような気がして。
ぷるんと頭を振った。
「いけない……」
僕がいつまでも暗い顔していたら、拓斗は余計な荷物を背負ってしまう。
ベッドの間にワゴンを置いて、ベッドサイドを椅子代わりにした。
差し向かいでする食事は初めてではないが、広げられたワゴンテーブルに一輪挿しのバラ、ワインクーラーとグラス。風呂あがりの拓斗。
訃報による旅行でなければ、一生の思い出になるほど楽しいシチュエーションだ。ややもすると、他人事の感覚で新婚旅行気分になってしまう。だからこそ、男にしか分からない痛みなど与えられてしまうのだと、自分を叱ってみた。
拓斗にして見れば、甚だ迷惑な同行者。拓斗に僕しかいないと一生言って貰えるだけの人間にならなきゃいけないのに。僕がしたことと言ったら、わがままを言って、甘えただけ。
このままでは情けなさ過ぎる。
「紳士であれ。だな」
「なにが?」
独り言に返事が返ってきて飛び上がった。
腰にタオルを巻いた拓斗がワゴンを見下ろしていた。くんくんと鼻をひくつかせて。
「美味しそう。もう、冷めちゃった?」
「まだ大丈夫。ちゃんと保温器に乗ってる。……中辛口の白だけど、飲める?」
「うん、大丈夫」
拓斗のグラスにまず注いで。続いて僕のにも。
注ぎながら、拓斗がタオルのまま座ってしまったのを見とがめた。
「シャツ着ないの?」
「汗引っ込んだら着る。先食べちゃだめ?」
「……いいけど……。一応お通夜になっちゃうわけだから……」
本当の理由は違うところにあったが建前の返事をした。拓斗はグッと詰まってから、ニッと笑った。
「行儀悪いけど、湿ったシャツ着て寝るの嫌なんだ」
「汗引っ込んだら食事中でもちゃんと着ろよ。風邪ひくぞ」
「うん……」
ワインを一口飲んで、取り分けた料理を口にして。拓斗は俯いたまま手を止めてしまった。
「口に合わない?」
「ううん。美味しいよ。龍樹さんの料理には負けるけど。ただね……」
「?」
「こんな時でも腹減るし、食えるんだなって……」
「うん……。生きるって、そういうことでしょ。辛いことあって、食欲無くなっても、どっかで割り切って食べ始めるんだよね。生きようって……身体が要求するんだ」
拓斗が自嘲的な笑いをクスッと漏らし、ワインを一口飲んだ。
「俺、何か変なんだ。どっかで冷めてる。家族なくしちゃったのに。ちゃんと確かめたのに……。他人事みたいで……。俺って、冷たい奴なんだなって……分かった」
「そうじゃないよ。違う。僕が言うのも変だけど……。後からゆっくり来るんだ。そういうの。救命センターで、そういう遺族を沢山見た。実感湧かないって感じで妙に冷静で。まるで他人事みたいで……ってね。その人達は冷たい人達じゃなかったよ」
「じゃあ俺、その間ずっと龍樹さんに迷惑かけるのかな……」
「迷惑なんかじゃないよ。今度そんなこと言ったら……!」
言いかけて絶句した。
「言ったら……? ねえ、どうするの? 途中でやめるなんて、だめだよ」
しつこく訊ねてくる拓斗……。
「僕を嫌いにならないって約束してくれるか?」
「? ……うん」
「……無理矢理犯してやる……って。言おうとした。冗談だからねっ」
口にして頬に血が上るのを意識した。きょとんとした顔でそれを聞いた拓斗はやがて笑い出して……。
「うん。冗談でも怖いから気をつけるようにする」
二十四時間ぶりにこんな声を聞いた。明るく優しい、僕のことを可愛いと感じてくれているらしい声。
こういうときに思う。恋愛に年齢は関係ないって。五つ年下の彼が僕を子供のようにあしらうのも、僕が甘えてしまうのも、好きな相手に対する特別な気持ちなのだ。他の誰にも踏み込めない領域でのやりとり。
食事を美味しく感じるのは拓斗と一緒だから……。
ボトルを空け、皿を綺麗にし、ミニバーで紅茶を煎れた。最後のアップルパイでまた拓斗の手が止まった。
「どうしたの?」
「これ、甘過ぎ。龍樹さんの方がずっと美味しい」
「無理しないで。残してもいいよ」
「うん、ごちそうさま」
言った途端にくしゃみを連発した。
「ああほら! シャツ着て!」
かたずけながら彼を叱りつけ。
ワゴンを外に出して今度は僕の風呂の準備をして。
横目で拓斗がブリーフをはくのを盗み見た。風呂で今夜を無事過ごすための下準備をするために。
十代のように、自慰をしなければすみそうもないなど、これまた情けない話だ。
「龍樹さん!」
自嘲に押し流されている中、声をかけられ、ドキッとした。
「なんだい? ……僕は風呂入るから。先寝てて」
「うん……。明日の予定なんだけど。堀田さん、何か言ってた?」
「ああ。お父さん達が使ってた部屋に連れていってくれるって。処分する物は引き受けるから、持ち帰りたい物を選んでくれって。慌ただしいけど、そんなに長くいるわけにも行かないし。……葬式とか、日本でするよね。遺体は帰るとき一緒に移送するって」
「うん……」
「それと、事故現場……。君が行きたければ案内するって。どうする?」
「……行きたくないけど。行かないと後悔しそうだ……。俺がおかしくなったら、また、龍樹さんが止めてくれる?」
「うん……。側にいるから……。ずっといるからね」
「ごめ……」
言いかけて、笑った。
「危ない。やられちゃう所だった」
ギュッと心臓を掴まれたような感触。そんなに可愛く笑わないで欲しい。今の僕には辛いだけ。
「……こらこら……! くだらないこと言ってないで歯磨きしなさい。明日堀田さんが九時に迎えに来るから、七時半起床、八時に朝食だよ。君が洗面所終わらせてくれないと僕が風呂に入れない。早くしてくれたまえ」
「風呂入ってたって平気だよぉ。俺に龍樹さん襲う勇気ないもん。いいよ、入りなよ」
君に襲われるなら本望なんだけどね。
「……わかった」
拓斗は言い出したら割ときかないところがある。機嫌を損ねたくないという卑屈さが身に付いてしまったらしい僕は、大人しくバスルームに向かうしかなかった。
鍵は拓斗が使う予定を考えるとかけられない。つまりは自分を慰めることも取りあえず出来ないということで……。
洗面台の壁面が総鏡張りになっているせいで、卑屈な笑顔を浮かべたまま強張っている僕の顔と対面してしまった。
鏡に背を向けて服を脱いだ。
目の端にとらえた僕の肩口。数本のミミズ腫れが赤黒く伸びていたのだ。それは拓斗の小さな爪痕。
こんな所に君を抱いた名残が……。
うれしさに思わず微笑んだ顔が、また僕を覗き込んでいた。カーテンを引いてそれを隠した。僕は待つと決めたんだから。一々思い出していたら体を壊してしまう。
「色即是空、だぞ。龍樹!」
ゆっくりと湯船に身体を沈めて。
湯の温かさがじっくりしみ込んでくるのを楽しんだ。
何と慌ただしい一日だったか。異国の地で拓斗と二人……。想像もしなかった。
「疲れた……」
風呂に入った途端にそれを意識した。あまりの心地よさに眠気を催すほど。
「いかんいかん」
シャワーに切り替え、湯をおとしながら身体を洗った。カーテンの向こうで拓斗の影が動いていた。足を忍ばせ、そっと入ってきたのは分かっていたので、声はかけないでおいた。
洗いながら拓斗のことを考える。今夜、同じ部屋の違うベッドで眠る彼……。
どうか安らかな眠りとなりますように……。
聖者になった気分をそのまま持ち越して僕はバスルームを出た。照明をおとしながらベッドに向かう。ボストンのおかげで、望み通りの寝床を得て。
隣のベッドに目を遣ると、毛布をひっかぶった芋虫が出来上がっていた。
「おやすみ……」
起こすのも何だから、そっと自己満足の囁きを芋虫に振りかけた。
疲れがつかみ取ってくれた眠りを素直に受け入れて。僕は眠りの世界に速やかに導入された。
気配に気づいたのは真夜中だった。首を巡らして覗いた、ベッドを分けるサイドテーブルに組み込まれたデジタル時計が三時を示していて。
密やかな息づかい。僕を覗き込む凝視の視線が痛くて。
僕を見下ろす影を、目を凝らして見上げた。
「……拓斗……? どうした?」
照明を明るくした。
「…………」
拓斗が泣いていた。声を殺して、涙をぽろぽろこぼしながら。
「眠れないの……?」
頭を振ってただ僕を見つめる。
「拓斗……?」
ギュッと瞼を閉じて涙を切った。頬を紅潮させて、ポロッと言った。
「夢……見た。龍樹さんまで俺を置いてっちゃう……。だから……」
心配で眠れないらしい。枕元で一晩中僕を見張ってるつもりだろうか。
「置いていかないよ……。大丈夫だから……」
「だって……だっ……あ……うっああああっ」
いきなり嗚咽が激しくなって、火がついたように泣き出した。
号泣する彼を抱き締めようとしたら、身を退いて避けられた。
激しく頭を振りながら。
「みんなっ……俺っ……をっ……置いて……くっ……んだ! 俺な……んか……みんなを……ガッカリさ……させること……しかできなくてっ」
ヒステリックなほどの勢いで泣きわめいた。
「も……やだ……。何で……こんな……」
「拓斗……! 僕は大丈夫だから」
説得しようにも嫌々をしながら泣くままで。
自分で自分の身体を抱き締めるようにして嗚咽を抑えようとする。
僕が君から離れていくなんて、どう論理展開すれば思いつくんだろうね。君の心の中の僕が占める割合を押し広げるためならどんなことだってしてみせるくらいなのに。
「おいで……。どうしても心配なら……。触れてれば分かるだろう?」
毛布を持ち上げて彼のスペースを空けた。
激昂が去ったのか、ヒステリックな泣き方は治まったが……。
拓斗は直ぐに入っては来なかった。
「だって……」
「君の嫌がることは何もしないから、安心して。ちょっと寒いから丁度いい。温めあおうよ」
瞬間躊躇いを見せたその瞳は、すまなそうに僕を見据えた。
袖で涙をふき取り嗚咽の息苦しさを残したまま言った。
「うん……、ごめ……」
怖ず怖ずと僕の横に身体を横たえた。
腕を回して彼の肩を抱いて……。強張る肩から少しずつ力が抜けていくのが嬉しい。やがて拓斗の鼻先が僕の胸に押しつけられた。
「あったかいね……」
囁きは自然な気持ちで口をついて出た。
「うん」
拓斗の吐息が直に肌に触れる。
それが低い嗚咽になって……。
「拓斗……?」
拓斗の腕が僕の背に回された。
「龍樹さん……、優しすぎる。俺……、俺……!!」
「……もしかして……、さっきのこと、気にしてるの?」
「う……」
肯定とも否定とも取れる首の振り方で彼は瞳を潤ませたまま僕を見つめていた。
そんな彼の髪にそっとキスして。
「僕は……待てるよ。こうして君が僕を必要としてくれてれば……。待てる……」
「龍樹さん……?」
「しなくてもすごく心地良いから……。君が僕の腕の中にいるってだけで、満足感で一杯になれる……。ねえ、こんな気持ちは初めてだって言ったら信じる?」
今僕は確実に君の心の中に入り込んでいる。それは身体を合わせるよりもずっと難しいことで、だからこそ幸福だ。
「君は、僕が嬉しそうにしてるのが嬉しいって言ってくれたね。僕も同じなんだ……だから……」
拓斗の腕が僕の心まで優しく抱き締める。
「ありがとう……。龍樹さんがいてくれてよかった。一人にしないでくれてよかった……」
それはそっくり僕の台詞。
「眠りなさい。君を一人になんかしない……。頼まれたってしないから……」
「うん、うん……」
そうして僕たちは抱き合ったまま眠りに落ちたのだけど。
それがこの後の僕の立場を決定づけてしまった。
実際拓斗に言った言葉はどれも本気の台詞だったのだが、当然下心もたっぷりあったわけで……。我慢すると言っても、高をくくっていたのだ。拓斗と身体を繋いだという事実は消せないから。
僕はその夜から犬になったのだ。いや、ジャンキーだろうか。拓斗という麻薬に溺れ、そのためなら何でもする重症の……。
帰国後すぐに拓斗は立派に家族の通夜と葬式を出した。親戚は出てこなかったので本当の一人で。彼の言うとおり、向坂の家は拓斗だけになってしまったらしい。
弔問客はMS社、学校関係が中心。
通夜は僕の知人のケータリングを頼んだ。
檀家になっている寺も、墓も分かっている。
費用は保険から取り戻せる。
葬儀一般に関しては葬儀屋というプロに頼んで。
とにかくあわただしい。
般若心経をBGMに、黒服の集団が行き交う。
拓斗の高校の友人達には何人か顔見知りがいたが、打ちひしがれた拓斗をどう扱えばいいのか戸惑いながらそれぞれの言葉で弔意を示し帰っていった。
喪主席でうなだれる拓斗を見つめる。
これが普通の恋人関係なら、僕は当然のように彼に寄り添っていられるのに……。こうして黒子のように陰から彼を見つめるしかない自分が、少し悲しかった。
僕らのつながりは、端から見れば喫茶店のマスターとバイト学生。僕は拓斗の隣の席に座る権利を持っていない。
しかし、黒子の立場も悪いことばかりではない。遠慮せずに彼を見つめることが出来るから。
僕の可愛い拓斗。
喪服代わりの制服姿も色っぽい。詰め襟のホックからボタンから丁寧に外し、厚手の黒い鎧から現れるシャツの下に隠された堅い果実にキスしたいと思った。
いかん、不謹慎すぎる!
「桂川さん?」
ぷるんと頭を振って欲情を振り捨てたところで呼びかけられ飛び上がった。
「はい?」
つややかな黒い巻き毛を揺らしながら僕を見上げたのは受付を手伝っていてくれた拓斗の同級生だった。
畑山……。そんな名だったと思う。拓斗よりも童顔な少年は、顔に似合わずしっかり者らしい。
「香典、ここに。受付閉めましたから。後は残った客だけなのでって」
ぐいっと突きつけられた葬儀社の紙袋を受け取った。
「あ、ああ、そう。ごくろうさま、君も奥でひと休みしていって。料理とってあるから」
「はい」
畑山君が素直に奥の席に向かったところで後ろから肩をたたかれた。
「美味しそうじゃない?」
振り返ってそいつを見たとたん心の中で舌打ちしていた。
ニヤニヤしながら畑山君を見つめるその顔には下卑た欲情むき出しの表情が浮かんでいる。
「清田……、通夜の席だぞ。しかもお前は仕事できてるんだから。ウェイターに徹する気がないなら帰れ!」
こいつが付いてくるのならあのケータリングサービスには頼まなかったのに。
「ごあいさつだよねぇ。タッちゃんの特別の依頼だっていうから、わざわざ手伝いに来てあげたのに……」
昔一度だけ遊んだことのある清田は、出会った中で最も苦手な男だった。知人の店でソムリエをしている男。
ソムリエという仕事に関しては本物だが、好色で一晩十人切りとかを平気でやってのける。
細身で長身、優しげで華やかな顔立ち。職業柄か物腰は優雅で身だしなみも申し分ない。女性客のファンも多いという。ワインを楽しむために手を貸してもらうだけなら、この男に文句は出ない。
だが。性格に問題有りだ。一度寝ただけで豹変する。
「通夜の席にソムリエは必要ないんだよ」
「そうじゃなくって。タッちゃんに会いたかったんじゃないか」
きれいに磨かれた爪が媚びたように僕の耳をつねった。
「やめてくれないか、その呼び方」
「冷たいなぁ……。あの夜はあんなに熱く愛してくれたじゃない」
そう、この男は据え膳の危険性を僕に教えてくれたのだった。
拓斗に一目惚れしたときに、その手の付き合いがあった相手とは全て別れた。大体相手にしてもドライなもので、セックスだけの関係だったから、復縁を迫るようなものはいなかった。
この、清田以外は。
清田の遊び方からいって、後腐れ無さそうだったので一夜を共にした。後も清田は相変わらずのプレイボーイぶりだったが、僕に対しては執着があったようで。
「愛してない。セックスしただけだ」
何を言っても堪えないというようなしつこさを持つ清田には、同じ様な台詞を何度もぶつけたような気がする。
その日の清田は瞬間こわばってから無理矢理笑顔を作った。一瞬僕は清田の本気を信じた。
この男、僕に特別な感情を持っているのか?
それは僕の姿に重なる。
拓斗から見れば、僕もこんな風にしつこい男なんだろうか。
「うん、それでもいい。タッちゃんのは好き。また……しようよ」
だが、本気なら尚更だ。
絡み付いてくる腕を振りほどきながら吐き付けた。
「だめだ」
愛のないセックスなんて、二度と出来ない。
「セックスだけってのはやめたんだ。お前のことは愛せない」
「ふうん、そういうこと言う?」
意地悪げににんまり笑った。
「じゃあ、あの子としちゃおうかな……」
「清田?」
「あの喪主、可愛いじゃない。今度の恋人は粒ぞろいのお友達もオマケなんだ。味見済みのでいいから僕にも一人わけてよ」
「ふざけるな」
「何怒ってるの? コマシのタッちゃんが……」
僕の中で何かがブチッと切れる音がした。
無意識のうちに僕は清田の胸ぐらをつかんで高く掲げ、壁に彼を押し付けていた。
「なっ」
苦しげに言う清田の襟首を、片腕で持ち上げたまま締め上げた。
「あの子は貴様の扱うワインや男達とは違うんだ。一寸でも手を出して見ろ、命は無いと思え。どんな事してでも貴様を葬ってやるからな!」
手を離すと真っ青になった清田はどさりと音を立ててしりもちを付いた。
「それと……。僕をタッちゃんなんて呼ぶな!」
ドスが巧く利いたかどうかはしらないが、怯えた表情のまま清田はそそくさと帰っていった。
大体、清田にコマシなんて言われるのは心外だ。拓斗以外は口説き落とした相手なんていない。
僕の怒りは自分の過去にも向けられていた。清田が反映させる昔の僕は、来る者拒まずだった。……出来れば拓斗には一生知られたくない存在で。よりによって彼の家族の通夜の席にそれが現れたのは、僕への試練としか思えない。
「龍樹さん……どうしたの?」
「え?」
「怖い顔してる……。あの人……誰?」
清田の去った方を振り返りながら、拓斗が訊ねてきた。
話を聞かれた様なそぶりには見えない。
本当のことを言うのはリスクが大きすぎる。
「……知り合いの店のソムリエ。ほら、通夜の料理を頼んだ……。用は済んだから帰って貰った」
「ふうん……。ケンカしてんのかと思った。ね、客もみんな帰ったし、葬儀社の人ももう帰るって。畑山達に料理持たせていい?」
疑惑の欠片さえ見せない微笑みを浮かべて拓斗が言ったので、僕はホッと胸をなで下ろしていた。
聞かれていなかった。まだ猶予がある。つり込まれるように僕も微笑んでいた。
「ああ。綺麗に折りを作ってあげる。君は食事は?」
「まだ……。なんか、食べる気しなくって……」
「疲れたんだよ。消化のいいものを何か作ってあげよう」
「ん……。龍樹さん、今日、泊まってく?」
「いや……泊まっていきたいけど、帰ったほうがいいだろう? 周りの眼があるから……」
ダイニングの明かりの方に一歩踏み出した背中に、拓斗がしがみついてきた。
「いやだ! おいてかないで……! 一人にしないでよ」
「拓斗……」
「周りの眼なんて、いいよっ。あ、甘えてるのは分かってる。でもっ! ここ、広すぎるんだ」
「君がそういうなら……喜んで」
「う……ん」
瞳を潤ませて頷く拓斗の肩を抱いた。
震える肩がやり切れなさを伝えてきた。
「一緒にいよう、ずっと……。帰るなんて言ってごめん」
拓斗が僕を必要としている。こんな時だが嬉しかった。
「さて、まだかたずけが残ってる、もう一息頑張ろうね」
「うん」
接客用に使っていた酒と煙草と料理のにおいでむせ返るようなダイニングとリビングを見渡した。
今居るのは拓斗の旧友達と、葬儀社の者。ケータリングの者達は元々清田を残して料理を運び入れると帰ってしまっていた。支払いの時に、清田のことは念押ししておかなければと思った。
手つかずの料理と、喰い散らかしを分け、簡単な折りを作った。もちろん持ち帰る者の希望を聞いて。
親戚のいない通夜というのは、後をひかないようだ。
しつこく居残る酔っぱらいもいない。
疲れた顔をした拓斗にとってはその方がありがたいが。
折りを持った畑山君達を送り出してから向坂家のキッチンを使って二人分の雑炊を作った。
急に人気がなくなった家はやけに静かだ。こんな夜は確かに一人ではいたくない。
「龍樹さん風呂……先にして」
拓斗が声をかけてきた。
「着替えは……どうしよ。龍樹さんが着れるの……あるかな」
君が世話を焼いてくれるなんて……。何だか心地良い。
「裸でいいでしょ」
囁いた途端に拓斗は赤面してしどろもどろになった。
「エッ? そ、それは……」
落胆を押し隠してプッと吹いて笑って見せた。
「冗談! Tシャツとトランクス、貸してもらえるといいんだけど」
「うん。出してくるから入ってて! お湯張ってあるから」
僕が素直に風呂場に向かうのを確認して、あからさまにホッとした顔で彼は二階の部屋へ向かった。
「今日も……お預けらしいね」
溜め息混じりに呟いた。
「ま、当然か……。明日は告別式だもんな」
案内された向坂家の風呂は桧の桶。湯気に混ざる桧の香りはリラクゼーションの効果を高めてくれる。
高めの天井と広い洗い場。ポトスがはびこっているのは拓斗のせいか?
「まるでジャングル風呂だな」
クスッと笑った声にエコーがかかった。
こんな風呂なら二人で一緒に入りたいものだ。
拓斗の甘い喘ぎをここで耳に出来たら……。
昨日は空港から僕の部屋に直行して、電話で出来る段取りだけして取りあえず寝てしまった。
今日は朝から通夜の準備。
「やっぱりちょっと疲れちゃったかな……」
たっぷりとした湯船は僕の体がのばせる広さ。ゆったりと横たわって眼を閉じた。
拓斗の艶めかしい姿を想像する。夜を無事に過ごすためにも何本か抜かなければならない。多分一緒に寝る羽目になるだろうから。
拓斗が次に使う筈の湯船から出て座り、そっと自分のものを手に取った。ゆっくりとしごきながら彼を思った。
拓斗……!
存分に欲望をほとばしらせ、熱い湯をかけて流した。
清田の存在が僕を不安にさせている。拓斗の目に映る僕という男は、あくまでも紳士的でいなければ。
拓斗が案内した寝室は彼の部屋。シングルベッドと、机と本棚。作り付けのクロゼット。拓斗らしい乱雑さと小綺麗さの同居した部屋。僕は彼に気づかれないように彼の匂いをたっぷり吸い込んだ。
これが……拓斗の匂い。
「シングルじゃ狭いけど……。龍樹さん、一緒に寝てくれる……?」
「ああ。君を……抱き締めてもいいなら……。おやすみのキスはしてもいい?」
「うん……」
彼の唇に触れた途端、我慢できなくなって舌を差し込んでしまったが。それ以上は何とか思いとどまった。
そうして僕は湯上がりの艶めかしい彼を、何もせずに抱き締めて眠るという苦行に挑戦したのだ。
紳士を装った獣の僕。
過去を語らなければいけない時が来る。その時の彼の反応が怖い。
午前中の告別式の後、焼き場には僕と拓斗の二人きり。焼き場での読経の後、坊さんはスケジュールが混んでいたのか先に帰ってしまった。三体のお骨をつまむ作業は儀式的に済ませて。
小さな骨壺に納められてしまった拓斗の家族。
お骨納めのその日まで、向坂邸で時を過ごす。
「二人一緒に箸でつまむなんて、龍樹さんがいなかったら出来なかったね」
骨壺と遺影を積み込んだ借り物の黒のベンツを走らせながら、バックシートから声をかけられ苦笑した。
「怒られるかもしれないけど……僕は嬉しかったよ。君を手伝えるってのは……悦びなんだ」
「龍樹さんてば……すぐそんな事言って」
呆れたように言われてカッと頬が燃え上がった。
「しょうがないよ。恋は盲目って言うでしょ? 僕は熱烈に恋してる。君に……」
そうなんだ。恥ずかしいとかも通り越して。自分をコントロールすることの難しさを拓斗に出会って知ったんだ。
「気障すぎるよ、そういうの……」
同じように赤い顔をした拓斗の責めるような言い方に、ホンの少し腹が立った。僕の本気を信じてもらえないなんて。
「でも、本当だもの……。ま、確かに口に出せちゃうなんて恋に狂ってる証拠かもね」
冷静に考えるなら、確かに恥ずかしげもなく、と言うところだから。
笑われると思ってそっとフロントミラーで伺って。予想に反して涙ぐんだ顔を見つけてしまい、僕は慌てた。
「拓斗……君……?」
「え?」
掌で顔を拭うように涙をふき取り無理矢理微笑んだ。いじらしい微笑み。どうして君はそんなに魅力的なんだろう。表情というのは、けして造りの美醜で左右されるものではない。拓斗の愛らしさは、その喜怒哀楽の表情を素直で誠実な性格が裏打ちしているからこそ。
「大丈夫……。初七日、今日やっちゃうんだよね?……どうするんだっけ?」
声が少し震えているね。
「お経はさっき一緒に上げてもらっちゃったから、もう一回お焼香して料理食べるぐらい……かな。……僕らだけだけど」
「料理って……?」
「ありがちなごちそう。普通、親戚とか大人数だったりで、仕出し頼んだりするけどね。今回はホントに二人きりだし。……まあ、精進落としと兼ねてもいいかな」
「精進落とし?」
「元町の店、予約してある。葬式ご苦労様会みたいなもんだな」
「なんだよそれぇ?」
「覚悟しとけよ。ボリュームの多さでは有名だからね。一度君を連れていってみたいって思ってたのさ」
拓斗があの料理の数々を嬉しそうにかたずける時の表情を楽しみたい。そんな気持ちでチョイスした。僕の疲れを吹き飛ばす拓斗の嬉しそうな笑顔……。こんな時だが少しは見せてくれるかな……。
車のデジタル時計に目を遣ってアクセルを踏む足に力を込めた。
「ああ、時間ぎりぎりだな。遅刻厳禁の店なんだよ。部屋が七部屋しかなくて、全部個室。お父さん達を並べておいても、気兼ねいらないから」
言いながら元町から外れた駐車場に車を入れた。
「店に駐車場がないから、ここから歩きなんだ」
遺影を重ねて春美ちゃんの骨と一緒に預かり、拓斗には両親の骨を持たせて車を降りた。
外人墓地の裏側に面した住宅街のど真ん中にあるため、少々歩かなければならない。
「ここ?」
不思議そうに建物を見つめる拓斗。確かに、ただの民家に見えるかもしれない。そういう意味でも少し変わった料理屋だ。
「うん。元町梅林て、名前入ってるでしょ?」
店の小さなのれんを指さした。もう片方の手で彼の肩を抱き、促して。
小さな部屋へ通された。実際、二人くらいでいくと、個室とは言いながら大きめの部屋に衝立で隣の客と仕切られての食事の場合があるのだ。
「ホントは一部屋丸々ってのは三人以上らしいんだけど……精進落としだって言っておいたからかね」
予約が詰まっていなかった結果かもしれないが、とにかく水入らずなのに感謝した。
上座に拓斗の家族を並べて二人で向き合った。
「……懐石なの?」
「季節料理でね。料理法は色々。懐石って言い切っちゃうにはバラエティありすぎるかもね。小食だと降参になっちゃうんだよ」
どうやら僕の台詞を大げさなものと思っていたらしい拓斗は料理が出てくる度に表情を変えていった。
「……まだ……あるの?」
「……降参?」
「いや。コンディション整えて計画的に食べる。俺、残すの嫌いなんだよ。手を着けて残すのって、作った人に失礼だろ?」
妙に生真面目な言い方に笑ってしまった。では、アップルパイを残したときは本当にコンディション悪かったって事だ。
「あ、龍樹さんの作った物は義務でかたずけたことないからね!」
「分かってるよ」
言われなくてもね。君の表情でわかる。最後の一口まで美味しそうに食べてくれる君だもの。
「で、ここは美味しい? 食べきれなければ持ち帰れるのもあるよ」
「うん! 大丈夫」
二時間かけて全部をかたずけて。満たされた気分で帰り路についた。
帰宅して直ぐ葬儀屋が用意していってくれた祭壇を設えて線香をあげて。
本当は息子さんを下さいと挨拶を入れたいところだけれど。
拓斗の目には僕に彼が抱かれるのを嫌がる父親が見えるという。生きていれば当然そうなるだろうけれど。僕を息子には近づけたくないだろう彼の両親に、僕は背を向けた。
拓斗の中でそういう考えがある以上、まだ彼を完全には僕のものには出来ないということで……。
しんみりと夜までの時間を過ごした。
拓斗の家でコーヒーを煎れる。あった豆はマンデリンとモカ。これの七対三が拓斗のごきげんブレンドだ。今の拓斗の気分を考えて少しだけマンデリンの配分を増やした。
溜め息をついてコーヒーを啜る拓斗を見つめる。
どんなことをしても欲しい人。但し、その人の不興を買う行為は一切出来ない。大切で、だからこそ不用意な手は出せないでいる。
そんな彼がまだ僕を完全には受け入れられないというのなら。僕は大人しく待つしかない。側にいて、息づかいを感じて。抱き締めることもできるのに。存分に愛し合うことだけは禁じられている。
ベッドで彼を抱き締めながら、彼が僕を必要としているという幸福だけで満足するには、彼のことを知りすぎている自分を恨んだ。
セックスが全てではないけれど、僕は彼との行為が大好きだから……。それを抜きにして、というのは生殺しに近いものがある。それがために、いい加減逃げ出したい気分になっていたのかもしれない。
翌日の店の準備のためという言い訳を自分に与えて、その夜は帰宅するつもりでジャケットを着た。それを拓斗に見とがめられて。
「龍樹さん……? どうしたの?」
「ああ、今日は……帰らないと。明日は店開けなきゃ。今夜はこれで……」
玄関に向かおうとして後ろからしがみつかれた。
「俺もいく!」
「え?」
「龍樹さんが大変なのは分かってる。だから……俺が行く!」
「ちょっと、ここどうするの?」
「夜だけでいいんだ。龍樹さんの所に連れていって。邪魔しないようにする。手伝いもするから……!」
甘えるように縋る瞳で見上げられて僕は……。
思わず頷いていた。
それが毎夜生殺しという目に遭わされるということになるのも分かっていて。
以来。
拓斗は僕の家に泊まり込んでいる。広すぎる家で一人夜を過ごすのが未だに耐えられないらしく……。
僕のベッドで、僕の腕の中で。僕にしがみついて眠るのだ。
朝食を済ませると自分の家へ帰る。昼に店に寄り、昼食。夕食の時間までふらりと出かけて行き、帰ってきてそのまま朝まで僕の部屋に。
数日が過ぎて。拓斗が変わった。
僕に自分のことを話してくれなくなったのだ。それは、ただの常連客だったときよりも、僕との間に距離を作っているように感じさせるほど拓斗らしくない態度で。
「いつもどこに行ってるの?」
「別に……」
我慢しきれず訊ねた結果がそれだった。
視線を逸らし、僕の顔を見ようともしない。
おはようとおやすみ以外には僕が訊ねたときに最低限の返事のみ。食事の時さえ黙々と食べるだけ。心此処にあらずというようによそよそしく上の空。
僕は彼を怒らせるようなことをしたのだろうか。記憶を辿り、困惑する。思い当たらないのだ。
不機嫌そうにしか見えない拓斗は、それでも夜になると当然のように僕の寝床に潜り込んでくる。僕の胸に鼻先を擦り付け、僕の腰に腕を回して……。
困惑したままの僕は、つい彼の感触が嬉しくて抱き締めてしまう。それは今、お預けばかりさせられている僕に与えられる中で一番嬉しいご褒美だから。
抱き締めながら、胸の内で呟く。
僕は君の何?
熊の縫いぐるみか何かか?
詰め寄って問いただしたくなるのを拳を握りしめて耐える。
禁断症状は、そんな状況のせいで早まったんだと思う。拓斗の瞳に僕は映らないのだと思ってしまったから……。
誰かいる。外に誰かいるんだ。僕から拓斗を奪おうとしている誰かが……。
『あの子としちゃおうかなぁ』
そんな台詞が頭に浮かんだ。
清田だろうか……。
まさか。あいつは本当に怯えていた。第一、拓斗が相手にする訳無いではないか。
でも……。
疑心暗鬼にとりつかれた僕はそんな馬鹿な疑いすら振り払えないほど心を病んでしまっていたらしい。
朝、拓斗が出て行ってから後を付けることにした。
そぞろ歩きのような足取りでさえ、優美な軽快さを感じさせる。一定の間隔をとって散歩の顔で歩く。彼の後ろ姿はそれはそれで僕を楽しませる。
拓斗はどこに寄る様子もなく自宅に戻った。モルタルの土塀は結構高めの造りだが、僕の目隠しには足りない。伸び放題の庭木に邪魔をされながら、それでも外から様子をうかがった。
まるで、片恋の苦しさを紛らわせるために徘徊していたときのように。
二往復ほどしたところで、不信気な顔の主婦に見とがめられてしまった。仕方なく門を開け中に入る。そっと、音を立てないように、けれど堂々と。玄関には行かず、庭に回る。
サンルームの奥に、障子でしきられた和室があり、そこに仏壇が設えてあるのだ。
予想通り、開け放たれたままの障子の向こうの仏壇の前に拓斗はいた。ぼんやり座り込んで遺影を見つめている。
儚げで、寂しげで……。
自分が侵入者であることを忘れ、抱き締めに向かおうと一歩踏み出した途端。拓斗の肩に乗せられた手が目に飛び込んできた。ブルーグレーの袖からカフスの光るワイシャツの袖口が覗く。明らかに男のものと判る筋張った長い指先。
拓斗は振り返ってその腕の主を見上げ、微笑みかけた。それは僕だけのものだと信じていた極上の微笑み。
色っぽくて、可愛くて、頼りなげなくせに意地っぱりな……。抱き締めずにはいられない微笑み。
それが今、他の男に注がれていた。
僕の中で暗い澱が逆流し始める。体中がそれに支配され、変質していく。
嫉妬、憎悪、失望。
でも……愛してる……。
飛び出していきそうになる自分を抑えながら二人を注視した。
手の持ち主は藍本だった。
葬式の時に、MS社側の手伝いを仕切っていたのも彼だった。会社がらみの処理は、全て彼がやってくれたと拓斗が言っていたっけ……。
だからこそ、あの微笑みが……?
僕は子供っぽい嫉妬に狂って行動を起こさなかったことに安堵の吐息を吐いた。
そう。拓斗が自ら男を誘惑するなど。あり得ない。
拓斗の状況を自分の身に置き換えて考える。
僕が両親を亡くしたら……。ピンとこない。
僕に自分たちの敷いたレール通りの人生を歩ませようとする両親に対する反発心はいまだに胸の中に燻っている。
僕がゲイであること。医者として生きることを拒んだこと。『El Loco』を開いたこと。どれもこれも両親にとっては気に入らないことで。
何かにつけて干渉してくる母や、顔を合わせる度に戻ってこいと言う父。
決してしっくりきているような間柄ではないのだが。それでも、彼らが今すぐ亡くなるなどとは考えにくい。
なんだかんだといっても親なのだ。
もし、……もしも。
拓斗を今すぐ失ったとしたら……?
考えたくない。僕は多分狂う。彼が死んでも、ただ僕を捨てたに過ぎなくても……、僕は後を追う。追いかけて、追いかけて。抱き締めて離さないだろう。
元来僕は我が儘なのだ。拓斗を失いたくないが為に下でに出ているだけ。拓斗が僕から逃げたら……。本当に僕を裏切って逃げたら……。彼の心を取り戻せないと判ったら。その時僕は本性を現すだろう。僕の中の獣を解放して。彼を引き裂き、弄び、貪り尽くす。
「……僕に……させないでくれよな。そんなこと……。君は……そんな奴じゃない……よね……」
両親と妹をいっぺんに亡くした拓斗が、恋愛沙汰に浮き身をやつす余裕がある訳無いんだ。そう思い至って、狭量な嫉妬に苛まれる自分の姑息さに目眩がした。
「店……開けなくちゃな」
帰って、拓斗を待とう。特別に気持ちを込めてコーヒーを煎れて。彼の好きなメニューで昼食のテーブルを埋めよう。
以前のように、拓斗が自分から話してくれるのを待つんだ。
僕はそっと向坂邸から抜け出した。
昼食時。朝からどこかに出かけていた拓斗はいつものようにふらりと現れて。いつものカウンター席に腰掛けた。
僕は黙って彼用のブレンドを煎れる。
ここのところ、ずっとトラジャのみを煎れている。彼が気分の乗らないときに頼む定番だったから。深い香りと、マイルドで優しい味わいが浮上する手助けをしてくれるのだといっていた。
「今日もトラジャなんだ……」
拓斗は鼻をひくつかせてボソッと言った。
「うん、そう見えたんだけど。嫌なら換えるよ」
プルプルと頭を振り、僕を見上げた。
「それでいいよ!」
拓斗にコーヒーを渡そうとした瞬間、ドアベルが客の来訪を告げた。目を遣った先には藍本が。目で拓斗を探しあて、にこやかに笑うと彼の隣に陣取った。
「待った?」
「ううん、今来たとこで」
映画やドラマのデートのシーンでよく聞く台詞が二人から飛び出して。
僕は思わず彼らを睨んでいたと思う。
どこ吹く風で藍本は僕に会釈し、拓斗のコーヒーを覗き込んだ。
「いい香りだね、僕にもそれ、もらえます?」
カウンターに座れば誰でも客。お客様は神様で……。
僕は拓斗のおかわり用に煎れておいたトラジャを母から無理矢理プレゼントされたノリタケのボーンチャイナに入れて出した。
「あー、美味しいな。これじゃ、拓斗君が褒めちぎるわけだ」
「ありがとうございます。拓斗君、食事は?」
「ああ、いいんです。これから彼と出かけますから。店に予約入れてあるんですよ」
気軽な調子でいう藍本。僕は拓斗を見つめていた。藍本が何か言う度、縮こまっていくような拓斗。嘘が下手な拓斗は、確かに後ろめたいような顔をしていた。
僕がどんなに焼き餅焼きか、彼は知っている。店の客と拓斗が親しげに話しているだけで僕が嫉妬に狂ってしまうのを知っているのに。何故、ここで待ち合わせをする必要がある? まるでデートのような待ち合わせを。
「あの、親父の保険のこととかで会社まで行くんだ。学費とか……葬式の費用とかあるから……。なるたけ早くおりるようにって……」
申し訳なさそうにいいわけを口にして。内容を聞いて幾分落ち着いた僕だが、まだ藍本に対する腹立ちは残っている。
「そう……。学費っていえば……。保証人の書類は出しといたから。あの時にそのまま預かってたでしょ。なくさないうちにと思って」
何げに思いついたことを言った途端、拓斗はビクッと飛び上がった。
「あ……。うん。でも…………」
言葉を濁す拓斗を藍本がすくい上げるように立ち上がらせた。
「拓斗君、時間が……。ちょっと急いで。桂川さん、お勘定をお願いします」
「一五七五円です」
拓斗の分も勘定に入れて請求した。『El Loco』を手伝っていた拓斗の頭には全ての値段がインプットされている。
もちろん目を丸くしていた。
拓斗からはブレンドの値段しか取ったことがなかったし、実を言うとメニューにトラジャは載せていないから。
だがトラジャの正規の値段は七五〇円だ。ぼってはいない。大体、トラジャは拓斗のためにいれたのだ。
藍本も気にする風でもなく支払った。
拓斗は店を出ていくときまで僕を見ていた。僕は、営業スマイルで彼らを送り出して。拓斗にだけ僕が怒っていることが解ればいい。
話の腰を折られたのも腹立たしい。僕の拓斗を連行の形で連れ去ってしまったのも腹立つ。
他の客がいなければ僕は藍本の使った器を床にたたきつけていただろう。
閉店までの半日、僕は中っ腹で仕事をしていた。何人かの常連客にはどうかしたか? と心配されて。
いつも下世話なからかいをする同じ商店街の電気屋の親父には、たまってるんじゃないか? などとまともに図星を指され。
ついでに変な届け物。
拓斗達と入れ違いに店に入ってきたのは花屋だった。
「こちら、『El Loco』……えるろこ……ですよね? こちら気付で、ええと、向坂……拓斗様にお届け物です」
「……確かに彼はこちらでアルバイトしていますが……。誰からです? なんでまたうちに……?」
「ああ……と、その。ご自宅は留守がちだからと、ご指定いただきました。お名前は差し控えるようにと。現金でお支払いでしたから記録がないんですよ。ただ、イニシャルをA……とだけ」
「A……?」
物はただの花束だったので、仕方なく預かった。
次々と運び込まれるバラ、バラ、バラ。
深紅のバラの大きな花束が五束。
居合わせた客達が黄色い悲鳴を上げた。
「すごーい。拓斗君てぇ、どういう人に目を付けられてるの?」
「え?」
「だって、これ、一輪でも滅茶苦茶高いじゃないですかぁ。第一、赤いバラって、《あなたを愛しています》って花言葉でしょう?」
「そうなの?」
平静を装いながら、この情報に僕は動揺を隠せたかどうか。
「イニシャルAの人としか分からないから。……本当にどんな人なんだろうね。拓斗君が来たら聞いてみようかな」
「マスター、差し支えなかったら、今度どんな人か教えてね。なんか、好奇心そそられるわ」
常連のOL達が帰った後。花束をどこに置くか考え込んで。取りあえず事務室に運んだ。
(あなたを愛していますだって? 冗談じゃない!)
本音では即ゴミ捨て場に直行させたい花だが、拓斗がどういう反応をするかも知りたく、Aという人物も……。僕が知っている中ではAは……。
藍本……!
「あの野郎……!」
低く呟いたつもりだったのに、ふと視線を感じて客席に目を遣ったら、隅の席にいた一見のカップルがさっと視線を逸らした。
「失礼」
すました顔で水を換えてやった。
全くどいつもこいつも!
勝手にイチャついてろよ!
拗ねた気分を全て営業スマイルでくるみ込んで仕事をしていたのだが。
その日はどうやら僕の厄日だったらしい。
夕方のかきいれ時に珍しく閑古鳥が遊ぶ店内で。僕が考えることといったら拓斗のことばかり。
どうして君は……。
どうしたら君を……。
そんな物思いを突き破ったのはけたたましいドアの開け方と甲高い少年の声。
「マスター、マスター!」
入ってくるのと同時に僕にせっつくようにかじりついてきたのは向かいの床屋の息子。小学六年生だというが、少し太めでタッパもあるから、中高生と間違われることが多い。
デザート専門だが、常連の一人だ。
「太君、どうしたの?」
「どうしたのじゃないよ! 外! 外!」
引っ張られて出て見れば。
「……!」
入り口周辺にネズミの死骸。それも数十匹。
「……これじゃ、お客は入れないよぉ」
「ああ……そうだね……」
道理で閑古鳥が居座るわけだ。この死骸の山を踏み越えてまでコーヒーを飲みたい客はいないだろう。
太君は、意を決して知らせに来てくれたわけだ。
「かたずけ、手伝うよ」
「ああ、わるいね」
死骸を集めて黒ビニール袋に詰め込み、煉瓦引きのたたきの染みは、消毒薬を撒いてから水でこすり落とした。
「手の消毒、していきなさい」
「うん」
綺麗になった店の前を眺めてから彼を促した。手を洗わせ、ジュースを出して。彼が飲んでいる間にケーキを包んだ。
「手伝ってくれたお礼だ。今日のスペシャル、お土産にして。太君これ好きだったでしょ?」
その日のスペシャルケーキはフレーズショコラ。苺とチョコの組み合わせのケーキだったのだが、ネズミのおかげでホールのまま残っていた。
「え? これ、全部?」
「お母さんに切って貰って」
「……うん! ありがとう!」
嬉しそうにケーキの箱を抱えて出て行く太君を見送り、気分の悪さだけを引きずってカウンターに座り込んだ。
ネズミは……どう考えても嫌がらせでしかない。バラの花だって、考えようによっては……。
だが、なんのために?
拓斗を愛しているという誰かは、僕が邪魔だから……?
「邪魔にされるほどの立場じゃないんだけどね……」
口に出してみて、かえって不愉快な気分が増幅した。
そういうわけで、いらいらは拓斗が夕食に訪れたときにも続いていた。
バラの花束を前にした拓斗の反応は。
全く持って身に覚えなし、……という顔。
「Aって、藍本さんくらいしか僕は浮かばないんだけどね。君は?」
「分かんない……。なんか、気持ち悪いな……。こういうの」
「あなたを愛していますっていう花言葉だって。お客さんが教えてくれた」
「そんなの……。……龍樹さんくらいしか思いつかない……でも、違う……んだよね」
「残念ながら。ま、花には罪ないからね。綺麗だし、貰っておけば? 何でも高い花なんだって」
我ながらつっけんどんな言い方になってしまった。拓斗は身を縮ませるように俯いてしまって。
「昼間はごめん……」
「なにが?」
いらいらしたまま聞き返した。拓斗の申し訳なさそうな顔が、更に曇る。
「藍本さんのこと……。ほんとに事務処理手伝ってもらってるだけなんだ。でも、龍樹さん怒ってるから……。ここで待ち合わせなんてしない方がよかったね」
そうとも!
僕は吐き出した。
「藍本は……。あいつは嫌いだ」
「龍樹さん……?」
成田での藍本の目つきが、含みのありそうな、嫌な感じのものだったせいもある。初対面の筈の僕らに対して送る視線ではなかった。
あの時はそれどころじゃなかったが、記憶の端にあの視線が残っている。
時が経つほど気になってくる。
あれは悪意だ。明らかに……。
「取りあえず何も起きてないからいいけど、悪意を感じるんだ。嫌な予感ていうか。君にはあいつと関わって欲しくない。君があいつと一緒にいるだけで吐き気がする」
それは、あのネズミの死骸の山よりも威力があるくらい。
「龍樹さん、焼き餅は程々にしてくれよ。藍本さんは親切だよ。変じゃないよ」
「焼き餅なんかじゃない。そうじゃなくて……」
どう言えば彼に伝わるんだろう。これは本能的な危険予測だと。
「龍樹さんにだって、紫関さんがいるじゃない? 藍本さんと俺は……、友達……じゃないけど、すごくそれに近いものなんだ」
「紫関は……僕らに悪意なんて持ってない」
「……龍樹さん、どうかしてる……。どうしてあの人が俺らに悪意持つんだよ? このあいだ初めて会って、利害関係だってないじゃないか……」
利害関係はもう生じている。藍本の目線は、にこやかに笑いながらも僕から拓斗を奪ってやると挑戦してきていた。それも、単なる恋敵というものではなく。
「多分、あいつもゲイだ。そういう目、してた」
「龍樹さん……! あの人、彼女いるよ。そんな話、ちらって聞いた。」
げんなりしたように拓斗は僕を見つめていた。
「じゃあ、両刀遣いなんだ」
意地になっていた。拓斗が藍本の味方に付いたから。
「もうっ! マジで怒るよ。とにかく、俺、龍樹さんが怒るようなこと、してないから。藍本さんにも変な態度しないでくれよな」
叫ぶように言い放ってバラを抱えた。
怒った顔のままバラを処理し始めた彼は、一言声を掛けるのさえ憶してしまうほどの不機嫌さ。
美しいけれど僕にとっては見るのが辛い薔薇の花を目に付くいろんな所にいけてまわって……。拓斗流の抗議行動に僕は怯えるばかりだった。
拓斗にだけは嫌われたくないのに。子供のような過ぎた焼き餅でこじれさせてしまうなんて!
「拓斗君、夕食は?」
拓斗の怒りにピークが過ぎたのを見計らってから、声を掛けた。
怒った顔のままいつものカウンター席にどかっと座った。
「キーマカレー。……昼がイタ飯のコースだったから」
瞬間藍本と拓斗が向かい合って笑い合うのを想像して爆発し掛けた。とっさに絞り出した台詞は、
「……美味しかった?」
なんて、つまらないもの。
「普通」
拓斗の口振りでは感動的な料理ではなかったようだ。少しほっとする。あの、うれしそうに食べる幸せな表情は僕だけの楽しみにしておきたかったから。
拓斗の好きな組み合わせメニューを思い出して言ってみた。
「……フルーツサラダ、付ける?」
「……うん」
拓斗は嬉しそうに食事をたいらげた。怒っていても、食べるときはご機嫌で。
「機嫌……なおった?」
食後のコーヒーを渡しながら恐る恐る聞いてみた。
プッと吹きだして僕に笑いかけた拓斗の屈託のなさ。僕は彼に振り回されている。彼の無意識の行動に一喜一憂させられながら、でもこんな微笑みをもらえるなら幸せだなどと思ってしまうあたり……。これを惚れた弱みと言わずして何を言うって感じだろうか。
「最初から怒ってないよ。龍樹さんの焼き餅がこれ以上ひどくなったら怒るよって言ったんだ。……それよりさ……」
真剣な色を瞳に浮かべて真正面から僕を見つめてきた。それは拓斗が真面目な話を持ち出す前兆で。
「俺……、学校行かないかもしれないんだ。だから、龍樹さんに頼んでた保証人の件も……白紙にして欲しい」
「医者にならないの? 入学金だって払っちゃったのに……」
「なるよ……。浪人して、来年もう一度横浜市大受ける。親父がああなった以上、早光大の学費はきついから。入学金は全部じゃないけど返してもらえるし」
「けど、予備校の金だってばかにならないだろう? もったいないと思うけど……。保険とか、どうしたの? 結構おりるんじゃなかったの?」
「入学金と、授業料、施設維持費……でかいのだけでも結構消えちゃうし、学生でいる間の生活費とかも……かかるし。入学金以外は毎年だよ。バイトだけじゃ……」
「生活の心配なんてするなよ。僕のところで暮らせばいいじゃないか。それに、授業料だって、文字通り僕は保証人してもいいんだ。だから……」
「俺はいやなんだよっ。龍樹さんにおんぶにダッコするような生活……。そんな飼われるような生活……嫌だ」
拓斗の思ってもみなかった拒絶の激しさは僕を怯えさせた。
「君を飼おうなんて思ってないよ? 僕はただ……」
君の夢は僕の希望でもあるのに。君みたいな人に医者になって欲しいって……。
拓斗の飼うという表現は僕を悲しませる。
僕の悲しみに気が付いた彼は疲れた笑いを浮かべた。
「ああ、ごめん……、言い過ぎた。そうだよね。今だって毎晩龍樹さんに迷惑かけてんだから……。言えた義理じゃないよね……」
「迷惑なんかじゃないって! ……ずっといて欲しいんだ、僕と一緒に。……そう願ったらだめ?」
拓斗はやるせない微笑みを浮かべたまま立ち上がった。僕の質問には答えず、いつもの棚から店を手伝うときに使うエプロンを取り出した。
「閉店まで手伝うね……」
「拓斗?」
答えをもぎ取ろうと彼の腕に手を掛けた瞬間にドアベルが客の来訪を告げた。
「いらっしゃいませぇ!」
拓斗の元気な声が響き、僕等のプライベートな話は棚上げになってしまった。
「何、それじゃ、今日は売り上げ全然だったの? 龍樹さんのフレーズショコラ、丸ごと太に?」
「うん」
風呂を終え、二人でベッドに潜り込み、いつものように拓斗の肩を抱いて。
それは苦痛と悦びを併せ持った毎夜の儀式。
最近、寝る前の会話はなるべく色気のないものを選ぶ様にしている。それは自分のためでもあり、拓斗を困らせないためでもあった。
その夜僕の口数が倍になっていたのは、非日常的な事件がまとめて起きたせいと、拓斗が以前のように話によく乗ってくれていたから。
「だって、今日はもう出そうもなかったし、太君は気持ち悪いの我慢してかたずけ手伝ってくれたんだ」
「俺、喰い損ねた。いつも太にかっさらわれるんだよなぁ。何故か。あの苺とチョコのケーキでしょ? 何でだか俺には縁がない……」
拗ねたように僕にかじりついたまま呟く拓斗の髪にキスして。
「また作るよ。今度は君のために」
「ほんと?」
「うん」
「じゃ、約束!」
キスの捺印。拓斗の唇は柔らかくて、張りがあって、敏感。チュッとそれが押し当てられた途端、歓喜の渦の中に巻き込まれてしまう。
仕事の終わりにもう一度拓斗に仲直りを頼んでみたときも、熱い口づけを返事にくれた。
このまま拓斗が僕の部屋に居着いてくれるなら、どんなにか幸福だろう。
「拓斗」
いま僕に許されている求愛行為はキスだけだったけれど。それをフルに利用して、おやすみを言う拓斗にキスの雨を降らせながら話しかけた。拓斗の表情が優しかったので言ってみる勇気が出たのだ。
「ん……? ちょっと、くすぐったいよ、龍樹さん……」
「今度の定休日、買い物に付き合ってくれないか?」
「……いいけど……? 何買うの?」
「ベッド……、買い換えようかと思って」
「ベッド?」
「ダブルに……したいんだ」
今使っているのは自分一人用のセミダブル。アメリカンサイズだが、身長一九〇センチの僕と一七八センチの拓斗が寝ると、やはり狭い。抱き合って、セックスする分には事足りるが、二人が手足を伸ばして眠ろうとすると、どちらかが転げ落ちる可能性は大きい。
「ダブル……って……。俺がいるせい? 龍樹さん窮屈?」
「窮屈って訳じゃ……。これから暖かくなると……広い方が楽かなって……。狭いのを理由に君が僕と寝てくれなくなっても困るし……。だめ……?」
拓斗の顔を覗き込んだ。
僕を見上げる瞳は複雑な色を浮かべていた。
「だめじゃない……。俺だって、身体伸ばしたいとき……あるし……。俺、ここにいていいの? ほんとにいいの? 龍樹さんに我慢ばっかりさせてるのに……」
「そう……思ったら、たまには僕のこと……考えて。僕が……爆発する前にね。まだ……だめかな……?」
今日の拓斗は以前のように僕に優しい。思わず禁忌の場所に手を伸ばしていた。ディープに彼の唇を貪りながら。
拓斗の応え方は僕を受け入れてくれそうな熱さで……。止まれなくなりそうな深い深いキスを返してきた。高ぶりを感じ合うほどきつく抱き合った。
なのに……。
「は……っっ、だめっ」
断固とした力で、パジャマのズボンを剥ごうとした手を振り払われた。
「だめ……。だめだ。キ、キスはいいけど……するのは……」
ああ、まだ君はお父さんが見えるの?
「……僕のこと……好き?」
お預けに耐えるためのよりどころが欲しかった。
「龍樹さん……」
困ったように呼びかける拓斗を見据えた。
少しだけ。少しだけでいい、僕に救いを。お願いだから……。
「ねえ、好き?」
カァッと頬を燃やし、申し訳なさそうに視線を逸らして。それでも言ってくれた。
「す……好き……」
僕はめいっぱい嬉しそうに微笑んで見せた。
「なら、いい。…………おやすみ」
うん、僕は待つって決めてたんだから……。
気力で猛る己を宥めながら拓斗を抱き締めて眠る体勢を取った。
「おやすみなさい……」
すまなそうな、辛そうな拓斗の声。
躊躇いがちに僕の腰に回された手をつかみ取り、しっかり僕を抱くように誘導した。
君が自然に僕を受け入れてくれるまで待つから……。
拓斗の吐息を胸で感じながら、愛しさを乗せて彼の髪を撫でた。
待てるのか? なんて言う心の声には耳を塞いで。
「龍樹さん……?」
眠りに導入しかけた頃。拓斗がもう一度僕に呼びかけた。そのまま胸に熱い吐息がかかって。欲望の残り火がまた力を盛り返しそうになる。
「何……?」
努めて平静な声を出して、拓斗のまろやかな声に耳を澄ませた。
「……考えたんだけど……俺達……友達に戻れないかな……」
「え……?」
僕は自分の耳を疑った。しかし凍りついた僕自身は無意識下で拓斗の言葉をとらえていて。
愕然とする台詞。
僕は思わず拓斗の上に覆い被さるように半身を起こしていた。
拓斗の瞳は奥底まで見通せるように澄んでいて、覗き込んだ情けない僕を映しだしてはいたけれど、何も語ってはくれなかった。
冗談ではないらしい。からかっているようでも、意地悪でもない。
拓斗の真意が分からない。それは僕を切り捨てようとして向けられた台詞としか思えなくて。
何か言い返さなくては、拓斗を引き留めることの出来る台詞を何か……。
そう心の中で焦っているのに、実際に僕に出来たことは拓斗の上にポロポロと涙を落とすことだけだった。
慌てたように拓斗の細い指先が僕の涙を拭った。
「あ、あ……。ごめん……、出来るわけ……ないよね」
「……どういうつもりで君は……!」
声が震えてしまう。
「龍樹さんに我慢ばっかさせて……悪いなって思ってて…………。でも俺、龍樹さんと一緒にいたいから……友達って言う方が気楽かなって……。ごめん、軽率だった!」
「と、友達はこんな風に寝ないよ」
「うん……そうだね……」
そう言って浮かべた微笑みはまたやるせないもので。一体拓斗が何を考えているのか、今の僕には全く分からない。
愛してるって言ってくれたのに。
「拓斗……」
「うん?」
「君は僕の恋人だ。もう、それは変えられない。……僕を裏切らないで……。そんな事されたら僕は……どうなるか分からない」
さもなくば僕をすっぱり捨てて……!
口にする勇気もなく胸の内で叫んでいた。ホッとしたように微笑まれて本当に捨てられたりしたら……立ち直れないもの。
「うん…………」
弱々しい返事を添えた彼の腕に微かに力が込められた。
あんな風に言った後で、それは優しく抱き締めてくれる君。
ねえ拓斗……君の気持ちは……同情なの?
君に愛されたいと思うのは贅沢?
僕が泣いたから別れを言えない?
君が愛してくれるなら僕は何でもするよ。いくらだって涙を流す。君の下僕になってもいい。
でも、一度知ってしまった幸せを取り上げないで。辛くなるから……。
いつの間にか眠りに落ちていた僕は、朝方まで彼を抱き締めたまま離さなかったらしい。
拓斗は身じろぎもせず僕の腕の中で眠っていた。けして安らかにとは行かない無理な体勢は、身体の節々に痛みを残し、そのせいか、カーテンを閉めて眠るようになってから初めて日の出と共に目覚めてしまった。
一人で夜を過ごしていた頃は、当然のように明け方には起き出して、鍛錬していたのだっけ……。
それを思い出して。
そう言えば、この一週間怠っている。身体がなまってしまうではないか。
つまりは拓斗が賞賛してくれた彼の言うところのギリシャ彫刻のような身体を崩してしまうということで。
今なら拓斗は眠っている。
僕が戻ってくるまでここに居てくれよ。
そっと拓斗を解放するとベッドからおりた。
気配を殺して部屋を出ようとして。
「どこ行くの?」
拓斗の声に捕まった。
ベッドから半身を起こし、眉をひそめて僕を見つめていた。
「起こしちゃった? 目が覚めちゃったついでに……ちょっと運動、してこようかと思って……」
「俺も行く」
さっさと起き出してきて、持ち込んでいた身の回りの荷物からウインドブレーカーを取り出した。
「俺、毎朝走ってたんだ。この一週間サボっちゃったけど。腹筋背筋各五十含めた柔軟と千メートル走と百メートルダッシュを一セットにして毎日三セットずつが部活の頃のメニューでさ。引退してからは時々手抜きするけど、最低一セットは必ずやってたんだ」
言いながら着替え続け、身支度をすっかり整えて、僕を覗き込んだ。
「龍樹さんのメニューは?」
慌てて僕もトレーニングウエアを取り出し、着替えた。
「走るのは同じなんだけど、後は違うな。僕は二キロ走って、後はジム。前は近くのに通ってたんだけど、時間が自由にならないからガレージに揃えた」
「ガレージに? あったっけ?」
「百聞は一見にしかず。案内しよう」
拓斗をガレージに連れていった。コルベットの横を通り過ぎ、小さなドアを開けて。
「すげ……」
中を見た第一声がそれだった。
「トレーニングジムそのものじゃないか」
「というほど、そろってないけどね。まあ、僕一人なら十分だし」
君が欲しくてたまらなくなったとき、身体を疲れさせるために夜中使えるジムが必要だったんだよ。本当はね。
……内緒だけど。
「これで走るの?」
拓斗が手を添えたのはランニングマシンだった。
「うん。速度と距離を設定してカロリー計算もしてくれる。モニターをつけて走れば脈拍なども監視できるから……。あ、でも、君が外を走るなら僕も……」
「龍樹さんもサーキット・トレーニングでいいの?」
「一キロと一〇〇メートルの三セット? いいよ。やってみよう」
「待って、今日は俺が龍樹さんと同じにしてみる」
「じゃ、二キロは外を走って、後は帰ってきてにしよう」
「うん」
国道に面しているガレージ側から外に出た。自然に目を見交わしスタートの合図。二人で駆け出した。
「龍樹さんのペースだと、俺のハイペース……だな……」
「ペースダウンする?」
「いや、いいよ。大丈夫。二キロなら軽い」
そのまま彼は息を整え最後まで僕に付いてきて。一通りのメニューを余裕でこなした。
荒い息が僕をそそる。
「さすが運動選手だね」
思ったことをなにげに口にしたら、拓斗がはにかんだ笑みを浮かべた。それは僕を動揺させ、舞い上がらせるには十分な威力を持っている。
「お預けが解けたら安心してめいっぱい出来る」
思わず囁いていた。拓斗が頬を赤らめる表情を楽しみたくて。
確かに彼は真っ赤になって。でも怖いことを呟いた。
「そんなん、俺死んじゃう。……一生お預けにしとこ」
「た、拓斗くうん」
抱きついて彼の瞳を覗き込んだ。
瞳の微笑みを探して、冗談だって確認したかった。
実際彼の瞳には笑みが浮かんでいたので、僕はホッとしたんだ。冗談じゃないなんて言われたら、今度こそ僕は彼を犯してしまったかもしれない。
僕を振り回す彼の気まぐれな態度に僕の我慢の閾値はゲージを下げっぱなしだったから。
結局言葉では冗談とも本気とも言ってくれなかったけれど。
「愛してる。待ってるから……。早くお預け解いてくれよね」
彼の笑みに満足する事にして、キスを盗み取ってジムから出た。
「朝食にしよう」
シャワーを浴びて身体を解し、朝食の用意に取りかかった。
この日は手早くできる和朝食。
かなり手抜きだったけれど、合格点はもらえたみたいだった。
拓斗は味噌汁とご飯を二杯ずつおかわりしてから、日課のようになった両親との対話をしに自宅へ戻っていった。
遺品などを整理しながら、考えを巡らせるらしい。
やっとの事で聞き出したその日課を僕は心の中で歓迎していた。
そうした対話を続けることで、拓斗の中で家族の死は少しずつ受け入れることの出来る事実となっていく。
僕との関係に対しても整理が付くだろう。そうしたら…………。
僕の前には幸せに続く道が延びている筈。拓斗が出す筈のゴーサインを待って、お預けに耐えるのだ。
しかし、そんな僕の期待を裏切るかのように、拓斗は閉店時間になっても現れなかった。どんなときでも必ず夕食は僕の店で取っていたのに……。
もちろん、拓斗にだって色々な付き合いがある。必ず僕の所に食べに来ると約束が出来ているわけじゃない。
拓斗の中で、日常が戻りつつあるのだろうか。それは歓迎すべき事で。
「あ……でも、そしたら僕のベッドに入ってこないかも……」
独り言と一緒に大きな溜め息が口をついて出た。
「十回目!」
声がして、まだ客がいたのを思いだした。
作り笑いをしかけて、友人の紫関相手に馬鹿馬鹿しいと思い止めた。
「何が十回目?」
「溜め息。何だ、また何か悩んでるのか? あの坊やとは上手くいったんだろう?」
ニヤつく紫関は、煙草の灰を落としながら言った。
「上手く……いったと思ったんだけどね」
店を見回し、紫関だけなのを確認してから答えた。
「十一回目の溜め息! ……ベタベタしすぎて嫌われたか?」
「っ……」
僕の目つきが露骨に怒りに燃えていたらしく、射すくめられたように紫関は首を縮めた。
「あ、わりい」
「……いや……、そうかもしれない」
拓斗は、確かにうっとうしく思っていたかも。
逃したくないばかりにしがみつくような真似ばかりしてしまった気がする。
「僕は……。こんな風に誰かを必要に思うなんて初めてで……。自分の気持ちを伝えるのに精一杯で、拓斗の気持ち……思いやること出来なかったのかな……。お前に言われるまで気づかなかった」
「あの子は……。お前の気持ちは重すぎるって言ってた。重すぎて、逃げ出したんだって。だけど、受け止めることにしたんだろ? 逃げずにさ。氷は溶けるの待たなきゃ。急激に溶かそうとするとひび割れちまうんだぜ」
「うん……」
友人というのは得がたい宝だと思う。
「少し……。考えてみる。……冷静に……」
「まあ……。店続けたかったら、そうしてくれ。今日のコーヒー、メチャ不味いぞ」
「うっ、そ、そうか?」
「この程度ならその辺でいくらでも飲める。仕事に出ちまうような恋愛はするなよ」
「……はい……」
シュンとなってしまう指摘だ。
これは言うなればプロとして失格だという事で。
「あ、あ、そんなに落ち込むなよぉ!」
「うん、大丈夫。話し合ってみるから……。……それでもだめなら……そんときは愚痴らせて」
「愚痴を聞かないですむこと、祈ってるよ」
紫関は絶対聞きたくないと顔に浮かべて出て行った。
男同士の恋愛の愚痴なんて、聞きたくないって事か……。
紫関のカップをかたずけ、ドアにCLOSEDの札をかけて。店の照明を落としたところで電話が鳴った。
「はい、『El Loco』です」
「あ、龍樹さん? 俺、拓斗です。あの、…………俺、……俺……今夜から家に帰ることにしたから……その、買い物も……しなくていいと思う。もう……龍樹さんとこに……行けなくなっちゃったんだ。ごめん……ごめん!」
「あ、あの、拓斗君? 拓斗? 拓斗>」
一方的に電話は切れた。
僕は呆然と受話器を見つめていた。電話の内容が頭にしみ込んでくるほどに僕の膝から力が抜けていく。カウンター席によろけるように座り込んだ。
「最後……通牒……か……?」
いや。僕は納得しない。こんなのは絶対納得できない。
僕は折り返しの電話をかけた。よっぽどの事がない限り彼に電話をしたことはないが、いつだって声がききたくてプッシュしては受話器を置くということが何度もあり、番号は指が空で覚えているほど。
「はい……向坂です」
「あ、拓斗君? よく……分からないんだ。あの……君の電話……」
僕の声を聞いた途端にハッと息を呑み、沈黙した。小さく溜め息をついて。
「……恋人だって思わないで欲しいってこと……だよ。ごめん!」
ガチャンと切られた。
「あ……」
そのまま僕の方で受話器を置かなければ繋がっていられた。なのに僕は動転してもう一度かけ直そうと受話器を置いてしまった。
今度は話し中の発信音だけ。何度かけ直しても話し中。
もちろんあり得ないと思い、電話故障サービスへかけた。
『受話器が外れています。信号音を送りますので、一分後にお掛け直し下さい』
僕は受話器を叩き付けた。
一分後だって出やしない。わざと外された受話器は、僕からの折り返し電話を阻止するためのもの。
「どうしちゃったんだよ……拓斗……拓斗……たくとぉ…………」
僕は泣いた。誰もいないのをいいことに。
涙にはストレス物質が含まれているという。涙を出せるだけ出してストレスを落とし、気分を切り替えて攻めに転じてやる。
「僕を納得させられるもんなら、させてみろってんだ」
その夜は久しぶりにバーボンに手を出した。
酔って、酔いまくって。また泣いた。
「拓斗ぉ。愛してるんだよぉ……」
呟きながら酒をあおって。
気が付いたら向坂邸の前にいた。
呼び鈴を鳴らしまくった。
インターホンの声はもちろん拓斗……。
ところが、僕だと判ると直ぐ切ってしまった。
僕は諦めきれずに門を飛び越え玄関の扉を叩いた。
いつもの僕なら出来なかったことだが、酒の力というのは気を大きくさせるらしい。
「拓斗! 拓斗ぉ! そこにいるんだろ? ここ、開けてくれ」
周りの家々の窓に灯が点る。
「龍樹さん! 止めてくれよ! 近所迷惑だよ」
僕は気にしなかった。がんがんとドアを叩き続けた。
「拓斗! ねえ! どういうことかちゃんと説明して! あんな電話じゃ納得できない。絶対に納得できないよっ」
「龍樹さん……飲んでるの?」
大きな溜め息が聞こえた。
「だめなんだ。俺、もうだめなんだよ。龍樹さんとつき合えない。俺にはもう……。お願いだから俺を苦しめないで……!」
ドア越しに叫ばれた最後の言葉に僕は硬直した。
「苦しめる……?」
僕は君を苦しめているのか?
「……君を愛してるだけなのに……」
「俺には愛される資格、無いんだ。ほんとに……。龍樹さんには迷惑ばっかかけたけど……俺……、俺……」
すすり泣くような声……。いや、拓斗は泣いていた。僕が泣かせてしまった……?
酒の勢いはすっかり消えてしまっていた。
「拓斗……、拓斗……。ごめん……。君を泣かせるつもりはなかったんだ……すまない……」
くぐもった嗚咽だけの返事に耳を澄ませ、僕は向坂邸から立ち去った。
僕は……振られたんだ。本格的に。
そうなって見れば、以前から思っていた殺意など全然湧かないことに気づいた。
拓斗を苦しめる事なんて出来ない。ふられたって、愛することは止められないんだ。僕が拓斗を思い続けるのも勝手。拓斗が僕の想いを拒絶するのも勝手。
誰にも取られたくないけれど、逃げ出そうとする者をとらえておくことなど僕には出来そうもない。
道々考えた。
愛される資格って……何だろう……。
僕は今だって愛してる。拓斗が欲しくて、失いたくなくて……。それを一方的に拒絶しているのは拓斗なのに……。僕には拓斗に愛される資格がないと言われるのなら、悲しいけれど納得がいく。なのに……彼は自分に資格がないと言っていた。
「それを決めるのは君じゃない……。僕だよ」
呟いても拓斗に聞こえるわけはないけれど。
シャワーを浴びていても、ベッドに入っても、拓斗のすすり泣きの声が耳について離れない。
何故? 何故? 何故?
考え込んだまま僕は眠りに入ったらしい。
最低最悪の気分での久々の独り寝は、最低最悪の朝を迎えるプレリュードだった。
つい二人分作ってしまった朝食が、手つかずのまま冷めていく。
おはようのキスも、美味しいと嬉しそうに笑う恋人もなくしてしまったんだと改めて僕に分からせた静かなダイニング。
たったの一週間。僕を舞い上がらせておいて、どん底まで蹴落としてくれた拓斗。
それなのに憎しみは湧いてこない。
情けないことに、どんなに踏みつけにされたとしても、僕は拓斗に逆らえないほど惚れてしまっていたのだ。
気が向いたときだけ僕にくれる笑顔を、辛抱強く待つ。しっぽを振って。抱き締めてもらえるのを待っていた。
「犬……だな……僕って……。店……開けなきゃ」
僕はまだ立ち上がれる。
自分がこんなにしつこい男だなんて知らなかった。
もう一度……彼が戻ってきてくれるのを待つためにも……美味しいコーヒーを煎れ続けなければ……。
それから毎日電話の前でためらっていた。あれだけ迷惑がられたのに、声だけでも聞きたくて。そのくせ、また嫌がられたらと思うと怖くて頭に貼り付いてる彼のナンバーをプッシュすることもできない。
一目姿を見たくて何度も向坂邸の前に立った。仕事に出してはいけないと思い、時間帯が限られていたせいか、愛しい人には逢えなくて。店を開けている間中その姿が入ってくるのを待っていた。
会いたい、会いたい……。どうかなってしまいそうだ!
相変わらず朝食を二人前作ってしまう。冷めていく皿を見る度に気が狂いそうになる。
ふいに頭の中で女の叫びが響いた。
『会いたかったの。迷惑かける気なんて……!』
必死な声で言ったのは……。
「あの娘もあの時……こんな気持ちだったんだろうか……」
拒絶されたからって諦められるものじゃない。
女性に興味ないからと断ったあの娘……。
僕がゲイだって告白しても毎日僕の顔を見に来ていた。
「……僕は……拓斗みたいに優しくないから……」
呟きは虚しさを増強するだけだった。
拓斗と買い物に行くはずだった定休日。
朝から天気が良く、デート日和。デートだけじゃなく、一方的に交際自体をキャンセルされた僕は頭の中に暗雲を抱えていた。
どんより気分な上、手持ちぶさたなので庭木の手入れでもして気を変えようと外に出た。ここのところ他のことにかまけていたせいで、少し荒れてしまっていたから。
正午近くに郵便配達夫が何かを投げ込んでいった。ゴトリという音が、奥で庭仕事をしていた僕の耳まで届いたのだ。
「なんだ……? これ……」
柚木美香という差出人名でポストに投げ込まれていた物は、ビデオテープだった。添えられたメモ程度の手紙には一人で楽しめと書いてある。知らない名前だった。
「ゆずき……みか……?」
音にしてみて、判った。
ミカ・ユズキ!
それは……忘れたくても忘れられないあの娘の名前。
アメリカで、本格的に医者を辞めたくなった原因。
『あなたに……愛されたかった。さようなら、私を忘れないでね』
涙でぐしゃぐしゃになった顔で微笑んだまま、ゆっくりと腰掛けていた窓から落ちていった。五階の窓から。
ドブッと鈍い音の後、五階の看護婦の悲鳴を追うように地階で叫び声。
『おまえのせいじゃない』
口々に僕に囁かれる台詞。
僕は彼女の怪我を治した。だが、心を治すことが出来なかったどころか、こわしてしまったのだ。
「何で……今頃?」
大変不愉快な気分だったが、中を見てみることにしてデッキにセットした。
家庭用のカメラで録画したらしい滅茶苦茶な構図の室内の画面。打ちっ放しのグレーの壁に、モノトーンのテーブルと椅子は無機的な冷たさだけを押し出している。
カメラを固定したのか、画面がベッドを撮したまま静止した。音声が低めだったのでボリュームを上げた。
途端に男のよがり声が部屋中に響いて、僕は慌てて音を低めた。
「エロテープ……か? 何でこんな物……」
今の僕には刺激が強すぎる。
スイッチを切ろうとして画面に目を遣り僕は硬直した。
「拓斗……?」
まさか……。
モノトーンの中唯一派手な色合いの寝具の中で細身の男が四つん這いで顔を伏せ、腰だけを高く掲げて後ろから男を受け入れていた。激しく責められるリズムに合わせ、腰をくねらせ、身体を仰け反らせながらよがり声をあげ……。固定された画面の中で、仰け反らせた拍子に横顔が振り上げられた。
これ以上無いほど色っぽい口元が震えて。それは僕のよく知っている……憧れてやまなかった横顔。
何かの間違いであると我が目を疑っていた僕は、間違いようの無い解像度でそれが拓斗であると確認してしまった。
そして、拓斗を責めているのは……藍本。
ふと痛みを感じ、自分の手を見て……。リモコンを握りつぶしていたのを知った。細かなプラスチックの欠片が刺さって出血している。
役立たずになったリモコンを床にかなぐり捨てて、テレビにかじりついた。
「拓斗……! 拓斗ぉぉぉっ!!」
画面に向かって絶叫している自分を、切り離された自分が見つめている。
僕は……狂ってしまったのだろうか。
フッフッという藍本の息づかい。肉の擦れるグチュグチュという音。拓斗の声……。拓斗の……。
『はぁっ、たつ……っんんっあんっああああっ』
泣き叫ぶようなその声が、僕を狂わせる。
「や……やめろぉぉぉぉっ」
テープがいつ終わったのか、どんな結末になっているのか、僕は知らない。
気が付いたときにはモニターは粉々になっていた。僕の中の獣が、力任せの手刀で破壊してしまったから。ショートした時の電気特有の焼けこげの匂いが蔓延する中で、僕はぼんやり座り込んでいた。
時間の経過は部屋の暗さが教えてくれた。
首を巡らして、デジタル時計に目を遣った。それは光を失っていて、ショートしたせいでブレーカーが落ちてしまったのだと知った。
ブレーカーを戻し明るくした部屋で、僕の激情の残骸を目にして。新たな喪失感が僕を襲った。
拓斗は来ない……。もう二度と……。僕は捨てられたんだ。
他の男とはあんなに熱く身体を合わせるくせに……。僕とはキスだけなんて。
「そんなにあいつがいいのか?」
跪いて点滅するビデオデッキの液晶を見つめた。
僕を狂わせたテープはまだこの中で無事でいる。
それすらも腹立たしく、ビデオデッキをつかみ取り、壁に向かって投げつけた。
デッキはがしゃっと鈍い音を立てて壁にぶつかると、ゴトッと床に落ちた。
耳障りな音だった。
しかし、もっと耳障りなのは……。
拓斗のよがり声を、こんなに不愉快な気分で聞くことがあるなんて。考えもしなかった。
悔しくて。悔しくて。それが僕がさせた声でないというだけで、それはそれは不愉快で。
頭に響く声を打ち消そうにも、どうにも手の届かないところに刷り込まれているらしく。
耳鳴りのように響くそれをやり過ごそうと座り込んでいるうちに、奇妙なことに気づいた。
差出人が柚木美香だったこともだが……。拓斗の呟き。あえぎに混ざって聞こえていたものは……。
「藍本は、なんて名だった?」
部屋を飛び出し、店と自宅を繋ぐ玄関ホール横の小部屋に飛び込んだ。オフィス代わりに使っている部屋で、経理用のコンピューターと、税務書類などを入れておく棚が壁を占めている。
名刺入れを探した。習性というか、僕は誰からもらった名刺でもきちんとリストアップして整理しておかないと気が済まないのだ。たとえそれがどんなに気に入らない、仕事の利害関係もない相手でも。それが役に立った。
顧客とは関係ないファイルを探す。
「あったぁ!」
藍本の名刺は、きちんとア行に収まっていた。
MS社の社員用で、自宅住所は載っていないが、名前が知りたいだけなので問題はない。
「藍本……雄一郎。ゆういちろう?」
後はもう一度ビデオを確認しなければならない。音声だけでいい。美しく、大好きな筈の拓斗の艶やかな姿だが、あのビデオに限っては、許し難い代物で……。
僕は燻った臭いの立ちこめたままの部屋にとってかえし、先ほど壁に叩きつけたデッキを拾い上げた。
テープが壊れていないことにホッとし、ヒステリーを起こすのはよそうと自分を戒めた。
「うるせー! 今何時だと思ってんだ!」
よその部屋から怒鳴られながらも、ガンガンとドアをたたき続ける。
「紫関! 紫関! 頼む、開けてくれ!」
安普請のアパートの、すりガラス一枚填め込んだ木製ドアが嫌々開くまで、僕は拳をぶつけ続けた。
「んだってんだよぉ? 畜生! ……龍樹……?」
目をこすりこすり現れた紫関の横をすり抜けるように中に入り込んだ。
「急ぐんだ。 ビデオ貸せ! ビデオ!」
「龍樹ぃ、どうしたんだよ? ビデオなんて、お前んちにだってあるだろが……」
勝手知ったるという感じで、紫関のビデオにテープをセットしながら答えた。
「こわしたんだ」
「え?」
「さっきたたき壊した。紫関、ヘッドホンくれ」
「ヘッドホン?」
「男同士のエロテープ、一緒に聞きたいか?」
「おとっ? 馬鹿野郎! 冗談じゃねぇ。今すぐテープ出せ! 俺様のビデオでそんな物見るなっ!」
つかみかかる紫関を引き倒して首根っこを押さえつけた。
「ひっ?」
「悪いけど、僕にとっては一大事なんだ。どうしてもこのテープの音声を聞かなきゃならない。ヘッドホン、貸してくれ」
紫関の小さな眼がまじまじと僕を見つめた。
僕の腕を振り払い、ゆっくり起き出して……。
溜め息をつきながら、オーディオのキャビネットからヘッドホンを出してきてくれた。
「お前がそこまで我が儘だとは思わなかった。あの坊やの前でもやってんの? 絶対振られるぜ。ほらよ」
投げて寄越したヘッドホンを直にビデオのジャックに差し込む。
「もう振られたよ。僕は納得してないけどね。だから……拓斗を取り戻すために、これを聞かなきゃいけないんだ。どうしても確認しなきゃいけない……」
「エロテープで何を……?」
言いかけて、紫関の顔が急に引き締まった。
「坊やが出てんのか?」
モニターのスイッチを入れようとした紫関の手を押さえた。
「つけたら殺す。本気だよ。僕はもう二度と見たくないんだ」
ヘッドホンをかぶった。
途中からグッと音量が低くなる部分がある。拓斗のよがり声が大きくなってから。本来なら送り主の目的から言っても、この部分で音量を低くするのはおかしい。
ボリュームを上げて耳を澄ませた。
拓斗は僕の腕の中でと同じように喘いでいる。
時折我に返ったように恥じらいを口にし、また悦びの声を上げ。僕の名を呼びながら口づけを求めて…………。
「たつ……き……さんっ……ああ……龍樹……さあああぁん」
僕の中でリフレインする甘い記憶がテープの声と重なった。
僕はヘッドホンをもぎり取ってテープを取り出した。気合いを入れてテープに拳をたたき込む。
「思った通りだ!」
「あ? おいっ! そんな事しちゃ……」
「このテープはもう要らない。残しておきたくもない。すまなかった、紫関。邪魔したな」
「おいっ! おいっ? 龍樹っ?」
追いかけてくる声に振り返った。
「本当に悪かった。向こう一ヶ月はコーヒー、タダにするから」
「……飯もつけろ」
「わかったぁ! 何でも注文して!」
駆け出した。
一刻も早く拓斗の所へ。たとえドアを蹴破ってでも拓斗を捕まえる。
どんな状況だったかは、あのテープだけでは分からない。だが、一つだけ。
拓斗は犯されたんだ。
合意の行為ではない。
後半よがってみせる拓斗の中で、彼を抱いているのは僕……。この僕なのだ。
心理的逃避なのか、何か薬物でも使われたのか……。それは分からないけれど。
拓斗は実際藍本に犯されている自分を忘れ、僕との行為に耽っているという認識の元にあれだけ甘く僕を呼び続けた。
拓斗……、君は……。
資格がないと泣いた君は……。
我に返った時、他の男を受け入れてしまっていた自分が許せなかったんだね。
「…………それでも僕は……」
愛してると呟きながら走った。
向坂家の門の前で。呼び鈴を鳴らしても無駄だと考えた僕はそっと塀を飛び越えてサンルームの方に向かった。
昼間と同じに仏間まで見通せる。中の照明が点いているせいで、夜目にも僕の位置からは全てが明るく見通せていた。
拓斗は仏壇の前で横たわっていた。
いや、横たわっているのではない。肘でにじる様に何かから逃れようと後ずさって……。
口元が動いて何か言っているのが分かった。
「いや……だ……?」
拓斗の目線の向こうは丁度障子で見えなくて……。
だが、やがて後ずさった彼の上に覆い被さってきたもので、状況が把握できた。
と、同時に僕は正拳をガラス戸に向けた。寸止めでも気合いを入れれば衝撃波で砕くことが出来る。きらめきながら降り続けるガラスの雨をくぐって飛び込んでいた。
「拓斗ぉ!」
彼の上に乗ったまま、仰天した顔で僕を見ていた藍本を体当たりで突き飛ばした。
藍本の手から注射器が飛んで畳に刺さった。
「拓斗、拓斗! 大丈夫? 怪我無い?」
驚愕の表情のまま僕を見つめる彼に手を差しのべたのだが。
奴は思ったより素早い動きで身を起こし、歯をむき出して僕に飛びかかってきた。
僕は咄嗟に反応して。
半歩退いて身体を斜に向けてやればそれはよけられる。僕にとっては条件反射に過ぎない動きだった。
実を言えば飛びかかってきたというのもよけてから気がついた始末で。藍本は自分の勢いでそのまま壁に激突した。
「……んの野郎っ」
いつもの丁寧な口調がすっかり消えていた。もう一度飛びかかってきた奴を避けながら襟を掴んで捕まえた。
畳に叩き付け、今度は僕が跨った。
「ざけんなよっ」
ヒッというような喉奥での悲鳴を聞いたような気がするが、僕は拳を奴にぶち込むことしか考えていなかった。
こいつが拓斗を…………!
悔しさと怒りでどうかなっていたとしか思えない。有段者である僕の拳は、素手でも凶器として認定されてしまうのだから。
それなのに。
奴の上に馬乗りになって、拳をぶつけ続けて。
とっくにぐったりしていたのを後ろから誰かに抱きつかれて初めて知った。
「龍樹さんっ!! それ以上殴ったら死んじゃう! 止めて!」
拓斗の声にカッとした。
(……っ、君はこんな奴を庇うのかっ? 僕よりもこいつがいいって?)
そんな叫びが僕の中で反響し続けて。
「た……つき……っっ!」
苦しげにもがく拓斗の声……?
「た、拓斗……?」
あわてて離した手の下で倒れた拓斗が咳き込んでいた。
無意識のうちに僕は拓斗の首に手をかけていたんだ。
自分のしてしまったことに驚きながら、彼を抱き起こして抱きしめた。拓斗の頬は殴られたらしく赤く腫れ上がっている。僕の指の痕は首にくっきりと浮かんでいて……。
ああ、なんてことを!
「すまない、拓斗、大丈夫か?」
「龍樹さ……ん……何で……?」
疑問符で瞳をいっぱいにしながら、僕の腕の中から抜け出そうともがく拓斗を解放して。口元に人差し指を持っていって彼に黙るように合図した。
「その前に」
拓斗にうとうとしていた薬を一滴出して、味と匂いで確認してから藍本の腕に静注した。
この際針先の滅菌なんか構っていられない。
それくらい僕は怒っていたのだ。
「あ……それ……」
「幻覚剤……だろう? 今日もこれうって君を抱こうとしたの? こいつ……」
「な……っっっ」
拓斗の頬がカアッと燃え上がった。
「資格ないって……こういうこと?」
のろのろと起きあがってこようとしている藍本の頸動脈に手刀を当てた。一定量の力で抑えれば、簡単に気を失わせることが出来る。こいつにはもう少しの間おとなしくして置いて貰いたいから。
「たっ……龍樹さんにはもう……関係ないよっ! そんなこと!」
そっぽを向いてうそぶくように言う拓斗を悲しい気分で見つめた。
「ビデオ……見たよ。おかげで僕の部屋はデッキとモニターの残骸が山になってる」
「えっ?」
「君とこいつのビデオ、送られてきた。こいつから……だと思う。だから、隠さずに教えて。君は僕よりもこいつを好きなの? それとも……」
驚きに目を見開いて僕を見つめていた顔が見る間に歪んだ。
拓斗は身体全体で嫌々をしながら泣き崩れた。僕が両腕を掴んでいたせいで、ぶる下がるように跪いて。嗚咽が漏れる口元を、首だけうなだれさせて隠してしまって……。
僕はたたみ込むように言いつのった。
「君が僕のこと嫌になって、もう絶対心が戻らないから別れようっていうなら……、キツイけどあきらめるように努力する。でも、それ以外の理由なら却下だ。僕は君をあきらめない。どこまでも追いかける。君がまた振り向いてくれるまで……」
「龍樹さん……」
泣き濡れた黒目がちの瞳が僕を見上げた。
「そうやって、俺を嬉しがらせといて、飽きたら捨てるんだろ?」
「え?」
「俺……嫌だから……。龍樹さんなしじゃ生きていけなくなってからポイ捨てされるの嫌だから……だから…………」
「どういうことだよ? 何で僕が……」
「龍樹さん、今までもそうやって恋愛してきたんだろ? する事して、飽きたら捨てるんだろ? ゲイって、自由恋愛が特権だって……。しがらみないから、簡単に乗り換えるんだろ? 俺、ゲイじゃない。そんな簡単に変われない。だから……俺の事ほっといてくれよ!」
「拓斗……?」
「龍樹さんは俺が逃げてるから欲しいだけなんだ。完全に手に入っちまえば、興味なくなるんじゃないの?」
「い……いくら何でも酷いよっ。ぼ……僕が何したっていうんだっ? どうしてそんな風に!」
「龍樹さんが俺に求めるのはセックスばっかだからだよっ!」
怒鳴ってしまってからしまったというように視線を逸らした。僕はそんな拓斗を見つめることしかできなかった。
「俺は……龍樹さんに小判鮫みたいに貼り付いてるしかなくって……。龍樹さんにしてあげられること……セックスの相手だけなんて、情けなさ過ぎる。そんなの、直ぐに飽きちゃうに決まってる!」
「君は……」
「俺は! ……龍樹さんが好きだ。恋人になれて嬉しかった。でも、気がついちゃったんだよ。親友ならずっと付き合っていけるのに。恋人は……飽きたら捨てられちゃう」
「捨てられる前に捨てれば傷が浅いってのか? 僕の気持ちは? 深みにはまって溺れてる僕の気持ちはどうなる? そんな風に思うなら、どうして僕を受け入れたりしたんだよっ。僕を苛めて、からかって……楽しい?」
どんどん惨めな怒りで一杯になっていく。
このとき初めて拓斗のことを憎らしいと思った。
「大の男が泣きながら君に縋る姿……見てて面白かった?」
眼に怯えを走らせた拓斗を組み敷いた。
「僕がどんな思いでいたか君は分かってないっ。身体だけなら……セックスだけなら……ほら、こんなに簡単だ」
拓斗の甘い匂いに埋もれるように彼の服を引き裂き、うなじに、鎖骨に、胸に……貪り付いた。
「特別だからっ、愛してるから……大切にしたかったのに…………っ、……っっくしょう!」
彼の足を無理矢理割り開き、身体をねじ込んだ。前戯無しで、一度は受け入れてくれた禁断の秘部に僕をあてがい……。
全く抵抗しない拓斗に気づいた。
抵抗どころか、固まってしまったかのように動かない。そっと顔をのぞき見て、ギュッと目をつぶっているのを知った。
予想される痛みに耐えるための心の準備というところか……。
服を引き裂いたときに擦れた傷が赤く浮かび、出来立てのキスマークと混ざって大小の斑になっている。
拓斗を痛めつけてしまったという自覚だけで僕は萎えた。
だから、彼を抑えつけたまま、ただ見つめていた。やがてそっと見開かれるだろう瞳をとらえるために……。
「…………龍樹……さん?……」
疑問符を浮かべたまま僕を見つめる拓斗……。
初めて会ってから一年たってない。
まろやかな卵形の輪郭……手にしっくり填るだろうって、憧れてた。
告白して、好きになって貰って、愛してるって言って貰って……。恋人になれてまだ一週間なのに。僕を拓斗無しじゃいられないように虜にしておいて今更捨てようとしてる。それも捨てられたくないからって……。
誰に吹き込まれたのか、ゲイに対する偏見に裏打ちされて。僕のことを見ないで、誰かの言葉を拓斗は信じたんだ。
「僕はゲイだ……。たしかに。君はそうじゃないのに、僕を助けるつもりで関係を結んだというのも分かってる……。それでも……愛してるんだ。……僕を捨てないで……。君無しじゃいられない……。痛いことなんて、しないから。君を傷つけたりしないようにするから……。だから……!」
この期に及んで縋り付くような台詞……。でも、言うしかなかった。プライドなんて欠片だって持てない。拓斗を失いたくない。ただそれだけ。
拓斗は僕の情けない台詞を聞きながら、瞳を潤ませて頭を振り続けた。
「うああああああっ」
やがて咆哮が漏れて。
「ごめんなさい、ごめんなさぁいぃぃ」
手放しで僕の下で泣き叫んだ。
「じ、自分のことしか考えらんなかった! 俺、俺……。こわかったっ! 龍樹……さんが甘えさせて……くれるの、俺の身体が気に……入ってるからで、飽きが来れ……ば直ぐ、他の奴が代わり……になるって……。あいつ、龍樹さんは俺があいつに……抱かれたの知ったら、もう、俺を許さないって……だから……」
嗚咽で途切れながら拓斗の口から飛び出す言葉。
僕が焼き餅焼きだから? 理屈も弁解も受け付けないと思われたのは心外だな。
「うん……許さないね」
拓斗が凍りついた。
堅く瞼を閉じて涙を切って。
「そ…………っか……やっぱ……」
虚脱感にとらわれたようにぐったりして溜め息混じりに呟いた。
拓斗のがっかりした顔を嬉しいと思えるなんて、僕はホントに自己本位だよね。
「君が僕のこと忘れて他の男とのセックスに没頭したりしたら……。僕はどうなっちゃうか分からない。今回みたいに薬使って犯されたなんてのでさえ、こんなに頭来てるのに……」
「え……?」
希望に目を輝かした拓斗はとっても素敵。失いたくない思いは僕と同じだ。
「自分のテープ、見てないの? 君はあいつとしてるときずっと僕の名を呼んでたんだよ。まるで、僕としてる時みたいに」
「あ…………」
「覚えてないんだろう? どんな風にしたか。……気がついたとき、肝冷やした?」
困惑に顔をしかめて、言いにくそうにぼそぼそと語った。
「う……。痛かったのは覚えてる……。けど、だんだん朦朧としてきて……」
彼の震える肩を抱きしめて、言葉を切らせた。細かく聞きたくない。僕よりも口にする拓斗の方が辛いはず。
「あいつの名前確認して、君の声、聞き直して。……僕は救われた。初めて見たときは逆上しちゃったよ。もう、こんな思いは嫌だ。だから……他の男なんて絶対寄せ付けないで……」
「うん…………」
「それにね、一番許し難いのは僕の気持ちを疑ったことだ。どうしてそう思ったんだよ?」
ピクッと拓斗の眉が寄った。甘えるように身を預けていたはずが、急に強張らせてしまって。
「龍樹さん巧すぎるから」
ボソッと言って顔を背けた。
「なに?」
判らないことを言う。
しかも聞き返した僕を怒ったように見据えてきた。
「通夜の日に来てた、あの人とも寝たんでしょ?」
!!!
「あ……き……清田のこと……?」
全てに合点が行った。僕等の内緒話を彼は……聞いていたんだ。
拓斗の様子がおかしくなったのは葬式以来だ。確かに。
「俺の前に……何人龍樹さんに抱かれた奴がいるの?」
拓斗の詰問口調に、僕の方が固まった。
「た……拓斗?」
「龍樹さんはその人達を愛したんじゃないのっ? 俺みたいに……」
「あ…………」
僕は言葉を失って頭を振ることしかできなかった。
「俺と、その人達と、何が違うの? 愛してるって俺に言わせて、ゲーム・オーバーじゃないの……?」
「っ……ゲームなんかじゃないっ! ゲームなんかじゃ」
気がつけば僕は泣いていた。
嫌いって言われて、ふられて泣いて。
でも今度が一番辛い。僕が何を言っても拓斗は信じてくれないんだ。もどかしくて、悔しくて。
自業自得という言葉が僕を嘲笑っている。
拓斗が問題にしてるのは僕の過去。
僕がキスや愛撫をする度に僕が過去に抱いた男達を思い浮かべるんだろう。
拓斗は違う。全然違うのに。
どうしたら分かって貰える? どうしたら!
「確かに……君に会うまでの僕は……恥ずかしいけど遊んでいた。君の言うとおり、何人も……付き合った。もう、僕なんか一生本気の恋愛なんて出来ないって思ってたから……」
やっぱりねという眼で拓斗が僕を見つめる。
「君に会うまで、だよっ。今は……君だけだ。君に一目惚れしてから直ぐにそういう付き合いは全部やめた。君が初めて店に来た……開店初日から……」
「そんな前? 何で……」
「意味ないからだ。君しか欲しくない」
信じて欲しいのに……。
「それとも……僕は……汚い? いろんな男と寝た男は不潔で触れない?」
「そんなこと言ってない。今の俺にそんなこと言える権利あると思う? ただ……」
「病気は持ってないよ。ちゃんと検査してる。定期的に」
「もうっ! そうじゃなくって! 言っただろ? 不安なんだ。あ……藍本が……べ……ベッドでの約束なんて、してないのも同じだって……。飽きちゃう前に何言っても、それは飽きてからは無効になるって……」
まだ君はあんな奴の言うことを信じるのか?
腹立たしさが僕を投げやりにさせた。
「じゃあ、僕が何言っても信じてもらえないわけだ……」
「信じたい、信じたいよっ! 初めて俺を抱いた後、龍樹さん、恋人だと思っていい? ってきいたよね。俺はそういう事するのって特別な相手だけだと思ってたのに……龍樹さんは違うんだって……。そん時はちょっと引っかかっただけだったけど……清田さんが……」
「あいつが何か言ったのか?」
恐れていたことが僕から拓斗を奪おうとしていたんだ。清田が拓斗に吹き込んだのは、過去の僕への告発……。
「龍樹さんは飽きっぽいから、本気になったら傷つくのは俺の方だって……」
……ったく、よりによって……!
「あンの野郎っ……! 言っとくけど、あいつとはずっと前に一晩つきあっただけだ。すっごく旨そうに包装されてる菓子が、滅茶苦茶不味かったって感じ、分かる? 二度と手に取りたくないくらいの」
拓斗がブッと吹いた。泣き笑いみたいに顔をくしゃくしゃにして。
「俺も……いつか清田さんみたいに振られちゃうんだって……怖くなった……。俺なんか、いいとこなしな奴だからって……」
バカなことを!
清田と拓斗が同じだなんてとんでもない。
「僕だって……怖かったんだ」
「え……?」
「……君が僕を受け入れたのは……ほだされたからだろう? 後悔しないって言いながら、本当は後悔したんだろう? 僕はそう思った。……君のあの態度で、自分に自信が持てるやつがいたら、僕はそいつに弟子入りするよ」
「ごめ……」
「君は忘れてる。僕が、君を抱く以前に一年近くも片思いしていたこと……。それも、君の近くで、いろんな君を見ていたことをね。確かに君の身体は魅力的だよ。大好きだ。でも、僕が欲しいのは君の全てだと言ったはずだよ。向坂拓斗という全存在を、僕だけのものにしておきたいんだ」
「……どうして俺なの? 俺自身が納得できないくらい、俺と龍樹さんじゃ不釣り合いだ」
「君は僕に一生一人で生きていけって言うの? 僕の中身は空洞なんだ。ぽっかり開いた穴は、君の形をしてる。君の笑顔が、君の持つ雰囲気が、僕を唯一安らがしてくれるものだから……。どんな事しても君を僕のものにしておきたい。そうでなきゃ、僕は生きていけない。よしんば生きていけたとしても砂漠で一人でいるみたいに乾いた人生だ。君がそのまま自然体で微笑んでいてくれれば、僕は……」
「俺はそんな特別なもんじゃないよ……」
「僕にとっては特別だ。他の誰も代われない。本当に、こんな気持ちになったのは初めてで……僕自身持て余してるくらいだ……」
「龍樹さ……ん……」
困惑げに僕の名を呟く拓斗に縋り付いた。
「君じゃなきゃだめなんだ。僕を……助けて……。僕を……愛して……」
そうやって縋るほど彼がほだされていくのが分かる。けれど、こんな風に縋って言葉を尽くしても、僕の気持ちを上手く伝えることが出来たという手応えは全くない。拓斗の揺れる瞳は相変わらず惑いを映していて僕を不安にさせる。
スッと持ち上げられた優美な拓斗の腕が僕の首に絡められ、僕の頭を温かい胸に抱き込んでくれたときでさえ僕は怯えていた。
拓斗の思いは、同情、哀れみなどで出来上がってしまっているのではないだろうか。縋ってくる惨めな犬を突き放しきれずに……。
拓斗は優しい。誰にでも優しいから……怖い。
「……君に……愛されたい……」
女々しいと笑わば笑え。甘えと、祈りと、切なさと……諸々の想いを込めての呟きだった。
僕の髪をゆっくりと梳くように、拓斗の手が頭を撫でている。何度も、優しく、慈しむように……。
耳から直に感じる拓斗の鼓動が、トクトクと僕に何かを囁きかけている。
その感触が僕の中で暖かいものを沸き立たせていく。
僕は……愛されている……?
「信じていい? まだ僕を好きでいてくれるって……」
「信じていい? まだ俺を好きでいてくれるって……」
ほとんど同時に飛び出したお互いの台詞に絶句し、見つめ合った。
どちらからともなく求め、口づけた。
「ごめん……変な焼き餅やいて……。俺、後悔してないよ。信じて。俺は……龍樹さんを失いたくない。だから……お……男……同士でもいいって……思って……。ホントはずっと欲しかった……、龍樹さんのこと、ずっと……」
吐息混じりにそっと囁かれた台詞と、僕の中心に這ってきた拓斗の手は僕を再び天国まで舞い上がらせた。
今すぐ愛し合いたかったのだが…………。
「待って、拓斗」
ギュッと抱き締めてから体を起こした。
「龍樹さんっ?」
取り縋るように拓斗が僕の服を掴んだので、出来るだけ優しくその手を外して。
「あいつ……。先に落とし前つけないと」
痛いほど動悸しているものを無理矢理しまい込んでから、まだぐったりしてる藍本を顎で差した。
「あ…………。ど、どうするの?」
瞳に恐怖の光が走った。心配そうに僕を見上げる拓斗の頬に軽く口づけて微笑みかけた。
「もちろん、僕の宝物に手を出しただけじゃなく、僕等を泣かせた罪は償って貰う。殺したりしないから安心して。それに……まだ確かめたいことがあるんだ」
藍本の顎を持ち上げた。
だらしなく涎を垂らしながら虚ろな瞳で有りもしないものを見つめている。
静注したせいで薬は速やかに効力を発していた。
「薬、効いてきたな。君はこのあいだも注射だったの?」
横に来て一緒に覗き込んだ拓斗は、首を横に振った。
「ううん。帰りの車で缶コーヒー飲んで……。気分悪くなったんだ。降ろされた所が変なホテルで……。俺……、あいつが俺にのっかってくるまでそういう事って気がつかなくって……。いきなり突っ込まれて……その……」
言いよどんで視線を逸らした拓斗をもう一度堅く抱き締めた。
「痛かった……?」
「あんなに痛いことだなんて知らなかった……。龍樹さんのの方がずっとインパクトあるのに、あんまり痛くなかったのって、優しくしてくれてたからなんだって分かった。龍樹さんのしてくれたこと思いだして、いつの間にか俺……。龍樹さんとしてるって錯覚してた。ば、バカだよね……」
甘えるように預けてくる体の重みと泣きそうな声で呟く言葉は、僕の中から嫉妬や拓斗に対する怒りを全て吸い取ってしまう。全ては藍本と薬のせいなのだから。
「そんなことない! これは……LSD25といって、きつい幻覚剤なんだ。薬のせいだったんだよ」
LSD25。分類は精神異常発動薬。開発過程で偶然生まれた合成麻薬で、通常は経口投与の薬である。効果発現までに一時間は見るもので。治療に使われることのない物だけに、薬と呼ぶには抵抗がある代物だ。アメリカではハッシッシなどと同じように扱われているが、天然物ではない。幻覚作用が強く、恍惚、または抑鬱状態を来す。もちろん、日本への持ち込みは違法だ。多分、出張の時にでも入手して密かに持ち込んだ物だろう。他の薬物に比べて習慣性がないことが唯一の救いだ。
「ごらん、藍本には僕等とは別のものが見え始めている」
拓斗は嫌悪感を露にしながら藍本の表情を見据えていた。
僕はもう一度藍本の耳に顔を近づけ囁いた。
「藍本、藍本雄一郎!」
「んあ………………」
「柚木美香とどういう関係だ?」
「あー、みかぁ? ああ、みかかぁ。うふ、うふふふふふ」
「何故美香のことを知っている?」
「ありゃいい女だったぁ。みかぁ、美香はぁ……桂川に殺されたんだよなぁ」
腕をギュッと掴まれた。拓斗がしがみついて僕を覗き込んでいた。
「殺してないよっ」
拓斗に言った言葉だったが、藍本が返事をした。
「んにゃ、殺したんだ……。美香の日記は桂川のことしか書いてなかった。桂川が声かけてくれた。桂川が心配してくれた。桂川は優しい! 桂川は紳士! 桂川は素敵! なのに……弄んで、捨てて……冷たくあしらいやがった。美香はぁ、いい女だったのに……窓から飛び降りちまった……」
「それと拓斗とどういう関係があるんだっ?」
ヒステリックに笑いながら僕の方に挑むように顔を近づけてきた。
「桂川が大事にしてるもんはみんな壊してやるんだ……。美香をあいつが壊したみたいに……、今度は俺が……」
確かに大当たりの所を突いてきた。憎たらしいほどに。僕を痛めつけるには効果的すぎる。
「君と彼女はどういう関係だ?」
「二度目の親父の……連れ子だ。……一度も妹だなんて思ったことないがね」
話の見えない拓斗のために説明した。
「柚木美香は……。僕の患者だった。ワシントン大学の留学生で。交通事故でかつぎ込まれたんだけど、同じ日本人てことで僕の担当になり、術後もずっと僕が担当してた。だからかもしれないが、彼女は僕に恋愛感情を持ったらしい。もちろん僕は相手にしなかったつもりだけど。しゃにむに僕を追ってきて、拒絶したら窓から飛び降りた……」
拓斗は眉をひそめて僕の瞳を覗き込んでいた。
「自殺……したの?」
「ああ……。僕の心に焼き付くためだって言ってね……」
柚木美香の最後の表情は本当に僕の目に焼き付いている。
涙でぐしゃぐしゃになりながら、窓から外に飛び出す瞬間にっこりと笑顔を見せた。
その時の目の色には狂的な光はなかった……。
だからこそ止めにはいるはずの足が出遅れたのだ。正気に返って思いとどまってくれたのかと瞬間思わせる、穏やかな顔だったから……。
美香の表情のフラッシュバックが僕にある可能性を思いつかせた。拓斗がされたこと、されようとしたことを考え合わせると……。
「藍本、お前……美香に何かしただろう?」
「何かした? 何を? 美香は俺の女だぞ。お前にどうこう言われる筋合いはない!」
「お前の女? 妹だろう?」
「妹じゃない! ……俺の女だ……俺のぉ!」
しくしくと泣き出した藍本を見ているうちに、事故で運ばれてきたときの所見を思い出した。
脾臓破裂、全身打撲、左大腿部骨折、頭部裂傷、そして外陰部付近の擦過傷。
ほとんどが事故の時の傷だが、動線の方向から矛盾した傷もあった。
「もしかして……自分の妹を暴行したのか?」
ただの推測だった。
「暴行じゃない! 俺のものにしただけだ!」
「合意じゃなかったら暴行だよっ! そ、その人が同じ気持ちじゃなかったら……」
拓斗は強姦とか、そういう行為には過敏だ。実際の被害者だからではない。意志に反した行為は、すべからく彼の不興を買う。
「事故の傷にしては変なところにも傷があった。小さなものだから二の次にしてたけど……。彼女は……その後車に飛び込んだんじゃないのか?」
「事故だ! ただの事故だ! お……俺が日本に帰った後だぞ。俺のせいじゃない!」
「運転手は急に飛び出してきたと主張していた。窓から飛び降りる瞬間だって、彼女は微笑んだんだよ」
そう、そうなんだ。僕は彼女の真意を誤解していたかもしれない。この、藍本と同じように。
「やっぱり僕は……医師失格だな……」
「龍樹さん……?」
「プライベートの感覚で彼女を邪険にするべきじゃなかった。治るまで医者として応えるべきだった」
狂的な熱情だと思えたあの目の色も、助けを求めているだけだったのかもしれない。
あの時は縋る者の気持ちなんて、分からなかったから……。女性に好かれるなんて迷惑なだけだと思って彼女を避けてしまった。
「彼女が僕に望んだのは獣にならない男だったんだろう。優しく扱ってくれる、安全牌……。何故だか分かるか? 藍本!」
「な……?」
「あの子にとってはお前は兄だったんだよ。保護者になるべき兄だったんだ。それがよりによって獣に変身した……。しかも獣の自分だけ見せて逃げ出した……。確か、両親は早くに亡くしたんだったな? あの子の信頼を裏切ったんだよ、お前は……。彼女を壊したのは……お前だ!」
「し……仕事が詰まってたんだ……だから……俺は……」
「仕事を言い訳には出来ないよっ。スケジュールがそうなら、最初からそんな酷いことしなきゃいいんだ。ほんとに好きなら……大切なら、ちゃんと時間かけて口説き落とすべきだ!」
拓斗の台詞をきいて、僕は彼を得るにあたって努力を払ったことに内心安堵の吐息を吐いていた。
藍本の姿は僕のもう一つの影だったから……。
藍本が泣き崩れた。何処まで話を理解しているかは分からない。薬の影響で暗示が強く効くからかもしれない。
「俺が……美香を……裏切った……俺が……壊し……た……俺が……」
よろよろと立ち上がった。そのまま僕が入ってきたところから出て行こうとした。その間ずっと同じ事を呟き続けていたようだ。
「あ……あの……。ねぇ、あの人怪我するよ。ガラスの破片、踏んでる……」
心配げに言う拓斗の口を唇で塞いだ。
「何であんな奴の心配するの? 君を……傷つけた奴なのに……」
「だって……」
「ったく……、君にはかなわない……」
僕は藍本の腕を引いて部屋に引き戻し、当て身を喰らわせた。
「電話、貸して」
僕は紫関をもう一度たたき起こした。
「……んだよぉ。龍樹?……いい加減にしろよぉ」
「ドラッグやってる男に拓斗が襲われたんだけど」
「んだって? それで犯人は? 坊やは怪我無いのか?」
「うん、大丈夫、捕まえた」
「……なら、所轄に突き出せよ」
「え? 僕が連れてくの?」
「警察をそこに呼んだら近所中が起きるぞ」
「あ、そか、確かに。ここで騒ぎになると困るな」
……だから紫関に電話してるのに……。
「俺は一課なの! そういうのは二課の仕事。いいから所轄でも交番でもつれていけよ」
「いや、だって、気絶してるんだ。朝まで待って」
「ばっかやろう! 何処まで我侭なんだよおまいはぁ! ……現状保存しとけよ。明日サイレン無しで行ってやる」
側の人間にまで届くほどの音響で怒鳴った後ガチャンと切られた。
呆れたように僕を見てる拓斗にごまかし笑いをする。
「所轄に電話すると、夜中に大騒ぎ。かといってあいつを担いで連行するのも嫌だ。サイレン無しで朝来て貰う」
「……それまでどうするの?」
「縛っておいとこうかな。あ、なるべくそのまんまにしておかなきゃね。寒いから雨戸だけは閉めよう」
頷いた拓斗が玄関に向かおうとした。ガラスの破片を避けて外から雨戸を閉めるつもりらしい。
僕が引き裂いた服のまま。慌てて僕のブルゾンを羽織らせた。
肩幅も丈も全てが拓斗には大きすぎる。それでも似合っていて可愛いなんて思ってしまうのは惚れた欲目?
軽やかな足取りで僕のブルゾンが駆け去った。
愛しさが盛り上がるほどに藍本への憎悪も増幅する。
あんなに可愛い拓斗を……あいつは……。
そう思った瞬間、奴への復讐を思い立った。殴るだけじゃ気がすまなくて。
奴が気を失っているあいだに奴の身体にちょっとした細工をした。道具がそろわないから仕上げは汚いが、あり合わせのカッターナイフと縫い針で、奴の神経を一部切断したのだ。
処置が終わったところで慌ただしい足音が背後に迫ってきた。
「……何処いじってるんだよっ?」
拓斗の低音の声は不機嫌な証拠。
「そんな奴のなんか、いじるなよっ」
僕が細工したのは奴のペニス。故に拓斗は……。
「……妬いてるの? もしかして……」
後始末をしながらの答えが嬉しげになってしまうのは赦して欲しい。焼き餅を焼かれるというのがこんなに幸福だなんて、思っても見なかった。
「バカ言うなよっ! ただ……俺は……」
沸騰寸前のような怒った声で言いながら僕の手元を覗き込んだ気配の後、声音が変わった。
「龍樹さん……それ……その小さい傷、何?」
「末端の神経切っといた。治癒するまでに三、四年かかる。その間は奴のものは使いものにならないだろうね。強姦なんかする様な奴は、勃たない方がいいんだよ」
言いながら勝手知ったるという感じでキッチンまで行き、手を洗った。カッターと針は新聞紙に包んで捨てた。拓斗のものだけど、新しいのを返すことにして。
「ひど……」
拓斗は僕に付いてきながらそう言った。けれど、口ほどにはそう思っていないらしく、声音にホッとした笑いが含まれている。
「だから言ったろう? 僕は医者に向いてないって」
「……丸ごと切断しちゃうよりましかな。俺、龍樹さんの剣幕から、そんなこと想像してた。殺さないから安心してって……」
「切断までしちゃったらモロ傷害にみえるじゃないか。奴の妹に免じて、神経だけにしとくんだ。……もし懲りずに君に手を出してきたら……そのときは……。ってのは、奴に言っとかなきゃね」
「俺……龍樹さんに恨み買わないようにしよう……」
「……怖い? 僕って……」
「怖くないって言ったら嘘になるかな。でも、もし俺がそこまでされちゃうとしたら、俺が悪いんだろうから……」
苦笑しながらそんなことを言われた日には、僕の理性なんてズタズタだ。拓斗をそっと引き寄せて抱きしめた。
「本当に君って……」
可愛い人だ……。
髪にキスしながら僕の中で溢れる愛しさを何とか伝えたくて腕に力を込めた。僕はもう、拓斗以外には目を向けることもできない。こんなに愛おしく思う人など、出会えないだろう。
一時の間、互いの温もりを楽しんでから、彼の肩を抱いて仏間に誘った。今こそその時だと思ったから。
「さて、と……。お線香あげさせて貰っていい?」
「へ? ……いいけど……」
「なんだかんだで僕はまだ、ちゃんとには君の家族に挨拶してないんだよね。だから……」
「龍樹……さん……」
僕はさっさと仏間に設えられた祭壇に並べられたお骨の前に座った。
線香をあげ、手を合わせて。
「ご挨拶が遅れて申し訳ありません。桂川ともうします。ご子息とのお付き合いを認めていただきたくこうして参りました。僕も彼も男……ですが。気持ちはあくまでも真剣なもので……、一生を共に過ごしていきたいと願っております。ご両親におかれましては拓斗君の行く末などさぞご心配でしょうが、これからは僕が……彼を支えていきたい。
皆さんの代わりに僕が彼の家族になることを……どうかお許し下さい」
「龍樹さん!」
肩を揺さぶられた。
目を開けて拓斗を見たら彼はボロボロに泣いていて。
「もうっ! いきなりなに言い出すんだよっ?」
拓斗の怒った声に、また僕は先走ってしまったのを知った。足下が崩れ落ちるような不安を覚えた。
「い……いけなかった? 君は……僕が君の家族になること……嫌……?」
「ば……か……! そういうのって、まず俺に言ってからじゃない? そんな、プロポーズみたいな事……」
「あ……そ、そか。そうだよね」
拓斗の方を向いて正座し直した。大きく息を吸って、吐いて。
「君が好きです。一生を共にしたいって思うくらい、愛してます。君と一緒に幸せになりたい。法律では……出来ないことだけど、結婚……して下さい!」
畳に頭を擦り付ける様に土下座。
自然にやっていた。
卑屈な気分ではない。僕にとってはそうまでしてでも欲しい人なんだ。
返事をもらえるまで頭を上げないぞと言う気分で固まっていたら、また肩を揺さぶられた。
「そんな事しないでよ! こんな俺に、そこまでする必要ないって!」
そっと抱き込まれ、柔らかな唇で押し上げるように顔を上げさせられた。
「愛してる……」
涙でぐしゃぐしゃの顔が近づいてきて。額にキス。瞼、頬、唇……。泣きながらのキスはしょっぱくて……。なのに甘さが僕を酔わせていく。
「龍樹さんと一生を共にしたい」
言って、涙を拳で拭ってから今度はお骨に向かって手を合わせた。
「父さん、母さん、春美、こういう人なんだ。驚いたよね?
俺、絶対ホモなんかなれないって思ってたのに……この人だけは……特別なんだ。俺のこと大切にしてくれて……、俺に関することで直ぐ動揺しちゃう……。でも、いつも俺を支えててくれる……。俺……龍樹さんがいないとだめなんだ。だから。俺達のこと、許して下さい。お、男に抱かれる息子なんてって思うかもしれないけど……、それでも俺、龍樹さんがいいんだ。いっぱい、いっぱい考えたんだけど、この人しかいないんだ……。ごめんなさい、俺、頑張るから。みんなの分まで頑張って生きるから……黙ってみてて下さい。俺達のこと……」
「お願いします……」
一緒に手を合わせて呼びかけた。心の底から真剣に。
「それと……。父さん達の部屋、使わせて貰います。この人と過ごすのに、俺の部屋じゃ狭いから」
それを聞いた途端に僕は横の拓斗を見つめていた。
僕の視線に気づいた拓斗は照れくさそうに笑った。
「いい年してダブル使ってたんだよ。この夫婦。このあいだ泊まって貰ったときは恥ずかしいから部屋見せられなかった」
その夜、桧の湯船の中で彼と抱き合いながら、僕は幸せに酔っていた。拓斗を説得し、一緒に風呂に入って。久しぶりに抱く裸の彼は相変わらずの艶めかしさ。
やはりこの風呂は二人で入った方が素敵だ。
「家族になるって……言ってくれて……嬉しかった」
とろけた瞳のまま、積極的に僕にキスをしながら彼が言った。
「千回以上愛してるって言われるより嬉しい……」
「どうして……?」
「いろんな意味持ってるから……。愛してるはね、消えちゃう言葉だから……。家族は形が変わっても家族だもん。親友よりすごい関係……だよね」
君のこだわりが、何だか少しだけ分かったような気がする。
それは、僕と一生を共にしたいっていう気持ちが本気だからこそ。
「君は……夫で妻で兄で弟?」
「うーん……龍樹さんは夫で兄……?」
……そんな風に僕の立場を限定しないで!
「僕だって甘えたいから……同じだけ」
肩を掴んで彼の胸に頬を擦り付けた。そのまま彼の中に潜り込む準備を始めるつもりだったのに。
「へんなのぉ」
クスクス笑いながら僕の腕からすり抜けて立ち上がった。
湯が滴り落ちる伸びやかな肢体に目を奪われ、僕はボーっと彼を眺めていた。瑞々しい張りを持った肌に包まれ、男っぽく筋張った贅肉のない身体は、あんまり綺麗で艶めかしくて。見る度にそれは更なる魅力を醸しだし、僕を虜にしてしまう。
身体目当てな訳ではないけれど、この美しい人は僕のものなんだと思うと、自分の今居る立場に畏怖さえ感じてしまう。
腕が優美に僕の前に差しのべられた。
「背中流すから来て。洗ったら、さっさと上がろう」
「拓斗……?」
まさか、ここまで来てまたお預けなのか?
露骨な問いかけを浮かべた僕のがっかり顔を覗き込んで、いたずらっぽく笑った。
「ここね、隣の家に丸聞こえなんだ。だから、するのは部屋で」
「そういうことなら……。でも、残念だな……ここでしたら素敵なのに……」
湯船の中で熱く膨張した自分を抑え込んだ。
拓斗の前では紳士でいたい。あくまでも拓斗の許すときだけと決めたんだから。
「風呂で戯れるってのは、龍樹さんちでね。ほら、座って!」
拓斗の示す椅子に腰掛けると、拓斗が僕の背中をこすり始めた。ただ背中を洗って貰っているだけなのに、僕はもう欲しくなってしまっていて。まるで十代の頃のようにドキドキと動悸が激しくなっていく心臓と分身を抑えることが出来なくて。
「龍樹さんの背中……大きいな……。ほんとに着やせするタイプだよね。俺、初めて見たとき見とれちゃったよ。あんまり綺麗な筋肉だから……」
「綺麗……っていうのは、君のための言葉だと思うよ。僕は……君の身体を見てから眠れなくなった……。眼を閉じれば焼き付いた君の姿が現れて、僕を刺激して……」
…………だめだ。
拓斗が僕に触れている。垢擦りで擦りながら、もう片方の手も僕の背に載せていて。優しく背中を這い回る拓斗の手の感触は僕の理性を奪っていく。
この状況で紳士でなんていられない。
我慢できずに彼の腕をとらえて抱き込んだ。石鹸のぬめりと湯気で、じっとりと濡れた彼の秘部に指を這わせて。
勃起した乳首を舌で転がしながら、彼の腰を支えるように僕の膝に跨らせた。
頬を赤らめながらも抗う様子のない拓斗を貪った。拓斗の腕が絡みついてきて、僕の濡れた髪をかき回した。これは許しの兆しだ。その反応に僕は図々しくも乗じてしまった。
「欲しくなるんだ……こんな風にしたいって……」
囁きながらゆっくりと二本指で犯して。
「は……ん」
腰を揺らしながら僕にしがみついてくる拓斗の手から、垢擦りがポトリと落ちた。拓斗の屹立はこれ以上無いほどの勢い。
「も……声……聞こえてもいいや……。して……」
甘く艶めいた囁きは僕の待っていた言葉。
「君がそんな風に言うなんて……夢みたいだ……」
拓斗を後ろ向きに座り直させ、既にとろけきったそこに僕をあてがい一気に貫いた。
「ああっ!!!」
拓斗の悲鳴。奥の奥まで僕を飲み込んで、それでも表情は甘くとろけている。僕を……待っていてくれた……?
熱く柔らかいそこは僕にも安堵感を与えてくれる。心地よく、離れがたい桃源郷。君だからこその悦び……。
背後から手を伸ばして仰け反る彼の胸を抱え、乳首を弄びながらもう片方で彼をしごいた。
「ああああんっ」
キュッと締め付ける柔襞に負けそうになりながら腰を揺らした。
「ああっあああああーっ」
仰け反ったまま激しく腰を使い始めた拓斗に促され、堪えきれずに射出してしまいそうになって持続のために集中しなければならなくなった。
突き上げのテンポを速めるしかなく……。
「俺……も……イかせて……」
荒い息の下での哀願。扱く力を強め射精の閾値に近づける。彼の手が僕の手に重なって。
「はぁっ、はぁっ、んんっ……あああああぁぁぁん」
僕の手の中で迸らせながら、裏がえって細く響く透明な声音を喉からも迸らせた。風呂場のエコーのせいじゃない。押し殺さずに放たれた彼の声。それはもうこの世のものとは思えない美しさ。
「ああ……君の声……セイレーンの歌声みたいだ……」
「な……に……ってん……の……」
グッタリしていきながら照れたように呟く、そんな色っぽさに早くも僕はまた彼の中で硬くなっていた。その感触でまた拓斗がびくんと身体をしならせる。
「あ……また……?」
「君の声のせい。……もう一度……聞きたい」
「ん……」
首を巡らせて口づけを求めてくる拓斗を深く貪って。
貪りながらゆっくりと突き上げた。
「あ……あ……あんっ」
体位を変えようと腰を抱く腕に力を込めた。
「拓斗……こっち向いて……」
「あ……や、やめないで! あうっやだぁ!」
身悶えしながらこのまま続けたがる拓斗を抱え上げて僕のを引き出した。
「嫌……っ!」
嫌々をする拓斗をこちらに向き直らせてもう一度貫いた。
「は……んんんん! い……じ……わるぅ!」
首を振り立てながら眉を寄せて呻くように言う様は、あまりにも扇情的だ。君は多分、年を取ってもずっと少年ぽさを失いそうもないね。可愛くて、色っぽくて……大らかだ。
黒目がちの大きな瞳も、細く通った鼻筋も、上下バランスのよいふっくらした唇も。寄せられた眉は微笑むときは綺麗なカーブを描く。ああ、童顔ではないのに幼く思えるときがあるのは……瞳の輝きが無垢だからだ。淫らな喘ぎを漏らしていても、ちっともそれは変わらない。伝い落ちる涙も口の端から漏れる涎も。全ては僕のため。僕だけの悦び。
「君の……表情が見たいんだ。この、色っぽい顔を……」
突き上げる速度を速め、拓斗の動きにも手を貸した。きつく抱くことで拓斗の怒張を腹でこすり上げる効果を強める。
僕の腕の中で激しく腰を使いながら我を忘れたように叫び始めて。外に聞こえることなど、もう念頭にはないらしく。
「ん、ん、ふうん、あ、あ、ああああぁぁアアアアアァァァァァ」
絶頂を迎える拓斗の表情を堪能する。
「拓斗、拓斗、拓斗……! 綺麗だっ……素敵だよっ」
「あ……あ……あ……もう……だめえっ」
肩に食い込んでくる絆創膏の指に掻きむしられながらドクッと下腹部に圧力が来るのを至福の思いで感じた。
キュッと僕を引き絞り、僕の吐精を促す熱いうねり。拓斗の中に存分に撃ち出しながら、射精が終わりでないことを自覚していた。それはこれから始まる夜への誘い。愛しくて、何度抱いても欲しくて。
「は……あ………………」
痙攣しながら崩れ落ちていく彼を抱き留めて肩にキスした。冷え始めている。
「し……死にそう……」
とろけたままに呟かれるそんな台詞に、思わず微笑みが浮かんでしまった。
「確かに…………今なら死んでもいいかな……」
湯船から湯を汲み上げて身体にかけた。
「ベッド……いこうか」
囁けば、こっくりと頷いて。
「うん……。抱いてってくれる?」
僕の肩にしがみついて言った。
「もちろん。喜んで」
タオルでお互いを拭っていたら、拓斗が笑い出した。
「どうしてかな……」
「え?」
「ねえ、俺、やっぱりホモってわけじゃないんだよ」
クスクス笑いながらそんなことを言う。こんな状況じゃなかったら僕を地球の裏側まで落ち込ませそうな台詞を、簡単に吐く拓斗が小憎らしい。
「あんなによがっといて、そういう事言う?」
つるんと彼のペニスをタオルで撫でたら、ア、と瞬間酔ったように呻き、もう一度笑った。
「だって……俺、男に触られて総毛だったもん。気持ち悪くて、悪寒が走った……」
「僕も……男だよ?」
抱き上げて拓斗の示す寝室の方へ向かった。
「俺の言いたいこと分かってるくせに……。龍樹さんだけ特別なんだ。俺ね、ホントは天性のホモで、自覚無かっただけだったのかなって、……考えてたんだけど……」
「藍本にされて分かった?」
「うん。龍樹さんなら抱かれるのも嬉しくて……。でも、他の奴はだめだ。どうしてかな」
「ドイツで残したアップルパイだよ」
「なにそれ」
「君が残したパイ。不味くはなかったけど、僕の作った味の方が気に入ってたから……でしょ。食欲を満たすだけならどっちを食べても同じ。でも、それだけじゃないから食べなかった。性欲を満たすだけなら娼婦相手でも事足りるけど、愛し合えるのは愛してる人とだけ。どっちがいいかははっきりしてる」
「じゃ、俺がもし急に女になっても龍樹さんは愛してくれる?」
「今の君と寸分違わず、まるっきり同じ人間性なら……。そうだね、僕はゲイじゃなくなってたかも。僕の両親は万歳三唱だろうね」
性別も何もない。拓斗という人が僕を魅了しているのは、見かけだけではないのだから。
「でも、俺は男で、がっかりか……」
「これも縁だろう。ゲイじゃない君が僕とそういう関係だってのと同じ。……もしかして、僕は藍本に感謝しなくちゃいけないのかな。君がそんな自覚持ってくれるなんてさ。すっごく腹立ってるのに。ねえ、あいつ……ここも触った?」
「あん」
拓斗が感じる脇の下にキスした。
「こんな事した?」
ベッドに組み敷いて彼のペニスをくわえた。
「ああっ」
「あいつの感触、全部忘れなきゃだめだよ」
「あふっ……っ……お、覚えてないよ。元から……あんっ」
「悪寒が走ったんだろう? 僕が……忘れさせてあげる」
「あああああんっ」
「今夜は一晩中……眠らせないからね」
前戯を念入りに、拓斗が高ぶって身も世もなく悶えるまで。僕の全てをつぎ込んでよがり狂わせてみせる。そんな気持ちで彼を抱き締めた。
「龍樹さん……許して……俺、死んじゃう」
それは何度目の絶頂を共にしたときだったろうか。涙を流しながら拓斗が訴えてきた。
拓斗の両親のベッドで何度も彼を抱いて。
数えることをあきらめるくらい拓斗の身体を貪りながら……今だに消えない欲望を全て流し込むつもりで彼を煽り続けていた。
「大丈夫。僕は医者だもの……。ちゃんと、してあげる……」
「ああんもう……お願い…………」
許してと呻きながら、僕を駆り立てるのは拓斗自身。長い脚が開いて、僕を誘う。ゆらゆらと揺れる男根は僕に早く来てと手招きしているみたい。
「だって……愛してるんだ。何回しても欲しくてたまらない……」
彼を上に跨らせてもう一度僕を呑み込ませた。恥じらいと戸惑いを瞳に浮かべながら、僕の手の要求通りに動き始めてくれて。突き上げに合わせて腰をくねらせながら僕を絞り上げた。
「ああっ……いいっ……ん……ん……あああああっ………………っ」
絶頂を迎え、喜びを迸らせながら腰を振り続けて。
やがて僕の上で力を失い、ぱたりとそのまま気を失ってしまった。僕の向こうを張る体力を持っていると思っていたが……。
「今まで通り、日課のトレーニングはしようね……」
そっと囁いて、拓斗の重みを嬉しく感じながら彼の髪を撫でた。
無防備に僕に身を任せる彼は、今度こそ本当に僕のものになってくれた。
素直に応えてくれた彼は、電撃的な早さで僕を受け入れてくれた訳だ。
恋人から家族へ。お互いの心を少しづつ溶かしあって一つになっていくのにはまだ時間がかかるだろう。
ほんとうの家族になれるまで、僕は努力を惜しまないつもりだけど。
願わくば、君の想いも一生変わりませんように。
明け方近く、僕等は繋がったまま眠りに落ちた。
朝の気怠いまどろみの中でふと思い浮かんだこと。
僕の願いである同居を、今言ってみたら……きいてもらえるだろうか。
眠りから覚めて身じろぎした拓斗に声をかけた。
「ねえ拓斗……」
「ん……?」
僕の上でほんの少し身を起こし、チュッと軽いキスをしながら返事をしてきた拓斗は、あまりにも自然で、かえって僕をおののかせた。
朝を迎えても彼は夜と同じように僕に身を任せている。甘く、僕を呑み込んだまま。
以前はまるで罪深いことをしてしまったかのように恥ずかしがった彼が、当たり前のように愛しげなキスをくれたのだ。
だから僕は言おうとした言葉を飲み込んだ。
この幸せを自分の言葉で壊したくなくて……。
「やっぱりいい」
拓斗のサラサラの髪を指に絡めながら僕の胸に彼の頭を押しつけた。
「なんだよ、言ってよ」
チクリと胸に軽い痛みが走って。拓斗が僕の乳首をつまみ取ったのを知った。
「言わないと抓るよ」
「た、拓斗……!」
拓斗の頭を掴む手に力が入ってしまった。痛みのせいではない。拓斗が僕を刺激している。それが嬉しくて。感じてしまった。
「ほら、早く。言わないともうキスしてあげないから!」
「そんな! い、言うよ。あの……」
「ん……?」
指でくりくりと悪戯されていた乳首に吸い付かれて息を詰めた。
「い、一緒に……」
「ん……」
濡れた熱い感触が乳首から戦慄を伝えてきて。僕の拓斗がそんなことをしてくれるというだけで、悦びに溺れそうになる。昨夜からの行為で燃え尽きた後でなかったら、とっくに彼の中にまだいすわっている僕の分身は大暴れしていただろう。
今は、僕の言葉に真剣に耳を傾けてくれない拓斗に苛ついてしまっていた。
「ちょっと、ちゃんと聞いてる?」
「聞いてるよ……一緒に……なんだよ?」
「君と一緒に住みたい。朝も、昼も、夜も……一緒にいたい。君のプライベートな時間は全部……僕のものにしたい」
「同棲……したいってこと?」
念押しのように聞いてきた。拓斗の不機嫌そうな聞き返しはあの、「恋人と思っていいか?」という僕の失言を思い出させて……。言わなきゃよかったと後悔しながら頷いた。
「うん……。結婚……なんだし。変……かな……?」
「あっはははは」
怖ず怖ずと言ってみれば答えがそんな笑いで。
「なんだよ。何かおかしい?」
ぼくが真剣に話しているのに……、拓斗ときたら……!
「い、いや、龍樹さん、相変わらずだって……。もう、その性格……ぷぅ〜っっ!!!」
我慢できないと言うように笑い続ける姿は可愛らしく、愛おしいものなのだが……。今度だけは、ちょっぴり……憎らしく感じた。
「たくっ……!」
頭にきて口を開いた途端に拓斗の唇が押し当てられた。甘く貪られて、怒りを吸い取られてしまった僕は弱々しい瞳で彼を見つめることしかできない。
瞳に優しい笑みを浮かべた拓斗は、僕を見下ろして囁いてきた。
「また俺が何か疑ったと思ったでしょ。俺達、悲観主義な所が似たもの夫婦……だよね」
夫婦? ……夫婦!
そんな一言で感動して固まっていたら……、拓斗が僕を抱き締めてきた。固く、精一杯に力を振り絞るようにして。
「龍樹さんが可愛い! すごく愛しい! 俺、龍樹さんの所に押し掛け……女房……するつもりだったんだ」
女房というところで照れたように口ごもりながら、それでも真剣な目の色でそんなことを……。
「俺が先に言わなきゃいけないこと、龍樹さんが言っちゃうんだもん……。だから俺……」
「拓斗……本当に?」
「うん……ここ、売っちゃうつもりだし」
「え……?」
「学費。龍樹さんが浪人するのももったいないって言ったでしょ。やっぱ、俺、早く医者になりたいし、一年無駄にするのも損だから……。昨日までは、龍樹さんとこにも行かれないと思ってたから、どっかアパート探そうかって……考えてた」
「じゃ、僕と住んでくれるの?」
「龍樹さんさえよければ……、明日からでも……お願いします。家賃も払うし、家事の役割分担もちゃんとさせて貰うから」
「家族なんだから、家賃は却下。でも、そうだね、家事は分担しよう。そうか……僕の所に……! 君と一緒に暮らせるなんて、ホントに夢……みたいだ」
感激を半身を起こしてキスで伝えた。そうしてるうちにまた欲しくなってしまって。
「……っ。龍樹さん……、また……?」
拓斗の中にいたままだったせいで直ぐにそれとばれてしまった。
「俺……マジで壊れちゃうよ」
お互い絞っても一滴も出ないくらい愛し合ったあとで、自分でも呆れるほどの勢いだと苦笑した。
「壊れちゃうのは困るな。たっぷりして満足したから、今は我慢する」
そっと彼から引き出した。
「あん……」
あまりに甘い声音に、やせ我慢を後悔していたところ、いきなり仰向けに押し倒された。
拓斗が僕の上に跨り、愛らしい唇が迫ってきて。
「た、拓斗……? 君……」
戸惑い声は拓斗の唇に遮られてしまった。
「あと一回だけ……だからね……」
たっぷりと媚薬を含んだ拓斗の唇。それが甘く囁く言葉に僕は……。止まれない欲望のジェットコースターに乗ってしまった。
高ぶる怒張はまるで塔のようにそそり立っている。いつものように拓斗を組み敷こうとして、もう一度キスで遮られた。
「じっとしていて」
「拓斗……?」
その意味は……すぐに分かった。拓斗は僕の上に跨ったまま、僕の怒張に自らの秘部をあてがったのだ。
ゆっくりと僕の上で腰を沈め、僕を呑み込み始め。
「あ……ん……ん……」
甘く呻きながら息を整えるようにして僕を深く深く呑み込んでいく。拓斗のそこもしっかり立ち上がっていて、僕を呑み込む感触を快感と認識しているのが分かる。
拓斗の重み、拓斗の熱さ……。全てが僕を陶酔の域に追いやっていく。
「あ……あ……んんっ……」
絞り上げるように腰を浮かせては沈め……。身をよじるように腰を揺らしながら僕を締め付けては柔らかく包む。拓斗が自らの意志で僕の遂精を誘おうとしている。
「いい……?」
息を荒げながら訊ねてきた。
「ん……いい……。いいよ……。嬉しい……!」
本当に。
「怖いくらいに……幸せ……だ……」
僕は手を伸ばして彼の怒張を握った。彼と同じテンポで扱いた。
「はあああっ」
「いきそう……?」
「うん……龍樹さ……んは……?」
「僕も……限界……。一緒に……いき……たい……」
「ん……一緒に……!」
動きを早めながら二人で息を合わせた。
存分に声を上げ、悦びを分かち合い……見つめ合ったままいった。
「すごく……素敵だった」
満足感をキスで伝え合い、さらに囁きで念押しして。それくらい、幸福だったのだ。
昨夜は今までにないほど燃えてしまった。拓斗の『壊れちゃう』は、ほとんど本気の台詞だったろう。
ダブルベッドの心地よさが思いの外だったせいもある。拓斗に触れた他の男の存在も刺激だった。悔しさに燃えた。そして、それを払拭するような拓斗の熱さに、僕はさらに焦がれた。
他の男……。
階下に転がされている藍本を思いだした。
「藍本!」
「あ!」
「忘れてた!」
慌てて下着をつけずにパンツをはいた。
「た、龍樹さん?」
半身を起こした拓斗は瞬間苦痛に顔を歪めた。
「無理するな! 君は寝てて!」
足音も荒く、階段を駆け下りた。
藍本が僕を見上げた。
「桂川……」
「昨日のこと、覚えているかい?」
肯定なのか、否定なのか、視線を逸らしてそっぽを向いた。
「君の使った薬は違法だ。これから警察に君を連れていくつもりだけれど。もし二度と僕等に手出しをしないと誓うなら見逃してあげる。どうする?」
返事をしない藍本を引っ張り起こした。
「君がそういうつもりなら……。警察へ行こう。妹と同じように拓斗にしたことも償って貰う。大体薬盛って無理矢理なんて……酷いよ。君の妹が嫌がったの、仕方ないね」
「バカな!」
返事になっていない。でも、僕にとってはどっちでも同じだった。
「とにかく! 君の身体には細工させて貰ったから。……僕は本気で怒ると、結構危ない奴になるらしい。君は僕を怒らせた……」
言いながら、わざと彼の股間を探った。刺激を与えるように。
「君のここ……、男でも感じるんだろう? バイ……なんだよね。元々なのか、僕の拓斗の色気で目覚めたのかは知らないけれど……。ま、無理ないかな。拓斗は彼自身が麻薬みたいだものね」
「なっなっ……!」
藍本は柔らかいままの股間を蒼くなったまま見つめて、素っ頓狂な悲鳴を上げた。
「……感覚……ある? 一度目は僕への復讐だったんだろうけど、二度目は……味をしめて拓斗を抱こうとしたね。だから、君のは使いものにならないようにしておいた。運が良ければそのうち使えるようにはなるだろうけどね。もう一度拓斗に手を出したりしたら……生きていたくないような目に遭わせてやる。よく覚えてるがいい。……言っておくが、僕は君以上に執念深いよ。そうだ、君の会社……、スティーブが会長だったな。実はね、あのコルベット、彼から貰ったんだ。例の定時連絡の時には君のことも書き添えることになりそうだ」
MS社は大きな会社だ。彼の人となりにしても、違法行為をしていたことも、会社のデメリットになる。僕は知人として事実を社主であるスティーブに連絡する義務がある。それ以上でも以下でもないつもりで言ったのだが。
彼は真っ青になった。他にも何かつつかれるとまずいことでもしていたのだろうか。
すっかりしおれた彼を紫関に引き渡した。
ぶつくさ文句を言いながらも、拓斗の世間体を考えてくれた紫関は、自家用車でそっと訪れてくれたのだ。
藍本の家で薬が見つかれば、更に罪は重くなる。空の注射器に残った薬液でもそれが何かは分かるけれど。念のため、僕の指紋はふき取って彼に持たせておいた。
小狡いのは分かっているけれど、僕は今の幸せを邪魔されたくなかったから。
後で出頭するという約束で帰って貰って。
ベッドの中で僕を迎えた拓斗の額にそっとキスした。
「警察……、帰ったの?」
「まだ鑑識の人が残ってるけど……もうすぐ帰ると思うよ」
「俺……降りていかなきゃ……」
「君は具合が悪くなって寝込んでるって言ってある。もう少し元気になったら、出頭するって言ってあるから」
「……強姦て、申告罪だよね……」
「うん……」
拓斗の場合は、傷害なんだけど。
「俺、告訴したほうが……いいのかな……」
階下で入れてきたコーヒーを渡しながら答えた。
「君の自由だよ。藍本の場合、他の罪がくっついてるし……。どっちにしろ証人にはなってしまうけど……。告訴するかどうかはまた別……だな」
「ホントいうとね、そっとしておいて欲しいって感じ。……一発殴らせて貰えばよかったかもしれない。俺バカだから、そういうのって、いっつも後から思いつくんだ。あーくそ、損したなぁ」
大して悔しいとも思っていない顔でそんなことを言う。
僕はきゅっと彼の頭を抱きしめて撫でた。
クスクス笑いが堪えきれずに漏れてしまう。
「君さ、お人好しって言われるでしょ?」
「え? ……俺が?」
「腹立つことあっても、すぐやり返せないで、かえって相手のこと心配したりしてさ。僕のこと殴ってもいいんだよ。君が嫌な思いや痛い思いしたのは僕のせいなんだから……」
「……龍樹さんを殴るなんて出来ないよ!」
真剣な瞳でそう言ってから、ニッとイタズラっぽく笑った。
「……Hを一ヶ月我慢とか……の方が痛くない?」
「た、拓斗っ?」
それだけは勘弁してくれっ!
悲鳴のような上擦り方で叫んだせいで、拓斗の笑いが爆発した。ひとしきり笑い転げて、涙のにじんだ瞳を僕にまっすぐ向けた。
「うそ、嘘だよ。俺の方が我慢できないもん。龍樹さんのせいだなんて思ってないし。……あの人、本気で龍樹さんのせいだと思っていたのかな」
「どうだか。……自分のせいだとは思いたくなかったかもね。多分、妹のこと、本気で好きは好きだったんだと思うよ」
「強姦したのに?」
「強姦てね……、相手のことを後先見失うほど愛してるか、憎んでるか、どっちかなんだって。普通の心理だと」
「連続暴行犯みたいな人は?」
「特定の人物じゃなく、たとえば対象が女性なら女性全般を憎んでる……って事になるのかな」
「ふうん……」
「何考えてるか当てようか?」
「え?」
「……龍樹さんが俺のこと強姦しなかったって事は……そこまで愛してないって事か……? とか」
「う……」
図星だったようだ。
僕はベッドサイドの拓斗の横に腰掛けて、彼の肩を抱き寄せた。
「僕はね、欲張りなんだ。一度の快楽のために君を失いたくなかった。……タイミングから言ったらぎりぎりセーフってところだったけどね」
「そうなの?」
「うん。かなり……危なかった。そんなことになってたら、君は僕を捨てただろう? 軽蔑して……」
「軽蔑は……しなかったよ、きっと。でも、怖がったろうね。龍樹さんに近寄れなくなったかも……」
ポソッと言って、何か思いついたのかクスッと笑った。
「……一発で目覚めちゃって、もっとして! なんて縋ってたかな……。ありうるでしょ?」
悪戯っぽい目で見上げる彼の可愛さと言ったら……!
「君に関しては……可能性低そうだな……。だって、君、無理強いが嫌いでしょ?」
「……うん。本当に龍樹さんが我慢強くてよかった……」
甘えるように僕の胸に頭をもたれさせて……。
その感触の心地よさはそのまま僕の幸せを表している。温かく穏やかな、この世の全ての存在に感謝を表したい気分。
「あの時……こんな思いを経験した後だったら……彼女をあんな風に死なせることはなかったかもね」
「……受け入れていた?」
「少なくとも、冷たく拒絶したりは……しなかったと思う」
「医者にそこまでの義務はないはずだよ」
「患者を健康にするのが医者の役目だ。彼女に必要だったのは獣にならない男の存在だよ。それを認識させることもできずに絶望させてしまった」
「美香……さんは……龍樹さんの心に焼き付くためだって言って死んだんだよね。俺は龍樹さんが応えなくて良かったと思う。応えてたら、俺はその人と龍樹さんをめぐって喧嘩しなきゃいけなかったから……」
拓斗の腕が僕を抱き締めようと絡まってきた。
「龍樹さんを安全牌にしたかったんじゃないよ、龍樹さんを手に入れたかったんだ。だから……。応えなくて良かった。俺、心せまいね……」
「焼き餅? うれしいな」
「俺も……龍樹さんに裏切られたら当てつけで死ぬかもしれないよ……」
「それは困る。嫌だ。……裏切られたと思っても、必ず僕に問いただしてくれよね。勝手に思いこみで僕に罪をかぶせないでよ」
「うん……」
何度も口づけをかわした。
ベッドの上でだったけれど、神様の前での誓いに等しいほど、神聖な気分で……。
早光大の入学式。
桜吹雪が舞う花曇りの中。
僕は時間を見計らって校門そばにショッキングピンクのコルベットを停めた。外に出て車に寄り掛かり、キャンパスの中を眺めてから、ドアミラーに姿を映して確認した。ダークなワインレッドのスーツに、黒とグラスグリーンのネクタイ。ネクタイは拓斗が選んでくれた彼の父親の形見。
入学式の後、拓斗を拾って湘南までドライブ。海を眺めながら食事をして、老舗のホテルで一泊。それが今日の予定。
初めてのデートらしいデートに、僕の心は躍る。うきうきした気分が外に出ているのか、道行く人に時折じろじろ見られるけれど、そんなことは気にしない。拓斗がかっこいいと言ってくれたから。
眠くなるような話を一通り聞かされた後らしい晴れ晴れ顔の新入生達がその日配られた書類を持ってホールから出てきた。校門からホールまで出来た部活の勧誘のアーチをくぐり、盛装に近いきらびやかさで付き添いの親と共に歩いてくる。
これからの六年間、何度も歩くキャンパスの銀座通り。そこを埋めている未来への夢で一杯の顔、顔、顔。
その中を一際元気に駆け抜けてくる男がいた。
誰もが自然に目線が吸い寄せられてしまう不思議な空気をまとった魅力的な男。
初々しい夢一杯の輝きが一番似合っている、細身で綺麗な……。温かくて、素直で、可愛い男。
校門の外で待つ僕のところに真っ直ぐに駆け寄ってくる。自分が集めてしまう周囲の視線をものともせずに。
僕は誇らしい気分で近づいてくる彼を待った。
彼は向坂拓斗。今日から医学部の一年生。
居合わせた全ての人に声をかけたい気分で、心の中で叫んだ。
見て下さい、皆さん!
今駆けてくるあの素敵な男は僕の恋人で、大切な家族なんです!
前を読み返す
◆1◆2◆3◆4◆5◆6◆7◆8◆9◆10◆11◆12◆13◆14◆15◆16◆17◆18◆
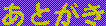

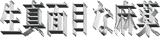 龍樹サイド
龍樹サイド
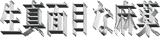 龍樹サイド
龍樹サイド