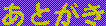誠実な偽薬
「また……痕つけたな……」
首筋を指先でなぞりながら呟いた向坂拓斗は、鏡の前で困惑していた。
四月の早光大医学部入学式から二週間が過ぎて。
晴れて医学生となった拓斗は目新しい環境に順応しようと必死だった。
新しい知識、新しい仲間。予備校仲間でもいない限り一人一人が初対面同士の百人以上が、同じ学びやで六年という長い月日を過ごさねばならないのだ。
そのために、親睦会を兼ねたクラスコンパなどが存在する。同郷の先輩が企画する県人会コンパ、部活動内でのコンパ等も同種だ。
どれもが酒の席だというのが曲者である。
「拓斗君、いつまで髭剃ってるの? そろそろご飯たべて行かないと遅刻するよ!」
甘く艶やかな低い声の呼びかけに小さく舌打ちした。
「曲者がここにもいた……」
ため息をついてダイニングに向かった。
拓斗が暖簾をくぐった途端に味噌汁とご飯をよそってセッティングし始めながら、美しいギリシャ彫刻が微笑んだ。精密に計算し尽くされて配置されたとしか思えない造作を惜しげもなくクシャッと歪ませて。それは、冷たい大理石ではなく熱い血をたぎらせた肉でできあがっていることを思い出させるのだ。
桂川龍樹。
拓斗の下宿のオーナーという名目だが、実態は法律にはない内縁とはいえ、結婚の約束までした恋人である。
食後のお茶をつぎながら、龍樹が覗き込んできただけで拓斗は次の台詞を予想できた。
「今日はどういう予定?」
朝の決まり文句にまた溜息が出る。
「二限に体育があって、四限までびっちり。その後クラスコンパ……」
大学の授業はやけに長い。九十分授業のために午前中二時限、午後二時限でも夕方になってしまう。コンパは大体六時半から二時間ぐらいの予定で、一次会の後に、飲み足りない人間達が各々の二次会三次会に散っていく。
拓斗は一次会にしか参加したことがなかった。
「またコンパ? 今日は定休日なのに……僕一人で夜までいなきゃいけないの?」
甘く華やいだ声が途端に地を這うような暗さを見せる。これが一次会のみ参加の理由。
声の主が一次会の終わる頃には愛車であるショッキングピンクのコルベットに乗って店の前で待っているのだ。
帰らないわけにはいかない。
「今度のは二クラス合同の奴。……それより、昨日、あんなに痕付けないでって言ったのに……。今日、体育あんのに、どうすんだよ! またからかわれちまう」
拓斗の不機嫌さを悟った瞬間に泣きそうな光を浮かべた瞳で見つめてきた。
「だって……拓斗君の生肌……みんなに見せるんだろう? 君にはそういう関係の恋人がいるんだって早めにみんなに知らせとかないと……。君に恋する奴が出てくるかもしれないじゃないか」
「……そんなことしなくたって、ピンクのコルベットの男が俺にくっついてるってのは学年全部が知ってるよ。おかげで、好奇の視線浴び続けなんだからな!」
入学式の日に校門前で待ち合わせたのがまずかったと後悔している。
この恋人はとにかく目立つ男だからだ。
一九〇センチの身長、顔と同じく均整のとれたギリシャ彫刻まがいの身体。しかも着やせするから、すらりとした様子の良さを持っていて、まるでモデルのようなムードを無造作な服装の時まで醸し出している。
そんな男が、ただでさえ目立つショッキングピンクの外車に、よく似合うスーツ姿で寄りかかって立っていれば、誰だって振り返って見なおしてしまう。
『向坂くうん、入学式の時のあの人、向坂君の何?』
おかげで学年の女子からはほとんど全部声がかかった。最初の二日間くらいでだ。
『遠縁の人で、下宿させてもらってる』
とか、
『お目付役なんだ』
とか……。
冗談めかしく
『援助交際の相手』
なんて言ってみたこともある。言った相手が悪かったのか、この情報が一番大きく広がってしまった。
《向坂拓斗は男のパトロンを持っている》
などということが、すでに定説となりつつある。
従って、着替えの時にキスマークの一つも見つかれば、イコール男につけられたものであると言うことになる。
『向坂ぁ、今日は見学の方がよくない? 腰、大丈夫?』
なんてニヤつきを含む余計なお節介を向けられるのだ。
「俺の学生生活、お先真っ暗な感じ。すっかりオカマ扱いされてるんだぜ」
「プライベートがどうであれ、ちゃんと勉強してればいいじゃない」
「それは理屈! ホモがどういう目に遭うか、龍樹さんだって知ってるだろっ?」
言い放った途端に龍樹がすうっと目を細めた。
龍樹の怒った表情というのは滅多に目にすることはないが、これはその数少ない経験の中で拓斗が学んだ怒りの第一兆候である。
「君は……そういうの分かってて僕と結婚する気になったんじゃなかったの? 僕らの仲ってそんなに隠したいこと?」
「だって……」
「君は僕のこと、パトロンって言ってるんだって?」
「な、なんで……」
知っているのかという前に、むっつり口調で龍樹が言い出した。
「君のクラスのおしゃべり雀は、もう何人か店の常連になっている。彼女たちが君が話さないことを教えてくれる」
「……店に来たの?」
「ああ、君の住所を学生課で聞いてきたんだって。こんな小さな喫茶店の店主がパトロンなんて、君は嘘つきだって言ってた」
畜生、誰だよ?
俺のことは嘘つきだっていいさ。でも、こんな所まで来て、龍樹さんに突っ込みいれて……。そんなのプライバシーの侵害だ。
拓斗は胸の内で舌打ちしながら、おずおずと説明した。
「最初、冗談で援助交際の相手って言ったんだ。そしたら尾ひれがついてさ……」
「……ほんとに冗談だったの?」
「どういう意味だよ?」
「君は、飼われる生活は嫌だって言ってたよね。僕にはそんなつもり無かったのに。君の中で、まだこだわりがあるんじゃないの?」
そんな龍樹の言葉に腹の底から虚しい笑いが湧き出した。
(こだわりだって? こだわりはあるさ。おおありだ)
売りに出した家はまだ買い手が付かない。日々の生活費も、生活の場も龍樹持ち。飯を食わせて貰って、夜の相手をする。
龍樹の所有欲ときたらエスカレートするばかりで、けして恩着せがましいことは口にしないが、行動を制限することは多い。当初の予定ではアルバイトをするつもりだったが、それも龍樹の店『El Loco』以外では却下なのだった。小遣いが欲しければ用立てようとの龍樹の申し出にいたって拓斗は爆発した。
『俺は契約愛人じゃない!』
そんな喧嘩をした日に冗談めかしく口にした援助交際。
自嘲の意味を込めての援助交際呼ばわりだった。
だが……。
「今の方が、こだわりあるかもな。俺、飼われるのも嫌だけど、縛られるのはもっと嫌だ! 龍樹さんは俺のこと縛ってる! 全然信用してくれないからあんな風に……」
「拓斗く……」
「結婚したって、俺だけの時間てものがあってもいいはずだろう? 俺は龍樹さん以外の恋愛対象はもたない。それは約束する。でも、付き合いは必要じゃないか。
最近どうかしてるよ龍樹さん。どんな時でも一緒にいなきゃ気が済まないなんて、ガキの恋愛みたいだ。どうしたら俺のこと信じてくれるのさ?」
「ガキで悪かったねっ! 君が襲われやすいからいけないんじゃないか! 信じる信じないの問題じゃないよっ。直ぐ犯られちゃうくせに!」
「……っ! 蒸し返すつもり?」
拓斗が好きでもない男に薬を盛られて犯されたのは一ヶ月前。それを苦に別れようとまで考えた拓斗に、結婚を申し込んだのは龍樹だ。
「あんな思いはもう二度としたくないんだ。だから、不安要素は全て除去したい。君のことが心配なんだよ。君は……魅力的すぎる」
「そんな風に俺のこと見るのは龍樹さんみたいな物好きだけだって!」
一ヶ月前の事件だって、拓斗の魅力が招き寄せたことではなく、間接的な別の理由からだった。後日同じ男が拓斗に魅せられてしまったのは、あくまでも行為によって龍樹だけが知る拓斗の色香を知ってしまったから。似たようなきっかけがどこにでも転がっていたら、それこそ生きた心地がしない。
「……そんなに心配なら、護身術教えてよ。武道得意なんだろ? どうせどっか道場通うって言えば、他の男との絡みなんて許せないって言うに決まってるんだから。龍樹さんが教えるしかないじゃないか」
「護身術だけで君の貞操が守れるとは思えないね」
「俺があまちゃんだから? 用心はするよ。それでいやなら……」
別れるしかないね。
苛ついた拓斗の顔にはそんな言葉が続くぞと浮かんでいた。
龍樹は頭を振りながら続く言葉を遮った。
「……分かった。明日からトレーニングのメニュー変えよう。それと……」
琥珀の瞳をうるうるさせたまま拓斗を見つめていた龍樹は、溜め息をつきながらキッチンのキャビネットから出してきた真新しい携帯電話を拓斗の前にさしだした。
「なんだよ? これ」
「充電してあるから。君がマスターするまではこれ持ってて。授業時間中は電源切っておいてもいいから。もう、待ち伏せしたりしない。迎えが必要になったら電話して。どこでも、何時でも、迎えに行くから」
「そんなこと言って……一時間ごとにかけてきたりしない?」
疑り深い瞳で責めるような声音を発する拓斗の顔は龍樹の心を曇らせる。最近目にするこんな彼の表情は、自分がさせてしまうのだという事も分かっているから。
「いや、僕からは……かけないようにする。本当に用事のあるときしか……かけないから……」
「本当の用事って、たとえばどんな?」
「……少なくとも、君が心配しているようなことでは電話しないよ。そのかわりと言っては何だが、帰宅時間を教えてくれること。それより遅くなるなら必ず連絡すること。約束してくれ」
「門限? 子供みたいだな」
「家族の最低限のマナーだろ。心配させるな」
拓斗は家族という言葉に弱い。龍樹が大人の顔で言って聞かせる厳しい口調の台詞を、単なる焼き餅とは異なると受け取ったらしく。
「……うん。わかった」
素直な返事をして見せた。
拓斗の物分かりの良さは、龍樹にとって大いなる魅力の一つである。
「今日は……十時までに帰る」
懐に携帯電話をしまった拓斗がふっと口元に笑みを浮かべた。
「俺が用もないのにかけたら龍樹さんは怒るかな」
「とんでもない! ラブコール大歓迎だよ」
龍樹は縋るように微笑みかけた。
いつだって待っている。そんな言葉を瞳に浮かべて。
拓斗は瞬間そんな龍樹を困ったように見つめてから、腕時計に目を遣った。
「行かなきゃ。電車の時間に間に合わなくなる」
言い置いて玄関に走った。
「待って、お弁当。今日はクラブハウスサンドと果物だから、容れ物捨てて来ちゃっていいよ」
慌てて差し出された包みを受け取った拓斗は、靴を履きおえてから身を伸ばし、引き寄せた龍樹の頬に口づけた。
「サンキュ、この愛妻弁当は俺の自慢なんだ」
学食の不味さは早光大医学部中退の龍樹も過去に経験済みの味。拓斗の味覚を満足させるための弁当を、最初は恥ずかしがったものだが、今では文句もなく携えて登校している。
愛妻弁当と表現した拓斗に甘えるように、龍樹は唇を指さした。
「愛妻に感謝のキスは?」
頬を赤らめた拓斗がすっかり馴れた態度で唇を重ねてきたが、初々しいぎこちなさは甘い吐息まじりの息継ぎに残っている。
離れようとする頭をがっしりと押さえて更に深く舌を抉り入れた。
唇を貪りながら龍樹が囁いた。
「愛妻で思い出した……。昨日来たおしゃべり雀には、僕が君に抱かれてるって匂わせてあるから。オカマは僕の方だって、話し合わせておいて……」
ばっと拓斗が身を離した。
銀の糸をぬぐい取りながら赤面して口をぱくぱくさせる拓斗をプライベートの玄関から押し出した。腰砕けの体の彼はズルズルと押し出されながら、それでも言いたいことを押しだそうとしていたが……。
「いっといで」
グイッと外へ。
「……龍樹さんのばかぁっ! そんな嘘、誰も信じないよっ」
ドアを閉めた途端に拓斗の罵声。
龍樹はドアにもたれてそれを聞き取り、幸福感に緩んだ自分の頬を両手で拭った。
不機嫌な沈黙よりも、赤面したままに怒鳴られる罵声の方がよっぽど好きだ。
泣き落としだけで彼を捕まえておける時期ではなくなったのかもしれない。拓斗は何よりも対等な関係を望んでいる。受け身だけをさせてしまっていたために彼がこだわりを抱いているのなら……。
「本当に……僕を抱いてもいいのにね……。君と愛し合えるならどっちだっていいんだよ、僕は……」
静かな呟きは急に広くなったように感じられる家に染み込んだ。
始業ギリギリで滑り込んだいつもの講堂のいつもの席。幸い教授はまだ来ていなかった。
「遅いじゃない」
隣から囁いてきたのは入学式の日に隣席になった笹沢。以来何となくつるんでいる新しい友人だ。
育ちの良さそうなおっとりした雰囲気そのままに、穏やかな話し方をする。中肉中背に地味なオールバックと銀縁眼鏡。服装や顔立ちも地味で真面目そうな印象の割に、遊びにも慣れているのか、どんな場所でももの慣れた様子で振る舞うので、拓斗から見ればなかなかに新鮮な存在だ。
また、男のパトロン説に動じた様子もなく変わらぬ態度で接してくれる笹沢には、心の中でかなり感謝していた拓斗である。
「奥さんと喧嘩?」
「奥さん?」
「コルベットのパトロンのこと! 蚤の夫婦って奴なんだろう? 水野が言いふらしてたぜ」
ああ!!!
龍樹さんの言っていたおしゃべり雀は水野!
拓斗は頭を抱えて突っ伏した。
水野彩は学年第一位のラウドスピーカーだ。何にも知らなかった拓斗は援助交際などという冗談をよりによって水野にしてしまったのだった。
(あ〜、俺ってついてないよ)
そんな物思いを後ろから肩を叩かれて遮られた。
「向坂、お前テクニシャンなんだって? 例のパトロンよがらせてるなんて、それに違いないって、もっぱらの噂だぜ。見回してみな、女どもの目つき、違うだろう?」
サボり魔赤羽の下卑た囁きに飛び上がった。
水野彩! 赦すまじ!
水野への怒りをそのまま赤羽にぶつける気分で睨み付けた。
「……俺、男じゃないと欲情しないんだ。女だと勃たないんだよ。テクニシャンかどうか、お前が試してみたら?」
……嘘だけれど。
怒りが言わせた投げやりな台詞だった。いつもの拓斗なら、口にすることすら思いつかないかもしれない。
「……遠慮する」
赤羽は慌てた様子で席を別の列に移した。
「おい、挑発するなよ」
「……どうでもよくなってきたんだ。笹沢だって、俺といるとホモだと思われるぜ」
自分の今の発言がまた物議を醸し出すのも覚悟の上である。
銀縁眼鏡の奥の小さな眼を和やかに細めて、笹沢は軽く肩をすくめた。
「共通の話題がない今だから、みんなで観察してくるんだよ。そのうち飽きるさ」
無責任な好奇心。バラバラな筈の新入生達が全てこのゴシップでまとまっている。
話題に詰まったら共通項の向坂拓斗を肴にすればよいといった暗黙の了解。
「何奴もこいつも暇人だよな」
溜め息が出る。
「ホモは医者になっちゃいけないってか?」
「そうじゃないけど……。普通、そういうのって隠してるじゃない?」
笹沢の苦笑は温かく、拓斗は本気で愚痴っていた。
「隠せるんなら隠してたさ」
「入学式の時……。目立ってたもんなぁ……」
「ああ、あのコルベットの色には俺たちも困ってるんだ」
「ピンクの車も目立つけどさ、向坂ってば全力疾走で駆け寄ったじゃないか。なに走ってんだろうって見たら、外人みたいな美形の男がデレデレの笑顔で手ぇ振っててさ。注目して下さいって言わんばかりだったぜ」
「……そうだったっけ……」
言われてみれば……。
その日は初めての本格的なデートの予定が組まれていた。鎌倉を通って湘南をドライブ。葉山の海沿いのレストランで、春の海を眺めながらの食事。古くからある老舗のホテルで一泊……というスケジュールだったのだ。
何しろその時は新婚気分のままで、入学式を無事に済ませた安堵と待っていてくれる人のいる幸福を全身に感じていたものだから……。龍樹の姿を目にした途端に足が勝手に駆け足モードに切り替わってしまった。
「とにかく、あの人は目立ちすぎるよ……。でかいし、綺麗だし……料理も上手い。向坂の弁当ってあの人が作ってるんだよな?」
「うん……。家事全般で完璧なんだ」
「奥さんにしてはがたいよすぎるけど……。好き好きだもんな」
(弁当のせいか!)
体つきから言って、誰もが拓斗を受け入れる側だと判断するのはしかたがない。しかし、それを覆す情報を、みんながあまりにすんなり信じてしまったファクターは弁当にあったと拓斗は推測した。
彩り、バランス、味。どれをとってもその辺で手に入るものより上質な弁当を、毎日欠かさず持ってくる拓斗を羨んでいる者も多い。
大学はあまり開けていない県央にあり、学生が寄れる店にも限りがある上に、学生食堂は不味いのが自慢だ。仕出し弁当も幾つか入っているが、龍樹の弁当の方が勝っている。
家事をやる方が奥さん→奥さんは女→女は受け身……。単純な図式が描かれているらしい。
そう思い至って馬鹿馬鹿しいと溜め息が出た。
「奥さんとか、旦那とか……関係ないんだよ……」
思わず呟いていた。
呟いてみてハッとした。
俺は……何てくだらない事にこだわっていたんだろう。
俺達の関係は、そんな単純じゃない。
どっちがどんな風に抱いたって、愛し合うことに変わりなかったのに。あくまでもボディトークだって事、当に認識していた筈なのに……。
もしも従属的な立場に自分が陥るとしたら、それは自分の責任なのだ。
卑屈なまでに拓斗に縋る龍樹の弱々しげな瞳を思い出した。
愛しくて、抱き締めたくなる切なげな表情。
龍樹という男を恋人として、また伴侶として受け入れたのは、あくまでも自分が彼を慈しみたいと思ったからだった。
「……帰る」
「向坂?」
「弁当はお前にやるから……。代返できるやつはしといて。あ、容れ物は捨てちゃっていいって」
鞄から弁当を取り出して笹沢に押しつけた。
「ちょっと、どうしたんだよ?」
しっかり包みを受け取ったまま囁いてきた笹沢は、つまみ食いの経験があって、龍樹の味を知っていた。故にこの申し出は大変に嬉しく、返せと言われても返すつもりはないようだ。
「講義より大事なこと、思い出したから……。コンパもパスっていっといて」
「おい、教授来てんのに……」
声を潜ませて呼びかける笹沢を後目に講堂を抜け出した。出席カードを頭数分配る講義で代返は頼めない。カード配りは講義開始後四十分と頑ななまでに決めている教授なので、その日は自主休講と覚悟を決めた。
教授には急病を告げ、出来るだけ静かにドアを閉めて、人気のない校舎裏で携帯電話を取り出して。
定休日の『El Loco』ではなく家に電話した。
「はい、桂川です」
龍樹の穏やかな声音がしっとりと耳に染み込んできた。
「……拓斗です」
瞬間息を呑んでの沈黙。拓斗には龍樹の気分が落ち込んでいくのが手に取るように分かった。
そういえば、この状況は拓斗が一方的な別れ話を出したときに似ている。彼は多分それを思い出しているのだ。
「……どうしたの? 授業中でしょ?」
平静を装いながら探るような響きで龍樹が言った。
「声……聞きたくなったから自主休講」
声音に甘える響きを載せ、受話器に向かって囁いた。
「どういう風の吹き回し? ……嬉しいけど……」
最初の不安を掻き消した声は華やかな響きを持っていた。
「……帰る。コンパも行かない。龍樹さんに会いたい……。帰ったら……しよう。いっぱいしよう……。痕もいっぱい付けていいから……」
「拓斗……? どうした? 泣いてるの?」
「泣いてない。けど……泣きそうな気分だ。……龍樹さんがあんなこと言うから……苛められた……」
甘え心が大げさに表現させた。
「え?」
「水野がふれ回って、もう……みんなに知られてる。……龍樹さんには慰める義務……あるんだから……。ちゃんと慰めてくれよね!」
「うん、喜んで。……迎えに行こうか?」
「いい……ちゃんと……帰れる……」
「……じゃ、待ってる。電車ん中を走っておいで」
囁きが含む甘く扇情的な響きは拓斗の身体に染み込んでいる龍樹の感触を思い出させ、甘い疼きを全身に走らせた。
「バカ……」
図らずも色っぽい呟きを吹き込んで携帯を切り、拓斗は駅に向かって駆け出した。
受話器を置いて龍樹は溜め息をついた。
(ごめんね、拓斗……)
胸の内をそんな言葉が渦巻く。
拓斗はバカ正直だ。素直で、優しくて誠実。何でも顔に出て……。嘘をついても直ぐ分かる。
(処世術を知らないかのように幼い面を持った君を、僕は随分辛い立場に追い込んでいるんだよね。
それでも僕は君を離すつもりはない。思いがけずこの腕に捕らえ込んだ君の全てが、僕にとって失いがたいものだから。
君が苦しむのを分かっていても、更に君を追い込む。君が、僕以外の手を取ることが出来ないように……。
いくらでも謝ろう。いくらでも優しくしてあげる。でも君の手は離さない。君が離してって言っても絶対に……)
龍樹のもの思いは、永久運動のようにそこから外れることがなかった。慌ただしい電話のベルが遮るまで。
「……龍樹? 龍樹なの?」
受話器を耳に当てた途端、母の声がヒステリカルに耳をつんざく。
「……どうしたんです?」
「泉が……泉が……!!」
「泉?」
「流産しそうなのっ! 早く来て頂戴!」
「……待って下さい。流産て、何の話です?」
第一、龍樹は産婦人科が専門ではない。実家の大きな総合病院にはプロがきちんと雇われている。
「あの子! あの、向坂って子はそこにいるの?」
「学校ですよ。もうすぐ帰ってきますけど……」
「あの子の子供よ! あの子も連れて来て頂戴!」
「……どういうことです?」
声が怒りのために低くなってしまう。
拓斗と泉が寝たのは知っている。龍樹が告白したのはその後で、拓斗が裏切ったわけではないし、泉の積極的な誘いに乗ってしまって悩んでいたのを、気にするなと水を差した覚えすらある。
「……妊娠というのは初耳ですよ。第一、拓斗の子だなんて……。冗談でしょう?」
「過去六ヶ月の間に、他に泉とそういう関係だった人がいて?」
「……知りませんよ、そんなこと……」
「とにかく、来て頂戴。芹が谷の方よ!」
それはまだ泉の収容されている精神病院の方ということで……。
慌ただしく切られた受話器を置くと、龍樹は額を押さえた。
「拓斗に……なんて言えばいいんだ?」
君は僕の妹を妊娠させていた。多分あの、初めての時……なのだろう。
……なんて。
彼はショックを受けるに決まってる。
ただでさえ身体の欲望に負けて泉とそういう関係になってしまったことを気に病んでいた拓斗が、子供まで作らせていたと知ったら……。
「責任とるって……言い出すかな」
つまり、植物のような感情の欠落してしまった泉と結婚……。
「嫌だ。だめだ!」
それが、ただの紙切れだけの関係だとしても許せない。
「拓斗は僕のものだ。僕と結婚するんだから……」
誰に聴かせるわけでもない呟きが無意識に漏れた。
(でも、血のつながりに勝てるだろうか………)
心の中の暗闇がどんどん拡がってくる。
「ただいま」
声と共に後ろから腰を抱かれて龍樹は飛び上がった。
「あ、お、おかえり」
「……どうしたの? 変な顔して……」
甘い唇を龍樹のそれに押し当てながら、上機嫌の顔で問うて来る拓斗の瞳には欲情の光。
いつもなら感極まった瞳でそれを受け止め、拓斗のしなやかな身体を貪るのが常の龍樹が、ぼんやりと立ちつくしたまま反応してこないのを見て取ると、真剣な表情にすり替えて覗き込んできた。
「龍樹さん……? 何かあった?」
「な、何にも……」
「龍樹さんっ?」
「なんでもないっ、大したことじゃない!」
「龍樹さん!」
怒ったように見据えてくる拓斗の瞳は、ごまかされないぞという決意を表していて。龍樹は怖ず怖ずと核心から離れた部分から口にした。
「実家から電話……あった。泉が……」
「泉さんが? 正気になったとか?」
「いや、そうじゃなくて。流産しそうだって……」
「は……?」
「母は、君の子だって言ってる」
「…………?」
ぱかっと口を開けたまま拓斗が固まった。
「子……ども……?」
「これから芹が谷に行く。君も来るようにって……」
「俺?」
「嫌なら行かなくていいよ。僕もよく解らないんだ。でも、君のことは守るから。君に変な荷物を背負わせるつもりはないから」
「龍樹さんも知らなかったこと?」
「ああ……」
「じゃ、行く。龍樹さんのお母さんは俺に何をさせたいのかな……? 想像つく?」
「おそらく……泉と結婚、もしくは桂川家への養子入り。子供は桂川の跡継ぎとして育てる目的としか思えない」
「龍樹さんがいるのに?」
「僕がゲイで、泉があれじゃあ、この先子孫は絶えてしまう。君と泉の子供がうちの両親にとっては救いなんだ」
「今頃になって、どうしたんだろう」
「僕が知れば、おろせと言うに決まってると思って、知らせてこなかったんだ。本当に君の子供だとしたら、月数から言っても、もうおろせない。殺人になる。……この時期に流産なんて、本当だったら泉の命だって危ない」
「とにかく、行ってみよう。龍樹さん、車だして」
「拓斗……」
「行ってみてから考えようよ!」
「う、うん……」
バタバタとガレージに向かった。ふと車に乗り込もうとして拓斗は龍樹を見据えた。
「俺が結婚するの、龍樹さんだけだからね。泉さんには悪いけど、もうそれに関しては迷わないから……。龍樹さんは安心してていいよ。そのかわり、一緒に戦って」
感激が龍樹の瞳を走った。
「……約束する!」
ガレージの電動シャッターが開くのを待つ間に拓斗が小さく溜め息をついた。
「……どうした?」
「 俺の子……さ……。俺が育てるべきだよね。泉さんには無理だから……」
「本音ではどうしたいんだ?」
「まだ、よくわかんないけど……。俺に育てられるなら……俺、ちゃんと親父になりたい。お前にはちゃんと愛してくれる家族がいるんだぞって教えたい」
「だったら僕はその子の母親になったっていい。桂川の親には渡さない」
「……母親……?」
「役割のことだよ。とにかく、あの両親に子供を渡したら、跡継ぎとしての道に脱線不可能のレールを引こうとするに決まってる。僕の時みたいに」
「龍樹さんは脱線したじゃない」
「だからこそ、泉の子供はさらに厳しく締め付けられる」
「龍樹さん……」
「僕だってこれでも大学入るまでは品行方正のいい子ちゃんだったんだよ。医者になるのが義務だって思ってた……。そういう家に生まれたんだからしょうがないってさ。親は僕のドロップアウトを未だに怒ってる」
「自分の意志で今の道を選んだことが、ドロップアウトなの?」
「親はそう思ってるのさ。だから泉には医者の婿をって、しゃかりきになってた」
「 俺は歓迎されないだけじゃなくて、憎まれてるんだろうな……」
車窓に目を向けて流れる風景や対向車を眺めながら拓斗が呟いた。
「君は僕を受け入れただけ。迫ったのも口説いたのも、僕たち兄妹なんだから……恨み言なら君の家族こそが口にすべきでしょ?」
「生きてたら親父にさんざん怒られただろうけど、良くも悪くも手出しできないとこ行っちまったんだ。独りぼっちの俺と寄り添ってくれる龍樹さんに恨み言なんて言わないよ」
拓斗の家族が事故で亡くなってから一ヶ月以上が過ぎた。少しだけ早めの四十九日の法要を明後日に控えている。
カミングアウトの必要性がなくなった天涯孤独の拓斗は、龍樹を唯一の家族として慕ってくれている。
では、もしも事故がなかったら 。拓斗は今のように龍樹の恋人でいてくれるのだろうか。そんな考えが龍樹の気分を尚更暗くした。
「……ねえ、龍樹さん」
「ん?」
「俺さ、あの初めての朝、一度は龍樹さんより先に起きたんだよ。龍樹さんの寝顔、いっぱい見ちゃった」
フフッと笑って言った拓斗にちらりと視線を投げる。運転中じゃなかったら、即座に拓斗は龍樹の餌食だったろう。
「ご感想は?」
扇情的な拓斗を少々恨みに思いながら、龍樹は話に乗った。何故今、拓斗がそんな話題を持ち出したのか、いぶかしんだからだ。
何を思い浮かべているのか、拓斗はホウと優しい溜め息をついた。
「スゲー可愛かったな。……あの時決めたんだ。親父達に龍樹さんとのことバレて叱られても、龍樹さんとの関係は続けようって……。親父達が死んで、そういうゴタゴタの可能性はなくなったけど……。気持ちは変わってない。龍樹さんしかいなくなったから龍樹さんの側にいるんじゃないんだ……わかる?」
「うん……」
溢れ出そうな涙で視界が歪んだ。瞬きでそれをやり過ごし、運転に集中しようとする。
拓斗に心を読まれたような気がした。互いに不安がる悲観主義者という表現は、拓斗が言いだしたのだったと思い起こす。
拓斗が自分を気遣っているというだけで、感激してしまう。
「……君がそんな風に言ってくれるだけで僕は……。戦っていけると思う。絶対負けないから。母が嫌なこと言っても、君は気にしないで。泣かれても、縋られても、ほだされちゃだめだからね!」
言いながら、拓斗を落とすのに自分も使った手段だという事を思いだして苦笑した。
「 泣き落としは母譲りなんだ。君、そういうの弱いでしょ?」
「……弱い……のかな。そんなつもりないけど。相手によるし、嘘泣きなら分かるよ」
「ホントに弱ければ、もっと早く君を落とせた?」
「まあね。でも、龍樹さんの泣き顔には特に威力あるから……。その手はあんまり使わないで欲しいな。たまだから効くんだぜ」
「っ、い、今の涙はうれし泣きだからねっ! 勘違いしないでよ」
「わかってるよぉ」
フワリと肩に載せられた拓斗の頭の重みがまた龍樹を感激に誘う。
信号待ちの間、対向車のドライバーが目を見張ってこちらを見ていた。
甘いカップルも、男同士というだけで好奇の視線を浴びるのだ。
「……学校で苛められたって……? 水野って誰?」
「……ああ、龍樹さんが言ってたおしゃべり雀だよ。あいつ、学年一のラウドスピーカーの地位をもう確立してんだ」
「へえ……」
「俺がテクニシャンで、龍樹さんのことをよがらせてるってさ。朝からからかわれたよ」
「……本当の事じゃないか」
「どこが……?」
「僕を君以外では不能にしたもの」
「……ば、ばかっ!」
「今度、その水野って娘の前でイチャイチャしちゃおっか? つっこみ入れたくなくなるまで見せつけてやるってのは?」
「絶対やだ。本当にそんな事したら、マジで一ヶ月H無しだからね。我慢してでも実行するんだから」
「……君、その後のこと考えてる? 僕にお預け喰らわせたらどうなるか……。泣いても許して上げないからね」
自然渋滞の徐行の間に龍樹は拓斗の耳元に息を吹きかけるように囁いた。
「う……」
グッと詰まった拓斗がむくれたように言いだした。
「いいもんっ。そしたらずーっとお預けにしてやるっ」
「……本気? 君はどうしても犯されたいらしいね。そういうプレイ、してみてもいいけど。あんまり好きじゃないな」
「どうしてそうなるんだよっ?」
「君が意地悪言うからだよ。いつも僕がそれで言うこと聞くなんて思うなよ。犬扱いもあんまりされると頭に来る」
「い……犬ぅ?」
「そうだよ。頭撫でて貰うために何でも言うこときく犬。それとも鼻先にHっていう人参ぶら下げられた馬かな」
「あ………………」
小さく呟いた拓斗は頬を真っ赤にして俯いた。
甘い空気は一瞬にして寒々しく消えてしまった。
言い過ぎたなと後悔しながらも勢いで口にした本音を撤回する気にはなれなかった。
「……ごめん……」
俯いたままで呟かれた力のない声は、拓斗が自分に非があったと認めていることを示していて。
気まずい空気を回復させる間もなく車は目的地に到着してしまった。
大きな敷地を占める県立の医療センター。総合病院の他に付属の高等看護学校と、小児専門の病院、精神病院が個別の名でもって林立している。
龍樹は精神病院の玄関に向かった。
後から付いてくる拓斗が袖で顔を拭ったのを目の端に捕らえ、立ち止まった。
「拓斗……」
声をかけた途端に濡れた光を瞳に浮かべて縋るように見上げてきた拓斗を、手を差しのべて待った。
追いついた肩を抱いて素早く髪にキスした。
「つけ上がったこと言ってすまない。君に振り返ってもらえたとき、犬でもいいって思ってたのに……。だめだな、幸せに馴れて図々しい事言うなんて」
そんな囁きに拓斗は頭を振って応えた。
「……龍樹さんが怒るの無理ない。俺……、下司なことしてた。恋人になれた時点で対等だったのに……。き、嫌われちゃうね……」
「頼まれても嫌いになんてなれないね。君の素直さに、また惚れなおしたとこだ」
「何で……?」
「僕の気持ち汲み取ってくれたから謝ってくれたんだよね? そういうの、すごく嬉しい」
「え……」
「一緒に暮らしてれば良い所ばっかりみせてる訳にも行かない。我慢だけして付き合うのにも限界がある。君が嫌だなって思ったことはちゃんと教えて。直すように努力するし、僕も言わせて貰うから。話し合っていこう」
「うん……」
うんうんと何度も頷きながら、拓斗はもう一度涙を流した。
「拓斗……?」
泣き笑いの表情が、龍樹の恋心を深く突いた。
「うれしいんだ。俺……、俺が望んでたの、そういう関係だから……。ふつつか者ですが、これからもよろしくお願いします!」
ぺこりとお辞儀をした拓斗を抱き締めようと腕を回しかけ、病院の玄関前だという事を思い出して肩を抱くだけに止めた。それなのに拓斗の方が頬を擦り付けるように龍樹の胸に身を寄せて、服越しにチュッと乳首を吸った。
ズンッと股間に痛みが走って龍樹は慌てた。
「……こんな所で、そんな風に僕を刺激して……どうしようって言うの?」
「二人だけになったらしよーねって、誘ってんの!」
「う……わ……。なんか、直ぐに帰りたくなった。それとも、どこか 」
「龍樹!」
甘い会話に割り込んできた遠くからの呼び声に、龍樹の腕の中の拓斗の肩の方が強張った。
「……お母さん?」
「うん……」
「似てるね。やっぱり綺麗だ」
「そうかなぁ。若作りだとは思うけど」
駆け寄ってくる母親を眺めながら拓斗の小さな囁きに囁きでもって応えた。
さして崩れていないプロポーションの良い体をシャネルのスーツで包んだ母は、確かに四十八才には見えない。おそらく白いものが目立ち始めた髪を染めてもいるだろう。龍樹によく似た色素の薄い茶目が射抜くように真正面から拓斗に向けられていた。
迫ってくる母の前に立ちはだかるように拓斗をかばった。
「お久しぶりです」
「その子! その子が向坂君?」
「……あの……は、初めまして、向坂拓斗です」
拓斗は龍樹の影から一歩踏み出して母の前に立ち、丁寧なお辞儀をした。
間伐を入れずバチンと拓斗の頬が鳴って。
ふわりとコロンの香りが流れた。母の定番のシャネルNO.5だ。
「なにするんです!」
慌てて拓斗を掻き抱いた。
「そんなことをするために呼び出したのなら、僕等は帰ります!」
今にも自分の母親に噛みつかんばかりの龍樹を押さえるように拓斗が言いだした。
「待って! 龍樹さん、いいんだ。泉さんのお母さんなら俺を殴るの当たり前だ」
「何言ってるんだ! 当たり前なわけないだろう?」
「お、俺が泉さんにしたこと考えたら、いくら土下座しても足りないよっ」
「拓斗!」
赤い唇がクッと歪んだ。
「良い心がけだわ、向坂君。責任をとる気があるのね?」
「……はい。あの、俺の子供がいるって、本当ですか?」
「ええ。泉はそう言っています」
「正気に戻ったんですか?」
「いいえ。相変わらずよ。時折泉って言う人格が現れて話してくれるらしいの」
「子供が無事産まれたら……拓斗は引き取りたいって言ってるんです。認知して僕等で育てますよ。もちろんDNA鑑定はするけどね」
「冗談じゃないわ! 子供は桂川の子よ!」
「……跡継ぎですか? やっぱり、そんなことだと思った。いっときますがね、拓斗は僕と結婚するんです。泉と形だけの結婚をさせるつもりでしょうがそうはいかない。大体、子供なんて、一人で作れるもんじゃない。泉が誘った関係だ。そんなことで拓斗を縛るなんてとんでもないことですよ」
「バカなこと言わないで! 男同士で何が結婚ですか!」
「今度の夏休みに式を挙げます。アメリカでね。必要なら養子縁組でもしますよ」
「ゆ、許しませんっ!」
「何とでも言って下さい。僕等には関係ない。縁を切って下さっても結構ですよ。とにかく拓斗は渡さない」
「た、龍樹さんっ! お母さんにそんなこと言っちゃだめだよ!」
「あなた! そういうあなたなら分かるわね? うちの息子と別れて頂戴! こんなバカげた関係、終わりにするのよ!」
きちんとセットされた髪を振り乱すようにして縋られた拓斗は、母親の言葉を耳にする度青ざめていった。
「…………っ」
泣きそうな顔で龍樹を見上げてから拓斗の唇から漏れた台詞は。
「……嫌です」
「え?」
真剣な決意に輝く瞳で母を見据えながら、言い出した。
「お、俺にとっては馬鹿げた関係じゃない。だから……、別れるのは嫌です。すみません。俺、他のことなら努力します。でも、龍樹さんだけは……俺から奪わないで下さい。俺の……たった一人の……」
「ききたくないわ!」
突っぱねようとする母に、縋るように言い募った。
「お願いです! 俺に……龍樹さんを下さい。俺の……家族に……下さい!」
深々と頭を下げた。肩も腕も、手も足も、全てが震えていた。震えながら固まった拓斗はただただ「お願いします」と呟き続けている。
「拓斗……!」
龍樹の腕にふわりと抱き込まれた拓斗の腕が、龍樹の背に回されて。ギュッと服を掴んだ。
頭を振りながら後ずさる母を龍樹はにらみつけた。拓斗が見たこともない程の冷気を瞳に浮かべて。
拓斗は驚きと畏怖を持って龍樹の瞳を見上げた。
金色の輝きは同じなのに。龍樹がくれる温かさが特定の者だけに与えられるものだと改めて知った。
「母さん、僕たちをこれ以上いじめないで!」
低く呟かれたはずの声はじんわり浸透するように遠くまで響く。
「何を子供みたいな事を……!」
ビクッと更に後ずさりながら叫ぶ母を威嚇するように睨み付け、次の瞬間泣きそうな歪め方で微笑んだ。
「子供の時は母さん達の人形だった。だから、独りぼっちだって平気だったけど……。今は違う。僕はね、人間なんだ! 拓斗がいないと生きていけない人間なんです!」
周りに人垣が出来始めた。病院の玄関前での修羅場では当然の成りゆきだが。龍樹も拓斗も世間体など頭から吹き飛んでいたのだ。
「拓斗はね、僕が唯一どんなことをしてでも手に入れたいと思った人でした。そんな彼がこんな風に言ってくれた。この奇跡が理解できますか? 僕は、この幸せを守るためなら悪魔に魂を売ってもいい。邪魔をするなら母さんだって許しません。僕の幸せを取り上げないで下さい!」
「龍樹…………」
母だけが周りの視線に貫かれる痛みを意識していた。
「……後で話し合いましょう」
「ええ、必要は感じませんが、見せ物になるつもりは僕等もありませんから」
「あの、泉さんは……」
おずおずと口をはさんできた拓斗を母が睨み付けた。ビクンと肩をそびやかせた彼はそっと龍樹に身を寄せた。
「泉が先でしょう!」
拓斗の腰に手を回した龍樹は有無をいわさぬ調子で母を促した。
「……何があったんです? 今更泉に何が……?」
隣接の総合病院に移送され、監視装置を付けた泉の姿を見つめながら龍樹が呟いた。
「泉じゃない人格が突然現れてお腹を拳で叩きだしたそうよ。取り押さえた手を振りきって部屋を飛び出したあげく、階段下にダイビング。殺してやるって叫き続けてたって……」
「……なんて、名乗ってましたって?」
「タツキ……だそうよ」
ちらりと横目で龍樹を眺め、強張った顔つきで母は呟いた。
龍樹は大きく溜め息をついた。
「泉の中で、僕はとことん悪者なんだなぁ……。お腹の子が拓斗のだから、タツキには許せないって事だよな」
「龍樹さん……」
拓斗の手がギュッと龍樹の手を握りしめた。
心配するなと握り返しながら、母を覗き込む。
「どうして僕等を呼んだんです? 僕等が知れば、騒ぎになるだけなのに……」
「生まれるまで内緒にしておけばよかったかしらね……。でも、死ぬかもしれないって思ったら……向坂君にも知る権利あるって思ったのよ」
本気の台詞だというのは目の色で分かった。
母の表情を龍樹は意外な面もちで見つめた。
いつだって形にこだわる母だった。世間体、見栄えの良さ、自分の都合。
「……あなたからそんな言葉聞けるとは思わなかったな……」
「鬼か蛇でも見るみたいな目で見るのね。私はあなたの母親なのよ?」
「あなたは全然分かってない。僕が、泉が、何をどう幸せに思うかなんて全然……。自分の都合を押しつけるだけだった……」
「……そんな風に……思っていたの? 私は……」
「お前のために! 聞き飽きました。大体、泉の子供だって、跡継ぎ欲しさにおろさせなかったんでしょう? まともじゃない状態の泉に子供を産ませたって、まともな子育てなんて出来やしないでしょうに」
「だって孫なのよ! この後望めないかもしれないのにっ。……私が育てればいいことでしょう?」
「何も分からないうちに型に填めて育てる気かも知れないけど。ロボットじゃないんだ。心がね、枠を拒否するんですよ。泉の子供だっていつか僕みたいに崩れるんだ! あんたに子育てなんて出来やしない!」
パンと頬がなって痛みが走った。
拓斗の腕が振り下ろされたままフルフルと震えていた。
「拓斗……?」
龍樹を睨み付けるように見上げていた拓斗の表情が泣き顔に崩れていく。
「だめだ……お母さんにそんな風に言っちゃ……いけないよ。俺の子供なんだよ。おろさせないでくれて良かったと思う。そんなこと言う龍樹さんは……俺……俺……」
拓斗は家族を事故でなくしたばかり。なくして解ることがあるんだとその瞳が泣いている。
「拓斗……帰ろう。母さん、話し合いは後日また。あの様子じゃ、何とかもちなおしたみたいだし……。ただ……泉のためにも、思惑抜きで子供のこと、考えて欲しい。お願いだから……」
言うだけ言って拓斗を抱えて逃げ出すように病院を出た。
叩かれた頬がずきずきと痛む。
拓斗の手形が赤く浮かび上がっているだろう頬に意識を半分とられながら、残り半分でどう拓斗との間を修復しようかと思いを巡らしていた。きっかけとなる第一声の言葉を選ぶのに、頭の中で瞬時にシュミレーションしてみたが。結局は正直な気持ちで臨んだ。
車の前で拓斗の腕を掴んで。
「拓斗……僕を嫌いにならないで」
「龍樹さん?」
「つい、逆上しちゃったんだ。すまない。僕は……ぼ……」
「俺こそごめん。殴っちゃって……」
拓斗の指先が頬を撫でた。
ポロポロと指に絡む滴が自分の涙だと気づく前にその指を口に含んでいた。
塩辛さを吸い出しながら唇に柔らかな掌を押しつけた。
「君に嫌われたくないんだ。子供だって死んだ方がいいなんて思ってない。本当だよ……」
「龍樹さんの家のこと知らないのに余計なこと言って……ごめん」
人目もはばからずに拓斗が龍樹の腰に腕を絡ませて抱き締めてきた。
「龍樹さんを泣かせるつもりじゃなかった。ただ……」
拓斗の温もりに触れる度、不安や辛さが抜けていく。
「親の替えはきかないって、分かってる。母さんが君を殴ったあたりでもう、僕はおかしくなってたんだよな……。あの人は、自分の価値観を押しつけてくるから……」
「俺達のこと馬鹿げた関係だって言っちゃえるみたいに?」
「ああ。すまなかった。君にも嫌な思いさせたね」
「……いや。ああ言われるのは覚悟してたから。あんな事でもないと言えなかったこと言えてよかった。だから……お母さんにも感謝してる。俺、ちゃんと挨拶できたよね?」
「うん。立派だった。僕にとっては最高の挨拶だ。こんなに幸せで良いんだろかって思うほど……」
拓斗の柔らかく張りのある唇を貪りながら、龍樹はその日を過ごす場所を検索していた。実家に電話番号を知られている家には帰りたくなかった。
図らずもしてくれた結婚宣言に対する喜びを拓斗に全て注ぎ込まなければ気が済まない。
「行こう、どこか……。どこでもいい……、二人きりになれるとこ。今すぐ欲しいんだ」
「うん、連れてって。俺も……欲しい!」
熱く応えながら囁く拓斗を抱き締めてから、もどかしい気持ちで車に乗り込んだ。
駐車場を出てコルベットを走らせながら、いっそのこと人気のない暗がりで致してしまおうかと思ったほどである。
国道を繁華街の方に向かった。恥ずかしがりの拓斗の好みを考えれば最中に人目を気にするところだけは避けたい。桜木町のホテルを目指した。人混みの多さが二人を隠してくれる。観光客も多いから、男同士で泊まってもさほど目立たない。
「ロイヤルパークホテルニッコーの電話番号しらべて」
「え?」
「ホテル、泊まろう。外から予約入れた方がトラブルないから。電話かけて」
「あ……うん」
「桂川で二人予約して。駐車場もね」
「うん……」
ランドマークタワーの名で親しまれる七十階の高層ビルにそのホテルはある。
ショッピングモールと最上階の展望台まで直通のエレベーターが観光客を呼んでいる。
ロケーションよりも出入りの便利さにそのホテルを選んだ。食事はメインダイニングを予約しようか、モールの中の店を選ぼうか。最近では他のホテルやショッピングアーケードもできて選択の幅は広い。
いや。
やはりルームサービスだ。出歩く時間さえ惜しい気がした。
「ツインの部屋はエグゼクティブルームしか空いてないって。ダブルってどうしても言えなかった。……ごめん」
無事予約を取り終えて携帯電話を切った拓斗のすまなそうな顔を横目で見てクスッと笑った。
「OKだよ。兄弟でダブルは変だもの」
「兄弟?」
「うん、同じ姓で泊まればそう思うのが普通じゃない? すぐホモだって思う方が変だもの」
「俺達似てないのに」
「造り似てなくても腹違いとかあるじゃないか。同じ姓で宿帳書くのは昔からよくある手でしょ。不倫のカップルよりよっぽど普通に見えると思うよ」
「……バレるとしたら態度で……かな」
「うん、そうだね」
言いながら空いている手を拓斗の内股に伸ばした。ふわりと撫でた途端にびくんと身体をしならせた。
「部屋で二人きりになるまでは勃たないように抑えとかなきゃね」
ブッと吹いて拓斗が笑った。身をよじらせ、劣情に燃えた手を避けて。
「龍樹さんのスケベ!」
「食事はルームサービス。気分が治まって余力があったらバーで飲みながら夜景を楽しもう」
「夜景なんてどうでもいい。龍樹さんと気兼ねなくイチャつける所にいたいな。今日はそのつもりで早引けしてきたんだもん」
「ああ……。そうだっけ。嬉しかったんだけど、君らしくないことを……って思ったんだ。そんなに苛められたの?」
「ううん。ただ、俺……。最近態度悪かったなって……反省したんだ。水野があることないこと言いふらして、やな気分なのは本当だけど……。龍樹さんに八つ当たりするのはよくないって……。そう思って……」
「苛められたってのは……過剰表現だったって事?」
「うん……。甘えたかっただけ」
龍樹は車を降りながら微笑みかけた拓斗を恨めしく思った。
ベルボーイに車のキーを預け、肩に回したい腕を握りしめたままフロントに向かった。
案内された部屋のドアが閉まった途端。
言葉は全て吐息に変わった。
互いの高まりは互いを煽り続ける。
拓斗の熱さに龍樹は歓喜の唸りを上げた。
「獣くさいよぉ、その声」
「嫌い?」
「好き。俺も獣になれる声だもの。大好き!」
拓斗は執拗な愛撫を繰り返し、龍樹の身体に腕や脚を絡ませてくる。
互いに積極的になりすぎて、まるでプロレスの技を掛け合っているかのようにベッドを転げ回った。しまいにはキスをしながら床にずり落ち、固い絨毯の上で何度も行為した。
インターバルの間に気怠げに寝返りを打った拓斗が、
「ヤバ……絨毯染みだらけ。クリーニング代請求されるかな」
……などと恥ずかしい染みを指でなぞりながら心配そうに呟いた。
「蛋白分解酵素剤の洗剤、まいとこうかな」
「んなもんまで持ち歩いてるの?」
「車に……。血液汚れを落とす医療用だけど、結構便利だからこの間手伝いに行ったとき一瓶もらっといたんだ。出すの忘れてたからまだあると思う。蛋白汚れには滅法強いよ」
「龍樹さんて、何でもありの人だね」
「そうでもないさ。出来るだけ君の希望に添いたいだけ」
「じゃ……キスしたい」
両手を差しのべて誘う拓斗の可愛らしさにグラリと来た。
誘われるまま夢遊病者のように腕の中に割って入り、彼の身体を抱き起こした。
「ん…………」
クチュクチュと貪り合って陶酔の海にいた二人だが、キュルルルという腹の音で我に返った。
「あ……」
頬を染めて俯く拓斗の肩にキスしながら龍樹は自分の空腹も確認していた。
なんだかんだで昼を抜いてしまったのだ。
「お腹……空いたね。ルームサービス、何頼もうか?」
慌てて拓斗が頭を振った。
「……外行こう。ここに誰も来て欲しくないよ。匂いで分かっちゃう」
「だって……大丈夫?」
「うん」
「じゃ、シャワー浴びようね。洗ってあげる」
頷くだけの返事をして龍樹の誘導に従った。
二人裸のままで手を繋いだ短い道行きに龍樹の心は躍る。
龍樹がいくら望んでも、行為の後始末をなかなか手伝わせなかった拓斗が、初めて素直に従ってくれた。
今日はどんなことをしてもOKなのだろうか?
嬉しさと訝しさの間で迷いながらも龍樹は己の欲望に従うことにした。
「あ……んんっ」
バスタブの中で熱い雨を浴びながら、龍樹の指に翻弄されるように呻く拓斗を抱き支えた。
自分が埋め込んだものを排泄させる。龍樹にとっては立派な後戯である。だが、それは同時に前戯に転じてしまうのだ。恥じらいを含んだ拓斗の甘い呻きが新たな行為を誘ってしまうため、拓斗は尚更のように拒絶を強めるのが常だった。
「キスだけ。キスだけだから……。食事が先だものね」
囁きながら拓斗を貪る。
「和食と……フランス料理、イタリアン、中華……何がいい?」
「……何でもいい。龍樹さんとなら何でも……」
「観光客っぽく、ハードロックカフェなんかどう? それとも……」
「ハンバーガー……いいかも」
「じゃ、ゆっくり支度してて。車から薬出してくる。それから出発しよ」
「うん……」
バスタブに拓斗を残して、龍樹は身支度すると駐車場に向かった。
名前の通りにがんがんとロックのリズムが充満した店内で、付け合わせのポテトとサラダたっぷりのハンバーガーを頬張る拓斗を幸せな気分で見つめる。
「本場だと、これより量多いんだよ。それに安い」
「あ、聞いたことある。別々にポテト頼んだりして失敗するんだよね。食べきれなくてさ」
「うん。最近は忠告してくれるウエイトレスも多いから、だいぶそういうミスは減ったらしいけど」
「感覚違うからしょうがないよね。やっぱりこっちのマクドのイメージで頼んじゃうもん」
「ドイツなんて、ハンブルグステーキって言ったら生で来るからね。ウェルダンでよく焼いてって頼まないと生の挽き肉食べなきゃならなくなる」
「俺は食べてみたいな、そういうのも。郷に入りては郷に従えってさ、言うじゃない?」
「冒険家だね」
「怖いもの知らずってか?」
「柔軟性があってよろしい。知り合いの旦那に、とにかくお母さんが作った味じゃないと不味くて食べられない奴がいてさ。ケーキにラム酒使ってもダメなんだ。変な味がするとか言われちゃう」
「じゃ、お店のケーキ食えないじゃん」
「うん、香辛料とかも香りの強いのダメなんだって。「変な味」の一言でかたずけられちゃうんだ。新婚旅行でジャマイカ行ってさ。ラム酒が特産だろ? 使われた料理の種類も多くて文句ぶーぶー。奥さんが帰ってきてから愚痴りまくり」
「あはは。もしかしてアジア系の旅行全滅だよね。カレーも、インド料理屋のはダメで、蕎麦屋のやつなら食えるって感じ?」
「そんなところ。本格レシピ通りだと不味いって言われるって」
「そういう味なんだって割り切れないわけだね。ま、楽しみは一寸減るけど、いいんじゃない? 奥さんが作った物食べるなら」
「うん。食べるなら心配ないんだけどね……」
「それより、その奥さん、龍樹さんとどういう関係? 女の人だろ?」
「看護婦。外科の」
「俺が逢ったことある人?」
「いや、あの人の前の人。結婚して辞めたんだよ。僕と同い年で、紫関と同級だった。僕と入れ違いのタイミングだったから、二、三日一緒に仕事したきり。紫関が同窓会で会ったとき聞いた話。……妬いてたりする?」
「正体が分かれば妬かない。龍樹さんは俺のものだもん。……その旦那のほうと友達なら……妬いちゃうかも」
「拓斗……」
熱を帯びた視線に拓斗は慌てた。食事だけはゆっくり済ませたいものだから。
「ね、食べ終えたら買い物……したいんだけど」
即座に部屋に戻ろうと言い出しかねない気配の龍樹を抑えるつもりでそう言った。
「いいけど……」
拓斗の意図を見抜いたがために少々ふくれて龍樹が答えた。
「何買うの? 普通の店は閉まるの早いよ」
「後二時間ある。簡単な着替え、欲しいんだ」
「ああ。そうだな。いいよ」
龍樹はすぐに気分を切り替えて微笑んだ。
二人ですることなら何でも楽しい。拓斗とショッピング。まさにデートだ。恥ずかしがりの拓斗からの誘いは珍しい。
「君に似合う服……探そう」
「龍樹さんのもね。俺、さっき歩いてるとき、龍樹さんに着て貰いたいやつ見かけたんだ」
「君の見立て? 嬉しいな」
そう、頭の中で自分を思い浮かべて貰えるというだけで嬉しい。
しかし、あんまり幸せを感じていると、運命の女神のへそを曲げさせるサインが出てしまうらしい。
ふと目を遣った入り口にその顔を見つけて。驚きに声無き叫びをあげ、顔を背けた。
何でこんな所で!
いや、そんなことより、どうやって彼に気づかれずに拓斗をここから連れ出すか……。
「……どしたの?」
「あ、いや。買い物いこう。待って、その前に水飲んでから」
「龍樹さんたら……急に変だよ」
奴が席に案内されたら入れ違いに出てしまおう。
そんな風にタイミングを計っていたら。
「タツキ! こんな所で会えるなんて!」
低くマイルドな響きの声が英語で背後から降りかかってきた。
振り返らなくても分かる。声の主はスティーブ。
シリコンバレーに本拠地があるMS社の会長。
(ウエイターのバカ野郎。何もこっち側に案内しなくてもっ!)
胸の内で何度も舌打ちしながら驚きを装って振り返った。
スティーブは連れの男たちを手で追い払うと、嬉しそうに龍樹に駆け寄った。
「僕のオリエンタルドラゴン。元気だった? 電話しても留守だし、会えないかと思ってたのに……やっぱり僕等には縁があるんだね」
甘い調子で囁いてきながらキスしようとするスティーブを押し返した。
「ス、スティーブ! ちょっと待て!」
横目で拓斗を伺う。
黒目がちの大きな瞳を更に見開いて見つめていた。程良い赤味の、ふっくら形のよい唇がぼんやりと開かれて、龍樹と視線が合った瞬間にへの字にひき結ばれた。
「龍樹さん、その人誰?」
低く放たれた拓斗の声に龍樹はギクリとした。聞いたことがないほど機嫌の悪い声。嫉妬と怒りであふれんばかり。
「あ、スティーブだよ。スティーブ・ヒクソン。ほら、コルベットの……」
ドキドキしながら拓斗を見守った。
コルベットの、といったところで賭の相手だというのを察した拓斗の目は、スティーブの観察に移った。
若々しい精悍な顔立ちを鼈甲縁の眼鏡で柔らかくしたスティーブは、ラフなポロシャツとスラックスを見栄えよく着込むことで細身の長身を強調している。キレのよいフランクな視線が龍樹の視線を追うようにしてちらりと拓斗に向けられた。
「可愛いな。弟?」
甘い眼差しは全て龍樹のために使いたいというように視線はすぐに龍樹に移された。
龍樹は拓斗の肩を抱いてスティーブの前に押し出した。
「スティーブ、彼は拓斗。僕のライフパートナーで……」
「ライフ……パートナー?」
凍り付いたまま、もう一度ゆっくりと拓斗に目を向けた。
途端に拓斗との間に火花が散る。拓斗には龍樹をめぐって真っ向から戦う意志があるらしい。闘争心に燃える瞳でスティーブと睨み合いを続ける拓斗を、場違いな幸福感に襲われてうっとりと見つめてしまった。
「一年近くかけて口説き落としたんだ。僕のハニーでダーリン」
英語での説明だが、ハニーだのダーリンだのは早口でも分かったらしく拓斗が途端に赤面した。
「ふ……うん……。ヨロシク、タクト」
気前良く握手の手を差しだしたスティーブにホッとする。
取りあえず握手。
龍樹の紹介のしかたでは既に勝敗は決まってしまっている。闘争心よりも勝利の優越感を瞳に浮かべた拓斗が余裕の微笑みを向けてきた。
「龍樹さん、もう少し話あるでしょ? 俺、買い物一人でも出来るから。先、部屋に帰ってるね」
「た、拓斗っ?」
慌てて引き留めた腕を払われて、拓斗がまだ怒っていることを悟った。許しを得るための手だてを咄嗟に思いつけず、立ちすくんで。
泣き出しそうな龍樹を、拓斗は瞳を微笑ませて見上げてきた。
「あの人、アメリカから来たんだろう? 旅行客には優しくしてあげなきゃ。少しだけ、龍樹さんを貸してあげるんだ。そのかわり午前様なんかになったら婚約解消だからね」
ひっそり囁きながら龍樹の耳たぶをきゅっと抓って。
スティーブに会釈して店を出ていった。
出た途端に駆け足になった拓斗の背中は泣いているように見えた。
(これは拓斗のテストだ)
慌てて後を追おうとした龍樹の腕をスティーブが掴んだ。
「もう少し説明が聞きたいね。ドラゴンが火蜥蜴(サラマンダー)になった経緯を」
人の波を縫うように走り去った拓斗はすぐに見えなくなったので、龍樹は溜め息をついて座り直した。
ウエイターにビールとレアのハンバーガーを注文してスティーブが見つめてきた。
「口説き落としたって言ったね? 彼、ストレートだったの?」
「うん。でも、結婚してくれるって」
「頬赤らめて言うなよ。……ストレートの男がよく受け入れてくれたね」
「泣き落とした。形振り構わず追いかけて」
スティーブが大きく目を見開いた。
「君が? 信じられない」
「僕だって……。でも、どんな事してでも手に入れたかった」
「どこがそんなに良いの?」
「説明が難しい。ただ……」
「ただ?」
「心から安らげるのは、拓斗の側にいるときだけ」
拓斗を思うだけで温かい気分に包まれる。それを安らぎと表現してみてそうなんだと自覚した。
「ストレートの男が本気で君を受け入れたと思う? 君の財産目当てなんじゃないの?」
彼の環境では当然の危惧を口にしたスティーブにフッと笑って見せた。
「それはないよ。彼は僕の財産なんてよく知らないもの。喫茶店やってる変な元医者って程度。金で僕を買おうとした君が言う台詞じゃないでしょう?」
「あ、やっぱりそんな風に思ってたんだ。君と同じで、どんな事してでも手に入れたかっただけだよ」
「ずっと変だと思ってた。あの賭けで君に勝てたのだってやらせだったような気がする……」
「考えすぎ。君は自分の能力を過小評価している。ま、僕にとっては負けても勝っても得になる賭けだった事は認めよう。あんな車一台では買えないくらい良いプログラムが出来た。君に月一万ドルのパテント料払ってもあまりある儲けをさせて貰ってる。十分元は取れたよ。勝てばそれに君との甘い休暇旅行が加わったんだよね……ちょっと残念」
切ない微笑みがテニス焼けした精悍な顔立ちに浮かんだ。
少しだけ胸の痛みを感じたが、それだけだった。
セックスフレンドよりは恋人に近かったが、恋愛ゲームの様相が強かった二人である。未練を残した方が負け。龍樹は常に勝者だった。
話題を変えて、出会いと別れを繰り返す知人達の話を聞きながら、サイクルの早さに苦笑した。
自分には耐えられない。心を預けるほどに惚れ込んだら、龍樹と遊んでいた者たちのような浮気の仕方をされたとき、相手を殺してしまうかも知れない。きっと、龍樹の束縛の仕方は彼らとしても歓迎できないだろう。
スティーブは彼らと同じ人種だった。
龍樹に惚れていると言いながら、何人もつまみ食いした。
金払いがいいから、食い詰めた美少年達なら簡単に食い放題だったのだ。
龍樹には忠誠を要求しながら。
龍樹が恋愛の形態をとりたがらなかったのは、怖かったからかもしれない。
独占欲も嫉妬深さも、人一倍の自分を全開にしたとき、遊び相手達はみんな退いてしまうだろう。そうやって、心を返して貰えずに置き去りにされるのが怖かったのだ。
「本気になったら、僕はとっても独占欲が強いんだ。君にはとても耐えられないと思うよ。僕は僕だけの恋人を手に入れる事が出来て、初めて本当の恋を知ったんだ。苦しくて、辛いけど、ものすごく幸せ……」
うっとり呟かれて、スティーブは苦笑を浮かべた。
「君はみんなのあこがれだった。文武両道、強くて切れるオリエンタルドラゴン……。あのタクトはやっぱりドラゴンかい?」
「どっちかというと猫……かな。僕を振り回す気まぐれさは心地良いほどだよ」
「メロメロだね」
「うん……。情けない程ね。ドラゴンじゃなくて、犬なんだ。今の僕は完全に犬」
「君とやり直したくて横浜まで足のばしたんだけど……。諦めないとだめかな……やっぱり」
「そうしてくれるとありがたい」
握手してさようなら。
別れた背中にスティーブの声がかかってきた。
「タツキ、それでも君を愛してる。犬に飽きたら電話して」
龍樹は返事をしなかった。
振り返らず、手も振らず、拓斗の元に走った。
在室をフロントで確認する。
部屋の呼び鈴を鳴らした。
そっと開けられたドアの中に滑り込んだ途端に拓斗がしがみついてきた。
「遅いよっ。待ちくたびれちゃったじゃないか」
「……泣いてるの……?」
暗くした部屋の中で表情は読みとりにくくなっていたが、涙声がそれと教えた。
「君が相手しろって言ったのに……」
「二時間もなんて言ってないもん。あのかっこいい人、龍樹さんの何? 俺のこと睨んでたよ。ライフパートナーって紹介された途端に……」
拗ねた声を愛しく感じて髪にキスして。拓斗の腰を抱きながらソファに移動して座った。膝の上に抱き上げた恋人の感触を楽しみながら、手に入れた奇跡に改めて感謝の念を覚える。
(ふっくらした敏感な唇も、力強くしなやかな舌も、敏捷で温かいこの体も全ては今、僕のもの)
クチュクチュとめいっぱい味わいながら、拓斗の質問の答えを呟いた。
「……MS社の会長……。スティーブ・ヒクソン……聞いたこと無い?」
聞いた途端にキスを中断した拓斗の目がまん丸になった。
MS社は拓斗の父親が勤務していた会社。アメリカのコンピューターソフト会社では草分け的な存在である。
ヒクソンが学生時代に興した会社が成長して、世界的な億万長者を作った。その名前は日本でも知れ渡っている。
「あ……まさかねって思って……。あんな若いのに?」
「若いって言っても……えーと、三十は越えてるんじゃないかな。あるゲイのカップルの結婚式で知り合った。そういう所って出会いの場所でね。半年ぐらい……付き合ったかな。あの通り若々しくて頭も切れる男だから結構面白かったんだけど、つまみ食いが好きな男でね」
「……コルベット賭けた相手……でしょ? どんな賭けだったの?」
「冗談だと思ってたんだけど、プログラミングの勝負。一ヶ月で一本、ソフト開発して、どっちがより良い物かで勝ち負け決めて。もちろん誰の手も借りないでだよ」
MS社でも売れ筋の有名ソフトの名をあげると、拓斗の目は更に大きく見開かれた。
「あれ……龍樹さんが作ったの?」
「……内緒だよ。著作権はMS社に帰属させてあるし。大体、遊び半分で作りはじめた物だもの。商品化するに当たっては、いろんな人の手が加えられてる……」
「もしあの人が勝ってたら……?」
「一週間旅行に付き合うって事になってた。その間僕は彼の奴隷。かしずく相手は選びたいじゃない? だからどうしても勝たなきゃいけなかった。後半は死にものぐるいって所」
「龍樹さんのことオリエンタル・ドラゴンて呼んでたね」
「僕の名前がドラゴンて書くって教えたし。拳法やってたのも知ってるから、ブルース・リーと重ねたんじゃないかな」
「今は俺のドラゴン……?」
拓斗がまた龍樹の耳たぶを愛撫し始めた。龍樹の感じるスポットを拓斗が頭に入れているのだというだけで喜びが倍増しになる。愛されている、関心を持たれているのだと思えるから。
「うん。君だけのだよ。君になら無条件でかしずいてもいい」
甘い口調で囁けば、拓斗は真顔になって見返してくる。
「……止めてよ。家族はかしずいたりしないよ」
「君ならそう言うと思った」
クスクス笑いを漏らしながら龍樹は拓斗のシャツの中に手を入れて撫で始めた。
「だめ。あいつを触った手でさわんないでよ」
拗ねた口調で軽く手を押しのけられた。ジンと下半身に熱が走る。
「握手しただけだよ。君だって握手……したでしょ?」
「やだったら……」
拒絶の口調とは裏腹にしがみついてくる拓斗を抱き締めて。既にはち切れんばかりに張りつめた勃起に彼の手を導いて囁いた。
「僕をこんな風にするのは君だけ……。君を待たせた二時間分……、取り戻したい」
「うんと気持ちよくしてくれなきゃヤだからね」
「仰せの通りに……」
腰が砕けそうになっても欲しくなる。性欲の範疇では語れない欲情に支配されながら拓斗を抱いた。
常になく積極的な拓斗に煽られ翻弄されながら、龍樹は胸の内で眉根を寄せていた。
拓斗がまた何か考えている。余計なことを悩みに持たれるとまた……。
そんな不安が更に激しく龍樹を煽った。
過去の自分が何度も、この本気の恋を邪魔しに現れる。自業自得だから仕方ないとはいえ、信じて貰えない苦しさはもう味わいたくはなかった。
「ねぇ……今の僕を見て。君のドラゴンになった僕だけを……見て」
拓斗の長くすんなりした脚を抱えて突き上げながら譫言のように囁いた。
ルームサービスの朝食を楽しみながら、龍樹は恋人を観察した。
狂おしく熱い夜を過ごした後。
いつもの朝のようにあっけらかんとした表情で食事している。
それなのに、胸騒ぎが龍樹を支配していたのだ。
嘘がつけない拓斗でも、全力で嘘をつくときがあると知っている。
拓斗の家族の通夜の時、龍樹は見事に騙された。龍樹の希望的観測が見誤らせたのかもしれないが、拓斗が心の中で何を疑おうと、それを知られたくないと思うなら嘘の表情も作れるのだ。
「……パスポート、いつ取りにいくんだっけ?」
突然の質問に頭の中で記憶を検索するように天井に目を向けた拓斗が、真顔になって龍樹を注視した。
「急に何? もしかして俺が迷ってると思ってるとか?」
「……そうじゃないけど……」
そうなのだ。
「……丁度今日。帰りに寄ってくれる? ここからすぐだし」
「いいよ。学校は?」
「午前中は休講。……あの人……式に喚んだの?」
やはりスティーブのことを気にしている。信じてくれとしか言えない今、それこそ拓斗を信じるしかなく。龍樹は胸の内で溜息をついた。
「いや。言わなかった。邪魔されるといやだから」
ふうんと頬杖をついたまま言う拓斗の、浮かない表情が不安をあおる。
「拓斗……」
「なんだよ?」
「いいのかな……?」
「なにが?」
「結婚……。後悔、しない?」
「しないつもりだけど……? 何だ、迷ってるの、龍樹さんの方?」
「だって、普通じゃないことだもの。君をそんな道に誘って……僕ってホント悪魔みたいだよね。学校で嫌な目に遭って、やっぱり止そうなんて、考えなかった?」
「今しか考えないことにしたんだ。今は龍樹さんしかいない。一緒にいたい。結婚もしたい。だから……」
「……怖いんだ。君がそんな風に言ってくれる度、君を不幸にしてしまうかもって怖い……」
肩を落として溜息をついた拓斗の瞳は、あきれながらも愛おしそうに優しく龍樹を見つめた。
「今更だよ。もう、後戻りできない。止まれない。不幸も幸せも自分次第。結婚だって、俺達日本人には法的拘束力はない。自分自身のけじめだろ? 俺は龍樹さんだけって決めたから結婚の形を取る。……決めるの早すぎた?」
「……僕は君を縛りたかった。そうだよ、君の嫌いな束縛のために結婚なんて……。スティーブがね、僕を金で買おうとしたから別れたんだけど……。どんな事してでも手に入れたかっただけだって。僕と同じだって……言われた。僕は君にスティーブと同じ事しようとしてるんだ……」
「そうなの? 同じ? 違うでしょ? 俺だって縛ろうとしてるんだよ。龍樹さん、俺に縛られるの耐えられない?」
ぶんぶんと首を横に振った。焼き餅も、束縛も心地よい。拓斗にされるなら大歓迎。
「でも、君は縛られたくないって」
「龍樹さんが全然焼き餅焼かなくなったら寂しいよ。俺……あの人よりも龍樹さんに愛されてるよね?」
「比較なんてしないでよ。僕が本気で欲しくて口説き落とすのに必死になったの、君だけなんだ。だから……今頃スティーブの気持ちも理解できた」
「……理解するのはいいとして、より戻そうなんてしたら赦さないからね」
「あり得ない」
「じゃあ、躊躇わずに行こうよ。結婚式と新婚旅行。これでも楽しみにしてるんだぜ」
龍樹はすうっと目を閉じて深呼吸した。
どこまで舞い上がってしまうか分からない。拓斗の真剣な口調が嬉しくて、胸からキュンと痛みが走ったのだ。全身の血流がランダムに方向を変えてしまったような気分。
「……朝から……あんまり刺激しないでよ。もうチェックアウトしなきゃいけないのに……」
ちらりと時計に目を遣って拓斗の腰に手を回した。
一度くらいなら……。
拓斗の手がキスをしかけて近づいてきた龍樹の唇を押し戻した。
「夜までお預け」
「クウウン……」
悲しい犬の鳴き声をまねてみせる。
「龍樹さんたら、もうっ……」
愛しげな眼差しを与えられた犬は元気を取り戻して恋人の鼻先をぺろんとなめた。
「うわっ」
真っ赤になって仰け反った拓斗を、大人の顔で見下ろして。
「帰り支度、始めよう」
余裕の声で囁いた。
「向坂、昨日は何だったんだ?」
三限の講義が終わった途端に笹沢がくいついてきた。
「……家族サービス。ってことにしといてくれよ」
途端にハアン、という顔で笹沢が拓斗の首をつついた。
「一日かけて痕付けまくったか」
「げ、見える?」
「嘘。お前、ホントに引っかかりやすいな」
「この野郎……」
赤面するのを止められずに力無く呟いた。そんな拓斗の表情を笹沢が冷たく見える眼鏡の奥で甘い光を浮かべて見つめているのに気づかないまま。
笹沢はやがて苦笑に顔を歪め、拓斗の頭を小突いた。
「悪く思うなよ。何時までもそんなだと水野につっこまれ放題だと思ってさ」
「やっぱり? 俺、馬鹿なんだなぁ」
「馬鹿?」
「高校ん時の友達によく言われたんだ。バーカ、やっぱ向坂だなーってさ」
「……馬鹿正直の馬鹿。開けっ広げって言うか。すれて無いって言うか……。うらやましいって意味で言ってるみたいな台詞だな」
「うらやましい?」
「向坂は信じやすい。相手の言葉を真剣にとらえて本気で対応するばっかりだから、翻弄されやすいし馬鹿を見る。それって、向坂がそれだけ幸福な家庭で育ったって証拠。人を見たら疑ってかかれってよく言うでしょ。そういう必要のない家庭で庇護を受けて育ったから、自分に害をもたらす人間がいるなんて思わないんだよなぁ」
「俺、結構疑り深いけど」
「じゃあ、警戒心が不足してるんだ。奥さんが心配して待ち伏せまでする気持ち、ちょっと解るな」
「……奥さんっての、止めろよ。信じなきゃ何にも始まらないじゃないか。結果やばいことになっても、出来れば俺、信じることは止めたくないんだ。人の善意って信じたい。見返りを期待しなければ、結構馬鹿でも生きていけるんだから」
「……そう言って、ずっと一人なんだ」
「え?」
「期待しないって事は、その相手を信じてないって事だよ。逆に」
「そう……なるのかな?」
笹沢の言葉は拓斗の胸に大きな抉り傷を作った。自分の足下が崩れ落ちていくようなおぼつかない気分。
しゅんとうなだれて考え込んでしまった拓斗の背中をバンッとたたいて、笹沢は笑った。
「ほら、また真剣に受け取る!」
「……んなこと言ったって…………」
笹沢の声音は確かに真剣な響きを持っていた。冗談になっていない言葉だ。
以前に、高校の友人の畑山にも、突っ張っていると言われた。
普通に生きているつもりなのに、端からそう見えるのだろうか。
頭の端に引っかかった思いに集中力を奪われたまま、一日をやり過ごして帰宅した。
「トラジャを切らしてるからご機嫌ブレンドでいい?」
「憂鬱そうに見える?」
「うん」
「龍樹さんは、俺が突っ張ってるって感じる?」
「……いや。今は感じない」
「今は……か……」
ふうと溜息をつき、コーヒーを一気飲みすると話は棚上げにしてエプロンを付けた。
「……確かに君は人を踏み込ませないところがあるね。僕としてはその方が君を独占できてうれしいけど」
閉店後。後かたづけをしながら、笹沢に言われた一部始終を聞かせた第一声がそれだった。
「……柏木先生に、君が僕には甘えた表情を見せるって言われたとき、すごくうれしかったんだ」
「……先生が?」
水切りの終わった食器を拭きながら戸棚に戻す。家事は分担という約束だったはずが、どうしても龍樹の負担となってしまう日常で、拓斗が出来る手伝いは休日の掃除と後かたづけくらいなのだ。
「……君は諦めが入ってる子供だったからって。何も期待しなければよけいに悲しい思いをしなくてすむって、自己防衛の規制だろ?」
「今は意識的にやってないんだけど。俺、いつも置いてきぼりだったからさ。サヨナラする度、少しずつどこかが凍り付いていったんだと思う。……患者時代のこと……龍樹さんに話してたんだ。そっか……」
くつろぐべき時間を寄り添うように立って過ごした龍樹の腕が拓斗の腰に絡まった。
「君がいろいろ僕に期待してくれるとうれしい……。僕が一方的に甘えるんじゃ、愛想尽かされそうで怖いもの」
髪に頬刷りしながら呟かれて、気分もくすぐったいままクスリと笑った。
「……これ以上わがままになっていいの?」
「浮気さえしなければ、もっともっとわがまま言ってくれてOK」
「……じゃあ、さっそく」
言いながらちらっと見上げてみれば、大まじめで次の言葉を待つ龍樹と目が合ってしまい、プッと吹きだした。
「明日の朝食はパンケーキとココット卵。ビジソワーズスープつけて欲しいな」
何だそんなこと? と言うように肩を落として溜息をついた。
「フルーツと海草サラダもつけよう」
「うん。それとね」
「なんだい?」
「背中流して」
「いいとも。それだけ?」
「今夜はゆっくり眠りたいから……」
途端に情けなさそうな顔になる龍樹をぎゅっと抱きしめた。
「二発までなら付き合ってあげる」
ささやいた途端に唇をふさがれた。
「お風呂で? それともベッドで?」
キスの合間にたずねられ、拓斗は恋人の隆とした筋肉の肩を指でなぞった。
「風呂で。それからベッドまでだっこ付き。……がいいかな」
「……了解」
感激を伝えてくる声音が拓斗をくすぐったい気分にさせる。龍樹の熱い想いは未だに変わりないらしく。体を繋ぐことよりも、それまでのこんなやりとりがうれしい。
「龍樹さん……」
「ん?」
「大好きだよ」
「うん……」
僕も、と口づけが伝えてきた。
「もっと……」
甘えた鼻声が発せられたのをしおに、龍樹は拓斗の中から自分を引き抜いた。
「あああっやんっ」
ひくひくと呼吸して捕まえたがるそこに指を入れた。愛液と精液で濡れそぼった柔襞は自在な締め付けで貪欲に快感を得ようとしている。
「二発目で終わりって言ったの君だよ……」
「……意地悪……。龍樹さんの二発のつもりだったのに……。いいや、もう。龍樹さんがいいなら終わりでいい」
拗ねた声がずきんと下半身を直撃した。
「いいわけない。したい……」
「ばか……だめだよ。もうっ」
身をよじって逃げた拓斗を捕まえて壁に押しつけた。片足を抱え込み即座に怒張を挿入して。やや乱暴に突き上げを繰り返した。
「あっああっんっ……やだあっ」
ポカポカと背中をたたかれる痛みすら快感。絡みついてくる脚を両方とも抱え込んだ。拓斗の重みがそのまま龍樹を更に奥まで呑み込む手伝いをする。
「ああ……拓斗……嫌だなんて言わないでくれ……。君に抱かれてる瞬間が一番幸せを実感できるんだ」
「抱かれてるのは俺の方だろ?」
「君はここで僕を包んでくれてるじゃないか……」
言いながら柔らかく挿入を許している蜜口に指を差し入れた。
「……っっ」
支える腕が減ったために慌てて拓斗がしがみついてきた。
「いた……っ。……ふっん……。……痛いのにイイっ。そこ、……なんっで……」
腰をよじりながら戸惑うような目の色で龍樹を見下ろした。
「Gスポット。快楽のツボだ。よくって抗い難いだろう?」
「龍樹さんはずるい……こんな事して俺を狂わせて……。余裕たっぷりでずるいよ……」
「余裕なんてない……。僕の腕の中で乱れる君が好きなだけ……」
勃起した乳首を甘咬みしながら言うと、指を残したままグイッと突き上げた。
「ひぃっ」
フルフルと痙攣する体を抱きすくめた。細身の強靱な肉体は、どこに触れても反応の鈍い部分など見つからない。
感度がいいのは内部も同じ。龍樹の些細な動きでびくびくと仰け反り、あえぎ、悲鳴を上げる。我に返った瞬間、恥じらいで泣きそうになる顔がまた色っぽい。
「こんな君は僕だけのもの……僕だけを感じてくれ……」
「あっあっあっ……っ! いいっいいーっ」
飛び跳ねるように体をひねりまくったあげく、勢いよく射精した。
「ああっ………………!」
きゅうっと絞られた龍樹も行為のフィナーレを覚悟して撃ちだし……浴室は荒い息と跳ね落ちる湯の音だけで埋められた。
脱力した拓斗をそっとおろして抱きしめ、行為の残滓を掻き出してやる。ピクピクと震える上気した背中に湯をかけてやり、湯船に浸けた。
「溺れないように捕まっててよ」
「何……?」
「バスタオルとってくる。抱っこでベッドまで……だろ?」
急いでバスタオルをとり、ぐったり浴槽にもたれている恋人をくるみ込んで抱き上げた。
「眠い……」
小さくあくびをする仕草に微笑む。
「いいよ、寝ちゃって。」
「うん……ごめん、マジ眠い」
規則的な寝息を立ててぐったり力が抜けた拓斗を、横たえるベッドはダブル。拓斗の両親の遺品である。
向坂邸を売りに出した都合上、処分したくない家具や荷物は全てトランクルームなどに移動させた。ベッドは龍樹が気に入り、セミダブルからの買い換え計画を変更して拓斗が持ち込みを許したのだ。
拓斗の父親が結構長身で、ロングサイズを購入してあったし、マットレスにしても材質にしてもかなり高級仕様で、これを眠らせておくのはもったいないとのこと。
両親のベッドでの行為に抵抗が無い訳はないのに、言い出しかねていた龍樹にあえて提案したのは拓斗。この、暮らしにも前向きな恋人を、なおさら愛しく思う。
「おやすみ、僕の天使」
拓斗の背後から掻き抱くようにして眠る定位置に体をずらすと、龍樹は幸せを噛みしめながら眠りについた。
桂川家の朝は早い。明け方近くに起き出して外を二キロ走るのは二人の日課である。帰ってきてからのジムは一日おきで、約一時間ほど続けられる。
加えて最近では合気道の稽古。拓斗が希望した護身術である。派手な蹴りや拳はないが、剛の者でなくとも相手を倒せる点では抜きんでている。
「才能……ないのかなぁ」
技をかけ損ねて投げ飛ばされた拓斗は座り込んだまま呟いた。
「……センスは悪くないと思うけど、君は闘争心がある意味不足してる。僕をスティーブだと思って向かってくれば?」
「何でスティーブ?」
「僕が知ってる中で、一番闘争心を露わにしてたのは、スティーブと睨み合ってたときだから」
「やだな。恋愛感情の闘争心しか俺にはないって事?」
「僕は他に知らない。僕を巡って戦う気になってくれたこと、すっごく嬉しかった。あんまり嬉しくて、その場で踊り出すとこだった」
「ぶっ」
龍樹は噴いて笑った拓斗の腕をグイッと引き上げると、きゅっと抱きしめた。
「変?」
「ううん……」
汗に濡れた胴衣がじっとりと体温を伝えてくるのを拓斗は目を閉じて味わった。
「踊りって言えば、ダンスの練習もしようよ」
「なんで?」
「結婚披露パーティでは二人で踊りたい。君を見せびらかして回るにはもってこいだもの。ねえ、踊ろうよ」
「そうやって、よけいな敵を作るんだ。龍樹さん、時々子供みたいなんだもん、驚いちゃうよ」
「一生に一度だから思いっきり鮮明な思い出になるように、やってみたいこと全部したいんだ。君が嫌なら……あきらめる」
「ああもうっ! やたらに泣きそうな顔しないでよ。俺がいじめてるみたいじゃないか。……一曲だけなら付き合ってあげる。それでいい?」
「うん!」
にこっと笑う龍樹を眺めて、拓斗はクスッと笑った。
「そんな顔されると、何でも言うこと聞いてあげたくなっちゃうから不思議だ……」
「え、どの顔? 覚えとかなくちゃ」
鏡を見ようとした腕を引き留め、チュッと頬にキスした。
「ばか……。わざとやったってきかないよ」
「嬉しいよ……。僕を見ててくれるんだね」
「愛しちゃってるからね」
思いこみなのかも知れない。勘違いとか、錯覚の類かも知れない。それでも今の暖かい気持ちが本物であることは確かで。だから拓斗は悪びれずに言ってのけたのだ。
「今日は四限が休講だから四時半には帰れると思う」
朝食の後片づけを手伝いながら、いつものように予定を確認した。
「僕は……スペシャル作ろうかな」
「……今日、何にするの?」
「ガトーオランジェ。最短で作れるから」
「……手抜きメニューだったのかぁ。俺の分、とっといてよ。オレンジ好きだ」
「OK。君のは別あつらえにしておくよ」
「ガトーオランジェ龍樹風? 楽しみだな。ねえ、覚えてる? 俺が初めて食べた龍樹さんのデザート」
「……ああ! そうだね」
「俺を虜にした味なんだから。ちゃんと作らないとだめだよ」
唇にチュッとキスを重ねて、拓斗は靴を履いた。
「帰ったらすぐ店手伝うからね」
「行ってらっしゃい!」
拓斗はスキップが出そうな楽しさで通学路を歩いた。
家で待っている恋人は奥さんではない。それでも、新婚の夫の気分はこんなだろうなと確信する。人生バラ色というやつだろうか。
横浜の乗り換え階段を下りる途中でトンと突き飛ばされるまで、夢見心地のままに浮かれていたのは仕方ないことだ。
些細な喧嘩が多かった二人の仲が、ここのところやけにしっくりきているのだから。
階段落ちをやらかして、あちこちに打ち身の痛みを感じても、なんだか幸せ気分は抜けきってはいなかった。
「君っ大丈夫かね?」
駆け寄ってきて助け起こしてくれた初老の男にも、幸せそうに微笑みかけてしまって胡散くさげに見下ろされた。
「あ、へ、平気です」
身を起こそうとして、ゆるりと生暖かいものが唇や顎を伝ってしたたり落ちた。
「あれ……?」
手で受けたそれは赤い血だった。ぽたぽたと手のひらまで染めるほど出る血を見て、男の方が慌てた。鼻血なのだが、場合が場合である。
「とても平気には見えんぞ。後ろ頭を打ったんじゃないのか」
「あ……いえ……」
後頭部を触れてみて、切れた傷からやはりどくどくと出血しているのを知った。血を見たからなのか、傷を確認したからか、拓斗は次第に気分が悪くなってきていた。気が遠くなりそうになり、立ち上がるのをやめにして。
男が呼んだ駅員が駆け寄ってきて、結局拓斗は担架に乗せられ、おとなしく病院へつれて行かれた。
またも自主休講になってしまった講義分の授業料をとっさに計算して、よけいに具合が悪くなる。医者との受け答えもぼんやりとしたまま手当を受けた。
連絡を受けた龍樹が真っ青な顔で駆けつけてきた時には、ベッドに腰掛けてぼうっとしている状態だった。
「拓斗! どうしたんだよ? 何があった?」
緊急入院の形で六人部屋のベッドを割り当てられた拓斗は、心配と恐怖に彩られた顔で現れた恋人にすまなそうに笑いかけた。
「駅の階段で背中押された。鼻血出たから、居合わせた人が心配してこんな大げさに……」
頭に巻かれた包帯は、後ろ頭の傷のため。
「大げさじゃないよ。頭、どのくらい打った? 検査……終わったの?」
「今日の分は終わった。大丈夫、傷は葉山さんにスパナで殴られたときより小さいさ。痛くないもん」
「痛みだけが判断基準じゃないぞ。後頭部なんて、危ないじゃないか。護身術より受け身の練習しなきゃだめだな」
「うわ……やぶ蛇だ……」
弱々しく微笑んだら、めっと怒った顔で龍樹が見下ろしてきた。瞬間泣きそうに顔を歪ませ、周りに視線を走らせると仮面をかぶるように冷静な表情を作った。
「今日明日は入院だな。明日精密検査されるだろう。とりあえず必要なもの持ってきたから。食欲はある?」
「……今何時?」
「二時半」
「……昼飯……喰い損ねたのか。食欲……ないのかも」
「パジャマに着替えられる?」
言いながら周りのカーテンを閉めた。視界だけしか遮ることの出来ない、開けっぴろげの個室の出来上がり。
拓斗はノソッと立ちあがった。龍樹が持ってきてくれたパジャマは、二人お揃いで色違いのもの。パジャマを着ないで寝ることの方が多い為、殆ど新品である。。
「これが役に立つときが来るなんてね」
拓斗の気恥ずかしげな呟きに、龍樹は替えの下着やタオルなどをキャビネットにしまいながら応えた。
「こんな風に役立つ日は来て欲しくなかったよ」
「まあね。……つぅ」
服を脱ぐときに背中を曲げたせいだろうか、ジンと痛みが走って拓斗は固まった。
「どれ、見せて」
龍樹が医者の目になって拓斗のシャツをめくりあげた。
「背中は手当しなかったのか?」
真っ赤な擦り傷の面積は背中いっぱい。所々出血と、黒く見えるほどの痣が盛大についていた。
「痛みをあんまり感じなかったから……気づかなかった。そんなにひどい?」
「今夜は俯せで寝るしかなさそうだな」
龍樹はナースコールを押した。
「はーい、どうしましたぁ?」
切られないうちに早口で伝えた。
「すみません、背中の傷が思ったよりもひどいので、そちらの手当もお願いできますか?」
ぱたぱたという足音と、ガラガラというワゴンの音がすぐに近づいてきた。
「失礼します」
そっとカーテンをめくりながら看護婦が覗き込んだ。瞬間ハッと固まる。やがてとろんと瞳がとろけてハート型に。職務に忠実そうな看護婦でさえ、仕事を忘れてしまうらしい。
龍樹を見た女性の反応には、もう慣れていたが、拓斗は密かに笑ってしまった。
龍樹の罪作りは本人も気にしていて、嫌悪している節さえあるから、あまりからかいの種には出来ないのだ。
「どうぞ」
場所を譲るために身をずらした龍樹の声が彼女を我に返らせた。ベッドに腰掛け、背中を出している拓斗を見下ろすと、小さく息をのんだ。
「ひどい。先生に言わなかったんですか?」
「どうやら、ここにも傷があったのを忘れていたらしいんですよ」
ものすごく間抜けな気がして、拓斗はうつむいて赤面した顔を隠した。
「あ、頭がぼーっとしてたから……」
「こちらで気づかないというのもアレですけどね」
苦笑に笑み崩して拓斗の傷を観察すると、脈を確認した。
「すみません。ちょっと待っていて下さい」
ワゴンを置いたまま行ってしまった。
「……勝手に使ったら怒られるだろうな。じれったい」
滅菌された器具やガーゼ、薬液などが並ぶワゴンを、恨めしそうに見つめながら龍樹は呟いた。
「やっぱり、縄張りってのがあるよね」
「うん。やれば感じ悪いと思う。君の担当医、結構いい人だし、意地悪したくないや」
「あ、来たみたい」
パタパタと看護婦と共にやってきた担当医は、目を丸くしていた。
慌てて処置する姿を、龍樹は冷ややかな目で見つめていたのだが、医者が立ち去った後で囁いた。
「君の肌に触らせるの、嫌だな。僕がやってあげたい」
「……六人部屋なんだから……やめてよ」
拓斗は赤面して周囲を伺った。
カーテン一枚で隔てただけで全ては筒抜けの、こんなところでカミングアウトをする必要性は全く感じていなかったから。
「ここに泊まり込みたいけど、そうもいかないだろう。階段で押されたって話だが、誰か犯人見てないのかな」
「駅員呼んできてくれたおじさんとか……見てるかも。……警察にも連絡したって」
「誰か調べに来た?」
「いや……俺は会ってない」
ふむと考え込んだ龍樹はおもむろに立ち上がると、部屋を出ていってしまった。
「何なんだ……?」
俯せに寝ころびながら、拓斗は呟いた。
「ばかを言うな、俺は忙しいんだ」
紫関の吐き捨てるような言い方に、肩を怒らせて龍樹は睨みすえた。
「僕の拓斗が殺されそうになったんだ! ちっともばかな事じゃない!」
県警の捜査一課に訪ねてまで大騒ぎをしたあげく取調室に押し込められた龍樹は、周りの目が無くなった途端に激昂して親友に詰め寄ったのだった。
龍樹は向坂拓斗のことになると簡単に理性を失う。
溜息をつきながら紫関は、落ち着けとばかりに短い腕を伸ばして、頭一つ半上の長身の肩をぽんぽんと押さえた。
「故意に押したんじゃないかも知れないだろう?」
そわそわと指を組み替えながら椅子に座り込んだ龍樹は、唇を噛みしめながら確信に満ちた口調で挑んできた。
「拓斗は毎日同じ時間にあの駅を通る。階段は使い慣れていて、混み方だっていつも通り。故意じゃなくて、駆け下りている男を突き落とすとなると、自分だって転んでいそうだろう? 少なくとも自分のせいで転げ落ちた男に詫びの一つも言うなり、駅員呼ぶなりするだろう?」
「そうとは限らん。下手に謝って訴えられたり損害賠償ふんだくられたりしたくないから逃げちまうってこともある」
「そんなの、ひどいじゃないか!」
「俺に怒るな! ……それが現実だって」
「そいつ殺してやる!」
「おいおい、俺の仕事増やす気か? バカ言うなよ」
「……拓斗を失ったら僕は……ぼ……っ」
震えた手で顔を覆い、小さく背を丸めた龍樹の頭をぽんぽんと軽くなで、紫関は溜息をついた。
「病院から電話があったとき、瞬間気を失うかと思った。症状聞いて少し安心したけど……」
「簡単に死んだりしないよ」
「人は簡単に死ぬんだよっ! 打ち所が悪けりゃ、自転車に轢かれたって即死する」
「そりゃ運不運あるだろうさ。とにかく、調べてやるけど。思いこみで動くなよ」
「ああ……」
「それよりあの子の付き添いしろ。入院は何日? 学校への連絡とか、やることいくらでもあるだろう? 店だって……」
「うん……」
自分の顔を泣き出す寸前まで歪めてしまったことに気づき、龍樹は笑おうとした。
「変……だよね? バカみたいだろう? お前からみれば」
「ああ……。俺の知ってる龍樹とはあまりにも違うから……ちょっと戸惑うな。あの子のせいなんだよな……」
まじめな顔でそういうと、紫関は親しみを込めた笑みを浮かべた。
「だが、お前も人間だったんだって思えて、ちょっと嬉しいぞ」
「昔は人形だったからな……」
「言うなり人形? そういや、そんなことよく言ってたなぁ……」
「僕にも執着や自己抑制の出来ない感情が在るんだって拓斗に出会ってから散々思い知らされた」
「……そこまでのろけられると、本当に羨ましいような気がしてくるから不思議だ……」
「僕にそんな恋が出来るなんて、自分でも最大級の幸運だって思ってる。宝くじに当たった気分だよ」
「いいかげんにしろ 」
頭を振りながら、龍樹を追い出しにかかった。
「のろけられるくらいに落ち着いたらさっさと帰れ! 俺は忙しいんだ!」
頭のおかしい人間になってしまうほどの恋なら要らないと、この時の紫関は本気で思ったのだった。
「あっだめ!」
「どうして……?」
珍しく龍樹の拒絶にあった拓斗は、龍樹の股間から手をはずすと、不思議そうに琥珀の瞳を覗き込んだ。
龍樹は瞳だけを微笑ませると、そっと拓斗のパジャマの中で膨れている股間に口づけた。
「なっ」
「欲しいなら、口でしてあげる。今日はそれで……」
そのままフェラチオを始めようとする龍樹を、拓斗は押しのけた。
「そんなんじゃない! 龍樹さんもヨくならなきゃやだ。しよ」
「退院したばっかりだよ。怪我してるのに、そんなことさせられない」
「握りっこもだめ?」
「止まれなくなるからだめ。僕の忍耐力を試すのは止めて」
「後ろからなら、平気だよ。してよ。なんか、すごく欲しい。こっちに欲しいんだ」
拓斗は自分からズボンを脱ぎ捨てると、四つん這いになり、龍樹に向かって双丘を割って見せた。呼吸するピンク色の菊花が龍樹を誘う。
「拓斗……。今日の君はどうかしてる」
呟きながらも、揺れる腰の誘惑に負けた男は淫らな舌をそこに忍び込ませた。
「あ……んんっ。舌も指もだめ。龍樹さんを入れてくれなきゃやだ!」
クチュクチュと湿った音をさせながらピンク色の肉襞が強く舌を締め付けようと収縮した。
「早く、入れて。欲しいよ。龍樹さんの精液をここに飲ませて」
喘ぎ混じりに叫ばれて、プツッと理性の糸が切れた。
揺れて喘ぐ拓斗の蜜口に限界を訴えるペニスを押し当てる。
双丘を割広げる形で支え、グイッと押し入った。
熱く滑るその中は、確かに待っていたものを得て嬉しそうに蠕動した。
「はあんっいいっ……熱くって……おっきい……龍樹さんのだぁ……」
悦びの声が龍樹を更に追いつめた。
「っっ、拓斗、待って」
「え?」
腹筋を使い、何とか堪えた。
「ああ、ごめん。大丈夫、あんまりヨすぎて、出ちゃいそうになったんだ」
言いながらゆっくりと腰を揺らした。
「っ、嬉しい……。龍樹さんが俺と繋がってる。今……俺達一つだね……」
「そうだよ。身も心も……一つになっていたい……ずっと……」
「病院で……寂しかった。二泊だけなのに……欲しくて堪らなかったんだ……。抱いて、強く抱いて! 俺の中にずっといて!!」
「た……拓斗……! 拓斗、拓斗ぉ!」
包帯だらけの背中が痛々しい。擦れないように密着して堅く抱きしめた。
腰だけを激しく動かしながら、拓斗の喘ぎを味わった。
荒く苦しげな吐息が理性の糸を全て断ち切ってしまう。薄紅色に染まった肌に光る汗の玉はムーンストーンのように淡く煌めいている。
乱れた黒髪はサラサラと拓斗の動きに併せてさや鳴った。
「ああ……拓斗……君の顔を見せて。見たい……」
淫らな喘ぎに震える赤い唇。涙を滲ませてとろけた黒く透き通った瞳。細く理知的なカーブの眉が色っぽくひそめられる様……。
そっと顎を抑えて振り向かせた。
「……キス……して」
揺れる瞳が愛しげに微笑んで誘った。
龍樹は肩越しから拓斗を覗き込むように顔を近づけ、愛らしい唇を貪った。
「う……ん……いいっ、すごい……いいっ」
口づけを続けながら拓斗が腰を振った。グチュッと湿った音が響き、舌の動きが鈍る。ぶるぶるっと震えて、ふつっと脱力した。
手放されたままだったところからドピュッと打ち出される灼熱の奔流が、シーツにジワリと沈んでいく。
「あ……俺……」
気恥ずかしげな呟きに、龍樹は手探りで彼のぐったりしたペニスををまさぐり、耳たぶを咬んだ。
「僕を感じてくれた証拠……嬉しい……」
未だにトロトロと出続ける精を掌にとって舐めた。
「甘い……君のだってだけですごく……甘いよ……」
更に腰を打ち付けて、龍樹もフィニッシュに入った。
「ああっああっ」
肉の擦れる音に拓斗の悲鳴が加わる。ドクン! と鼓動が強く頭の中で響いた瞬間。龍樹は拓斗の中に染み込んだ。
「はああああんんっ」
ピクピクと痙攣しながら、龍樹の精を受け止めた拓斗は、再度一気に射精していた。
「はあっはぁっはぁっ……たつ……きさんっ、でてっちゃだめだからね。抜いちゃ……だめなんだから……」
「拓斗……僕を抱いていて。ずっと抱いていて……」
見境を失ってしまう。
どうしていいか分からなくなる。この恋人の愛らしさは危険なほどだ。
狂った野獣は恋人の求めるままに彼の身体を貪り続けた。
「向坂、階段落ちしたってぇ?」
登校早々、赤羽に呼び止められた。遠巻きに見てる人たちの視線は、拓斗の包帯だらけの頭に集中していた。
「早耳だな」
苦笑しながら赤羽のギョロッとした目を覗き込んだ。大きめの頭と拓斗より小さな体躯。撫で肩のせいで、こけしのようなイメージだ。
唯一こけしっぽくないのが飛び出んばかりの大きな目だった。
それがパタパタと瞬きすると、肩を竦めて顎で背後を指した。そこには、二、三人の女子がいて、真ん中に艶やかな黒髪をシャギーカットのセミロングにした色白の顔があった。
「水野だよ。昨日の中に知れ渡ったぜ」
言うだけ言って、赤羽は講堂を出ていった。休み時間しか講堂にいない男は、今日も講義を受ける気はないようだ。
水野は濃いめのピンクに染めた唇を拓斗と目があった瞬間に歪めて見せた。
憎まれている。拓斗はそう思った。目があった瞬間の憎悪。
それは、もっと弱いものなら何度も経験したものだった。
泉、亜紀美、その他付き合った女の子達。破綻したときに拓斗を見つめる視線には必ずその光が隠れていた。
「俺のせいなのか?」
「え?」
独り言に返事をされて、声のした方に目を向けた。
隣りに笹沢が来ていた。
「あ、いや。俺って、水野に嫌われてるかも知れないなって」
「ふうん。なんかやったの?」
「覚えないんだけどね」
途方に暮れたように呟けば、笹沢がクスッと笑った。
「罪作りって奴? 向坂って、見かけに寄らず悪い奴だったんだ……」
「なんだよ? それぇ。俺、何にもしてないぞ」
「何にもしないって罪さ。多分ね」
「水野に何すればよかったわけ? 友達でも彼女でもないんだぜ」
「うーん。あいつ、君の奥さんの店にも顔出してるんだろ? のろけないこと……かな」
「龍樹さん目当てか……」
ハアッと溜息をついた。
「タツキって言うの? 奥さん……」
「うん。難しい方の龍と、樹木の樹で龍樹。俺が女だったらもっと虐められてたりするのかもね」
「美女と野獣の組み合わせはありがちなのに、やっかまれるんだよね。お前の場合、野獣ってほどじゃないけど」
「っま、バイだったら付き合いきれないだろうな。男だけでも大変なのに、女まで敵に回してたらノイローゼになる」
「……遊び人だったの?」
「うん。俺と出会う前の話って言うけど」
「心配?」
「ちょっとはね」
「おおっと、惚気入った!」
「……ちゃかすなよ。これでも結構悩みあるんだから……」
「ほう?」
「……この怪我だって、誰かに押されたんだ。俺って、色んな奴に憎まれてるのかもって思うと、落ち込むよ」
「大丈夫。同じだけ愛されてるはずだよ」
妙に力強い言い方に、拓斗の眉はひそめられた。これと言った裏付けはないが、不思議な感触を感じたのだった。どこかで似たような経験があった。何処でだったろう。
その時、教授が出現し、拓斗の思考はとぎれた。
「……拓斗君? どうした?」
携帯電話のとぎれがちな音声でも龍樹の声音はしんみり耳に染み込んでくる。
「俺のこと愛してる?」
「……うん。いきなり何?」
「んとね。迎えに来て欲しいんだ」
「いいよ。何処?」
「……今じゃなくてね。夜。九時半頃……かな。早めの店じまいになっちゃうけど……。ベイサイドクラブまで」
「何の集まり? 学校から随分遠いね」
「飲み会。コンパの二次会で行くんだ」
「二次会? めずらしいな」
「俺の全快祝いだって。だから俺んちに近い方の場所選んだんだと。……笹沢が、たまには顔出ししとかないとって言うんだ。クラブとか苦手だから……長くいたくなくて。電話させて貰えるかどうか分からないから、今から頼んどく」
「……わかった。店の中まで入って君を拉致してくればいいんだろ? どの服着てくのが都合がいい?」
「龍樹さんがクルージングしてた頃みたいな奴。見てみたい」
「水野って子の前でイチャイチャはしたくないんだろ?」
「イチャイチャしようなんて言ってないじゃん。俺の恋人を見せびらかしたいだけだよ」
「……何だか……」
「気持ち悪い?」
「変な感じ」
「だめ?」
「ううん。行くよ」
「じゃ、頼んだよ」
「ああ」
携帯を切って、拓斗は辺りを見回した。
恋人への電話は何となく気恥ずかしい。誰にも聞かれたくなかったのに、いつの間にか水野が側にいた。
「ラブコール?」
赤くなってる場合ではない。また酒の肴にされてしまうと思うと、精一杯の虚勢を張って見せるしかなかった。
「……まあね。うちの店まで来てるんだって?」
「家が近くなのよ」
「お前、たしか長野出身だろ?」
「三丁目のマンション、買って貰ったの」
三丁目と言えば、『El Loco』の裏の国道を挟んだ向こう側。駅前ではない分、特徴のある形をしたものが最近売り出されたのを思い出した。
「そういえば、前に買わないかって電話来てたっけな。レジデンス森ヶ丘……じゃない?」
「そうよ。今度遊びに来てね」
気軽に微笑まれて拓斗は固まった。
嫌われていたはずではないか?
単なる思いこみ。取り越し苦労……?
少し神経過敏になっていたのかも、と、拓斗は苦笑した。
「そのうち、機会があったらな」
さっさと講堂に戻ろうとむけた背中に、クスッと皮肉な色に染まった笑いが投げかけられた。
「向坂君て、バイなんでしょ?」
「へ?」
「あ・か・ちゃん! 出来ちゃったんだって?」
「……何でそれを……?」
「すごいよね、あの兄妹手玉に取るなんて……」
「……!」
「いつかそのテクニシャンぶりも拝見してみたいな」
「ざけんな。一生お断りだよ」
誰に聞いた? 龍樹さんか? 他にいないよな……。
何で水野なんかに……!
さっきまでの甘い感覚が全て消え去り、拓斗は苦い唾液が口の中にあふれるのを意識した。
おしゃべり雀は龍樹さんだ!
そんな気分の悪さを引きずったままに飲む酒は、美味くもなかったし、心地よくもならなかった。
予定通りに車に分乗してベイサイドクラブまで出たときも、投げやりな気分は消えなかった。このまま恋人に迎えに来て貰っても絡んでしまいそうだ。
後部座席でうつらうつらしながら、笹沢の運転する車は何だかシートが柔らかいな、などと考えていた。
キッと停まったところで、目的地到着かと身を起こしたのだが。
「あ……れ……?」
眠い目を擦りながら外に出ようとした拓斗は、そこがかなりイメージしていたものとは違うと思った。
「龍樹!」
「ハイ! 龍樹!」
「ひさしぶり!!」
絡みついてくる腕を適当にあしらい、愛想笑いをしながら目を泳がせた。拓斗は何処にいるんだろう……。
いつだってすぐに彼の姿は見つけられた。特別鮮やかな色で目に入る思い人だから。まして彼は、こことは色が違いすぎる。
「ここに大学生の集団来なかった? 場慣れしてなさそうな可愛い子が混ざってる……」
顔見知りのウエィターに声をかけた。
「さあ、分かんないな。可愛い子って?」
龍樹は懐からいつも持ち歩いている写真を取り出した。引っ越しの時に紫関に写して貰った記念写真。二人でにっこり笑っている。
「君の……パートナー?」
強張った声に眉をひそめた。そういえば、彼には何度か粉をかけられたことがあったと思い出す。
「……ホントに可愛いね。こんな子なら来れば目に付くんだけど……」
サアッと血潮が顔から抜けていく感覚に慌てた。
拓斗は何処に行ったんだろう。迎えに来てと言いながら連絡もなしに予定を変更することは、まず考えにくい男だ。我が儘なところはあるけれど、律儀な性分なのだから。
「ちょっとでも覗いたってことない?」
「待って、聞いてみるから」
龍樹の形相に、真剣みを帯びた口調で応えたウエイターは、ドア付近のガードマンに目配せした。
拓斗の写真を見せ、確認を取る。
全てノー。
逆上しそうになりながら、拓斗の足取りを考えた。
喧嘩はしてない。今日の連絡も甘い口調だった。
拓斗の意志ではない予定変更……。
慌てて彼の携帯に電話をかけた。
おきまりの圏外。
「拓斗……」
龍樹は即座にきびすを返した。
周りがザワッと道をあける。さながらモーゼが杖をふるった海のようだ。
羨望、嫉妬、賞賛、憧憬。様々な視線にさらされ、小さく舌打ちした。
今日の龍樹は、胸板を大きく見せるきつめのシルクシャツに、尻をプリンと強調するぴっちりした黒革のパンツ。飴色の髪をフワリとバックに流してジャケットを肩に担いでいる。
クルージングの服装でなんて言う拓斗の要望を聞いたせいで、色目を使ってくる女や男達を避けるだけでも煩わしい。
拓斗だけが欲情してくれればよかったのに。
心配と落胆で動揺しながらもクラブの駐車場から車を出した。拓斗がいないならもう用はない。
途中で何度か電話を入れてみる。誰も出ない。
伝言は入れなかった。
伝言が聞けるくらいなら電話に出てくれるはずだと思う。
夜の本牧は以外に明るい。二四時間営業のファミレスが軒を連ねているのだ。勿論拓斗はそんな所にはいないだろう。
「手がかりは笹沢と水野……」
龍樹は迷ったあげく、電話ボックスに車を横付け、電話帳を開いた。
目指すは早光大医学部外科学教室。
時間は遅いが、この研究室には誰かしら居るのが伝統である。
「夜分すみませんが、助手の狭間さんはもう帰られましたか?」
「今日は病棟で夜勤のはずです」
素直に教えてくれた新米らしい研究助手に礼を言い、狭間の居る詰め所にかけ直した。
「……桂川……?」
訝しげに呟いてから、ハッと息を呑んだ。
「あの……桂川龍樹か?」
「そうだよ、久しぶり……」
「お前から電話貰えるとは思わなかったな」
「え、そう……?」
「俺に挨拶無しで退学しやがって……」
「狭間……ホントにごめん。あの時は心のゆとりが無くて……」
「で? 今日は何をさせたい?」
「あの……?」
「お前が俺に電話なんて、頼み事以外にないだろう?」
「狭間……そんな……」
確かに。そう思われても仕方がない。
「やっぱりいいや。忙しい所すまなかった」
「待てよ。お前のそんな困り果てた声聞いたら、気になるじゃないか。言うだけ言って見ろ。出来ることならやってやるぜ」
「……見返りは?」
「お前って言いたいところだが、生憎俺も独り身じゃないんでね。そのうち夕食おごれ。二人前だぞ」
「一人に決めたのか?」
「ああ。俺のことだけ愛してくれる奴だ」
「よかった……」
しみじみ呟いた。狭間の真剣な気持ちを知って、逃げだした龍樹だったから。
「で? 本題言えよ。マジ忙しいんだから」
「あの……今年の医学部一年生の名簿、手に入らないかな。笹沢って奴と水野って奴、連絡取りたいんだ」
「何だ? それ……」
「僕のパートナーが帰ってこないんだ。そいつらと飲みに出たはずなんだが……」
「午前様くらい、仕方ないんじゃねーの?」
「迎えに来てって言ったとこにいないんだよ。遅れるなら必ず連絡をくれる子なんだ」
「……お前の所、ファックスある?」
「うん。店に」
「店?」
「案内、出したよ?」
「……実家帰ってない。いいや、とにかく番号教えろ。折り返しファックスしてやる」
「すまん……」
狭間からのファックスは、帰宅したときに吐き出されている最中だった。飛びついてはぎ取り、目を走らせる
笹沢玲、水野彩……。
水野の家は森が丘……。
「ものすごいご近所だな」
笹沢は……?
「緑園か……」
水野は店で何度も相手をしているあの子だろう。
笹沢は、何かと拓斗が口にする名前。
「笹沢……玲……」
龍樹は笹沢宅へ電話を入れた。
「どちら様ですの?」
「れい君と同級の、向坂の家の者です。今日は一緒に飲みに出たはずなんですが……まだ帰らないもので」
「……宅の息子のアキラは、今日はお友達の所に泊まると、朝、言い置いて出掛けましたが……」
「誰の所ですか?」
「ああ……ええと、同じクラスの赤羽さん……」
「ありがとうございます」
そそくさと電話を切って、赤羽の電話にかけた。
「あ、俺です。笹沢? いや、あいつは二次会に行ったはずですよ。向坂が一緒でしょ? 俺んち城山なんですよ。笹沢が泊まりに来るわけ……」
「ありがとう。分かりました。ところで笹沢君や水野さんの携帯の番号とか、判りますか?」
「あー、すいません、俺、あんまり親しくないんで……」
そうですかと電話を切る。
受話器を見つめながら、考え込んだ。拓斗の携帯にもう一度かけてみる。やはり誰も出ない。
笹沢は嘘をついていた。だが行方が判らない。
「水野か……」
拓斗の口振りでは、水野のことはあまり快く思っていないようだった。それが二次会まで?
店での様子を思い出そうとする。
いつも挑発的な会話をしかけてくる娘だった。他の女性客と異なる点は、龍樹のファンではない点だ。冷たい目で見つめてくる女性には、あまり慣れていない。それだけに敏感に察することが出来たのだった。
珈琲やケーキは美味そうに口にしていたので、純然たる店のファンだと思って相手をしてきたのに。
溜息をつきながら水野宅へ電話を入れる。
「……はい?」
「君、水野彩さん?」
「……」
無言の警戒心が電波に乗ってくる。だが、最初の声で本人なのは判った。水野の声は甲高くて鈴を振ったような声なのだ。
「僕、向坂の家の者です」
「あ! マスター? どうしたの?」
「拓斗が帰らないんだ。君、拓斗と一緒だったんじゃないの?」
「……」
いきなりガチャンと切られて龍樹は受話器を見つめた。無音状態が続く。どうしたものかと考えていたら、ドアフォンがなった。
「拓斗? 遅いじゃないか、今まで何処に」
言いながら開けてみれば、息を切らした水野が立っている。
「向坂君、何にも連絡してこないの?」
「ああ。迎えに行ったら居るはずの店にも居なかった。どういことだい?」
「クラブまで行ったの? その格好で?」
「拓斗の御指定でね」
「……クラブに行くって言ってたのに、お流れになったって伝言回ってきたの。向坂君達だって、どっか他で飲んでるんじゃない?」
「笹沢君だけが、赤羽君の所に泊まるって家族に言ってるんだ。赤羽君は知らないって」
「笹沢ぁ? あいつぅ」
「何か知ってる?」
「あいつ、向坂君のこと、狙ってたのかも……」
「って、ゲイって事?」
「自分で見た訳じゃないけど、二丁目に出入りしてるって噂有って。そう言っちゃなんだけど、マスターが援交の相手だって広まってから、向坂君、男子の中で浮いてたんですよね。笹沢だけがひっついてたの」
「拓斗はそのこと、感謝してたみたいだよ。学校行くのが辛くて、神経性の下痢も良く起こしてたけど、彼のおかげで追いつめられないですんだって」
「……あたしが追いつめちゃったって言いたいみたい」
「一番追いつめてるのは僕だけどね。君もあんまり人のこと取りざたしてばっかいると、いつかしっぺ返し受けるよ」
恨みを込めて言ってみれば、
「分かってますよぉ。それより、笹沢の居場所。探しましょ」
などと、全く分かってない笑顔で言い切って。
龍樹は疲れた溜息をついた。
「やけに熱心だね」
「べつに。笹沢の仲良い奴から攻めていきましょか。電話、貸して下さい」
「あ、ああ……」
テキパキと電話しまくる水野を眺め、龍樹は妙な違和感に眉をひそめた。
「判りましたよ。あいつの使いそうなところ。やっぱり二丁目で、《リリスの部屋》って店のVIPルームじゃないかって」
「その店は知らないけど、二丁目なら僕の縄張りだ」
龍樹は水野から受話器を奪うと記憶にある番号に電話した。
「あ、真由子さん、いる? 龍樹だけど」
お待ち下さいという、訝しげで慇懃な物言いは、新人らしい。
きゃあという悲鳴のような歓声が遠くで聞こえた。
「やーんっ、龍樹ちゃん、久しぶりぃ。どうしてたのぉ? ちっとも来てくれないじゃないのぉ」
「そりゃ、僕だって店持ってるんだから。真由子さんこそ、一度も来てくれてないじゃない。開店祝いのお花だけなんて、寂しいよ」
「お上手言ってもだめよぉ! 香奈ちゃんから聞いちゃったあ。可愛い本命の拓斗君、ゲットできた?」
「……香奈の口、縫ってやろうかな。いえ、いずれ紹介しようと思ってたんだけど。その拓斗が拉致されちゃいまして。《リリスの部屋》とかいう店のVIPルームに連れ込まれたらしいんです。すみませんが、人をやって確保お願いできますか? 笹沢玲って男らしいんですけど」
「いやっだぁ、大変! そこって、何でもありの店よ。龍樹ちゃんが惚れちゃうくらいの子じゃ、まわされちゃうかも」
「……脅かさないで下さい。僕もすぐ行きますけど、時間かかりすぎるんです」
「あたし達と別れてから二時間くらい経ってるわよ」
口を挟んできた水野に頷いて、真由子をせかした。
「店に着いてから三十分くらいじゃないかと。急いで下さい。恩に着ます」
「わかったわ。香奈ちゃんと弘樹クンに行って貰う。それでいい?」
「お願いします!!!」
言うなり切って、車のキーをつかんだ。
車に乗り込んだ所で水野が付いてきているのに気づいた。
「あたしも行ってもいいでしょ? 探してあげたんだから」
「また話のネタを取るつもり?」
「そんなんじゃないわよ」
露骨に膨れながら呟いた水野の瞳が真剣だったので、龍樹は仕方なく頷いた。
「大人しくしててくれよ」
助手席に乗ろうとしたのを制して、後部座席に押し込んだ。
「ナビシートは拓斗専用なんでね」
「つまんなんぁい」
「他の人間の痕跡なんかあったら、僕は捨てられちゃうからね」
「じゃ、髪の毛おいとこ」
「拓斗と別れさせたいって事?」
「うん。向坂君、ホモじゃなかったのに。変態の仲間入りさせるなんて、酷いわ」
「ホモはホモ同士でくっついてろって?」
「そうよ。なにもノーマルな向坂君を誘わなくてもいいじゃない」
「って言われてもね……。僕が欲しかったのは彼だけだから……」
「受け入れたんだから、素質あったって事なのかしらね」
渋々認めるという口振りに苦笑した。
「……拓斗のことが好きなんだね? 君の名前のイニシャルはAだし」
「なに?」
「真っ赤なバラ……贈ってこなかった?」
「ああ。あれ……。あのバラで圧倒しといて、入学式で一気にゲット! てつもりだったのよ。なのに向坂君、あたしのこと思い出してもくれなかったみたいね。無駄金使っちゃったわ」
「あの頃、ちょっとゴタゴタがあってね。イニシャルだけじゃ、判りようがなかったんだよ。それに、どういうつもりだったの? 学校から遠い、うちの方にマンション買ってみたり……」
「向坂君の追っかけだもん。あたし」
なんでもないことのように言う。執着の度合いは自分とどっこいの様に思えて、密かに龍樹は慌てた。
「追っかけ?」
「初めて見たのは国体の予選。彼、今よりもっと、きつい顔つきだった。まっすぐゴールを見通す鋭い表情が、すごくかっこよかった。なのに、二年からはいつも補欠で」
「拓斗は、自分のために走ってただけだからね」
「ええ、どんな人なのか、興信所も使って調べたの。付き合うのは女の子ばっかり、一度に一人だけ。なのに、いつも振られてた。真面目すぎてつまんないって事らしかった。ばかばかしい理由よね。志望校調べて、同じ所全部受験したわ。同級生になれたら、あたしにも望みありそうだったから。春休みの間にひっくり返されるとは思いもしなかったわ」
「拓斗のこと、いろいろ知ってる割には、全然近づいてないみたいじゃない?」
「一応、受験の時に声かけたのよ。でも、彼ったらぜんぜんおぼえてくれないの。最後の二校の時に、やっとうろ覚え程度には覚えてくれたけど……。考えてみれば、試験に集中したいものね、あたしなんて、ライバルの一人にしか過ぎないんだし」
「入学式には声、かけなかったの?」
「かけたわよ。だけど、マスター達、もうできあがってたじゃない。待ってるマスターに向かって全力疾走してた時の彼見たら、気力萎えちゃったわよ」
ふてくされ加減でシートに埋もれた水野を、そっと鏡で伺った。
「だから、ホモの噂流したの?」
「あのねぇ。あたしが流さなくったって、その噂蔓延してたわよ。コンパのたんびに迎えに現れる貴方見たさに、毎回女子は全員参加だったんだから。全く、向坂君には貴方目当てだって思われちゃうし、最悪の展開だわ」
「パトロン説は君のせいだろ?」
「確かに、あたしが尋ねたときにそう答えてたけど、あの場には他にもいたのよ。笹沢とか、女子も数名。何であたしのせいなのよ?」
「拓斗は君が言いふらしたって決めつけてた」
「ひっどーいっ。あのね、噂ってどうすれば広まるか知ってます?」
「ここだけの話、とか、内緒だけど、とか、付け加えとくんだろ?」
「それにね、自分も聞いたんだけどって付けるのよ。ネタ元の責任回避!」
「ああ、そうだな」
「向坂君の目つきが冷たいのって、そのせいだったんだぁ。ショック……」
「僕が拓斗の女やってるって噂は?」
「マスター、そう思って欲しかったんでしょ? 一応マスターの意向通りに、ちらっといっといてあげたんだけど。あたしは違うって知ってるもん。興信所の報告、めっちゃ詳しくて。窓のカーテン閉めなかった日なんて、盗撮写真もあるの。考えてみれば、あの日でしょ、出来ちゃったの」
「おいおいおい。それ、没収だ。渡すって約束しないと、ここに捨ててくぞ」
「わかってます。ぜんぶあげますよ。マスターの知らない向坂君のデータだって、有るかもよ。この際あげるわ」
「それはどうも」
「向坂君、大丈夫かなぁ」
「君の情報通り、《リリスの部屋》にいると良いけど……。違ってたら、お手上げだ」
ギュンとアクセルを踏み込んで、新宿方面を目指した。
薄暗い店は、思ったより静かだ。
「ここ……クラブ?」
「ああ、うん。イメージ違う?」
「なんか、テレビで見たのと違うね」
「向坂って、そういう所行ったこと無いの?」
「うん。部活と勉強で、一日終わっちゃってたから……」
「くそまじめ……なんだな」
「そういう笹沢はあるのかよ?」
「俺、ここのVIPルームメンバーだもん」
「へぇ……」
案内されるままに違う部屋へ歩いていく。
ボックス席の間を縫うように進むのだが、どれも顔が見えにくくなっていた。
気のせいか、女性の姿が少ない。
「踊るとこ、無いの?」
「あるよ。そこ」
顎をしゃくられ、目を移すと、確かに隅がダンスフロアになっていた。だが、踊ってるのはどう見ても玄人だ。
「あの男の人、ダンサー?」
「うん。好み?」
「まさか」
そりゃ綺麗な身体している。プロなら当たり前だ。
(だけど、龍樹さんの方がよっぽど綺麗だ)
胸の内でつぶやいて、笑った。
彼を受け入れたのはそれに惹かれたからではなかった。一途に愛してくれる、その心根に惚れたのだった。
「お前って、好みうるさいのな」
「……人間、見た目じゃないぜ」
(それに、性別でもないんだ)
龍樹と恋人になって、のめり込んでいく自分を振り返り、そう思う。
「滅茶苦茶面食いなクセによく言うよ」
笹沢の声音に眉をひそめた。
暗がりのせいで、顔がよく見えない分、声の表情が気になった。
「笹沢……なんか、怒ってる?」
「怒ってないよ。別に。それより、こいよ」
奥の扉を開けて明かりに照らされた笹沢の顔は、穏やかな微笑みを浮かべていた。
だが、確かに憎々しげに聞こえたのだ。
「わ……」
足を踏み入れた所がピンクの部屋だったので、思わず拓斗は仰け反って叫んだ。
男達がさざめきあっていたメインフロアとは違う。
「……カラオケルームみたい……」
ソファとラグと、クッションとテーブル。部屋がピンクなら、これら調度も金色と白とピンク。
カラオケルームよりは高級そうだったが、何しろ落ち着かない部屋だった。何故だろうと首を傾げ、誰もいないからなのだと腑に落ちた。
「……他の奴らは?」
落ち着き場所を見つけられないままたたずんで、拓斗は笹沢を見た。
笹沢は、もの慣れた様子で水割りを作っている。
「道に迷ってるのかな?」
「さあね。飲めよ」
心配するそぶりもなく、出来上がった水割りをよこした。
「ありがと……」
素直に受け取り、一口飲んだ。瞬間味に違和感を覚え、眉根を寄せる。
「これ、濃くない?」
「そう? 普通だろ」
首を傾げながらも、拓斗はそれを飲み干した。
やけにのどが渇いていたのだ。
腕時計は九時を指している。そろそろ龍樹が来る頃だ。拓斗はソワソワと入ってきたドアを盗み見た。
自分が帰ったら、笹沢一人になってしまう。せっかくの全快祝いの二次会を企画してくれたのに、お先にと言うわけには行かなくなって、困惑するしかなかった。
「みんな……どうしたのかなぁ」
やはり濃かった水割りに酔ったのか、少しめまいがしたのでソファに座った。
「何だよ、もう酔ったのか?」
クスッと笑いながら、笹沢が隣りに座ってきた。
グイッと押しつけられたお代わりの水割りをぼうっと眺める。
「向坂ってあんまり酒強くないんだな」
「そうかも。……普通だと思ってたんだけどなぁ。」
「もう、顔赤いぜ。可愛いな」
「へ?」
拓斗は自分の耳を疑った。
「からかうなよ」
可愛いなんて言うのはあんまり嬉しくない形容だ。
「からかってなんか、いないよ。事実を言ってる」
すっと笹沢の指先が頬を撫でて、項をなぞった。
ゾクリと走るのは不快感。
「よせよ! お前こそ悪酔いしてんじゃねー?」
じりじりとソファの端まで追い込まれ、拓斗は人が変わってしまったような友人を見つめた。
のしかかってくる銀縁眼鏡の男は、舌なめずりしながら拓斗の太股に手をかけた。
「笹沢……悪のりするな!」
「お前、男じゃないと起たないんだろ? 俺が相手してやるよ。テクニシャンぶり、見せてよ」
「……ざけんな!」
笹沢をはね除けた力の弱さに、自分自身驚く。
ニヤリと口を歪めたまま覗き込んでくる笹沢の顔は、見たこともないほど嫌らしかった。
「だるい? 眠いのかな。寝ててもいいよ。とりあえずお前を味わうことは出来る」
「クスリ……使ったのか?」
「うん。一次会の時も、今も……。大丈夫、習慣性はないから」
「そういう問題じゃないって! 俺、男だめなんだよ」
「今更言う? そういうこと。パトロンはどう説明するんだよ」
「パトロンじゃないって。あの人だけは特別なんだ」
「ホモじゃないけどホモな関係を受け入れてるって?」
「そうだよ。厳密に言うと、俺はあの人じゃないと起たないんだよ。だから無駄なことはよせ」
「試してみよう」
ズボンのジッパーに手をかけられ、拓斗は腹を決めた。
「話し合いは出来ないみたいだね」
「一回だけでいいんだ。あの人を狂わせたお前を試させて」
熱い囁きを吹き込みながらのしかかってきた身体を投げ飛ばした。
「いやだってんだ!」
サイドボードにガシャンとぶち当たった笹沢は、首を振り振り立ち上がった。
「乱暴だなぁ。クスリ効いてたんじゃないのか」
「力が足りなくってもコツがあるんだよ」
関節技と相手の力を利用するタイミングに長けた合気道が、女性の護身術として選ばれるのは当然だ。
この時拓斗は身をもってそれを確認した。
習ってきたことは無駄じゃない。
「友達を投げ飛ばしたりしたくなかったのに、お前、一体どうしたんだよ」
「お前なんか、友達じゃない!」
突然激しくなった口調に、拓斗は瞬間怯んだ。
「あの人に愛されて、そのくせ女にも手を出してるなんて! あの人を泣かせるなんて許さない!」
「あ……あの人って? 何のことだよっ」
「お前はあの人に愛される事がどんなに幸せなことか、全然解ってない!」
目尻に涙さえ滲ませて、笹沢がヒステリックに叫んだ。
自分を愛してる人とは、つまり……。
「……龍樹さんのことか……」
思わず大きく溜息をついた。
一体これから、どのくらいこのようなやり取りをすることになるんだろう。
スティーブや、清田などのことを思いだし、沸々と怒りがわき上がる。
「お前も龍樹さんと寝たことがあるのか? 来る者拒まずだったらしいもんな」
いきなり胸ぐらをつかまれた笹沢は、拓斗の豹変ぶりに目を見張った。
「さ……向坂?」
「言っとくけど、今は俺のものだからな!」
笹沢をかなぐり捨て、ソファに座り込んで頭を抱えた。
「過去のことだって頭では解ってても、こう後から後から出てくると、ほんとに頭くるよ」
「向坂……」
「俺にだって、独占欲ぐらいあるんだ。焼き餅だって焼くよ。なのに、終わったことだって言われりゃ、面と向かって責めることもできないんだ!」
「お前だって、兄妹を手玉にとってたんだろ?」
「それは水野の言いぐさだな。お前、聞いてたのか?」
「耳に入ってきただけだ。あの人の妹を、はらませたんだろ? あの人に愛されてたくせに」
「確かに俺は欲望に負けたよ。泉さんは……龍樹さんの妹だけど、龍樹さんが好きだったんだよ。だから、俺を排除するために先手を打って体を張ったんだ。龍樹さんに告白されたのは、その後の話! まさか妊娠したなんて、今でも信じられないよ。女の子って、そういう計算はするもんだと思ってた……」
クスリのせいだろうか。感情をコントロールできない。散々まくし立ててから、ハアッと脱力した。
自己嫌悪が津波のように襲いかかってくる。
「やだな、お前なんかに何でこんな事……」
震わせた肩を抑えるように置かれた手は、やけに優しくて、拓斗は振り払うことも忘れて俯いた。
「向坂……お前って、ホントに可愛いな……。どうやら俺は勘違いしてたらしい……」
「え……?」
思わず見上げたところで、すかさず唇を奪われた。
「なっ」
慌てて飛びすさり身構えれば、笹沢はプッと吹いて笑い出した。
「キスくらいで顔真っ赤にするなよ。キングとやりまくりのくせに」
「き、キング?」
「お前の彼。この界隈じゃ有名人だったんだ。もっとも、一年近く前からすっかりなりひそめてたけど」
「あ……俺達一年前に知り合ったから。恋人になったのは最近だけど」
この男は龍樹の過去を知っている。その証言で、龍樹が嘘を言っていなかったのを知った拓斗は、気が付けば素直に頷いたりして、笹沢となれ合っていた。
「あの人は、お前が振り向くまで待ち続けたってのか?」
「うん……。友達でもいいからって言ってくれてた」
これは惚気にしか聞こえなかったかもしれない。
笹沢は呆れたように天井を仰いだ。
やがて、まじめな顔で拓斗を見つめてきた。
「……寝てないよ。あの人は俺なんか、鼻も引っかけなかった」
「え?」
「確かに来る者拒まずだったらしいけど、後腐れありそうな相手は極力避けてた。あの人、俺になんて言ったと思う?」
拓斗は分からないと首を振り、続きを待った。
「僕は君向きじゃないよ。とことん不実だからねってさ。ホントに不実な奴は、そんなこと言わねーって」
「な、なんでお前はだめなんだよ?」
「俺が本気だったからさ。遊びの振りして近づいたのに、しっかり気づかれてて。あの人は遊びでしか付き合わないんだ。長く付き合うのは、割り切って付き合う奴だけ。だから、お前への執着ぶりで、別人のよく似た人なんだって思ってた。名前聞くまでね」
「俺……俺は……」
「キングに望まれた? 羨ましい限りだな。ま、わからないでもない」
フッと笑う表情はすっかりいつもの笹沢だ。
「お前みたいに可愛い男はなかなかいない」
「嬉しくないよ。可愛いなんて……」
「可愛いがだめなら……そうだな、愛し甲斐のある男」
「馬鹿な事言うな!」
部屋を出ていこうとして、足がもつれて転んだ。
「無理しないで寝てればいい。送ってくから」
助け起こされ、も一度ソファに逆戻り。
「電話……しなきゃ……」
今更のように薬の効き目がピークにきたらしい。どうしょうも無く怠い体を這わせて、拓斗は自分のデイパックに手を伸ばした。
「玲!」
甲高く掠れた声が、荒々しいドアの音と共に吹き込まれた。
「そいつ、訳ありだそうだな」
「もういいんです。誤解だった……」
男はつかつかと入ってくると、拓斗の顎をクイッと持ち上げた。
「……こいつ……?」
拓斗はかすんだ目で、朦朧と闖入者を見つめ、それが誰か認識した途端に男を突き飛ばそうとした。
男は拓斗の腕をつかみ、簡単にねじ曲げた。
二丁目のゲイバー《エリザベス》は、軒を連ねるその手の店の真ん中あたりに位置している。たたずまいは小さいが、老舗の一つに数えられ、ママの真由子がカリスマ的な人気を博している。かつて何度も龍樹が訪れた場所だ。そこは、相手探しよりも純粋に飲んで酔いたいときに訪ねることにしていた店なのだ。
「龍樹ちゃん! はやかったわねっ」
真由子がいち早く駆け寄り、龍樹の格好を頭からつま先まで一瞥すると、顔をしかめた。
「なあに? そのイケイケは」
「拓斗のリクエスト。この格好で迎えに来いって言われたんだ」
「悪趣味ね」
後ろから口を挟んだ水野を見て、真由子が更に顔を歪める。
「誰よ? この子」
「拓斗のストーカー。リリスの部屋の情報は彼女が調べてくれたんだ」
「ストーカーじゃないわよっ。追っかけよっ」
「だめよ、あなた、ゲイにくっついててもいいこと無いわ。そういうの、オコゲって言うのよ」
「そんなことより、リリスの部屋に連れてってよ」
「! そうだ。拓斗は?」
「まだ連絡無いの。オーナーには電話したけど、今日は休暇で支配人に一任してるって。でも、電話入れてくれたはずよ。案内させるわ」
真由子に送り出され、慌てて店を出ようとしたところで、走り込んできた者にぶつかった。
「あっ、マスター!」
派手な化粧に作ったハスキーボイスの女声。開店当初に手伝ってくれていた男である。
「香奈ちゃん! どうだったんだ?」
「入れてくれないのよ。ママが電話しといてくれたはずなのに。散々押し問答してたらオーナーが出てきて。顔見てこりゃだめだって思って急いで戻ってきたの」
「オーナー、知ってる奴なのか?」
「清田さん。マスター、トラブッたことあるでしょ?」
「あ……んのやろう!!!」
ギリギリと噛みしめた歯の音だけで威嚇できそうな表情だった。
「案内してくれ! 早く! 拓斗がっ拓斗がぁっ」
行き先を知っていれば即座に飛び出していただろう脚をもどかしげにバタつかせ、龍樹は吼えた。
「ちょ、清田さん! 乱暴しないで!」
笹沢の叫びに、拓斗はげんなりとした。
やっぱりあの清田だったんだ。
拓斗に龍樹への不信を吹き込んだ男。
ソムリエが仕事の、スマートで華やかな美男子だ。
龍樹に言わせれば、美味しそうな包装の下に滅茶苦茶不味い菓子が包まれてるそうな。
おかげで、しなくて良い喧嘩をして、危うく龍樹との中も完全決裂になるところだったのだ。
「玲、キングがらみだって、何で言わないんだよ? 言えばいくらだって協力してやったのに」
「関係ないでしょ」
「あるさ。こいつのせいで、俺のタッちゃんはおかしくなったんだ。今更の純愛に溺れて、バカみたいにこいつの犬やってる……」
「良いじゃないですか、あの人が望んだんだから……」
「良くないよ。タッちゃんは、みんなのキングだったんだから」
「あの人は、誰のものでもなかった。だからみんな憧れたんだ。あんたは全然わかってない」
もっと言ったれ、笹沢!
心でつぶやき、怠さにソファからずり落ちた拓斗は床に転がった。
「こんな、可愛いだけの男、他とどこが違うんだよ」
「……少なくとも、あんたよりずっと魅力的だよ。こいつはすれてなくて、いつでも馬鹿正直で、純情だ。本気でぶつかれば、本気で返してくれる。キングはずっと純愛したかったんだ、きっと。こいつに出会って、やっと……」
悔しいけどしょうがないという顔で、笹沢は目をこすった。
「なら、なおさら味見しないとな。キングを狂わした手管、見せてもらうか」
笹沢を押しのけ、清田がまたがってきた。
シャツをむしり取られ、ボタンが飛び散る。
(いやなパターンだ)
拓斗は動かない体で、ぼんやり考えていた。
人を信じないと言われた自分が、変なところで騙されやすいのは、やはり隙があるからなんだろう。
とにかく今は、龍樹に以前と同じ不愉快な思いをさせないように貞操を守ろうと決意した。
清田を挑発しながら牽制する科白を考える。
「俺も馬鹿だけど、あんたも相当だよな。進んで危険に首つっこむんだから」
「え?」
嬉々としてジッパーに手をかけていた清田が瞬間固まった。
「龍樹さん……あんたのこと、殺すよ。それか、二度と使い物にならなくされる……」
ろれつが回らないながらも拓斗は清田に言った。
「脅したって無駄だよ。お前が浮気すれば、あの人も目が覚めるに決まってる」
「強姦は浮気じゃない。龍樹さんは許してくれた……」
「た? って、お前……」
笹沢が興味津々の顔で食いついてきた。
「薬盛られて、ラリってるとこやられたことある。やった奴は二度と強姦できないようにって、神経切って起たなくされてた……。龍樹さんは俺じゃなきゃだめだって、泣くんだ。あんなに強いのに、捨てないでって泣くんだよ。泣かせたくないのに……いつも俺が馬鹿だから、こういうことになって泣かせちゃうんだ……」
拓斗は龍樹の泣き顔を思い出し、悲しくなったのだった。自分もぽろぽろ涙を流しながら、虚空を見つめてつぶやいた。
「今度のことで龍樹さんが泣いたら、笹沢、お前のせいだからな……。ろくでもない薬飲ませやがって」
「ごめ……」
「清田さん、通夜の時はありがとうな。おかげで龍樹さんと初めよりずっと仲良くなれたよ」
ぼこっと殴られた。本当の憎悪の瞳はこれだと思う。
拓斗は、何故かどんどん冷静になっていく自分を発見していた。
「……薬のせいかな、痛くない……。殴りたきゃ殴ればいい。気がすむんならね。でも、味見はやめてくれよ。龍樹さんがキレると、ホントに怖いんだ……。あの人が人殺しする所なんて見たくない」
「そういわれると、なおさら味見したくなるな。痛くないなら、ここの具合もいいだろう?」
いきなりパンツ越しにアナルを探られた。
「だめだね、感じない。あんたの臭い指じゃ全然嬉しくないや。俺をイかせることが出来るの、龍樹さんだけ」
立て続けにボコボコッと頭を殴られた。
「きっ、清田さんっ」
笹沢が後ろから羽交い締めにして清田を止めるまでに、拓斗の顔は無惨なほどに傷だらけになっていた。
「なあんか、俺、今、最高に不細工? 龍樹さんに見せられないなぁ」
ヘラヘラと笑いが漏れる。殴られる痛みは、龍樹に泣かれるときの胸の痛みよりずっと心地よい。
どんどんと扉を叩く音に、拓斗はゆっくり首を傾げた。
「何か、騒いでるぜ。案外龍樹さんだったりして。鍵、かけてあんの? 龍樹さんさ、こないだは硬質ガラスを正拳で砕いたんだぜ。俺を襲った奴、びびってたなぁ」
拓斗のクスクス笑いを聞きながら、清田はヘナヘナと座り込んだ。
清田を手放した笹沢は拓斗の側に駆け寄り、抱き起こした。
「向坂、ごめん。痛いよな……」
「痛くないって言ったろう? それより電話かけたい……。龍樹さんに早く来てって言わなきゃ……」
ドカッ、バキバキという音が拓斗の声を遮った。
「拓斗ぉっ!」
耳になじんだ声が、ひきつれた吼え声となって響いた。
「電話の必要……なかったね」
薬のせいか、脳内麻薬のせいか、拓斗はまだヘラヘラと微笑んでいた。
龍樹が清田を突き飛ばし、笹沢を押しのけて拓斗を抱きしめたときも、腫れ始めたぼてぼての顔で微笑んでいたのだ。
「拓斗、拓斗、酷い。何でこんな……」
龍樹は拓斗の傷を矯めつ眇めつ調べながら、何度も瞼や額にキスした。
「遅いよ龍樹さん、九時に迎えに来てって言ったのに」
「行ったよ、ちゃんと。君が居ないから探しちゃったよ」
ぎゅうっと抱きしめられて息を詰めた拓斗は、龍樹の耳元に囁いた。
「俺、ずーっとここにいたよ。龍樹さんを待ってた……」
「向坂、ここ、新宿なんだ」
拓斗は目をしばたたかせ、きょとんと笹沢を眺めた。
「笹沢ぁ、目的地は正しく教えてくれなきゃ困るよ」
「……貴様が笹沢かっ?」
拓斗が名前を口にした途端に笹沢は胸ぐらをつかまれた。
龍樹の形相に怯えた笹沢は、こくこくと頷くことしかできない。
「よくも……よくも拓斗をっ」
言いながらふるおうとした拳は拓斗に遮られた。
「笹沢を殴ったら怒るよ!」
拓斗の低い声で龍樹はピタッと動きを止めた。
「た、拓斗くんっ?」
「清田さんに殴られてたの、笹沢が止めてくれたんだから……」
泣きそうな瞳が途端に色を失って。
ぐるんとロボットのような仕草で龍樹が振り返った。気配で清田がビクッとすくんだのが分かる。
ズカズカと清田に迫る龍樹を、拓斗は止めようとしてまた転げてしまった。
「やばっ笹沢っ止めて! 龍樹さんキレてるっ」
「あ、ああ」
拓斗の声に慌てて龍樹の方に向かった笹沢だが、手負いの獣化している龍樹に近寄ることもできない。
「拓斗に近寄るなと言ったはずだ!」
バキッと清田が飛んだ。それに駆け寄り、ぐったりした清田の胸ぐらを掴みあげる。
「た、龍樹さん! だめだって!」
ずるずると這いよって、龍樹の足下にたどり着くと、拓斗はぎゅっと龍樹の脚を抱きしめた。
「龍樹さん、止めて。龍樹さんが殴る必要無いって」
「離せっ! こいつ、殺してやるっ。僕の拓斗を傷つけやがってっ」
「大丈夫だから! 俺は何にも傷ついてないよ。それとも、俺が不細工になったら嫌いになる?」
「そ、そういう問題じゃないっ」
「俺が許すって言ってるんだ。これ以上暴れたら、口利いてあげない」
拓斗の真剣な声音に龍樹は押し黙った。
ぼとりと清田が転げ落ちる。
「笹沢、清田さんをどっか連れてって。とにかく引き離さないと」
冷静でよどみのない声に、笹沢はぼんやり頷いた。
「向坂……」
「え?」
「お前って、すごいのな……」
感心した様子が拓斗を赤面させた。
「何言ってんだか。それより急いでよ」
ぼんやりした清田に肩を貸し、笹沢は出ていった。
ドアの残骸を踏みしめる音がとぎれると、龍樹は思い人を助け起こして抱きしめ、髪に頬刷りしながら呟くように名を呼んだ。
「龍樹さん、落ち着いた?」
「君は誰にでも優しいんだな。なのに、僕にだけ厳しい……」
「龍樹さんが特別だから……俺もわがままを言っちゃうんだ。ごめんね。龍樹さん、心配させてごめん……」
力の入らない腕を精一杯持ち上げ、龍樹を弱々しく抱きしめる。
「もっと、気をつけるから。飲み物にも食べ物にも人にも……。だから俺のこと、捨てないで……俺だけのキングでいて……」
「……キング?」
「龍樹さんは、みんなのキングで、とことん不実な男だったんだろ?」
「あ……それ……」
「こういう色っぽい格好で歩いてたんだろ?」
シルクのシャツを握りしめて引っ張った。
その腕を取り、龍樹はキスする。
「……過去のことだ。頼むから、その事で僕を虐めないで」
「虐めてない。知りたいだけ。俺には隠さないで。今の龍樹さんを、ちゃんと好きでいるから……。それに笹沢を怒らないで。あいつ、今でも龍樹さんが好きなんだ。泉さんの妊娠のことで、俺が龍樹さんを裏切ったと思ったから、こんなことしたんだよ」
いきなりムッとして覗き込んできた金色の瞳は、愛らしい輝きに満ちている。
「あいつのこと、好きなのか?」
馬鹿げた嫉妬の言葉でも、龍樹なら愛しい。見つめ合うだけで甘いうずきが体中を走るから不思議だ。
「バカ言うなよ……俺の男は龍樹さんだけだよ。もう友達で居られるかは分からないけど、これからの六年間はクラスメートだから」
「仲良くしちゃだめ。あいつの最後の表情は、君に惚れたって言ってたからね。絶対相手しちゃだめなんだから……」
「焼き餅焼きだな……。俺のキングは」
そっと唇を掠めた拓斗の指先は熱かった。殴られ傷のせいで、熱が出てきている。
「キングじゃない、僕は君の奴隷だもの……。あいつらが僕のこと、そんな風に呼んでるのだって、知らなかった……。帰ろう、早く。解熱剤、飲まないと。いや、注射の方がいいかな」
「……痛いのやだ。座薬にして貰おうかな。長く効くから」
「いいよ。確かボルタレンがあったと思う。僕が入れてあげる」
「……エッチなこと、考えてるでしょ」
「ふふ。楽しく治療できそうで嬉しいだけ」
コツンと額をくっつけて、嬉しい微笑みをかわしあった。
「……早く帰りましょうよ」
いきなり響いた鈴を振るような高い声に、拓斗は身体を強張らせた。
「な?」
「ああ、水野君。君を捜すのに、協力してくれたんだ」
「へっ?」
「向坂君、いちゃつくのはお家帰ってからにしてよ」
「ななななっみみみっ」
カアッと顔が燃え上がって拓斗は慌てた。
「いいいいっいっいつからっ?」
「……最初から。あなたのキングの車に乗ってきたんだもん」
「たったっ龍樹さんっ」
「拓斗、彼女の言うとおり。若い娘は早く送り届けなきゃね」
(エッチはその後ね)
わざといやらしく小声で耳に吹き込みながら、龍樹は拓斗を抱き上げた。
「やっおろせっおろせーっ」
実際熱が上がってきて歩くこともできないはずの拓斗は、それでも必死にあらがった。
「水野君、先に行って車のドア開けてくれよ」
「オッケー」
可愛らしくウインクして龍樹の投げたキーを受け取り、水野は駆け去った。
「今更恥ずかしがらないで。彼女は君の味方だから。本当に心配してくれてたんだよ」
「だって、あいつのせいで……!」
「彼女が積極的に流した噂は僕が君に抱かれてるって噂だけ。僕の意向を尊重しての行動だ。彼女は君に振り向いて欲しかっただけ」
目を白黒させながら聞いていた拓斗は、穏やかそうにそこまで語った龍樹が、いきなり鋭く睨んできたときも混乱したままだった。
「君、彼女の本心が分かっても、ほだされちゃだめだからね。僕を捨てたりするなよ」
「 !」
コルベットの横では水野がニコニコ手を振っている。
拓斗は狐につままれたような気分で身体の力を抜いた。
「すっかり遅くなっちゃったな。水野君、すまなかったね」
「いいけどぉ。真由子ママの所で何かご馳走になればよかったなぁ」
「ああ、ママたちにもお礼しなきゃなぁ」
のんびりハンドルを握りながら、今日は何人に借りを作ったのだろうと考えた。
拓斗の熱がひどかったので、挨拶もそこそこに帰ってきてしまったのだ。
「ご馳走は今度。僕の料理でよければディナーに招待するよ」
「本当? ママたちも招待する?」
「そうだね。受けてくれれば」
「弘樹君も呼んでね。ちょっと好みなんだ。ストレートだって言うし」
「いつの間に……なかなか手が早いね」
「失恋はね、新しい恋が癒してくれるのよ」
「まあ、確かに」
くすっと笑って色白の顔を伺った。
前向きな人は女でも嫌いじゃない。
「じゃあ、新しい恋のために一つ忠告」
「何?」
「外堀ばかり埋めてないで天守閣をねらいなさい。素直な君の気持ちをぶつけるんだ」
「当たって砕けろ?」
「うん。当たるタイミングは大事だけどね」
「ありがと、マスター。いえ、桂川先輩」
「なっ?」
今までぐったりしていた拓斗が目を覚ました。
「俺、龍樹さんが中退したこと言ってないぞ?」
水野はぷっと吹いて、けたけたと笑った。
「そーんなの、有名だって! 伝説の桂川龍樹。マスターと同級だった先生って、結構大学に残ってるもん。入学式の日、注目してたの新入生だけじゃないんだから」
拓斗はしおしおとシートに埋もれ込んだ。
「……まいったなぁ。忘れて貰えると嬉しいのに」
「それは贅沢ってもんです。ずば抜けて綺麗だから印象に残るんだもの」
「自分で勝ち取ったものじゃないことでそう言われてもね……。しかも、中退だよ?」
グイッとハンドルを切る。ガッと身体が傾いで、拓斗の頭がもたれてきた。
「俺は飯と心に惚れたんだからな」
低い囁きは耳元を掠めるそよ風のようにひっそり過ぎった。
「拓斗?」
「……眠い……」
うつらうつらしながら呟く唇を愛しげに横目で見て、龍樹はアクセルを踏んだ。
レジデンス森が丘の玄関に横付け、運転席側から水野を下ろした。
「ありがとう」
「こちらこそ。おもしろかったわ」
「あ、君!」
スカートを翻し玄関に向かう水野を呼び止めた。
「彼が、僕が勝ち取った一番の宝なんだよ」
水野は、急に何を言い出すの? という顔で首を傾げた。
「苦労したの?」
「そりゃもう、忍耐を一生分使い果たした気分だったよ。諦めかけてたところを彼が手をさしのべてくれたんだ」
「そういうのって執着心煽るのかもね」
「……否定はしない。初めは一目惚れだと思った。でも、それじゃ気持ちは続かない。僕は毎日惚れ直してる。気持ちを積み重ねて、どうにも他に目を向けることが出来ないくらい入れこんじまってるんだ」
「……だから邪魔するな?」
「うん。オコゲなんて、僕らには邪魔なだけ」
「そんなつもりないわよ。もう、とっくに諦めてたって。これからはただのファンとして見守るわ」
しんみり微笑んだ水野は、ふと顔をしかめた。
「追っかけも廃業だからいっとくけど」
「?」
「向坂君の階段落ち。事故じゃないかも知れない」
「見たの?」
「興信所の報告だけ。ぶつかったのは今までに接点のない男だったのよ。でも、わざとっぽく見えたって……」
「写真とか有る?」
「撮り損ねたって。今までの資料は全部渡すから、目を通してね」
「……わかった。身の回りにも気をつける」
「またお店に行ってもいい?」
「お客ならいつでも大歓迎だよ」
「よかったぁ。マスターの料理のファンでもあるんだ、あたし」
「光栄だ」
「っじゃ!」
スチャッと敬礼のような仕草をして、水野は玄関の奥に消えた。
エンジンをかけようとすると、拓斗が目を開けた。
「水野、帰った?」
「うん。僕たちも早く帰ろう」
「ああ……そうだな。ちょっと痛くなってきた」
「どこ? みせて」
「いいから帰ろう。薬、入れて。龍樹さんの指で、ゆっくり押し込んで欲しい」
エッチな囁きにはエッチに。車をそっと走らせながら、拓斗に応える。
「中で動かしてもいい?」
プッと吹いて笑った途端に痛そうに顔をしかめた。
「だめにきまってるじゃん、うちち。笑うと顔痛い……」
「明日は腫れるだろうなぁ。骨が折れなくてよかった。歯医者も行かなきゃね」
ええー? っと不満そうな声を上げる。拓斗はあまり歯医者の世話になったことがないため、かえって恐怖感を強く持っているらしい。
「清田さんのこと許したくなくなってきたなぁ……」
「いいよ、許さなくて。あいつ、また顔見せたら今度こそ足腰立たないようにしてやる」
「ひねくれて考えれば、今の俺達、あの人のおかげでもあるんだから、あんまりそういうこと言っちゃだめ」
「なんでさ?」
「俺の気持ちぶつけて、龍樹さんの気持ちを確かめること出来たじゃん。こんなに早く結婚の話が出たのも、あの人のおかげ」
「……どっかの童話の主人公みたいによかった探し?」
「うん。出会えてよかった。恋人になれてよかった……愛されて……よかった……愛して……よか……」
抱き上げられ、ベッドに運ばれる間中、拓斗はよかったと呟きながら眠りに落ちていった。
「君が振り向いてくれてよかった……」
座薬を差し込みながら耳たぶにキスをした。ピクッと身体を震わせた拓斗は、眠りから覚める様子がない。
拓斗を狙う男の存在は不安だったが、今は恋人を取り戻せた悦びに浸ろうと考えた。
「……拓斗と結婚までこぎ着けそうでよかった……」
全ての後始末をして拓斗の横に滑り込むとき、『おやすみ』の代わりにそう唱えたのだった。
もう一度読み返す